ホーム 未來の歴史 入会案内 未来最新号 バックナンバー ライブラリー カレンダー コンタクト Q&A

ホーム 未來の歴史 入会案内 未来最新号 バックナンバー ライブラリー カレンダー コンタクト Q&A |
|||
 |
|||
時 評 |
||||||
|
|
||||||
| 2025年6月号 |
||||||
| 『写実・写生・叙景』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
「歌よみに与ふる書」を読んでみると正岡子規は「写実」を提唱していなかった。子規は「客観的にのみ歌を詠めと申したる事は無之候」「古今東西に通ずる文学の標準(自らかく信じをる標準なり)」で論評せよと言い、安易な定義づけを避けた。そのせいか短歌ではリアリズムの「写実」とスケッチの手法「写生」は混同される。一方「叙景」は金子薫園・尾上柴舟らによる「叙景詩運動」にルーツを見出せる。 鳥のかげ窓にうつろふ小春日に木の實こぼるゝおと志づかなり 金子薫園
瓶にさす藤の花ぶさみじかければたたみの上にとどかざりけり 正岡子規 「赤ちゃんがおなかにいます」という人が満員電車に目を閉じている 玄関に取り残された小説がふくらんでいる冬の空気に |
||||||
| 2025年5月号 |
||||||
| 『〈私〉は誰なのか』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 終バスにふたりは眠る紫の〈降りますランプ〉に取り囲まれて 穂村弘『シンジケート』 「ふたり」を見る〈私〉は誰か。桑原憂太郎が『現代短歌の行方』で問いかける。桑原は、短歌には「作者」あるいは「主体」の〈私〉が存在するとした上で、この歌から感じ取れる「ふたり」を見る〈私〉は、それらどちらでもない「語り手の〈私〉」であり、「小説世界と同様に、作品の中に〈作者〉は存在しない」という。 この問いはバルト以来のテクスト分析を短歌に用いる限界を示したと思う。桑原が到達した説から、もう一歩先に進みたい。短歌の認識の主体は、三人称の小説のような神の視点・誰でもない視点で語られる地の文とは本質的に異なる。歌は短い。テクストを読むだけでは小説のように人称を断定できない。桑原は作者でも「ふたり」でもないと、消去法で考えていないだろうか。客観的な分析を続けようとするあまり〈私〉から「自分」を捨てていないか。 歌を〈うたう〉〈しらぶる〉ときに〈私〉を置くのを止めてゆっくり読んでみよう。 この歌が優れてるのは、読者=自分が「ふたり」のすぐ近くにいると感じられるリアリティにある。なぜ近くにいると感じるか。文章として読めば結句「れて」は倒置で「ねむる」に続くが、読者が読後に倒置の可能性に気づくまでのわずかな時間においては「言い差し」となる。 このとき「れて」は主語が定まらずに浮遊し「ふたり」と「自分」は重なり合う。「ふたり」かもしれない「自分」はバスの中でランプに「囲まれて」いる体験をする。そのあとに「れて」は倒置となり、作中の「ふたり」と読後の現在の自分ははっきりと分かれ、目の前の「ふたり」は透明な壁の向こうで眠る不可侵な存在となる。 状況を正しく伝えるならこう改作できる。「て」の前後の時間はひとつになり、一枚の絵の中にすべてのパーツが置かれており平面的でつまらない。原作では「二人の姿」/「ランプの光」は句切れによって別のレイヤーの画像として想像できる。囲まれながら「ふたり」が眠っていくまでの時間を「れて」から想像できるだろう。 初めから「語り手の〈私〉」を置いてしまうと「ふたり」と「自分」は重ならない。わたしは歌とまったく同じ状況になった経験はないが「うたう」行為によって、過去のある瞬間が今起こっている感覚と、現在から過去を想う感覚を、追体験している。「自分」だったかもしれない「ふたり」の認識の仕方は、自分の過去の思い出を想像するときと似ている。 歌の読み方は「病床の正岡子規」のような歌の外部にある作者の状況を想像する「作者読み」・社会構造や神話世界を背景に考える「社会読み」・読者個人の体験から読む「自分読み」があり、それぞれの〈私〉の認識を行き来して読むと思う。 小説のような長いテクストでは、読者の心の中にひとつの新しい世界が構築されて、そこに没入できる。情報が少なく読者の補完によって読まれる短歌においては、状況の理解は二次的なもので、〈私〉はひとつに収束せず、拡散し、重なり合う。 歌の作者は読者にとって〈他者〉だが「うたう」のは読者だ。〈私〉をはっきりと分けて読まない短歌において「語り手の〈私〉」の線引きが示すのは、ひとつの世界を立ち上げきれない小説未満の短いテクストという虚しい領域ではないか。 |
||||||
| 2025年4月号 |
||||||
| 『口語の領域』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
呼びかける厚労省のポスターにとまりつづけるかげろうがいた どこまでも広がる空をみていたら鼻血を出していたことがある ぷくぷく「散歩している」 第七回笹井宏之賞の受賞作である。タイトルが連作のコンセプトそのまま、ほぼ嘱目詠の連作での新人賞受賞はめずらしい。 名詞が少なく音の隙間を動詞がゆったりと埋めている。初句の軽い入り方、結句の抜き方はうまい。全体的にゆるやかでわずかに凹凸のあるリズムが心地よい。気持ちは明るいがどこか寂しい感じがする。連作には結句が「ことがある」「こともある」で終わる歌が目立つが、読んでいてあまり気にならなかった。 選考委員の山崎聡子は「舌足らずな言い回し」「ひらがなで読むスピードをコントロール」といった点から文体が「そのままを見たような感覚」を作り出しているといい、「ここ十年くらいの現代口語短歌の技術が取り入れられている」と述べた。 ここ十年くらいの現代口語短歌の技法、この感覚はよくわかる。 一首目では、動詞「つづける」を助動詞「たり」のように継続のニュアンスで使う〈動詞の助動詞化〉、二首目では結句「いたことがある」で「みていたら」の時間を過去に動かす〈体験の出来事化〉のように蓄積されてきた技法を指摘できる。 誰でも利用可能な「音の間を埋める技法」が口語短歌に見えるようになったと思う。いま「なりにけるかも」を使うのは勇気がいるが「いたことがある」は真似して使ってみたくなる。歌の中の時間を動かしほどよい詠嘆を醸し出すのに良いだろう。 口語短歌の弱点と言われる助動詞の少なさ・時間表現の少なさは克服されたのではないか。口語の短歌が多数派となって、文語に対抗する口語という構図がなくなり、現代の歌人たちは大きな葛藤なしに文語/口語を選べる(その上で口語に傾いている)ように見える。 「ここ十年くらいの現代口語短歌の技法」という発言が示すのは、〈口語〉の書き言葉としての成熟ではないか。 そもそも短歌の〈文語〉は独特であり、たとえば明治時代の手紙で用いられた候文のような文語は「短歌の文語」とは言えない。また、名詞については口語/文語で語るのが難しく、雅語/俗語や古語/現代語といった分け方の方がわかりやすい。 〈口語〉においては、正岡子規が「歌よみに与ふる書」で短歌に取り入れると宣言した「俗語」は「話し言葉」だけだったはずだ。そこから長い時間を経て、短歌では「話し言葉」だけでなく「現代の書き言葉」まで合わせて〈口語〉と呼ぶようになった。ただ「現代の書き言葉」と言っても、散文の〈です・ます〉〈だ・である〉調の書き言葉を短歌で積極的に使うのは難しい。〈口語〉には一般的な話し言葉・書き言葉の概念で説明できない領域がある。 話し言葉には「ぜ」「わよ」のような話者の属性や役割を示す記号が多分に含まれるが、書き言葉の属性はニュートラルである。「いたことがある」は書き言葉に近い語彙だ。「ここ十年くらい」よりもさらに前の時代では〈口語〉と言えば話し言葉だったのではないか。書き言葉に寄りつつある現在の〈口語〉に慣れると「ずるいなあ」のような言葉を選びにくい時代だ。 書き言葉化する〈口語〉の向かう先が作者の属性を感じさせない短歌だとすると、「ぷくぷく」という作者名は現代的かもしれないと思った。 |
||||||
| 2025年3月号 |
||||||
| 『秀歌と秀歌性』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
二〇二四年は歌会やネプリなどさまざまな短歌の営みがメディアに取り上げられた一年であった。『文學界』九月号の特集「短歌と批評」に触れておこう。体感として二〇二二年五月号の短歌特集「幻想の短歌」からあまり時間が経っておらず、間隔の短さに驚いた。今回の特集では「十三名による大歌会」として無記名・互選の歌会の模様が収録されている。 夕暮れの色の卵を割り開きこころは慣れていく夕暮れに 堂薗昌彦 堂薗の歌に対して、井上法子は「色の」「割り開き」に注目して「丁寧に丁寧に手入れされた盆栽のようなきれいな歌」と評した。ここは私も同意で、井上の読みで補足したい点は、堂薗が「夕暮れの卵」と暗喩にせずに「夕暮れの色の卵」としているところだ。 景色のスケールが大きな「夕暮れ」から始まる歌のイメージは一度「色」で抽象化され、今作者が持っている卵にゆるやかにスケールダウンする。夕暮れの景色が像を結ぶ前に「卵を割って開く」瞬間までが示される。この時間のフレームの切り方が絶妙で、読者は読後に初めて「丸い卵の黄身がどろりと流れ出す」「買った卵の色が赤かった」イメージを想像できる。 サブリミナルな初句の「夕暮れ」の印象と結句の倒置から、歌以前の時間にある「買い物の帰り道で、夕暮れの景色のスペクタクルに感動した」体験をじんわり味わえるだろう。「色の」は「夕暮れ」を歌以前の過去の時間に置く効果がある。歌の中の〈現在〉で作者が見ているのは卵を割る自分の手元で、その瞬間に直接「夕暮れ」を見てはいない。それゆえ、結句の「夕暮れ」は夕暮れの印象であって「慣れてゆく」とは、目の前にあらわれた黄身の強烈で具体的な姿が、夕暮れの印象を上塗りして消してしまった様子を言っているのだ。 人間はいつまでも感動し続けられない。夕暮れを見てたかぶった気持ちが萎んでいく、日常の感覚に戻っていく寂しさが詠まれている、と読めないだろうか。 歌会では次のような批評が続いていく。「共同体が磨いてきた秀歌性に精度高く球を当てている印象」(穂村弘)・「狙って当てている感じが採れなかった」(青松輝)といった「秀歌性」批判があり、伊舎堂仁は「慣れていく」の言葉の選択に「秀歌性に私を渡さないための最後の抵抗に感じます」と返す。 テキストに起こされた三人のやりとりに恐ろしさを感じた。良い歌に票を入れにくいと感じるのは歌会に慣れている人ならばよくわかる感覚だろう。ただ、ここでの「秀歌性」は言葉を抑圧するマチズモの符丁になっているのではないか。 年長者の穂村が「秀歌性」批判をして、青松が同調する。伊舎堂は反駁のポーズを見せているが、論点を細部に逸らしているだけだ。男性の歌人では永井祐だけが「穂村さんが名前を挙げた歌人が持っている秀歌性とはちょっと違う」「むしろ作者の個性、面白いところ」と述べる。しかし場の流れが戻ることはなく、歌の読みは深まらなかった。 秀歌に〈性〉をつけるとコンセンサスのある概念のように感じるが、「共同体が磨いてきた」秀歌と、出自がバラバラな「大歌会」参加者それぞれの秀歌〈観〉が完全に一致するはずがない。秀歌かどうか判断をはっきり言えば良いところを、具体的な理由を言わないでいるから反対のしようがない。同調か沈黙を強いる〈性〉は短歌の批評には不要だ。 |
||||||
| 2025年2月号 |
||||||
| 『詠み人知らずの演出』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
十二月、宮城県多賀城市の史跡の前に次のような看板が突如としてあらわれ、ソーシャルメディア上で話題になっていた。 多賀城南門 2週間前 ★★★★★ 南門を 目の前で見れて 最高です 朱色が映えて とてもきれい 一見して、看板はGoogleマップ(地図のウェブサービス)の口コミのデザインを模しているとわかる。★の数は場所の評価で最高評価を示す。その下に短歌のかたちで感想が添えられている。自治体が観光事業の一環で短歌を公募したのだろうか。 歌を読んでみる。句ごとの一字空けや「映え」の使用はあどけなく秀歌のセオリーをことごとく破っているのだが、全体に気持ちがよく出ており、嫌な気がしない。心の底から言葉が出てきている感じがする。特に三句「です」で切ったあとの下の句の「映えて」「きれいで」の語を畳み掛けるようなリズムに惹かれる。柱に塗られた赤土の朱色が美しかった、ただその一点を歌いきっている。良い歌ではないか。 しかし実は現代美術家の松田将英の作品であったという。看板は松田の作品群「Bashō Sampling」のひとつで、Googleマップに投稿された口コミから短歌や俳句になりそうな部分を抜き出して、匿名の投稿という設定の作品にしている。ウェブ上にしか存在しない声が現実世界に置かれると異質さが際立つ。ウェブ上が仮想世界であることを思い出させてくれる作品だ。 そして私は落胆した。「Bashō」つまり「芭蕉」を選ぶ松田の安易さに……ではなく「匿名を装った作品にする」行為に対して、である。作品の元ネタは「東北グルメ」というアカウントが十一月に投稿した口コミだ。対象箇所を引く。 南門を目の前で見れて感動です! 朱色が映えてとてもきれい 厳かな迫力ある南門に見惚れました。 松田はこの口コミの中から、偶然短歌になっている言葉を見出した。そしてそのまま匿名の作品にしてしまった。ここには自分の感覚のフィルターを通す工程が一切ない。松田自身の作者名をつけるリスクを取る勇気もない。サンプリングやコラージュといった再構成の手法ではないのだ。なぜ看板から投稿主のアカウント名を消してしまったのか。端的にいって、盗用である。 何を言っているんだ。「自分ひとりのものにする」行為は「詠み人知らず」の文化には絶対につながらない。現地の看板に作者名が書かれていないため、作品は匿名のまま流通したのだろう。この点は「詠み人知らず」の状態ではあるが、現地にいても見えないソーシャルメディア上で美術作品として一人の作者名をつけられているのだ。 名前を伴って記録された言葉を「詠み人知らず」として流通させる行為は暴力である。松田の作品は口コミ投稿者を二重に収奪した。言葉そのものと「詠み人知らず」であり続ける機会を奪っている。これはむしろ「詠み人知らず」文化の冒涜だろう。 他者の言葉を盗用する行為は、制作コストをかけない広告クリエイティブの手法として洗練されすぎている。また、言葉を扱う歌人が言葉の盗用を許容する態度を見せるのはあまりに愚かではないか。 |
||||||
| 2025年1月号 |
||||||
| 『遠くで鳴っている』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
歌詞やミーム(流行り言葉)といった他者のテクストを取り込んだ短歌をどう読むか考えたい。 愛のWAVE 光のFAKE どうしよう、とりあえず、生きていてもらってもいいですか? 青松輝『4』 いーじゃんいーじゃん 春だけ電車が止まる駅 すげーじゃん 梅満開の庭 郡司和斗『遠い感』 小島なおの短歌時評(朝日新聞二〇二四年十月二十日「ミームと創造」)に注目した。小島はこれらの歌をまとめて「嫌疑の台詞(せりふ)が生の肯定へ、形式化した春の景物が一周回った良さへ変換される」という。 小島の指摘を補足しておこう。一首目はひろゆきの「なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか」という相手を否定する煽り文句からミーム化した言葉が、相手を肯定する言葉に変えられている。二首目は、「仮面ライダー電王」の主題歌の歌詞「いーじゃん! いーじゃん! すげーじゃん!?」を分割した上で整形しており、歌によくなじんでいる。「梅満開の庭」に作者の気分が加わり、なんでもない景色が特別な体験へと異化される。 小島はこれらの歌をまとめて「ブリコラージュ」(レヴィ=ストロース)の範疇で考えられないか、と提案するのだが、まとめてしまうと読みが深まらないような気がした。二つの歌の「取り込み方」は似ているが、思想に大きな差異がある。 青松の歌は出典元の文脈を知っていると印象が変わる。ひろゆきの言葉は、たとえば「絶対におかしい」という相手に対して、主題となる「おかしい」ではなく「絶対に」だけを取り上げて、「絶対に」に客観的な根拠があるか問い詰めて、問題から目を背けさせる詭弁的な技法である。青松の短歌では言葉のニュアンスが生の肯定に変わっているが、ここにひろゆきの言葉への批判を読めないだろうか。 ひろゆきは二〇二二年に沖縄を訪れて、辺野古の座り込み抗議の看板の「3011日」を、人がいない日があるなら0日にしたほうが良いとツイートしたことがある。客観的に測定できる定義や厳密さを、感情が込められた言葉や文字に求めてしまうと、怒りや悲しみの感情は抑圧されるだろう。「生きていてもらってもいいですか」は弱者の立場に寄りそう言葉ではないか。元の言葉にはなかった「も」の補い方からは切実さが感じ取れる。どうしようもない怒りや悲しみに直面している人に対して、当事者たりえない作者が生きてほしいと声をかけている。上の句は作者自身の焦りを落ち着けようとする感じがある。 切実さと同時に、当事者の気持ちに向き合わず、感情的な言葉を排除しようとする圧力への、作者の怒りを読んでも良いと思う。抵抗のブリコラージュである。 一方、郡司の歌はレヴィ=ストロースの概念によらず原義のブリコラージュで考えられる。捨てられているコーラの空き瓶を楽器にするように、元の素材が持つ記号的な意味は削ぎ落とされている。 もし元の歌詞をそのまま取り込んでいたら、歌詞が浮いてしまって作者の気分が全然感じ取れないだろう。歌詞に景が挟まる短歌の方が歌が遠くで鳴っていて、読者は景色に集中できる。極端に言えば元ネタと歌の関係は深く読まない方が良い。 もうひとつ、郡司の歌の元ネタはミームになっておらず、記号が成熟していない。これからもミームになることはないと予測した上で自分だけが選べる素材と考えて歌に取り込んでいるのかもしれない。 |
||||||
| 2024年12月号 |
||||||
| 『短歌のしをり』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
吹かれ来るかまきりの仔ら淡あはとすき透り立つ卓のともしに 近藤芳美『冬の銀河』 「短歌研究」十月号、髙良真実「冗語と詠嘆性への回帰」を読んだ。右に挙げた近藤の歌に対して、髙良は玉城徹が『近代短歌の様式』で見出した戦後短歌の「冗語の排除」を近藤にも見ようとする。また、「かも」「かな」のような「文法的詠嘆は徹底して排除されている」が「かまきり」の見せ方は「中途半端」な抒情であり、抒情=詠嘆の排除に失敗しているという。 高良のいう「中途半端」は詠嘆を排除しようとしているが排除し切れていない、という意味だと思われる。しかし「冗語の排除」を詠嘆の排除と直接結びつけるのは無理があるのではないか。 歌を読もう。読み終えた後にイメージするかまきりの立つ姿は静止しているが、「吹かれくる」によって時間の流れとかまきりの動きが示されると、風に逆らって姿勢を保つ様子や、光を反射しきれずに体に光が浸透してしまう幼虫のもろさが感じられる。調べがゆらゆらとする助動詞を用いず、全体に濁音がなくスッと最後まで読める軽さはかまきりの質感にちょうどよく、韻律が魅力的な歌だと思う。 感情は直接示されていないが、作者の心は落ち着いている。風景をみるように、冷静にかまきりを見ている感じがする。「すき透り立つなり」と助動詞を補うと、かまきりへの心よせが強過ぎて、軽い調べと合わなくなる。 文法的に詠嘆を示す言葉がなくても、心の様子は読み取れる。そもそも短歌は「うた」であり、詠嘆は「うた」の機能だ。「冗語」は言葉の分類であって、詠嘆と直接イコールでは結べない。 玉城徹が『近代短歌の様式』「近代の濾過」で触れた「冗語」には、枕詞「あしびきの」のような文字通り余分な言葉と、助詞助動詞(この呼び方を玉城は嫌う)などが含まれる。そのほかに、冗語ではないが助動詞「をり」とちかいニュアンスを持つ言葉も「冗語性」のある語として冗語の範囲に入れている。 近藤の歌は自動詞の歌だ。自分とは関わりなく存在するかまきりを見つめている。ここには「をり」の「冗語性」がある。 もう少し玉城の言葉に触れておこう。玉城は「冗語の排除」を「短歌のしをり」から離れる動きとして語った。短歌の「しをり」とは「イメージを持たない気分」のことだ。具体的なイメージではなく、そのもっと奥にある心の状態を「おちつき」や「ふぜい」だと言う。その上で「しをり」から完全に離れてしまったら短歌の韻律は保てないのではないか、というのが玉城の主張であった。気をつけたいのは、玉城が危惧しているのは最終的に「短歌の韻律」が崩れることであって、「冗語の排除」を否定しているわけではない。 短歌である限り、読者は作者の「気分を直接見せない」心の様子を読み取ろうとする。「冗語の排除」によって「イメージを持たない気分」から離れようとしても、読者が感じる「しをり」はなくせない。髙良の「中途半端」は読者と作者を厳密にわけられない短歌の性質をよく表している。 近藤の自動詞の歌は自分の視点が風景に溶けこんで一体化している感じがする。実景を詠んでいても、歌全体が気分を抑えようとする心の暗喩に思えてくる。どれだけ対象と距離を取ろうとしても、完全には離れられないのだ。「しをり」とどう向き合うのか、正解のない問いが短歌にはある。 |
||||||
| 2024年11月号 |
||||||
| 『フリーライド批判』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 平日の明るいうちからビール飲む ごらんよビールこれが夏だよ 岡本真帆『水上バス浅草行き』 X(ツイッター)上で、企業アカウントが岡本の短歌を模倣したと思われる広告をポストしていたのを見た。 「ご覧よシャウ、これが夏だよ」 シャウエッセン
@schauessen_nh 「ごらんチーズベーコンポテトパイ、これが祭りだよ」 マクドナルド @McDonaldsJapan ゾッとした。端的に言って文化の収奪ではないか。岡本の短歌は下の句「ごらんよ〇〇これが△△だよ」(以下「ごらんよ構文」)+「〇〇」の対象を写した画像をアップする形でXからミーム化し、ネット上で広く認識されている。暗黙のルールとして、起源や所有をだれも主張せず、だれでも利用できる共有資本となっていた。 今回の企業の行為は、先住民が育ててきた森や湖を奪う植民地支配と同じ構造であり、わたしはこれを軽蔑する。 マクドナルド社がウェブ公開している問い合わせフォームから、今回の広告はモラルに反しているのではないか、と意見を送ったところ「短歌の引用は行っていない」というメール回答をいただいた。引用の話はしていないし、そもそも引用ではない。意図はうまく伝わっていないようだ。 ミームは、遊びの中で育まれた共創的な文化である。外から来た企業が、安易にミームに乗っかろうとするのは精神が貧しいと思う。コストをかけずにフリーライドしようとする精神を強く批判したい。 歌の話をしよう。三句の「ビール飲む」は調べがぎこちなく、音数の都合で助詞を削ったように見えて、素人っぽい。三句は素直に「飲むビール」にすれば調べが整うだろう。「ビール」で軽く止めると上の句を読み終えたタイミングで作者の視点はビールを見つめる形になり、視点を移動せずにビールに語りかける下の句に滑らかに接続する。しかし、作者の感覚が欠落してしまう気がする。 もとの「ビール飲む」では、ビールそのものではなく、自分がビールを飲む行為や周囲の環境をまるごと客観的に捉えているのではないか。上の句では自撮り的な視点で、下の句では手元のアップで、上下両方の句に「明るい背景」が感じられる。「背景の前に存在する」ビールと作者自身は等価の存在であり、ビールへの語りかけは作者自身への語りかけとなる。作者自身は戯画化され、夏を実感する暇がないほど忙しかった、といった歌以前のやるせない時間を、読者は想像できる。 歌の内容は夏にビールを飲む開放感を歌っている。しかし、カップに入ったビールが輝きながら少しずつ泡を失っていく様子はどこか悲しい。ビールにとっては今この瞬間一回限りの夏である。開放感のある光景が屈折感のある感情を際立たせる。 「ビール飲む」には、メタ的に自分を捉えてモノと自分を同一のものとして眺められる効果がある。それゆえに、読者は深読みをしなくても、ビールが置かれた状況を作者の心の暗喩として、自然に読み取ることができる。この歌が本質的にユニークなのは「ごらんよ構文」を見いだしたことではなく、一見すると稚拙な三句の処理に秘密があったのではないだろうか。 屈折感を読み取ってから広告のコピーを見ると、上の句は企業が望むような消費を促すテクストではない。開放感のある下の句だけが広告に利用されていると思うと、今回の件は一層グロテスクであった。 |
||||||
| 2024年10月号 | ||||||
| 『時間の感覚』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
十七時 港を離れた客船が 十七時半 岬を過ぎる 北山あさひ「幽霊 2024」 Wi-Fiの乏しき力(りき)にすがりつつ雨の一日を家居(かきょ)するわれは 山下翔「入梅前」 「現代短歌」の九月号、瀬戸夏子が選んだ「ニューアララギ」十人の連作から歌を引いた。 まず一首目、時間の始点「十七時」が初句で示される。機械的に計測された時間の経過と事実の二つの文の流れは、交互に並べられ、複雑なリズムを作っている。読後に感じる歌の中の現在時刻は岬を過ぎようとする「十七時半」だが、初句の印象が強く、もう一度はじめから読みたくなる。 何度か読み直すと、アンナ・カヴァンの『氷』のような具体との距離感を保った幻想的な文体に思えてくる。それにしても、三十分間同じ景色をずっと見ているのはなにか変だ。目で見ているのではなく、カメラを固定して撮影した動画を観ているのだろうか。見通しが良く明るい景色を想像できるが、主体は映像に違和感を感じているのではないか。映像を何度も巻き戻して、おかしなところがなかったか探す。テクストの内容とは違って、密室のような息苦しさがうっすらとある。 文体の選択にも意図を感じた。全体的に辞が少ない歌なので、リズムを崩さずに文語へ置き換えられる。 十七時 港を離れし客船が 十七時半 岬を過ぎん (棒線部を改作) ところが文語にすると、歌の魅力はゼロになる。口語の時よりも、風景を大げさに受け取ろうとする意識が過剰である。この歌に文語の音韻はうるさいようだ。 原作の簡素な文体はどこか不穏である。初句五音があれば、たとえば夕暮れの海の様子や気候といった実景を補うことも十分にできたはずだ。しかし、作者は景色のディティールを徹底的に削ぎ落としている。時間の変化を直接言葉にする技法は、何度も使える技法ではないだろう。技法と内容が嚙み合った秀歌だ。 北山とは対称的な二首目。雨で外に出られない日の様子をユーモアを交えて詠んでいる。たぶん「力(りき)」は通信速度のことで、動画を見るのがやっとなデータ量なのだろう。歌の内容は切実なのに暗い感じはしない。「家居する」を過去形にしないのは、まだ雨が続くから、と読んだ。 「雨の一日」は一首目の三十分と比べてかなり長い時間が示されているが、歌を読んで感じる時間の長さは、一首目のほうが長く感じる。どちらの歌にも独特な時間の流れがあるのがおもしろい。 今の時点では「ニューアララギ」は文体に関わらずリアリズムをやっている若手、くらいのニュアンスに思う。玉城徹は『近代短歌の様式』で、一首のなかの時間を一つに固定する「内面的時間の統一」の原理を見出した。さらに、一首のなかに複数の時間の流れを置いて、原理を破る先鋭的な歌人として、土屋文明を挙げていた。 「ニュー」を外した「アララギ」の範囲はわからないが、土屋文明を抜くことはできない。「近代の原理から外れる文明を内包する集団としてのアララギ」と置くとして、近代短歌以降のリアリズムに新しい時間の感覚を見出せれば、それも「ニューアララギ」の特徴と言えるのではないか。 「文明以前」の内面的時間の統一への揺り戻しの動き、「文明以降」の時間の感覚の重層性をより先鋭的に進める動き、この両極端を「ニューアララギ」として考えると、見通しが良くなりそうだ。 |
||||||
| 2024年9月号 | ||||||
| 『当事者性を考える』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
死ののちのみずからを凧にたとえたる詩を読むガザに殺されし人 私たちは見捨てられたという声す もしかしたら見てもいなかった 吉川宏志「魔芋」 「角川短歌」七月号、吉川の迢空賞受賞後第一作から引いた。これらの歌では「現代詩手帖」五月の特集「パレスチナ詩アンソロジー 抵抗の声を聴く」への反応が歌われている。 歌の背景を補足しておくと、「みずからを凧にたとえたる」は、パレスチナの詩人リフアト・アルアライールの短い詩「If I must die」の一節を指している。凧の尾(tail)が空を泳ぐように、もし自分が死んでも物語(tale)として語り継いで欲しい、という願いのフレーズを、短歌の韻律に載せて言い換えている。 アルアライールは二〇二三年十二月にイスラエル軍の爆撃によって殺害された。爆撃の一カ月前、X(ツイッター)上に、本人のアカウントによって投稿された一枚の画像に書かれていた詩が「If I must die」(初出は二〇一一年)であった。「現代詩手帖」に松下新土+増渕愛子による詩の全訳が掲載されているのでぜひ読んで欲しい。冒頭を引用すると〈わたしが 死ななければならないのなら〉の後に〈あなたは、生きなければならない〉と続いており、詩の主題は残された人々への励ましだとわたしは受け取った。 吉川の歌には物足りなさを感じた。詩の一節を一首に持ち込む場合、ほとんどのフレーズは収まらないので言葉の抽出が必要となる。抽出する際に主題を生かすのか、異なる観点を与えるか、何かしらの選択が必要となるはずだ。吉川の場合は詩の内容が序詞的に「自分が詩を読む」行為に添えられていく。あえて心寄せをしないよう、感情をフラットに見せているのだろうか。四句は「詩を読む/ガザに」句割れを経て、詩の作者はガザに暮らす人であると示す。「たとえたる」「詩を読む」の最後のウ音のリズムは魅力的だが、韻律の豊かさに歌の内容が釣り合っていない。 アルアライールの死によって詩は物語に取り込まれてしまったが、「死ののちのみずからを凧にたとえたる詩」とまとめてしまうと、死が前提になってしまう。「If I must die」は現在形だからこそ、詩の中でいま声を発する生きている作者は、この後に訪れる死を強く意識しながら、今生きている人々へ語りかけるのではないか。詩の言葉は死者の語りではない。アルアライールは自らに訪れる死を受け入れていないし、死への抵抗は侵略への抵抗でもある。 「現代短歌」七月号のコラムで、川野里子はアルアライールの詩の精神性を読む。 「you must live」の「you」とは誰なのか。〈略〉凧がこの詩人の魂であり、詩そのもの、さらにはそのような精神を象徴するならば、「you」とはこの死を受け取った全ての人でもある。〈略〉「あなたは生きねばならない」には「あなたも当事者だ」と名指す力がある。死ぬのではなく、生きて「当事者」になれと彼は私達に遺言したのだ。「must」の強さはそのためのものだ。 川野は、東日本大震災が人間や文明の脆さを突きつけて、誰もが当事者であることを認識させた出来事だと言う。わたしも川野の考えに賛同したい。もちろん、出来事と直接向かうときに当事者性をどう考えるかは、歌人それぞれのスタイルで考えれば良いと思う。出来事ではなく詩を踏まえるならば、詩の精神性は無視できない。 |
||||||
| 2024年8月号 |
||||||
| 『アンソロジーが示すもの』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 「現代短歌」二〇二四年五月号のアンソロジー特集「Anthology of 40 Tanka Poets selected & mixed by Haruka INUI」を読んだ。乾遥香が選んだ歌人四十人の作品、それから、瀬戸夏子との座談会が三十八ページにわたって掲載されている。まずは印象に残った作品から。 あたたかい波打ちぎわで目を閉じて砂浜に頭から刺さりたい 今井心 ああふくらはぎ朽ちてゆくいづれみなペンギンとなる秋の夕暮れ 夜羽ねむる あっ、そのツイート ロンです はだし 一首目、今井の歌は回想的なゆったりとした時間の流れが続くと思いきや、四句の後半三音から急展開を迎える。「砂浜に頭から刺さりたい」はユーモアにしてはやや過剰で、わざわざ苦しまなくても良いのにそうせざるをえない感じを読み取った。あえて「あたたかい波打ちぎわ」と相反するような言葉を選んでいるように見える。 二首目の夜羽は四十人中ただひとりの文語旧仮名であった。初句を七音で読んでも句跨りで読んでもおもしろい。「ああふくらはぎ朽ちてゆく……秋の夕暮れ」だけでも詩情があるのだが、発想を入れてイメージが飽和したところを結句の「夕暮れ」に全て集約する。力技ではあるが枯れた技術をよくわかっている作者だ。 三首目はアンソロジーの最後に置かれた歌だ。どう見ても定型の規格外だが、句の欠落はこの一首だけなので、短歌として読みたくなる。体感としては二句で終わって残りは空白と言ったところか。空白は読者おのおのが補完すれば良いのだが「ツイート」であることが強調されるように思う。 画期的な企画ゆえにもう少し言いたい。四十人の作品をひとくくりにして何かを語れるだろうか。「現代短歌」では過去にも九〇年以降生まれのみの歌人にフォーカスしたアンソロジーが組まれたことがある。それと比べると、世代をキーに語るのは難しい。四十人のプロフィールを見ると世代や所属はバラバラで、外部情報から共通点を見出すのは難しいのだ。 乾ただ一人が選んだ、ここから語るのが良さそうだ。特に「mixed」とあるように、作品の掲載順番にも選者の操作が入っている点は過去のアンソロジー企画とは異なる。作品群への批評は乾の操作に対する批評として深められるのでは。と、思って先ほど引いた歌から共通点を考えてみた。 それなしでも歌が成り立ちそうな過剰な強調で音数を埋める。過剰さから、歌の背景にある苦しさの存在は感じ取れるが、はっきりとは読み取れない。この読み取れなさは読者だけの感覚ではないだろう。作者自身にとっても、どんな構造が私を苦しくさせているのか、どう対峙するかはっきりと見えていないのではないか。 つまり「見えなさそのもの」の存在が強調されたアンソロジーだったのではないか。乾は編集後記でアンソロジーの目的についてこう書いている。 アンソロジーを起点に、現状ほとんどルーティンとローテーションで回っている「短歌の仕事」が新たに分配され、若い書き手が起用される場面がひとつでも多く増え、その仕事それぞれがより社会的な影響力を持つことを私は望んでいます。 |
||||||
| 2024年7月号 |
||||||
| 『偶像との向き合い方』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 廣野翔一の第一歌集『weathercocks』批評会に参加した。パネリストは田中槐・堂園昌彦・上本彩加・平出奔(兼司会)の四名。この歌集は編年体で歌が並んでいたり、あとがきで作者自身がどの時期に何をしていたか大まかに書かれていて、作者の人物像を想像しやすいタイプの歌集……のはずなのだが、私は歌集の特徴を捉えきれずにいた。批評会を経て、自分で納得できる読み方を見つけられたので、その過程を書いてみたい。 秀歌の多い歌集だ。例えば〈少し見ていいですかって聞かれてる春の時間は使うしかない〉の下の句には愛唱性があり、強く惹かれる。ただ、こういった軽い口語文体の歌は文体に幅のある歌集の中では目立ちにくく、次のような作者自身を詠んだ歌の印象が強く感じられた。 作業員・廣野翔一、醜聞の特に無ければ赤だし啜る 冬の夜に遭えば驚く大男として真冬の夜をとぼとぼ歩く 堂薗は一首目に〈野口あや子。あだ名「極道」ハンカチを口に咥えて手を洗いたり〉(野口あや子『夏にふれる』)との類似を指摘したが、私としては、歌の性質は逆だと思った。野口は実際の行動から「極道」の見立てを引き出して作者像を変容させていくのに対して、「作業員」は実際のプロフィールを換喩的に述べるだけで自己のイメージに広がりがない。野口の歌とは異なり「赤だし啜る」が「作業員」に対して具体的なイメージを付加しないのだ。 堂薗はさらに、二首目から「大男」なのに繊細さがあるというギャップを読み取っていたが、男に「大」がついているためか、男は強くなければならないという古い価値観がひときわ強調されるように思える。ジョークとして消費されそうだが作者はそれでいいのだろうか。切実な気持ちがあるのではないか。そう思って歌集を読み直してみると、歌集のテーマを見落としていたことに気づいた。 釘付けにされたわけでもないのだが私はここで朝焼けを待つ 長男の座を丸釘のごとわれに打ち込みしその手付き思えり 序盤と最後、二〇〇ページほど離されて置かれるこれらの歌からは、建設関係の仕事という男性中心の世界にいながら、自分がいる世界に対して強烈な違和感を感じるているのがわかる。「釘付けにされたわけでもない」のに、「丸釘のごとわれに打ち込」まれてそこにいる自分。違和感から逃れようともがき続ける苦しさが、過剰な自己認識の歌に現れている。 「大男」は他者から見られる自身の姿、つまり偶像である。装丁を見ても、真っ黒で光沢のある表紙に描かれた目を細めてこちらを眺めている人間のデフォルメと、歌集タイトルが意味する「風見鶏」は、ステレオタイプを補強する力を暗示している。 「もがき続ける」をキーワードに置くと、パネリストの他の発言とのつながりが見えてくる。堂園の「社会詠・挽歌・吟行詠など、〇〇詠をすべてやっている」と、平出奔の「私・俺・僕といった人称の使い分けに『社会性』がある」という指摘、河野美砂子の会場発言「否定形がとても多い歌集」はどうだろう。 どれも歌集の傾向をざっくり述べたもので、その場で発言の深掘りはされなかったが、文体や題材の広さは偶像から離れるための試行の跡だった、と読めないか。言葉にする過程で偶像の存在を認めているが、肯定はしていないのだ。 |
||||||
| 2024年6月号 |
||||||
| 『モダリティを読む』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
このごろはオフラインの短歌のイベントが増えてきて嬉しい。二月二四日に行われた「『キマイラ文語』を読む会」は盛会であった。登壇者のひとり、桑原憂太郎の発表から取り上げたい。 アメリカのイラク攻撃に賛成です。こころのじゅんびが今、できました 斉藤斎藤『渡辺のわたし』 桑原によれば、斉藤のこの歌にはモダリティ(発話者の心的態度)がないのだという。発言を聞いた瞬間は、新しい観点を得られた気がしたが、新しさを感じた以上に深い理解はできていなかった。時間が経って、ようやく思考が整ってきた。 「モダリティ」は日本語だけでなく世界中の言語にも当てはめられる通言語的な概念である。『現代日本語文法4』(日本語記述文法研究会=編・くろしお出版)によれば、文章は命題(文が伝える事柄)とモダリティ(発話者による事柄の捉え方、心的態度)の二つに整理できる。日本語でいえば、例えば「明日は雨だろう」の「だろう」の推量のように文末の文節にモダリティが現れやすいとされる。 桑原は二〇二二年の現代短歌評論賞受賞作「口語短歌による表現技法の進展」において、口語の文末処理の一つの方向性としてモダリティの活用を挙げて、「作品を独り言や他者への発話といった話し言葉で叙述する」と定義した。 また、前述の斉藤の歌については「擬似的な対話形式を構成したことで〈主体〉の発言の欺瞞性や信憑性がうかがわれる作品」「果たして本心なのかそうでないのかについて、読者は判断を保留しなくてはいけなくなる」と述べ、自然な対話ではあり得ないテクストから「モダリティがない」と判断していた。桑原の会場での発言はこの部分を拡大したものだろう。 わたしは、斉藤の歌を完全に「戦争に反対している」と読んでいたので、論を読み直して、判断を保留にすると書かれていて驚いた。また、テクストに書かれた主張と逆の主張を読み取る以上、そこに心的態度がないと読むには強い違和感があった。 桑原はモダリティを、本来のモダリティよりも狭く捉えているのではないか。心的態度には発話者のあらゆる態度が含まれる。『現代日本語文法4』にある「簡略化して示した」というマトリクスだけを見ても、〈叙述・疑問・意志・勧誘・行為要求・感嘆〉といった表現類型を縦軸に、横軸に〈評価・認識・説明・丁寧さ・伝達態度〉が掛け合わされる。一まとまりの文章には必ず命題とモダリティが存在するのだ。斉藤の歌を見ると「です」「できました」から叙述・丁寧さを表すモダリティを読み取ることができる。 通言語的なモダリティは心的態度の部分的・表層的な整理に向いている。しかし、短歌のようなハイコンテキストな文章を読み解くには、何がこの歌のモダリティを作り出してるのか、という問いも必要なのではないだろうか。 あらためて斉藤の歌を読むと、恐ろしい感じがしてきた。「アメリカのイラク攻撃に賛成です」は他人が書いた文章のようで「こころのじゅんびが今、できました」の平仮名に開かれた文字は弱々しく、まるで強制されているようだ。過剰な丁寧さが怖い。正しく読み上げないと殺されそうだ。 |
||||||
| 2024年5月号 | ||||||
| 『思想は違うのか』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
個人的な短歌観なのだけれど、どれだけ強烈な個性のある歌集であっても読者の主観をゼロにして読むことはできない。他者の声を介して、自分の認識を発見することがあるし、それが歌を読む体験の本質だと思う。だから歌集を読む時は、歌を読む私と歌の作者だけの一対一で考える。同じ歌を読む他の読者の評価が、私だけの体験に干渉しないようにしたい。 あらためてそう思ったのは、乾遥香による水原紫苑『快樂』の書評(
「現代短歌」二〇二三年九月号)を思い出したからだ。〈共和國につぽんが來むその日までいのち在らむかわれも短歌も〉などの歌を引きながら乾はこう述べる。 乾は作者だけでなく「前川佐美雄賞」「迢空賞」の選考結果や読者の受け取り方に対して疑問を投げかける。たしかに、歌の主張はシンプルで、わからないところが何もない。結句の発想もあえて取り立てるところはない。ただ歌集全体をみると、次のような良い歌もあり、仮想敵に反対するための結論が先にあって、その後に歌を選んでいるのではないか、とも感じた。 わが罪はそも何ならむ一房の葡萄のごとく在りしことのみ 鳥もまた狂氣は在らむ飛ぶことをうたがひにつつ星に近づく 罪の意識は近年の水原の歌に通底する意識であり、二首目の鳥は水原自身のメタファーと読める。「共和國につぽんが來む」の歌も遠く離れていないだろう。歌集全体に歌が厳選されていない印象はあるが、モチーフにまとまりのある歌集だ。 ちなみに私は、水原に対して、自分とは遠く離れた位置に立っているな、と過去に感じたことがある。その時の発言を引く。 佐太郎の歌は、この上なく美しい。だが、その美しさにはあらかじめ断念されたものがある。〈略〉希望の無い現代に生きる若い歌人たちが、佐太郎をどう読むのか、ぜひ聞いてみたい。 水原紫苑「あらかじめ断念された夢」 (「現代短歌」二〇一九年九月号) 悪気はないと思うが「希望の無い現代に生きる若い歌人たち」と言われてしまうとがっくりくる。だから『快樂』を読むときに先入観を消して、フラットな気持ちにするのは少し大変だった。 同じ水原の歌集でも『天國泥棒』はスッと向き合うことができた。毎日一首というコンセプトが、たしかにそこにいる作者の存在を示してくれる。 犬の毛にふるるすなはち過去現在未來繫り球となりたり 三月三十一日(木)『天國泥棒』 直線的に意識する時間の流れからふっと離れて、すべてが球となる感覚に惹かれる。後半のイ母音のリズムには心地よさがある。やわらかな毛の手触りから、原初的な記憶が呼び起こされる。 歌の読解は常に読者の主観的な語りである。何が作者と自分の思想の違いを生んでいるのか、語る余地はあるのではないか。 仮想敵を置くのは便利だが、敵の範囲を広げすぎると分断は増えてしまう。侵略をやめろ・虐殺をやめろ・差別するな、といった切実で素朴な願いを発信できて、多くの人と共有できて、世の中が少しずつ変わっていく現在を見ると、まだ現代に希望はあると思っている。 |
||||||
| 2024年5月号 |
||||||
| 『句切れがわからない』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
実は「句切れ」がよくわかっていない。三省堂の『現代短歌大辞典』を見てみると「短歌を構成する五句のいずれかで、文が切れること」(島田修三)とあり、詳しい解説はない。連作を作るときに、同じ句切れが続かないようにしたり、句切れによるリズムの違いや読まれ方の違いは感覚的に認識しているが、現代の句切れは定型ほど分かりやすいものではなく、読み手の感覚に左右される曖昧なものだと考えている。 角川「短歌」二〇二四年三月号では句切れの特集が組まれた。古典と現代に時代を分ける、初句切れから順番に句切れなしの歌まで分ける、という形で各論が展開された。それぞれの論はおもしろかったが、全体を見た上での総論がなく、特集タイトル「句切れの真相」は期待を上げすぎている感じが否めない。むしろ、真相までの遠さを感じる特集であった。特集の最後に大松達知の「句切れは難しいなあ」という呟きがあるように、今は各論をもっと積んでいく局面にあるのだろう。 特集で初句切れを担当した上條素山の論を掘り下げてみたい。歌を引く。 動じちゃう 底辺バイトと言われたら 化粧を工事と喩えられたら いーじゃんいーじゃん 春だけ電車が止まる駅 すげーじゃん 梅満開の庭 群司和斗『遠い感』 まず、上條が初句切れの歌としてこれらの歌を引いていることに驚いた。上條は二首目について、「いーじゃんいーじゃん」で初句切れ、「すげーいじゃん」で二回目の句切れがあると読んでいる。「文が切れること」で考えるならば句切れである。さらに一字空けまであり、切れているとしか言えない気がする。が、わたしとしては句切れは「すげーじゃん」の四句切れただひとつだけであった。「いーじゃんいーじゃん 春だけ電車が止まる駅 すげーじゃん」までが概念的な駅への驚きで、ゴツッとした表記の「梅満開の庭」が唐突に今この瞬間に見ている光景を立ち上げる。 「じゃん」のリフレインが詠嘆のフレーズとして新鮮で、心の声から視覚的な描写に傾く歌に心の高鳴りを加えている。 一首目は「動じちゃう」の初句切れの感じが強い。初句と三句で一字空けがあるが先ほどと同じように言葉の塊を見ていくと「たら」は並列である。切れ目と言うよりは「動じちゃう」理由を並べている。ここでわかるのは、一字空けは文の切れ目とは言えないと言うことだ。現代の口語は従来の句切れから離れつつあるのではないか。 上條は、「玉の緒よ絶えねば絶えねながらへば忍ぶることの弱りもぞする」(式子内親王)から句切れの重なりが歌全体の印象を変えていく様子(上條の言葉では「有機的な全体を成す移ろいの相」)を感じ取り、現代の口語の歌については「口語の特徴として、言葉の流れの奔流により言葉が大きい塊を成しやすい」と言う。ここでの「大きな塊」とは、例えば一首目の「動じちゃう」や「いーじゃんいーじゃん
」が作者が発する声そのものに近く、その後に続くテクストは地の文に近い、というように言葉の連なりが性質の違いによってわずかに分断されることを指すのだろう。 口語と比較して、文語の歌は言葉のひとつひとつが磁石のように感じる。言葉を結束させる力があるために、句切れがあっても歌は一首の塊(上條の言う「有機的な全体」)であり続ける。文語の佇まいをベースに現代の言葉を取り入れるのとは異なり、口語の歌は言葉の磁力のゆるさを逆手にとって発展していくのかもしれない。 |
||||||
| 2024年3月号 |
||||||
| 『それぞれの読み方で』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
あんたがどっか行こうもんなら/道という道ぜーんぶかきあつめて/火つけて焼き滅ぼしたるからな! 大井は年間時評「2023年の短歌界」で、原作の「君が行く道の長手を繰り畳ね焼き滅ぼさむ天の火もがも」(狭野茅上娘子)から「天の火もがも」が削られている点を快く思わないが、歌の心を変えずに大胆に翻訳することで現代の多くの人に伝わる共感性を得ていると指摘する。 削られた言葉に注目してみよう。翻訳という形で短歌の文字数制限からは離れていながら、言葉の省略がある。ここから著者の意図を読み取れる。「天の火」の醸し出す神話的世界は現代にはなじみにくいのだろう。翻訳では「天の」ニュアンスがなく「火つけて」で火を付けるのは言葉の発話者たる主体である。そうすると「火」は人間の存在を超えた天から降り注ぐ火ではなく、手に持てるような小さな火を想像させる。そうすると「焼き滅ぼしたる」は大袈裟で、現実とは離れた大きなスケールの言葉なのだが、こちらを残したところに「歌の心」を抽出しようする佐々木の意志を感じ取れる。大雑把な翻訳に見えて、文化の取捨選択が緻密に行われているのだ。 前田は同号の時評「『万葉集』の沼」で、佐々木が翻訳したテクストではなく、ベストセラーとなっている事象を見て、万葉集をもてはやして良いのかと苦言を呈す。 『万葉集』は日本文化の古典であると同時に、きな臭い共同幻想構築のツールであるというカルマを背負っている。〈略〉今の若い世代の『万葉集』贔屓は過去と切り離されているように見えるが、〈われ〉が負の方向の〈われわれ〉に同化していく時代の不気味さには、敏感であって欲しい。 前田の意見には同意できない。ここで言われる「過去」は明治以降の万葉集の利用のされ方であり、「古典であると同時」ではなく、積み重なった歴史のごく薄い表層である。佐々木の翻訳はエンタメであり、これまでの歴史から見ればタブーに触れている。だからこそ、こんな読み方もありなの?という意外性が話題となり、ベストセラーになったのではないか。 佐々木も読者も「過去」と読み方が異なるが、万葉集の歴史から切り離されているとは言えないだろう。むしろ、「過去」を踏まえろという声は読み方の多様さを認めようとしない圧力であり、この圧力こそが「〈われわれ〉に同化していく時代の不気味さ」なのではないか。 全体主義的な〈われわれ〉を万葉集の利用の歴史だけで語ろうとすると、原因と結果がごちゃ混ぜになって問題の範囲が局所的になる。中野敏男『詩歌と戦争 白秋と民衆、総力戦への「道」』によれば、植民地の拡大によって故郷から離れて暮らす人が増えたことが契機となり、童謡や民謡が歌う郷土への哀愁が植民地主義の肯定に利用され、価値観の違いを排撃する総力戦へと傾いていったのだ。 |
||||||
| 2024年2月号 |
||||||
| 『ラップ的な韻律』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
もう一年前になってしまうが、二〇二三年二月「ねむらない樹 vol.10」で発表された第五回笹井宏之賞大賞受賞作・瀬口真司「パーチ」から感じた新しさと疑問をようやく言語化できたので書く。 渋谷駅のみんながしてるイヤホンは二〇〇二年のW杯 萬緑の GAME BOY のディスプレイをみんなで覗いたのを覚えてる
君の身体は君のものでも人生は人生は天皇に生きられて
国民の再−統合の再−想像 SPACE MOTHERSHIP が WARP 瀬口真司「パーチ」
笹井宏之賞は五人の選考委員のうち一人が歌人以外となるゲスト枠があり、第五回はラッパーのMoment Joon(モーメント・ジューン)が参加した。「パーチ」へのコメントを引く。
この作者が見ている今の日本というものはたぶん過去の二つの栄光、光の上に立っている影みたいな感じじゃないかなと思って。戦前の天皇制の上に建てられた日本と、その戦前の日本と地続きの高度成長期の日本があって。この二つの栄光の後で色が褪せているのに、その二つを鏡みたいにして自分を映しながら今を生きている、現在の日本があるんじゃないかなと思って。 光のメタファーの光源となる「栄光」は経済的な成長にフォーカスした言葉で、アイロニカルに捉えている。たしかに「パーチ」は、過去の「栄光」に照らされる停滞した現在を批判的に見ている。
二首目の「萬緑の GAME BOY」は世代を示すアイテムだ。連作の主体の年齢は九四年生まれの作者より一回りほど上だろうか、二〇〇〇年ころに二〇代と思われる。そうすると連作冒頭の「渋谷駅のみんながしてるイヤホンは二〇〇二年のW杯」は、就職氷河期の苦難から目を背けさせる構造への批判と読める。群衆が一体となって同じ体験をする様子を体言止めで過剰に強調し、画一化への違和感を示している。ここでの国民の熱狂は、五首目の「国民の再−統合」の「再」が指すように戦前戦中の翼賛体制や天皇制とも重ね合わさる。
「国民の再−統合の再−想像 SPACE MOTHERSHIP が WARP」からわかるように、「パーチ」では連作の象徴となる歌に母音のパターンを過剰に繰り返すラップ的な韻律が見られる。ソリッドな名詞がプツプツとリズムを刻む。
ヒップホップカルチャーの主要な要素として体制へのカウンターの歴史を持つラップが、その文化を保ったまま短歌に持ち込まれている。韻を踏む形式を短歌の定形に当てはめただけでなく、ヒップホップの文化の継承がある。これが抜群に新しい。
そして弱点でもある。
「パーチ」は主体の属性(氷河期世代・ヒップホップ)を示すのに歌数が割かれている。カウンターとしての立ち位置が見えるが、具体的な主張は読み取れない。主体と構造の中間がすっぽりと抜けていて、主張に先立つ体験が見えないのだ。天皇制批判のように見えて、批判する姿勢を匂わせるだけ、つまり何も批評していないのではないか。 集団的な熱狂や経済の停滞に注目させる歌と天皇制をイメージさせる歌を一つの連作のなかに置いて文脈を繫ぐのは、ステレオタイプな日本人文化論(集団主義的な行動の原因を文化によるものとする考え方)に陥る危うさがある。本当に作者≠主体の形を取る必要があったのか、疑問である。 |
||||||
| 2024年1月号 |
||||||
| 『内面化されるヒエラルキー』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
今月は『『女人短歌』小さなるものの芽生えを、女性から奪うことなかれ』(濱田美枝子)を読んで、過去の歌壇から見える男性優位性を考えていた。 歌誌『女人短歌』(一九四九年〜一九九七年)には、五島美代子・長沢美津・葛原妙子・中城ふみ子・阿部静枝・生方立つゑ・森岡貞香など、戦後を代表する多くの女性歌人が集まり、終刊までに六二四冊の「女人短歌叢書」が刊行された。濱田の著書では、創刊と終刊の経緯や主要な歌人の功績を、歌誌そのものの内容に触れながら整理しており、読み応えがあった。 特に、創刊に至るまでの内部のメンバーの葛藤と周囲の反応に注目した。 五島美代子は創刊にあたって「女人」の名に難色を示した。戦前から男性に混じって歌壇で活躍していた五島には、女性だけの歌誌が時代錯誤に思えたという。 外部からの反発もあった。近藤芳美は文学は男女平等であり、女性だけで集まるのは古い考え方であると、創刊に反対し、性別の偏りによる言論の閉鎖性を憂慮した。しかし『女人短歌』は男性歌人や小説家など外部からの批評を積極的に掲載し、女性だけに閉じない誌面を作りつづけた。 折口信夫は『女人短歌』第六号に「女人短歌序説」を寄稿した。濱田はこれをエールだと捉える。一部を引く。 ここで女流の歌が大いに興るだらう。此は希望を含んだ期待であるあなた方女性の方々が協働して、男の歌壇に認めさせるといふ劣等感に基づく気持ちを捨てて、日本の歌壇のために、こゝで新しいものを寄与しようといふ気になつてほしいものだ。 折口信夫「女人短歌序説」 多様性と多文化が当たり前に言われる今からみれば、男女二元論的な考えであり古めかしく感じる。ただ七十年前という時間を差し引いても、まだ向き合わなければならない、現在も繰り返されている差別があるような気がする。 当時女性の歌人は少数であったという。性別を抽象化して考えると疑問が見えてくる。「少数派が集まって少数派のための場を作る」に対して、どうして「文学は全員に平等」を理由に反対され、少数派が「多数派に認められたい劣等感」を持っていると外から言われてしまうのか。 五島と近藤の考え方は、端的に言うなら「良い作品は作者の属性と関係なく評価される」というもので、作品が先にあることを前提にしている。性差がないように見えるが、一方で、作品を作る環境や作品が批評される「場」へのアクセシビリティの差が考慮されていない。思想と実態の差がなかったことにされている。 「場」について、多数派と少数派を、例えば「都市と地方」に替えると異質さが分かりやすい。もし地方で「場」を作るとすると「文学は平等」が反対の理由に上がることはなく(むしろ「地方の特色を活かす」のような形で称賛されて)、閉鎖性だけが問題になるはずだ。 多数派を強者として考えると、新しいヒエラルキーを作るとは「強者がしなくても良いこと」である。弱者あるいは強者のなかでサバイヴしてきた弱者が、同じ弱者に対して「新しい場を作らなくてもいい」と言うのは、弱者の排除である。 男性を前提とするような「女人」は一九四九年時点でも時代に逆行する古い言葉であった。しかし排除へのカウンターとして「女人」ほど直接的な言葉はなかっただろう。性差による差別は、性差をなかったことにしてもなくならないのだから。 |
||||||
| 2023年12月号 | ||||||
| 『規範の正体』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 『うたわない女はいない』の出版記念トークイベントを観た。この本は、読売新聞のウェブサイトに掲載された「三十六人の女性の歌人が『働くこと』をテーマに短歌とエッセイを紡ぐ」という企画を、中央公論新社が今年七月に書籍化したものである。 トークイベントでは執筆者の飯田有子と十和田有(ひらりさ)が対談を行った。まず飯田は「真夜中の疲れたOLが読む」という本のコンセプトを受けて、読んだ人を励ませるように意識したと言う。 誤字憎し時にはたのし 淡々麺、幸子明太子、オレンチジュース 飯田有子「オレンチジュース」 職場での出来事があたたかく感じられる連作から引いた。校正者として文字ひとつひとつと向き合う緊張の時間に、ふっと息が抜ける瞬間があるのだとわかる。連作の後にあるエッセイでは、産休・育休によって起こる働き手の減少が忌避された九〇年代と、祝福の言葉を素直に言えるようになった現代との違いが軽やかに描かれる。 飯田は、かつて職場で受けた理不尽な体験の五割は女性であることに由来するものだったと話し、現代はここまでよくなりましたよ、と作品によって示せれば想定の読者への励ましになるのではないか、と本に収録された作品の背景を述べた。 十和田は、自身の創作の志向について、フェミニズムとの結びつきや、異性愛規範に囚われない意識があると話した上で、飯田の歌集『林檎貫通式』(二〇〇一年)をいま読んで「規範に収まらない意志を感じた」と言う。 十和田の感じた印象に共感しつつ、規範に収まる/収まらない、この二つの区分を見ると居心地の悪さを感じる。なぜなら「規範」を先に仮定して置いてしまうと、差異を示すだけではなく、善と悪の区分を意識してしまうからだ。 『林檎貫通式』について飯田は、女性でいることが好きではなかった自分が、女性を引き受けるために過剰な女性性を歌にしたとも話す。嫌いなものを嫌いと認める。ここには内面化された「規範」があるのではないか。九〇年代の過剰な女性性が、現在もなお「規範に収まらない意志」を感じさせるなら、世の中が確かに良くなっているが、規範は変わっていないのではないか。 本のテーマ「働くこと」について、規範の意識と同じく善悪の間でゆれる感覚を捉えた短歌やエッセイに注目した。 将来の夢にどうして職業を書かされるんだろう、何になってもいいはずなのに。 手塚美楽「【業界最遅】22卒就活報告記」 本当は「働い」ていてもいなくても、生きているだけで「社会参加」している、という事実がちゃんと理解されるような世界になってほしいと思っている。 橋爪志保「大丈夫なアルバイター」 自分を自分のままに認めるために、規範から離れていると考えなければならない、それは孤独だ。人を孤独にさせる構造を作る「規範」とは端的に言えば、全体主義の影である。戦前の隣組のような、上から強制的に決められた繋がりによる「逸脱するもの=悪」を炙り出す相互監視の仕組みの亡霊が、現代まで残っているのだ。 実体的な「規範」は存在しない。良くするために必要なのはそこにある差を正しく捉えて区別することで、善悪の評価による分断ではない。 この本は自己の肯定と否定の間で揺らぐ多様で生々しい実体的な人間の姿を読者に見せる。飯田の言う励ましは孤独を作る亡霊を日差しのもとに晒す力になるだろう |
||||||
| 2023年11月号 |
||||||
| 『道具とスタイル』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
短歌研究二〇二三年八月号の特集「AI短歌の時代に備えよ」を読んだ。歌人二十人が生成AIソフト「ChatGPT」にテキストチャットで指示して短歌を作る試みが新しかった。AIが出力したそのままの歌と作歌を指示した歌人を併記して左に引く。 紫陽花咲き外套纏いて黙り込めば雨に濡れたまま静けさ満ちる (栗木京子) 過ぎ去りし命のかたちよ幽霊の吟こころに残りて記憶となる (平出奔) 一首目、たどたどしさはあるが「雨に濡れたまま静けさ満ちる」はなかなか良いではないか。平出による二首目は企画中のベスト一首にあげたい。短歌に最適化されていないAIが二句切れの詠嘆をするのには正直驚いたし、「こころに残りて記憶となる」下の句の使い方も良い。 どちらもAIがセロから歌を作ったわけではない点に触れておきたい。栗木はAIと何度かやりとりする中で、詠み込んで欲しい単語と使ってはいけない単語を指示している。平出は「最終的にはシンプルに単語だけでいくつもテーマを与えて大量に生成させて比較的マシなものを選ぶことにした」と、両者の歌とも語彙の選択に指示者の意識が入っている。 座談会で、坂井修一は「短歌の危機」として、そう遠くない未来に一首単位で見れば新聞歌壇や短歌大会で入選できるレベルの作品が作れるようになること、ChatGPTを辞書のように道具として使うことが当たり前になると予想する。AIの作品の語彙選択に作者の意識が入り、さらに作歌の技術が上がったなら、上にあげた歌のとなりにある(歌人名)の括弧を外す人が主流になるのだろうか。そんな気はしない。大量の作品を読んで自分の趣味にあった短歌を見出す作業をやってのけられるのは、何か特別な理由がある人に限られる。 語彙を絞ってプログラムに短歌を作らせる方法で言うなら、AIよりもっと素朴で直接的なやり方がある。二〇〇八年に佐々木あららが開発した短歌自動生成プログラム「星野しずる」は、佐々木自身によって選ばれた五五〇の語彙と句切れの位置や音数を組み合わせたいくつかのパターンを入れたアルゴリズムから歌を出力できる。ここまで選択が絞られると、歌の背後にうっすらと個性が見えてくる。 良い歌を見出す・語彙を絞るとは、本質的には作者の歌の個性の現れであろう。連作や歌集のように大きなまとまりを扱うほど、個性を保つのは難しくなる。自らの意志を持たないAIには、万葉風とか啄木風といった過去の模倣が限界である。 個性をスタイルと言い換えてみると、言葉の見通しが良くなる。セオドア・グレイシック『音楽の哲学入門』(源河亨・木下頌子 訳)の「耳に触れる以上のもの」という章から引く。 すべての音楽が芸術であるのは、どの音楽もスタイルをもつからである。スタイルを持つことが意味するのは、どの音楽もそれを育んだ伝統に積極的に携わろうとしている、ということだ。伝統への携わり方には、それを受け入れるというかたちも、それに抵抗するというかたちもあるが、いずれの場合でも伝統が現れている。 既に存在するものや変えがたい過去を、受け入れたり抵抗したりする。これは人間だけの営みだ。AIによる「短歌の危機」はごく限定的だろう。AIが人間を作れるレベルになるまでは静観で良い。 |
||||||
| 2023年10月号 |
||||||
| 『守られることへの無自覚さ』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 七月に刊行された第一歌集を読んでいて頭に稲妻が走るような感じがした。まずは長谷川麟『延長戦』から。 空振ったけどもこれは悪くないスイング 春は一気に迫る 屋上のドアがつめたい 生きてたらどれくらい良いことがあるんだろう 一見すると、ゆったりとした会話体ベースの口語文体だが「春は一気に迫る」「屋上のドアがつめたい」のような言葉を切り詰めた句に光るものがある。一回のスイングと繰り返し訪れる春、背中でもたれるドアの冷たさと自分の将来のこと。一首の中に瞬間と永遠の対比がある。過去よりも未来へ意識が向いているが、未来にあまり期待していないようだ。 歌集タイトル『延長戦』を思いながら詠んでいくと、過去よりも未来の方が長いような気がしてくる。過去を回想する歌に過去への執着がない。過去が美化されることもなく、思考がそのまま差し出される。それがあまりに生々しく、新しかった。 句の切れ方にも注目したい。一首目を読んでいると、四句の句割れから少し間を空けてから時間の対比に気づく感じがする。同時に、会話体から書き言葉の方へ文体が移り変わっていくのを感じないか。 二首目は反対に二句切れを挟んで書き言葉から会話体へ移行する。句切れや句割れを挟んで会話体と書き言葉を滑らかに行き来する。全体的に軽い言葉の中にあるわずかな重みを感じたくなるような、味わいのある文体である。 セックスは確か一回したようなしてないような春雨のなか 追うものも追われるものも勝ちたがる直線、それは濃密な生 ぼんやりとした春の雨に身体感覚が溶けていく性愛の歌がある。他者の姿が淡いのだ。野球のイニングが進むような直線的 ・ 一次元的な時間の感覚だろうか。あるいは他者に干渉せずに生きる、線が交わらずに並行するような感覚だろうか。 同時期に刊行された塚田千束『アスパラと潮騒』は長谷川とは対照的だった。長谷川が抽象化した「濃密な生」を、塚田は他者との関わりに触れながら具体化する。 虐待のニュースに母の名は見えずそこに私の名があるような 我という容れ物まぶたをこじあけてこじあけられて冬の雨降る 雨は雪にしなだれかかり晩冬の屋根を洗って 言葉では無理 クロワッサンばさばさたべて白衣からうろこを落とすよう立ち上がる 屋上は胸すかすかとはためいてだれにも会えぬ日々やわらかい 「私の名があるような」他者が自分であるかもしれない、他者と自分の線がときどき交じるような感覚。「こじあけられて冬の雨降る」突き刺さるような冬の雨。塚田の歌集は、他者との関わりのなかで生きる自分の姿を詠んだ歌に特長がある。 医師の姿や母の姿のようにいくつかの役割を行き来するのは大変なことだ。自分自身のかたちを守るために固い鱗をまとい、ドアにもたれることなく風のなかにひとり颯爽と屋上に立っている。 現実は脆い。気を抜けば一瞬で崩れてしまう。長谷川の歌集から感じる絶望も期待もないフラットな世界は、公正なルールのもとで競い続ける安全な世界なのかもしれない。長谷川の淡さは守られていることへの無自覚さから来ているのではないか。歌の形式を介して無自覚さを自覚しようとする試行錯誤が「延長戦」なのだろう。 |
||||||
| 2023年9月号 |
||||||
| 『盗用的な短歌技法』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 今月は「作者自身で考えた言葉がまったくない歌」について考えたい。 残響音があるうちは、新たに鐘をつかないで下さい 広島市 斉藤斎藤『人の道、死ぬと町』 May Peace Prevail On Earth 世界人類が平和でありますように 鈴木ちはね「そばの花」 斉藤の歌は、平和の鐘の近くにある看板の文章をまったくそのまま歌にパッケージしている。鈴木の歌は昨年「うたとポルスカ」のウェブサイトで発表され話題になった連作から選んだ。観光地でよく見かける白いポールに書かれている言葉(どうやら新興宗教に由来する言葉らしい)を、ほぼそのまま短歌として切り取っている。 どちらも手法は似ている歌だが、歌の効果がまったく異なる印象があるので、ここを言語化したい。「盗用的な手法」という点では、短歌に先駆けて七〇〜八〇年代の現代美術にあらわれた「アプロプリエイション」という概念が補助線に使えそうなので、二つの歌に当てはめられるか考えてみる。美術評論家:松井みどりの『アート:”芸術”が終わった後の”アート”』によれば、アプロプリエイションの効果は次のようにまとめられる。 消費社会に溢れる「幸福」のイメージを別の文脈に置くことで意味を変化させたり、あるいは、人間の身体や階級や美についての既成の価値観を媒体している表象の洗脳的な機能を暴き出したりするための批判的な方法なのです。 「消費社会に溢れる」ほどではないが、すでに身近に存在してしまっている「表象の洗脳的な機能を暴き出したりする」点は鈴木の歌には当てはまるのではないか。平和であってほしいか?という問いは否定しがたがく、それ故に個別のケースを考えない全体主義的な「洗脳」のドアをノックしてくる。短歌でない言葉を短歌の場に置くと過剰な注目が生じて、そこに疑問が生まれる。一見して無害な言葉に隠されてきた不気味さが、ありありと炙り出される。 一方で、斉藤の歌は、借用元の言葉が鐘の説明のためだけに作られた「目的が一つで誰が見ても明確」なものなので、鈴木の歌のような言葉に隠された性質の暴き出しが起こらず、批判的なニュアンスが感じられない。一首全体が象徴詞として新たな姿に変わっている。例えば「残響音」を「放射能」に、「鐘」を「核兵器」という具合に、元の言葉から離れた性質を持つモチーフに置き換えて読んでもいい。ただ、なんだろう、好きな歌なんだけど読みがうまく誘導されている気がする。 詩性を意識せずに作られた(と、思われる)言葉を、象徴として受け取れてしまうとはどういうことか。おそらく斉藤は、消え去ることがない過去を「広島市」の体言止めに乗せて強調している。偶然とはいえ看板の言葉から短歌を見出すだけでなく、わかりやすい短歌の技法(体言止めと語順の良さ)まで入ってしまったのはちょっと出来過ぎだと思う。 斉藤は借用こそしているが、言葉が置かれている文脈は「平和の鐘」から想像される大きな文脈の外に出るものではない。ここが鈴木との大きな違いだろう。斉藤の歌はオマージュの一形態と言った方がいいかもしれない。 オマージュといえば、短歌にはすでに本歌取りがある。もしかすると斉藤は本歌取りの制約を「短歌に限らないすべての言葉を本歌にできる」そして「句数無制限」にまで拡張してしまったのではないか。 |
||||||
| 2023年8月号 |
||||||
| 『なぜおもしろいのか』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 二〇二三年は斎藤茂吉の没後七十年となる年だ。「現代短歌」三月号では「ボクらの茂吉」という特集が組まれた。そのなかの座談会「『つきかげ』はなぜおもしろいのか」がおもしろかった。 参加者は小池光・花山周子・山下翔。茂吉の遺歌集『つきかげ』収録の約千首からそれぞれが七十首を選び、そのうち三人全員が選んだ歌が十一首もあったという。世代や系譜の異なる三名でこの結果は驚きである。全員が選んだ歌から、いくつか見てみよう。 われ病んで仰向にをれば現身(げんしん)の菊池寛君も突如としてほとけ 菊池寛の急死の知らせを受けて作られたと言われる歌。茂吉としては真剣な歌なのかもしれないが、結句はちょっと変わっている。山下は「げんしん」のルビについて「カンクン」と重なるような音の響きがあると指摘する。小池は、寝ている茂吉と垂直に交わるように菊池寛の姿がポンと現れる様子に「空間の造形」を感じると言う。 目のまへの賣犬(ばいけん)の小さきものどもよ生(せい)長(ちやう)ののちは賢(かしこ)くなれよ 茂吉の語りかけが不気味だ。「賣犬(ばいけん)」は売られている犬を短く言っているのだが、子犬の可愛さのような誰でも感じる要素がごっそり抜け落ちていて、生殺与奪の権を他者に委ねている怖さがある。花山は「のちは」の「は」から優しさと悲しさを感じ取ったが、端的に言えばあわれみのニュアンスなのだろう。 どちらの歌も茂吉の感じ取り方が異様なのだが、助動詞がなく漢語を多用した乾いた歌いぶりからは、茂吉が自身の異様さに気づいていないように見えてしまう。一人称の短歌の構造ゆえか、ツッコミが不在のシュールなギャグのようでもある。異様さに無自覚な主体におもしろさを見るのは、八十年代の劇画調の漫画が新しいギャグのモードとして発掘され、ネットミームにな った感覚と似ているだろうか。 そう思って小池の最新歌集『サーベルと燕』を読むと、〈青森の吉幾三がつくりたる小学校の校歌よき歌〉というあっさりとした歌が目に止まった。全体に力みのない調べ、吉幾三の枕詞としての「青森の」は案外だれもやったことがない気がして、不思議と新鮮な歌だと思った。 ここまであげた小池の歌も茂吉の歌も、歌集の主題とはやや遠く感じる歌だ。茂吉の歌の背後にある戦争を挟んだあとの絶望感や、あるいは小池の歌集で触れる親しい人の死とは遠い題材である。それでも歌集から外せない歌だと感じた。言葉の新しさは必須だが、それだけでは説明できないところがある。 もう少し、共通点を考えてみよう。小池の歌は、先にあげた茂吉の歌のような題材の異様さはないが、なんでこれを歌にしたのか、と思わせる点では主体の注目の仕方が異様だ。茂吉と同じく、主体の感じ方の異様さに主体が無自覚である(と読ませてしまう)と言える。 菊池寛の死も、売られている子犬も、吉幾三の校歌も、どれも主体とは関係なく起こった/そこにあったものだ。関係のなさでは、読者も主体と同じである。だから、歌集を読んで行って、本当にあったものに囲まれていくと、より切実に主体の体験を追体験できてしまうのではないか。 主体の無自覚さは、オーケストラの指揮者の呼吸や腕を振る音のように作品に影響しないもの、技法とは言い難いものだが、歌集全体の真実性や切迫した感じを増幅させる効果がありそうだ |
||||||
| 2023年7月号 |
||||||
| 『光の当たらない面』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
新潮社のPR誌「波」三月号では、書評家の三宅夏帆が、岡本真帆・上坂あゆ美・木下龍也らの歌に触れながら、短歌ブームを紹介していた。山田航の歌壇時評を読みながら論点を探ってみよう。 まず、三宅は自身の観測を整理する。いわくSNSの普及によって、短歌との関わりが薄かった人たち、特に「ひと昔前だったらミニシアターに通ったりレコードを集めたりすることを楽しんでいそうな、サブカル系ーーちょっと文化的でお洒落な趣味を持つ友人たち」の間で短歌が流行っているのではないかと言う。 三宅のエッセイに対して、山田航は「朝日新聞」二〇二三年三月十九日の短歌時評「肯定からの逃走」で反応した。 時評では、三宅の言う「サブカル系」のニュアンスに「オタクカルチャーとの対比で形成された都会的な大衆文化」を捉えて、短歌ブームを「『短歌のサブカル化』という文化現象が表面化しているとみた方がいいのかもしれない。」と見解を示す。 三宅はほかに、木下龍也の『あなたのための短歌集』に触れて「現代短歌の特性」として、「日々の合間にさらっと楽しむことができる言葉の大喜利であり、疲れた読者を肯定する」点を挙げる。 これに対して山田は、歌の効用のひとつに焦点を絞り過ぎていると感じたのだろうか、「実用的なものとして受容されてしまうのは、作風の固定化をもたらす危険をはらむのではないか」と、反発を見せる。山田の時評はこう締め括られる。 魅力を伝えるための好意的な表現として書かれているのだが、私はこれをむしろ現代短歌への鋭い批判のように受け取った。 山田の言う文化現象の表面化は、歌壇の外から短歌の活動が見える状態を指していると思われる。SNS利用者のほとんどが大衆である以上、SNS上で誰でも容易に見られるほどの表面化とは、単に短歌の大衆化、あるいは大衆とは言わずに歌壇の周縁が広がったと言い換えてもいいのではないかと思う。ここで私は立ち止まる。 三宅が木下の作品を介して指摘した短歌の特性は読者目線のものだ。山田は読者である三宅の短歌受容の仕方に問題を感じ、作者が読者にへつらうのではないかと警鐘を鳴らしたのだろう。しかし読者に見出した問題が、翻って作者の作風を狭めるものとしてしまうのは、安易ではないか。 歌を見てみよう。木下の作品では先に題が提示される。例えば、「高校で美術の先生をしていますが、学校が好きではありません。これからも頑張って働いていけるような、勇気をもらえる短歌をお願いします」と言う題に、次にように応える。 先生は光の当たらない面を見つめるための時間をくれる 木下龍也『あなたのための短歌集』 一つひとつの言葉は幼げだ。しかし全体は成熟している。三句の頭「ない」による意味の転換、二句以降全てが結句にかかるように文を長く保つ構造からは、すみずみに意識が通っているようにすら見える。 「あなたのため」とは、モチーフにすぎないのだろう。木下は定型と定型以外の制約を個性の領域に押し上げている。題を介して読者との共通認識を作りながら、認識できていないものの側面を強烈にえぐり出している。三宅の言う短歌の特性は、木下の歌に内包される成果物の一つでしかないのだ。逃走ではなく、深化がここにある。 |
||||||
| 2023年6月号 |
||||||
| 『対話のために』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
「短歌研究」二〇二三年四月号の巻末に、出版社としていかなるハラスメントも許さないという「反ハラスメント宣言」が掲載された。遅すぎるが、画期的だと思った。 二〇一九年から二〇二二年にかけて、連句人の高松霞がネット上で行った短歌・俳句・連句のハラスメント体験談の収集や、ガイドラインを作成して各団体に送るクラウドファンディングが多くの支持を集めており、波及するような動きが続いている。 出版社自身の過去を省みるコメントがなかった点は残念だが、宣言が明文化された意義は大きいだろう。誌面の半数近く、九〇ページに渡る特集「短歌の場でのハラスメントを考える」に寄せられた連作の歌を引きながら考えてみる。 出産も育児もマンモグラフィも何でも我慢われら女は 岡崎裕美子「夕闇がくる」 岡崎の歌には二つの大きな省略がある。上の句に繰り返し現れる「も」は、上の句に入りきらない省略された事柄があることを詠嘆している。下の句では「われら女が」と集団が主語になっているが、そこには一人で我慢しているというニュアンスがあるのではないか。「何でも我慢」とはなんとそっけない言葉だろう。多くの人が抱える痛み、共有可能な痛みを個人だけの問題に見せかけて、ありふれた事実を認識の外側に追いやってしまう。 岡崎の詠嘆は、言葉をそっけなくさせてしまう力の存在を示している。思考を放棄せざるを得ない状況を客観的に捉えて言語化し、向かい合おうとする。否定するために、貴重な三十一音の一部を犠牲にして、存在を認めるのだ。 おまえの眼に小さく光る星がありよくないおいで剥がしてあげる 平岡直子「野鳥図鑑」 人を孤独にさせる力は、時に当事者同士の間でも働く。平岡の歌では「剥がしてあげる」が不気味だ。親しさと逆らえなさが同居している。相手の眼の光を剥がして暗くさせるというメタファーを使い、我慢を他者にも強いてしまうことが正義であるかのように演じている。 「よくない」詩情に乏しいそっけない言葉がここにもある。句割れの技巧でもって四句にねじ込んでいる。 引つぱり出して台に立たせて頬を打つやうな批評と思つた 雨だ。 黒木三千代「雨」 言葉をそっけなくさせる力とは、言い換えれば場の圧力だろう。私は、短歌の場でハラスメントを見過ごしたことがある。親しい人に対して向けられた、対等に議論ができない場でのコメントにすぐに反応せずに、発話者に悪意はないし仕方がないか、と飲み込んでしまった。 頬を打たれている人を目の前にして、行動できなかったことを悔やんでいる。その場ですぐに反論ができれば、悪意のないハラスメントは打ち消せる。 ハラスメントと名付け得ぬまま葬りし記憶いくつか遙けき丘に 松村百合子「花の色は」 反ハラスメント宣言は、今後ハラスメントを許さないという宣言であるとともに、なかったことにされてきたハラスメントをあったことにする、という宣言でもある。短歌の創作の場に深く関わり、多くの人の目に触れる媒体が宣言を出したことで、個人ではなく集団としての共通認識が変わっていくはずだ。対話の前提がようやく出来上がってきたと言えるだろう。 対話を恐れない。 |
||||||
| 2023年5月号 |
||||||
| 『口語定型の調べ』 嶋 稟太郎 | ||||||
| 「角川短歌」短歌年鑑令和五年版の特別座談会のテーマは「『調べ』の現在」だった。「調べが優れている近年の作品」として挙げられた短歌から特に印象に残った歌を引いてみる。 薔薇窓をみて死にたきと薔薇窓にあの人の声ふはつと浮かぶ 尾崎まゆみ『ゴダールの悪夢』 うますぎるゲルニカの模写 図書室をちょっと入ったところにあった 土岐友浩『僕は行くよ』 今井恵子が選んだ一首目、「薔薇窓」に付する助詞を変えて回想から実景に転換する鮮やかさ、力の抜いた音がする「ふわつと」が意外な展開で、主体が窓をみている場面が際立って感じられる。 今井は歌の基本形の一つとして「四句あたりに歌の重心が来る形」をあげて麗しさを感じられると述べた。この歌は二句の時点では「死にたき」と発言した人が誰なのかわからず、四句「あの人の声」で確定する作りになっており、歌全体の文脈を変えてしまうような四句は重心があると言えるかもしれない。 それに比べると二首目はどうだろう。この歌を選んだ加藤治郎は、定型のリズムに乗って読める点、三句以降に濁音が無くなって促音が現れる構造を転調と呼び、高く評価した。対して林和清は促音の使い方など技巧は認めつつも、詩的な要素がどこにあるのかと困惑を見せ、そこから対話が深まらなかったように思う。 おそらく問題は二点ある。①前提となる過去の定義がなかったこと、②韻律の分析だけでは読み方が変わらないことだ。 文語定型には積み重ねられてきた美意識がある。かつて玉城徹は「歌を鍛える過程」を「しらぶ」と呼び、そこから生じるものを「しらべ」と呼んだ。(『藜の露』) 今井や林の短歌観もこれに類するものだろう。座談会ではこれまでの調べを定義せずに調べの現在を議論してしまい、逸脱しているのか歴史に付加できているのか認識を合わせるのが難しかったのだと思う。 小原奈美は、調べというと流麗な調べのようなイメージがあると発言しており、ここから議論を始めてもよかった。 もう一つ、土岐の歌に詩性を見出した加藤の直感は正しいが、定型に収まった音の要素を整理するだけでは、技巧から生じるはずの「しらべ」を他者に説明するには不十分だったのではないか。 私は土岐の歌に新しさを感じた。 二句は「模写が」とすれば違和感のない文章になるので助詞の省略と読めるが、そうではない。ここに言葉の圧縮がある。二句の終わりに名詞を置いて小休止を作り、句切れの代用としていると読むと、歌の中の時間が「絵を見ている現在」に固定されているように感じられる。 下の句でいま現在に至るまでの短い道のりをそっけなく言って歌全体のテンションが下げられると、口語のフラットな言葉の群れのなかで「うますぎるゲルニカの模写」の優れた韻律が引き立ってくる。 主体は模写の技巧に魅力を感じているのだろう。おどけたような「うますぎる」の言い方は、絵と向かい合いながら、凄惨な無差別爆撃の様子を感じ取れないグロテスクさを客観的に捉えて強調する。 絶対的に詠嘆を示す助動詞を用いにくい口語短歌の弱みを逆手にとって、平らかな言葉の中にわずかに突出して感じられる言葉を置き読者に主体の今を追体験させる、いわば相対的な詠嘆を試み、そして成功した歌ではないか。 |
||||||
| 2023年4月号 |
||||||
| 『短歌とキャズム』 嶋 稟太郎 | ||||||
|
文通はきっと私で終わるだろう 遺跡のような静けさの町 深すぎるお辞儀でひらけランドセル スーパーボールスーパーボール 岡本真帆『水上バス浅草行き』 返せなかった手紙がいくつかある。終わらせると決めたのは自分のはずだが、いつまでも棘のように心に刺さっていてときどき私を苦しめる。長い時間を過ごした町にもいつか完全に静止する時が訪れるのだ。何かを終わらせようとする歌の結句を体言止めにして「町」を選ぶ作者の感覚に共鳴できる。二首目は時間の流れに注目した。「ひらけ」は願いの言葉であると同時に歌の中の時間をランドセルが開く前の時点で固定するための符号ではないか。「お辞儀でひらく」としても意味は通るが確実に起こる未来という感じがしてどうもスーパーボールの意外さが減ってしまう。言葉の過不足を熟知している作者なのだろう。上の句で描写が完成しているため下の句で名詞を繰り返しても余計な感じがしない。 昨年もっとも読まれた歌集のひとつはこの『水上バス浅草行き』だろう。三月の発売から二か月で累計一万部を超え今も重版を重ねている。私個人の体験だが、短歌とは関係のない仕事上の知人からこの歌集を読んだという話を聞くこともある。 これだけ市場に流通している背景には店頭に並べるために書店員や出版社のような供給側にいる人たちが時間をかけて流通を整備してきたこと、そしてネット上で、とりわけSNSのツイッター上で短歌の情報網が成熟してきたことを挙げたいと思う。 ネット上の短歌情報のやり取りといえば古くは九〇年代からメーリングリストや掲示板がありゼロ年代の歌葉新人賞の選考過程の公開など枚挙にいとまがない。現在と比べてネット上の個人間のランダムな繋がりが少ない初期のネット上の短歌シーンでコミュニティを拡張するには(拡張したかったかは別として)ネットを介さない口コミの力が必要だったと推察する。情報流通の構造を見るに献本を中心に歌集が流通する市場と同じように少数精鋭によるクローズドな場だと言えるだろう。 一〇年代に入ると投稿者がお互いに短歌の選をする投稿サイト「うたの日」が始まり、サイト内で高い評価を得た歌がツイッター上で簡単に拡散されるようになった。最近では毎月一万首が投稿されると言う。正確な発表はないがサイトを見るに千人を越すコミュニティとなっている。「うたの日」以外にもネット上で周知を行い短歌を集めて参加者が評価し音声や動画で配信され拡散される、というサイクルを繰り返す数百人規模の場がこれまでのクローズドな場と並行していくつも存在している。短歌を発信することが当たり前になってきた。歌壇の外周はここまで広がっているのだ。 二〇年代に入り短歌の流通はひとつのキャズムを超えたのではないか。マーケティングの用語であるキャズムは「市場の間にある簡単に超えられない深い谷」を表し、どんな商品にも限られた人の間で流通するニッチな市場とそうではない大きな市場があると言われる。ニッチな市場の一部であるネット上の歌壇の規模がかつてないほど大きくなりネットを介して歌壇の外側に大量の短歌を届けていくうちに興味を持つ人も増えてきた、と考えることはできないだろうか。歌を味わうには訓練がいる。売れる歌集が歌壇で評価されるとは限らないが良いと思った人が読み方をネット上に記録していけば多様な読み方が流通する。町を越える文通はきっと途切れることはない。 |
||||||
| 2023年3月号 |
||||||
| 『短歌時評について』 山川 築 | ||||||
|
一年間時評を執筆するにあたって、短歌の話をしよう、と決めていた。当たり前だと思われるかもしれないが、短歌時評の類を読んでいると、必ずしも短歌の話がされているわけではないと感じる。 時評は狭い文芸的なことだけでなく、短歌を通じて広く社会を語る器にもなりえると信じたい。そして、時評を通じて短歌を取り巻く世界に変化して欲しい。それが短歌自身の大きな進歩に繋がると信じたい。 佐藤博之「短歌に於ける時評の在り方」(「心の花」二〇二二年六月号) このような考えにもうなずくところはあるし、社会の存在が前提とならない純粋な短歌などというものはないのだから、短歌を語ることが社会を語ることにつながっていくのは、自然ではある。しかし、同時期の雑誌や結社誌などの時評欄をいくつか読んだかぎりでは、先に外部の問題を設定して、そこに作品を当てはめていくような時評もあった。そのようなやり方に対しては、短歌を副次的に扱ってしまっているという疑問を抱く。それならば、短歌である必要がない。 短歌を通じて社会を語ることに意味があるとすれば、作品を読む過程で読む前には見えていなかった問題を見つけ出していく点にこそある、と筆者は考える。「狭い文芸的なこと」を十分に考えた結果として「社会を語る」という方向に進まなければ、本末転倒になってしまうのではないか。筆者はむしろ「狭い文芸的なこと」にこだわりたい……というか、それは狭いものではないと主張したい。純粋な短歌など存在しないことを前提として受け入れた上で、短歌によって社会と向き合いたいのではなく、できるかぎり、短歌と向き合いたいのだ。 時評を書くときに決めていたことがもうひとつある。それは、「こんな価値観もあれば、あんな価値観もある」と紹介するのではなく、自分が「この価値観」を選び取ったと表明することだ。 染野太朗は、「歌壇」二〇二二年六月号の特集に寄せた「舌の複製について」で、短歌の世界で繰り返し言及される「断絶」について、嘆きや怒り、あるいはマウントやべき論を見ることはあっても、「断絶によって本当に困っている人の文章や発言には触れたことがない」と述べ、「断絶」の有効性に疑問を呈する。個人的な印象を集団的な傾向に偽装しようとすることへの疑念には同感したし、平岡直子「パーソナルスペース」(「歌壇」二〇二二年一月号)を引用しつつ、「外側を繊細に意識する必要」を説き、「断絶」は、外側の多様性が尊重されさまざまな価値観が等価になることではなく、それらを根本的に否認することから生じるはずだと指摘する流れにも納得した。 一方で、価値観の相対化の受容を徹底することは、いかなる評価も下さない態度に近づく危うさを孕んでいる。評価という行為は、自らの価値体系を定めた上で、対象をどこに位置付けるかを決めることだ。それが一切伴わない言論に意味があるとは思えない。価値観の相対化を十分に認めた上で、「この価値観」を選び取ることが重要なのだ。 染野は「感情や価値観が、論理の意匠とともに投げつけられるとき、排除され殺される何かがある」と批判する。対抗するわけではないが、筆者はまさに、感情や価値観を論理の意匠とともに投げつけることを念頭に置いて、時評を書いてきた。排除し、殺したものについては考えなければならないが、生かしたものもあると信じる。 |
||||||
| 2023年2月号 |
||||||
| 『対立を超えて』 山川 築 | ||||||
|
昨年の七月に開催された、現代歌人集会春季大会のパネルディスカッションで、笹川諒の発言が強く印象に残った。笹川諒は、近年の短歌のラベリングとして使用されることのある「人生派」と「言葉派」の二項対立に疑義を呈し、実際にはそれらはグラデーションではないかと指摘した。ある歌や作者を「これは人生派」「この人は言葉派」と分類できるものではないという主張で、筆者も賛同する。しかし、同大会の感想を述べた北辻一展「丁寧に読むということ」(「現代短歌新聞」十月号)では、「人生派」と「言葉派」の二項対立を所与のものとして扱っており、笹川が批判した読み方を踏襲してしまっている。その結果、笹川の発言の要約が不適当なものになっているのは残念だった。 具体的で細やかな議論が必要な場に大雑把な分類を持ち込めば、当然うまくいかない。そんな例を、時評を書き始めて以降の短歌に関する文章・発言、と限定しても、複数目にしてきたのは、すでに何度か書いた通りである。思いのほか、そういう磁場は強いのかもしれない。 そんなことを考えながら、同人誌「のど笛」第二号の座談会を読んだ。同人四名(青松輝、佐原キオ、橋爪志保、平出奔)が短歌観や短歌界についての考えを丁寧に語り合っており、特に、中盤から後半にかけて、定型に対するアプローチを語る部分には強く興味を惹かれた。五七五七七のリズムが生物的におもしろく感じるよう組み込まれているという説に対する、青松の「僕はけっこう真逆で、ゲームとしておもしろいからやってますね。この島国でなぜかそういうルールになってるゲーム、としておもしろがってます」という返しは痛快だ。 刺激を受けた箇所や立ち止まって考えた箇所を挙げるときりがないのだが、筆者の関心事に思いきり引き付けるならば、橋爪が「人生派」と「言葉派」について言及しているほか、「意味」と「技術」、「わかる」と「わからない」といった事項が、二項対立ではなく、「もっと複雑なそれぞれの作用が互いに絡み合っていく」(橋爪)ものだという把握が共有されている感じが、とてもよいと思った。 少々、若い世代の発言に偏ってしまったが、なにも世代差を強調したいわけではない。川本千栄『キマイラ文語』(現代短歌社新書)もとても興味深い一冊だった。本書は、帯文にも明記されているように、「文語/口語」という対立を一貫して批判する立場から書かれている。それはなにも、文語または口語という概念を否定しているわけではない。「文語も口語も基本は現代語」と捉え、対立的に扱うのは的外れだと主張しているのだ。川本の論旨は常に明快で、かつ近代短歌の源にまで遡る歴史的な視点を備えており、説得力がある。また、小池光、島田修三、河野裕子の口語の取り入れ方について書かれた「短歌口語化の伏流水~古語を使う人々」など各論もおもしろく、後半の、いわゆるニューウェーブ世代について論じた箇所では、かなり踏み込んだ批判もあってスリリングである。 川本は「私がキマイラなどと言うのは、文語は千年以上続いてきたとか、短歌はそもそも文語で書くべきだなどという、錯誤とも思える意見に反発を覚えるからだ」と述べてる。このような感情面にも共感した。 分類すること自体には意味があるし、二項対立を想定することが有用な場合もあるだろう。しかし、それを乗り越えることが、実態の理解につながっていくことの方が多いのではないだろうか。 |
||||||
| 2023年1月号 | ||||||
| 『細かさが伝えるもの』 山川 築 | ||||||
|
「短歌」十一月号で第六十八回角川短歌賞が発表された。座談会で最も興味深く読んだのは、次席となった福山ろか「さえずりに気づく」の評価だ。三人の選考委員が福山作を評価したのに対して、坂井修一は「細かいテクニックやその場の心理の追及という以前に考えないといけない大切なことが文学にはある」として強硬に受賞に反対し、選考会の終盤でも「中身がないのに技を詰めて行く」と否定的に評する。 坂井は福山作を「ダメ」としているが、姿勢が強硬である一方、一首一首への具体的な論評は少ない。「一番大きな理由は、優等生であると自分で言ってしまっていることです」と述べている通り、それがかなり決定的な評価のポイントとなったようだ。 露天風呂に浮かんだ月をぐしゃぐしゃに壊した 優等生やめたくて 坂井が強く否定している一首である。語り手が自分を客観しているが、その結果、かえって幼さが無防備に表われてしまっているのではないか。よって、筆者もよいと思えなかったのだが、問題は、それを全体の評価にまで拡げられるのかという点だ。 連作は、一首の集積と相互の関係によって形作られる。一首一首から全体が判定され、総合的な評価がなされるべきだ。坂井は一首に表れた「自意識」を「作家として自立していない証拠」と捉え、全体に否定的評価を下しているが、あまりに性急で、ことば足らずだ。「考え方や生き方の根本的なところに安直さがあります」とまで言われる根拠が、十分に示されてはいない。「文芸」「本当の歌」といったことばも、坂井の中でははっきりとした基準があるのかもしれないが、正直なところ、うさんくさく思えてしまう。 筆者自身は福山作を、ベタな対比の構図に回収されてしまう歌が気になる部分もあったものの、おもしろく読むことができた。 多分もう会わない猫にばいばいと言う 人に言うときの感じで ずっと見てられるよねって言ったあとゆっくり席を立ったカップル 賞状の額にさわったことがある職員室の前の廊下で 一首目、「人に言うとき」と「猫に言うとき」では「ばいばい」の言い方が違う。その小さな差異は、親愛の度合いの違いなのだろうか。さまざまに想像させる。 二首目、ことばの微妙なニュアンスを捉えた。「ずっと見てられる」という言い方はポジティブなようだが、「ずっと見ていたい」でも「ずっと見ている」でもない。違和感を行動の描写で表現したのもうまい。 三首目、賞状は語り手に関係したものなのだろう。その額にさわる行為に込められているのは、誇らしさか、自嘲か、なんにせよほとんど無意味すれすれなほどかすかな感情だ。また、さわる場面ではなく、「さわったことがある」という回想の形も、また別種の感情を盛っている。 これらの歌にはたしかに細かいテクニックがあるが、それが目的化しておらず、細かい情感を表現しえている。坂井は「中身がない」と批判するが、どのように中身がないのか、より細かく述べてくれないと納得できない。 湧き上がる入道雲を見ていると主張のような雨が降り出す 最後にこの歌が置かれている。雨を主張のようだと感じるのは、語り手が主張したいことを抱えている反映だ。露天風呂の月を壊す、といったものだけでなく、繰り返し表現されている微量の心理の動きも、語り手にとっての主張なのだ。 |
||||||
| 2022年12月号 |
||||||
| 『現代短歌評論賞受賞作を読んで』 山川 築 | ||||||
| 「短歌研究」十月号にて現代短歌評論賞が発表された。 受賞作である桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展~三つの様式化」は、八十年代以降の口語短歌を概観した上で、文末処理の問題に着目して、口語を定型になじませる試行として①動詞の終止形②終助詞③モダリティの三つを取り上げる。言語学を援用して口語短歌ならではの技法を論じる後半部分を特に興味深く読んだ。 ただ、大ざっぱな把握にところどころで引っかかり、桑原の主張する「進展」をひとつの史観として納得させられるには至らなかった。たとえば、前半で触れられている「口語短歌の三つの分かれ道」に関して、第一および第二の道について「大きく進展することはなかった」「洗練されて進展していく、ということにはならなかった」と述べているが、検討なく退けてしまうのは受け入れがたいし、例歌の分析が曖昧なのも物足りない。あるいは、斉藤斎藤の歌を取り上げた箇所で、モダリティの活用と「現代社会の一断面」の表現を関連させているのもすんなりと飲み込めなかった。たとえば、桑原が斉藤と対比する俵万智の「ハンバーガーショップの~」の歌も、「現代社会の一断面」の表現と言えてしまうのではないか。そもそも「現代社会の一断面」という言い方自体も、やはり曖昧である。総じて、着眼点や構成の意図はおもしろく思えたが、前提や根拠となる部分が弱く、論全体の説得力を薄めているのが残念だった。より引き締まった形の論を望みたい。 もうひとつの受賞作、高良真実「はじめに言葉ありき。よろずのもの、これに拠りて成る――短歌史における俗語革命の影」は、「口語短歌は書かれた時点ですでに口語ではない」という一文に始まり、「口語とは考えていることを自然に表現できる透明な言葉なのか。発話と書かれたものは断絶しているのではないか」という問いを追及する。問いの立て方に、しばしば自明とされる事柄に疑義を唱える姿勢が端的に表われている。「普通文」や「俗語革命」という語すら知らない筆者にとっては簡単ではなかったが、刺激的な論文だった。 口語と文語、話し言葉と書き言葉にとどまらず、俗語、方言、標準語、国語といった観点を導入しつつ、口語による「抵抗」が可能なのかと問いかける展開がとてもおもしろい。口語の背後に話す身体を統制する言葉=国語があると指摘し、標準語/方言の不均衡を踏まえた上で、斎藤茂吉が文語にこだわった理由を推測するのもスリリングだ。筆者はぼんやりと、文語とナショナリズムの近しさを感じていたが、髙良の論ではむしろ口語(言文一致体)が国家によって制度化された言葉であることが指摘されており、これも蒙を啓かれる思いだった。 情緒的な断言に流れることなく、国家と言語の関係にまで分け入って論じられるのは、「口語短歌の歴史的考察」という課題への正面からの応答と言えるのではないだろうか。 惜しむらくは、選評で寺井龍哉が指摘しているように、結尾がいかにも駆け足で、茂吉と現代の口語短歌の比較検討が十分ではない。また、「口語短歌の可能性を信じている」という座りのよい収め方ではなく、問いを投げかける着地点もありえたのではないか(それが筆者の本心であるにせよ)。いくつもの論点が提示されているが、まだ論じ切られていないという印象を強く持った。さらに多くの分量で読みたいと思う。 |
||||||
| 2022年11月号 |
||||||
| 『再び、分断や伝統なるものについて』 山川 築 | ||||||
|
「現代短歌」七月号の川野芽生「幻象録」第十五回を読んだ。ほとんど全面的に賛成したい内容で、とりわけ「基本的歌権」という語が、若手世代の短歌観を表わすものとして粗雑に使い回されていることを批判する箇所には、非常に強く共感した。 また川野は、筆者も本欄六月号で取り上げた奥田亡羊「短歌地図が違う」(「歌壇」一月号)を批判しつつ、「歌壇が分裂してもかまわない」という意見には同感だと述べる。これに補足する形で、川野はTwitter上で、「分裂」「分断」といったことばがちゃんと議論されないまま「悪いこと」として語られていると指摘し、「「分断されていない、まとまった状態がよい」という価値観は結局少数派への抑圧につながるので、「棲み分け」の方がいいのでは」という見解を示している。 https://twitter.com/megumikawano_/status/1553731916192706560 筆者も「分断」に類する語を濫用してきた身なので耳が痛いが、川野の主張は明快で腑に落ちるものだ。 そして、「棲み分け」のために求められているのは、相手を拒絶し、「わたしとあなたは違う」と決めてかかる態度ではない。きちんと差異を認識するために、相手の言に耳を傾け、理解しようと努めることが……必ずしも理解に至らないとしても、そこに至ろうとすることが、重要であるはずだ。 「幻象録」第十五回は「話を聞いたらどうですか?」と題されている。話をしっかりと聞いた者による反応を望む。 ここで筆者もひとつ、反応を返したい。 「八雁」五月号の「続欅の木の下で」第三十八回で、阿木津英が本欄四月号に触れている。 阿木津は筆者の批判する「短歌」一月号座談会の島田修三の発言について、島田は「正統とはなにか」といった論を展開しておらず、座談会の雰囲気も〈正統〉を問題として意識するものではないと指摘する。この点には、筆者も異論はない。その上で、「ほんの数か所」にさらりと〈伝統〉という語が使われてしまう点にこそ、問題の根深さがあると、筆者は主張する。 また阿木津は、〈正統〉や〈伝統〉は言語と同じく個人が修得するもので、「山川築さんが誤解するように、個人の外に「判定」の尺度として存在するものではない」と書く。誤解していたとは知らなかった。筆者も〈正統〉〈伝統〉が外的な判定の尺度だとは考えていないからだ。四月号本欄で〈伝統〉とは「甚だ曖昧なことば」だと述べているし、〈伝統〉とつながっているか否かを、個人の内的な基準によって判断し評価することの危うさも指摘している。 筆者は、〈伝統〉が完全に内的なものだとも考えない。共有されたイメージとしての〈伝統〉も、曖昧なものであるにせよ、否定しがたく存在する。〈伝統〉とは個人が発見し、創造するものだという阿木津の主張は筆者にとって新鮮なものだったが、語の定義の問題に過ぎないのではないか。 また、〈伝統〉が阿木津の言うようなものならば、なおのこと、選考会で評価の根拠とするものとして適切だとは思えない。 阿木津は現代短歌社賞の選考座談会の中で「問題意識を共有しない虚しさ」を感じると述べているが、筆者に対しても同様の虚しさを感じているのかもしれない。一方で、筆者の問題意識も阿木津と共有されてはいないのだろう。阿木津の文章は、筆者への反応ではあるが反論ではなく、そもそも反論は意図されていないようだ。筆者もまた、虚しさを感じる者のひとりである。 |
||||||
| 2022年10月号 |
||||||
| 『短歌ブームから遠く離れて』 山川 築 | ||||||
| 『短歌研究』八月号の特集は「短歌ブーム」。冒頭で述べられている通り、昨今メディアで短歌ブームという文字を目にすることがある。そしてこの特集は、「ブーム」を「現象」としてくくるだけでなくもう一歩踏み込んで考えたい、という意志から企画が立てられたと説明されている。 とはいえ、ブームの実感ついては寄稿者の間にも温度差があり、土井礼一郎が「短歌ブームは起きている」という実感をはっきり述べているのに対し、山田航は「昨今が短歌ブームと呼ばれていることの実感は個人的には全くない」と書く。筆者の印象は山田と同じで、相変わらず伊勢市内最大の書店でも歌集を売っていないし、ブームってなんの話ですかと思うのだが、住む場所や短歌との関わり方によっては、違う捉え方があるのかもしれない。 特集の中心は岡野大嗣へのインタビュー。岡野は、「いったい「短歌ブーム」とはなんだろう?」という問いの答えは自分にもよくわからないと応じ、「短歌ブームと言われるものがあるとして、それに対して僕は冷静でいたいと思っています」と言う。そして実際に、そのことば通りの受け答えがなされていると思うし、頷く部分も多い。 たとえば「(引用者注:朝のワイドショーの)番組内でさらっと紹介された歌に「あるある!」「エモい!」と盛り上がっているのを見ても、自分が密かに大切にしている宝物を軽く扱われているような気になってしまう」というのはよくわかる感情だし、「誰かに認められたいという気持ちはなくて、自分自身が自分の歌に納得がいくかということだけを徹底している」というのは、筆者もそうしているというか、そうしたいと思っていることで、共感した。 一方で、意識の隔たりを覚える箇所もあった。岡野はカート・コバーンの「売れたいが、売れるような曲は大嫌い」ということばを引用し、「おそらく、歌人の多くはこれに近いマインドを持っているんじゃないかと思います」と述べる。この考えが当たっているのかはわからないが、少なくとも筆者は、短歌によって売れたいと思ったことがない。 岡野の「短歌の総合誌は原稿料が信じられないぐらい少ない」「なぜ短歌の人たちが短歌に価値を見出せていないのだろうと思う」「作業量に対して人件費的にもおかしい」といった指摘にも、たしかに半分は頷かされる。総合誌の原稿料は、それだけで生活していくのはとても不可能な金額であり、いつまでもその状態では短歌の世界がよくならない、という考えもあるだろう。 一方で、原稿料の多寡が短歌の価値と関係があるのだろうか、とも思う。金銭が関わってくるとき、筆者には、短歌以外の話をしている、不純なことを話している、という感覚がつきまとう。 岡野は「売れていようがいまいが良いものは良い」とも言っている。同感だ。そしてそれは、売れていようがいまいが悪いものは悪い、ということでもあるはずだ。しかし、「売れている」という事実、もしくは広く届いているということが作品の価値(の少なくとも一部)を担保するとみなす言説は多い(岡野がそう主張しているのではないが)。そのような言説を見聞きすると、筆者はそれこそ「宝物を軽く扱われているような気になってしまう」のだ。 「お金で買えない価値がある」と書くとあまりに陳腐かもしれないけれど、短歌のみならず、表現物には、金銭や人気に還元することのできない、独立した価値があると思いたいし、信じたい。 |
||||||
| 2022年9月号 |
||||||
| 『認識の歌』 山川 築 | ||||||
| 毛羽だちて雪うかびゐる空間を地にとどまれるわれは見てをり つややけき墨の面にふるる穂にたちまちにして墨はのぼりぬ 葉先より雫落つれば透きとほる蜘蛛の子ひとつともに落ちたり 昨年出版された横山未来子の最新歌集『とく来りませ』から引用した。一首目は「毛羽だちて」の働きで雪の質感を伝え、下の句では「われ」の姿を映して雪と対比させる巧みな歌だ。二首目は筆の穂先に墨が染み込む動きがゆったりと詠まれている。三首目は無生物と生物がともに葉先から落ちる様を詠み込んで、自然の摂理の美しさと残酷さを感じさせる。いずれの歌も、まず見過ごしてしまうような事物の微細な動きを捉えており、静かな凄みがある。場面を映像としてくっきりと思い描くことができるのは、鋭い着眼と引き締まった文体によるものだろう。 明け方の川はまだ見たことがない散歩している犬連れの人 のつちえこ「凍れる川面」(「くくるす」Vol.1) 窓からは凪いでいる木々 だいたいの目薬の水面は揺れている 池田輔「わからないまま大丈夫になりたい」(「早稲田短歌」五十一号) 食い違う意見を持った課長代理と課長の見ているメモが読みたい 水沼朔太郎「兄の腹這い」 こちらは、今年発行された学生短歌会誌や同人誌、ネットプリントから引用した。 のつの歌は三句切れで読んだ。明け方の川を見ようと思えば見られるが、そのために早起きするほどではないから、まだ見たことがないのだろう。下句の、姿かたちを捉えつつ細部に立ち入った描写はしない詠み方には、対象とのある程度の遠さが感じられる。その視点は、意識しつつも距離があるという、上句の思考と相通じている。 池田の歌には凪いでいる・揺れているという対比が見られるが、どこか漠然としている。木々に関しては「窓から」という受動的な視点や、窓一枚を隔てた遠さがあるし、目薬に至っては「だいたいの」が非常にざっくりとしている上に、根拠もわからない。また、目薬は目の前にあるわけではなく、想像しているだけかもしれない。曖昧さを重ねたような読み味が後を引く。 水沼の歌では「食い違う意見」の中身がわからないし、「課長代理」と「課長」の存在はのっぺりとしている。語り手は人間よりもメモの方に関心を寄せているが、その文面にたどり着くことはできない。事物の表面と語り手の感情だけがあって、事物の内容がまったく不明なのだ。 横山の歌が事物の細部に焦点を合わせることで背後の奥行きや広がりを感じさせるのに対し、のつの歌ではもう少し距離が取られているし、池田の歌ではさらにぼんやりと把握されている。また水沼の歌では奥行きや広がりのなさが奇妙に印象的だ。 認識をことばに移し替えるとき、なにを認識したかだけでなく、どのように認識したのかもおのずと表現される。先に引用した歌は、それぞれに題材も詠まれ方も異なるけれど、認識の仕方、過程を表現している点で、指向が似ている。 歌を読み解くことで、世界がどのように認識されているのかが明らかになっていく。それは、歌を読むという行為の刺激的な部分のひとつであり、他者の存在と世界の豊かさを濃密に感じる体験でもある。筆者はそんな体験をさせてくれる歌が好きだ。 |
||||||
| 2022年8月号 |
||||||
| 『人生を短歌にする』 山川 築 | ||||||
| 近ごろ自分の年齢や家族・親類の老いをよく意識するからだろうか、遅ればせながら萩原慎一郎『滑走路』を読んでまず印象に残ったのは、年齢や年代が積極的に詠み込まれていることだった。 〈青空〉と発音するのが恥ずかしくなってきた二十三歳の僕 こんなにも愛されたいと思うとは 三十歳になってしまった 一首目、無垢や未来の象徴たる青空に対する、恥ずかしさが生まれてきた。社会人経験を積み始めたころであろう「二十三歳」が効いている。二首目、語り手は年齢の区切りをひとつ越えたが、抱いている感情や感覚は、かつて想像した「三十歳」とはかなり異なったものであるようだ。 『滑走路』には、「自分は大人になったが、まだ何者にもなれていない」という思いが満ちている。具体的な年齢が繰り返し詠み込まれることで、それに対する語り手の敏感さが表現され、青臭い感慨に生々しさを付け加えている。 抑圧されたままでいるなよ ぼくたちは三十一文字で鳥になるのだ 日記ではないのだ 日記ではないのだ こころの叫びそのものなのだ かっこよくなりたい 君に愛されるようになりたい だから歌詠む 短歌そのものに言及する短歌が多いのも特徴のひとつだ。『滑走路』における短歌は、地上から離れるための手段であり、「こころの叫び」であり、かっこいいものなのだ。 若い世代の傾向として、しばしば「具体的な社会生活を歌に表さない」「プロフィールと歌を結び付けられることを嫌う」と言われるが、萩原はまったくそうではなかったのだろう。短歌に人生を詠む、短歌と共にある人生を詠む、という勢いである。 『滑走路』から連想したのが、昨年出版された橋本喜典の遺歌集『聖木立以後』だ。二~三十代と八~九十代という違いはあるが、こちらも歳を重ねた身の上が多くの歌に詠まれている。 徐々に目が見えずなりゆく体験の さう いま 途上なのだ確かに われの眼はわが身にあれど眼が克つか現身(うつしみ)が勝つか楽しきごとし 一首目、視力が失われていくさまがある達成の途上だという、逆転がおもしろい。ポジティブな捉え方の一方で、二度の一字空けと結句の句割れが思考の逡巡を表現しているようでもある。二首目は視力が失われるのが先か、自分が死ぬのが先か、という深刻な内容だが、それを「眼と現身の勝負」になぞらえたのには微笑ましさすら感じてしまう。結句の「楽しきごとし」も一首目と同じく、晩年の苦しみをも前向きに受け止める視点がありつつ、あくまで「ごとし」であるところに揺らぎと陰影がある。 おそらくは消したる歌の一千に支へられゐるわれならずやも 歌による表現者われ九十歳の胸にすこしく荒野(くわうや)を残す 歌を人生の同伴者とするような意識にも『滑走路』との共通点がある。こちらの語り手を支えるのは、詠んだ歌以上に多い、消した歌の方だ。「胸の荒野」は心や感情、そこから生まれる短歌そのものの比喩であろうか。老境に至ってそれは小さくなったが、均され切ったわけではない。 『滑走路』の直線的な表現の連続には迫力や痛切さがある。だが、やや飽き足りない気持ちを覚えたのも正直なところだった。自らの境遇に対する感慨を表現するにも、「こころの叫び」だけでなく、さまざまな方法がある。『聖木立以後』を読むと、つくづくそう思わされるのだ。 |
||||||
| 2022年7月号 |
||||||
| 『幻想とリアリズム』 山川 築 | ||||||
|
「文學界」五月号で「幻想の短歌」と銘打った短歌の特集が組まれている。それは一見すると、「現実の短歌」と対立するもののように思われる。しかし、大森静佳・川野芽生・平岡直子による座談会「幻想はあらがう」では、そのように単純には捉えられていない。各々の幻想観や定義を確認していく中で、通り一遍ではない考えが提示されるのが刺激的だった。 川野は「幻想というのは両眼をカッと見開いて対象を観察していく中でむしろ見えてくるもの」だと指摘し、それを受けて大森は「写実と幻想が実は全然対立していない」「写実が突き抜けると幻想になるし、簡単に裏返る」と述べている。「写実」は、現実をそのまま写し取ろうとすること、という意味合いだろう。現実を精密に写し取ろうとした結果、幻想が現れてくるのだ。 では、幻想とはなにを指すのか。平岡は短歌特有の幻想性として「身体的じゃない」「身体っぽくない」ことを挙げる。「仮に非現実的な表現が含まれていても、それはあくまで心の中の景色であって、その外側には安定した身体がある、という構図が強固なので、歌自体を非現実的な位相に置きたかったら、その構図を崩す必要がある」という指摘は鋭い。歌が非現実的な位相に置かれるというのは、語彙や詠まれている景といった歌の内側が非現実的だということではない。歌の外側、つまり読者の側の現実感覚という、歌を読むときに前提となっている構造に作用し、影響を与えるということなのだ。ここでは作品だけではなく、読者の側にも幻想が意味づけられている。幻想と現実を対置するのではなく、より根本的な部分に揺さぶりをかけるものとして幻想を定義するのには、読み方が更新されるような鮮やかさがある。 頭の位置をととのえてから目をつむる 夜の中で日焼けしていくような 永井祐『日本の中でたのしく暮らす』 平岡が「幻想の短歌」として選んでいるこの一首は、現実からかけ離れた表現を志向したわけではないだろう。逆に、語り手の感覚した現実を正確に再現しようとした結果として「身体と意識の回路にバグが起きている」ような表現になった。逆説的だが、現実的な表現を突き詰めた結果として、歌が非現実的な位相に置かれるのである。 短歌に関する文章を読んでいると、「リアリズム」あるいは「口語リアリズム」という表現を目にすることがある。リアリズムの短歌とは、いうなれば「現実の短歌」であろう。しかし、リアリズムの定義は曖昧で、論者によって異なった使い方がなされている。 また、リアリズムという語には、対立概念として、リアル(現実)でないものが想定されているはずだ。しかし、先に挙げた座談会では、現実/非現実(幻想)という対立を超えたラディカルな指摘が、説得力を持ってなされている。リアリズムという語をもっと厳密に定義し、これに対応する言説を打ち出さなければ、現実と非現実という対立関係は、表面的なものにとどまらざるをえないのではないか。 さらに、そもそも対立関係が成り立つのかという問題もある。平岡は「短歌って、極論を言うとぜんぶが幻想的」「ぜんぶが幻想的だということは、ぜんぶ幻想的ではないとも言えてしまう」と述べる。納得できる指摘である。そしてそれは「ぜんぶがリアリズム」とも言えてしまうということだ。だとすれば、短歌におけるリアリズムという語自体に、どの程度の有効性があるのだろうか。座談会を読んだあとでは疑問に思えてくるのだ。 |
||||||
| 2022年6月号
|
||||||
| 『「若手歌人」への批判を読んで』 山川 築 | ||||||
|
ときおり「若手歌人は読む短歌に偏りがある」という主張を目にすることがある。筆者はこのような主張を読むたびに、本当にそう言えるのか、疑問を覚えてきた。 「歌壇」一月号に奥田亡羊が寄せた文章「短歌地図が違う」および「短歌研究」三月号の柳澤美晴の時評「新しい短歌地図とは」では、「若手歌人」への批判や疑問が述べられている。想定されているのは、二十代から三十代の歌人だと思われる。筆者も射程圏内の一人と言えようか。 奥田は、よく話をする「ある若手歌人」の博識に感心させられると述べつつ、その人物が岡井隆を読んでいないことや、奥田の世代の歌があまり読まれていないのでは、と発言したことへの違和感を表明する。また、近年出版されたアンソロジーが若手中心の編集であり、それらだけを読んだ者の「短歌地図」は歪なものになると懸念する。 柳澤は奥田に同調し、興味のある歌人以外には目もくれない傾向が、特に若手歌人に強いと批判する。また、近年出版されたアンソロジーについても、「短歌界の一連の流れを尊重するなら、特定の世代に極端に選が偏ることは、あり得ない話だと思う」と否定的な見解を示している。 「もちろん地図など人それぞれ違うのだが、見ている短歌が年齢によってばっさり分断されているとすれば、やはりそれは好ましい状況ではない」という奥田の主張には同意するし、歴史と先行作品を知ることの重要性を説く柳澤の姿勢にも共感する。にもかかわらず、どちらの文章も、全体としては肯定的に受け止められなかった。 奥田は「ある若手歌人」との会話から得た印象を世代全体にまで敷衍しているが、それは筆が走りすぎというものだ。列挙した疑問を「個人的な印象」と断りつつ、「だが、歌壇の中にいま大きな断層が生まれつつあることは確かだ」と述べるのは不可解である。また、短歌を読み始めたばかりの者の「短歌地図」が、長年短歌を読み続けている者にとって歪に見えるのは当たり前で、特定のアンソロジーのせいではない。 柳澤は奥田の主張を補強するわけでもなく、あたかも「若手歌人」の「傾向」が事実であるように書くが、それを前提として話を進めるのは、土台が危うすぎる。なにものかを否定するならば、もっと丁寧に書かなければ、暴論になりかねない。アンソロジーに関する批判も飲み込みづらかった。言及されている『桜前線開架宣言』や『はつなつみずうみ分光器』は、そもそもある年代以降の歌人・歌集を扱うというコンセプトが明示されており、現代短歌の歴史を一から概観するという目的で編まれていないのだから、偏っているという批判はナンセンスだ。柳澤自身も述べているように、先行するアンソロジーがいくつもあるのだから、それらとの差異化を目指すのも、自然なことではないか。 柳澤は「最近の若手歌人は何もない地点に出現したわけではない」と指摘する。その通りではあるが、それを理解していない者がどれほどいるというのだろう。この指摘が「若手歌人」や近年のアンソロジーへの批判を意図しているならば、力いっぱい空を切っている。 奥田や柳澤が述べている批判や疑問は、斯様に的を外しており、筆者に「若手歌人は読む短歌に偏りがある」的な物言いへの疑念を一層強めさせるには十分なものだった。薄弱な根拠で下の世代を批判し、その「短歌地図」の歪みを強調する行為は、断絶を深めてしまうのではないか。それは奥田や柳澤の望むところではないはずだ。 |
||||||
| 2022年5月号
|
||||||
| 『議論を読みたい』 山川 築 | ||||||
|
吉川宏志が「短歌研究」で連載中の「1970年代短歌史」をおもしろく読んでいる。 岡井隆の失踪が取り扱われている連載第七回と第八回(二〇二二年一月号・二月号)で、吉川は、岡井の失踪は当時の歌壇では反体制的なイメージで捉えられたが、それは岡井の動機とはかなりのズレがあったと推測し、当時の岡井が「反戦や政治批判を前衛短歌的な方法で詠むことに限界を感じていたようだ」と指摘する。そして、岡井は時代の情勢と歌壇の動向を踏まえた上で、先鋭的に作歌意識を変化させていったが、その試行が「若い世代から正当に評価されていない孤独感」を募らせ、失踪に繋がったと考察している。岡井の行動を、あくまで歌人としての思想と結び付けて説明しようと試みており、失踪についてスキャンダラスな印象だけを強く持ってしまっていたことを反省させられた。 連載第四回(二〇二一年九月号)では、角川「短歌」一九六九年十月号の座談会「われらの状況とわれらの短歌」が紹介されている。座談会では、安保やベトナムなどの当時の切迫した政治状況に関わる歌、反戦的な歌を詠むべきだという風潮に対し、下村光男、村木道彦、河野裕子が各々批判・反発している。筆者には、このころは少なからぬ歌人が政治状況を題材にした歌を作り、そうでない歌人もそれを否定的には捉えていないという思い込みがあったため、当時頭角を現していた歌人たちが、そのような歌をむしろ積極的に拒否する姿勢を取っていたことが、意外に感じられた。 吉川自身も、調べていく中で先入観を正されることがあったと書いているように、当時の文献に当たることで、漠然と持っていた印象が覆されることは、多くの人にありうるのだろう。それが、歴史を学ぶこと、あるいは書くことのひとつの意味なのだ。 また、座談会や、それに対する岡井の激烈な反応(角川「短歌」一九七〇年一月号)が総合誌に掲載されたという事実にも、インパクトを与えられた。吉川も述べている通り、岡井の文章は感情的で、生産的なものであったのかは議論の余地があるだろう。しかし、若手歌人が大きなテーマでの座談会を行い、先行世代へ疑問が投げかけられ、それに上の世代が応答する、という構図が誌上に展開されているのは、いい意味で予想外で、強い批判を含む文章に紙面が割かれていることを、健全に思う。 現在でも、総合誌に掲載された文章から議論が始まることがある一方で、文章がWeb上で言及されるものの大きく広がっていかず、もったいなく思う場合もしばしばある。Web上での意見表明は紙媒体に比べて開かれているし、やりとりの速さなど利点も多いが、筆者は、雑誌の紙面で議論が展開されてほしいという気持ちが強い。それは、たとえば吉川が書いているような文章のための資料となるはずだ。Web、あるいは同人誌などに比べて、総合誌は後の時代になってからもアクセスしやすいのではないか。 とはいえ、原稿の依頼がなければ文章を載せることは難しいし、そもそも出版側にその意思がなければ誌上での議論は起こりようがない。総合誌には、多様な意見を拾い上げるため、広く目を配り、年齢や肩書以外のことも考慮し、歌壇内の権力の大小に囚われず、様々な方に筆を執らせてほしい。そして、生産的な議論を、もっと起こしてほしいのだ。たとえば、現代版の「われらの状況とわれらの短歌」は興味深いものになると思うが、どうだろうか。 |
||||||
| 2022年4月号 | ||||||
| 『正統 伝統』 山川 築 | ||||||
|
角川「短歌」一月号の「新春特別座談会 短歌の継承と変化 ~時間とともに見えてくるもの~」を読み、島田修三の発言が気になった。島田は立花開について「正統的な歌と繋がっている人ではないか」、藪内亮輔、吉田隼人について「正統派できちっと続けてくれれば、現代短歌の芯の存在になりそうな気がします」と評価している。ここでは「正統」ということばが留保なく使われ、座談会の中でも論点にはなっていないのだが、筆者には、そのことばの内実がよくわからない。それは、広い世代に共有されている概念なのだろうか。 「現代短歌」一月号で、第九回現代短歌社賞が発表されている。受賞作は打矢京子「冬芽」と永井亘「静けさの冒険」。 選考会で阿木津英は「歌というものの模範というか範型というか原型というか、その共有、了解がいま無くなっていっている。歌とは何かという了解の根本のところが分裂していっている」と指摘する。感覚的によくわかる指摘だ。内容、文体、韻律のいずれにおいても、「このようでなければならない」「これが基本の形だ」といった共通理解がほとんどないことは、候補作の抄出を読むだけでも首肯する者が多いのではないか。「正統」という概念は、もはや相当に危ういものとなっている。 阿木津は、一九九〇年代以降、短歌における〈伝統〉を断ち切る力が働いてきたと主張し、新自由主義の波に抗って自由と平等の精神が生き延びる方法を考えたとき、〈伝統〉を考えずにはいられないと述べる。そして「冬芽」を、「短歌は和歌の時代からずーッと積み重ねてきたものがあるでしょう。「冬芽」はそういう流れのなかにある歌なんです」と位置付け、高く評価している。 しかし、〈伝統〉も甚だ曖昧なことばで、どのような事象を短歌における〈伝統〉と呼ぶかということは非常に定めがたい。また、阿木津は「若い人たち」の歌を、「前の時代と連続していない」と批判するが、なにをもって前の時代や〈伝統〉とつながっている、あるいは切れていると考えるのかも、簡単に答えが出せる設問とは思えないし、白か黒かで語れるわけでもないだろう(そもそも、つながっていることがすなわちよいことなのか、という問題もある)。 ドア越しに聞こえる声の哀しみに、すぐに映画がありますように 夕焼けと夢がまざった真夜中にいるキッチンはいつもまぶしい 「静けさの冒険」から引用した。一首目では、隔てられて届かないものへの救いの希求が詠われる。そこに「映画」を持ってきたのが変則的だが、映画館を想起させる語の連関やふたつの「声」の重なりが絡み合って、重層的なイメージが立ち上がる。二首目の夢と現、明るさと暗さが混ざり合った不可思議な感覚。それが「キッチンはいつもまぶしい」で現実に引き戻されながら、一首にさらに別の明度を加えて美しさを損なわない。筆者にはまだ消化しきれていない表現も多い作品だが、たとえばこのような抒情的な歌を「前の時代と連続していない」と言っていいのか。阿木津は「静けさの冒険」を「これは〈うた〉ではない」と否定的に捉えるが、座談会という限界があるとはいえ、〈伝統〉〈うた〉などをより厳密に意味付ける必要があるのではないか。 正統であるか否か、〈伝統〉とつながっているかどうか、〈うた〉であるかないか……そのような判定は慎重に行わなければ、ただ相互理解を退潮させ、分断を促進することになりかねない。それは生産的ではないと、筆者は考える。 |
||||||
| 2022年3月号
|
||||||
| 『春原さんのこと』 山崎 聡子 | ||||||
|
東直子の短歌をモチーフにした映画、「春原さんのうた」を鑑賞してきた。短歌の映画化といえば、萩原慎一郎の『滑走路』、小島なお『乱反射』の映画化を記憶しているが、これらの映画では歌集のなかに提示された断片を繋いで「物語」を語るというアプローチがとられていたのに対して、「春原さんのうた」では積極的に物語が語られないことにまずは驚いた。原作となったのは、歌集『春原さんのリコーダー』全体ではなく、「転居先不明の判を見つめつつ春原さんの吹くリコーダー」の一首のみだ。歌集を通して「春原さん」が出てくるのはこの歌だけで、春原さんが誰なのか明かされることはない。同様に、この映画で喪失感のさなかを生きている主人公「さっちゃん」が誰を喪い、なぜ周囲の人たちが彼女に寄り添おうとしているのか、同じ空間を分け合って佇む女(春原さん)が誰なのかはっきりと語られない。さっちゃんはただ起きて洗濯物を干し、仕事に行き、人と話し、食事をして、眠る。それでも、そこに流れている時間やさっちゃんのまなざしに、確かな喪失の痛みが映し出されているのを観客ははっきりと感じ取るのだ。 この不思議な映画を観終えた後、「歌壇」十二月号に掲載された杉田協士監督のインタビューを読んで、私はこの映画を通して東直子の短歌を再発見したように感じた。このなかで杉田は短歌における「余白」と映画の「フレームの外側」の類似性について言及している。杉田が言うように、映画のシーンは登場人物たちの人生の断片をつなぎ合わせたものであり、映画が「一生の中の描かれていない時間が存在することで成り立っている」ことを私たちは本能的に感じ取っている。没入するように映画を観た帰り道、あの人たちはこれからどうするんだろう、といつまでも考えてしまうことがあるが、これは映画の中で示唆された時間の広がりが私にそうさせているのだろう。そして、東直子の短歌では「語られていること」よりも、この「フレームの外側」の領域が広大なのだとつくづくと思うのだ。 そうですかきれいでしたかわたくしは小鳥を売ってくらしています 「ママの手ってわかっていたよしめってて」脱皮したての蜘蛛に朝露 廃村を告げる活字に桃の皮ふれればにじみゆくばかり 来て 『春原さんのリコーダー』を久しぶりに読み返したとき、この歌集にはこんなにもリアリズム寄りの歌集だったんだ、と少し驚くような気持ちがあった。「そうですかきれいでしたか」の歌を東がある芸能人の言葉から着想したことを私は東の発言で知ったが、連作単位で見ていくと、親しい人を失くしたり、出産や子供のことだったりと東が実際(だと思われる)出来事ベースで歌を立ち上げていることが随所に感じられる。しかし、東の言葉の中に放り込まれると出来事の細部がそぎ落とされ、そこに取り残された感情だけがエコーのように増幅して体験の個人性を覆い隠してしまう。「ママの手って」は子どもの声のようだけれど、下の句でこの言葉が受け止められた様子はなく、声をかけられた母親は消えてしまっているようにも感じられる。また、一見写実的にはじまる「廃村」の歌でも何者かわからない声から「来て」と呼びかけられ、私たちはこの零れそうな言葉を受け止めることを余儀なくされる。 映画が東の短歌の忠実な映画化だと感じたのは、その中で描かれた喪失感が物語に奉仕しないとこと、わからないこと、言い切れないことをそのまま漂わせていることに尽きる。映画館からの帰り道、物語の隙間に沁み込むように存在する東の言葉を、いつまでも読んでいたいと思った。 |
||||||
| 2022年2月号 | ||||||
| 『「表現の現場調査団」調査から思うこと』 山崎 聡子 | ||||||
| 短歌研究一月号では林真理子・栗木京子・桐野夏生の鼎談が目を引いた。現在、林真理子は日本文藝家協会、栗木京子は現代歌人協会、桐野夏生は日本ペンクラブの理事長・会長職にあるが、これらの各団体で女性がトップになるのは史上初であり、三団体のトップが揃って女性になったことを象徴的な出来事であると考える向きもあるだろう。鼎談では理事長・会長職に選ばれた経緯やコロナ禍における活動実態、高齢化が進むなかでの新規会員の取り込みなど共通の話題も語られるなか、文筆家の職能団体としての意識が強い文藝家協会と「プロ」の定義が曖昧な歌人の団体との温度差を感じる場面もあり、歌人が結社や協会などの組織に所属する意義について改めて考えさせられるものとなっている。また、「ペンクラブ」の「P」は「ポエット」の略であり、海外では詩人の会員も多く社会的認知も高いという桐野の話は、例えば、昨年一月のアメリカ大統領就任式で二十二歳の詩人、アマンダ・ゴーマンが詩を朗読したという出来事を私に思い起こさせた。 さて、鼎談を読んで少しずつ地殻変動が起きていることを信じたい気持ちになったが、一二月十日の朝日新聞には文芸や演劇、映画、美術などにおけるジェンダーバランスを調査した「表現の現場調査団」の中間報告が掲載されていた。この調査によると、芥川賞をはじめとする小説に与えられる八賞では、審査員の男女比はおおむね男性六割、女性四割、受賞者で女性の割合が男性を上回ったのは二賞のみ、小林秀雄賞などの評論の三賞では審査員も受賞者もほぼ百パーセント男性だったといい、「一部の賞では男性主観の評価が常態化している」「歴代の受賞者が審査員を務めている賞では、女性の審査員が増えにくい構造になっている」とまとめられている。短歌は調査の対象になっていないものの、ここ十年ほど(二〇一〇年以降)の新人の登竜門と言える三賞(角川短歌賞、短歌研究新人賞、歌壇賞)と現代短歌評論賞について調べてみたところ※、審査員は男女同数か五名のうち二名と三名に分かれて累計ではほとんど同数という印象だが、作品賞の受賞者については短歌研究新人賞がほぼ男女同数、角川短歌賞では男性がやや多く、歌壇賞では逆に女性が多いなど賞によってばらつきがあった。一方、評論を対象とした現代短歌評論賞では受賞者の八割程度が男性であり、これが応募者のジェンダーバランスによるものか、何らかのバイアスがかかっているのかは不明なものの、分野を超えて共通の傾向がみられることは興味深く感じた。 この調査を受けて芥川賞選考委員の平野啓一郎が「(ジェンダーバランスに)偏りがあると自覚された時、実際の候補作の良し悪しの判断にその是正を反映させようとするのは難しい」(平野啓一郎Twitter)と反応したように、「作品ありき」の文芸分野の賞の選考においては、作品・評論の質が一番の争点であり、必ずしも作者のジェンダーによって受賞作が決定されるべきではないとする意見はあるだろう。しかし、アカデミー賞で「白すぎる(白人受賞者が多い)オスカー」が批判されてきたように、作品本位の評価をしているつもりでも、少数側の作品が正当に評価されず、無意識に排除されていることは当然あり得るだろうと思う。今回の調査では男女という区分けだったが、例えば性的マイノリティーや日本語を母語としない作品を評価することを考えたとき、「選ぶ側」にも多様な作品を感受し評価する土壌があることがますます必要になってくるのではないだろうか。 ※個々の性自認を確認したわけではないのは断っておきたい |
||||||
| 2022年1月号 | ||||||
| 『歌人名簿に思うこと』 山崎 聡子 | ||||||
|
二〇二一年度の「短歌研究年鑑」が発売され、今年から恒例だった歌人名簿への住所の記載がなくなった。時代の流れから考えると「個人情報を含む雑誌が全国の書店で販売されている」状態が異常だったとも言え、薄々と違和感をもつ人もいた「恒例」を廃止したという意味では一つの英断だと言えるだろう。これに関して、私には苦い思い出がある。はじめて歌人名簿への掲載を尋ねる葉書がきたとき、まさか個人情報がそのまま転載されるとは思わずに自宅電話番号(当時)を記載してしまい、何度か不審な電話を受けたことがあるのだ。あまりに迂闊だったと言えるが、最近では名簿を利用した業者による短歌商法などもあるようだし、コンプライアンスや個人情報保護の観点からもだんだんこの形態が厳しくなりつつあったのが実情ではないかと思う。 一方で、どうしても歯切れが悪くなってしまうのは、私自身がこの時評を含む短歌に関する文章をおおいに贈呈文化の恩恵を受けて書いているという自覚があるからだ。最初のうち、私が歌集や同人誌をいただくのは歌会で付き合いのある人や学生短歌会の知人など、ごく限られた知り合いに限られていた。以降、短歌に関わる期間が長くなるにつれ直接の知人ではない方たちからもいただく機会が増えたが、私でも恩恵に預かっているのだから、より歌歴が長い人のなかには歌集を「お金を出して買う」という感覚がなくなってしまう人もいるだろう。個人的には、読みたいと思っていた著者の歌集であれば「対価を払って書店で買いたかった」と思う一方で、贈呈していただかなければ知らなかった歌集との出会いもあり、贈呈文化を要不要で断じることに少しの逡巡がある。これはひとえに、(変化の兆しがあるとはいえ)歌集の多くが商業ベースで流通していない現状の反映であり、歌壇が互いに歌集を贈呈し合い、濃密な批評空間をつくりあげることで維持されてきた側面は無視できないのではないかと思う(もちろん、贈呈文化自体がマーケットを縮小させてきたとも言えるのだが……)。 この点について、同じ短歌研究年鑑で石川美南が「寄贈文化が残る歌壇において、住所録が入手しにくくなることが、さらなる読者の棲み分けにつながらないと良いのだが」と危惧を表明している。私自身もこれまで関わった同人誌などの寄贈を歌壇名簿を元に行ってきたが、今後は住所録が入手しにくい無所属や若手の歌人にとって「(読まれないかもしれないけれど)岡井さんや馬場あき子さんに贈呈しよう(例)」ということが難しくなるかもしれない。そうした、世代間の棲み分けも、商業的な出版ルートに乗っている歌集とそうではない歌集の二極化も、名簿の廃止によってより加速する可能性がある。 このほとんど避けられない流れへの一つの打開策として、編集長の國兼氏は、誌面に掲載せずとも連絡先の確認の連絡は継続するとしたうえで、「皆さんをつなげるハブのような役割をしていく」と編集後記で述べている。近年、詩歌を専門とする出版社以外での歌集の商業出版の例が増え、短歌を「広く」届けようとする流れがあるが、専門出版社が培ってきた人脈や密度の濃い情報は「必要な人に深く届ける」ためのアドバンテージになるだろう。 石川が指摘しているように、コロナ以降、授賞式や批評会などの短歌のイベントが中止になり、世代も背景も異なる人たちと短歌を通して濃密なコミュニケーションをとる機会が激減した。前出の「ハブのような役割」の具体は不明だが、この大きな変化を契機に新しい交流のあり方が模索されているのが今なのだと思う。 |
||||||
| 2021年12月号 | ||||||
| 『「歌集」が誕生するまでに』 山崎 聡子 | ||||||
|
第一歌集を対象とした短歌賞の発表が近づいてきた。今でこそネットや同人誌など短歌の発表媒体は多様化しているが、一人の歌人をその作家性も含めて見通したいと考えたとき、「歌集」としてまとまったものが読みたい、というのは読者の自然な願いだろう。実際、鋭敏な一首で知られた作者が歌集単位で素晴らしい歌人であるとは限らないし、点のように散らばって見えにくかったその作家の美質や哲学が歌集を通して立ち現れてくるのを読む喜びは、すなわち短歌を読む喜びであると言っても良い。 一方で意識的になりたいのは、「歌集」の出版によって新人が評価の俎上に上がるという歌壇のシステム上の格差だ。歌集の多くが自費出版という形態をとる以上、歌集を世に問うことができるのはこの費用を捻出できる人に限られる。私が第一歌集を出したのは三十歳を過ぎた頃だったが、積み立ててきた貯金から安くはない出版費用を出したのは、それでも自分の歌集をこの世に誕生させたいという完全なる思い込みによるものだったといま振り返って思う。そして、もっと若かったら、子供をもった後だったら、仕事ができない状況だったら、自分や家族が病気や障害をもっていたら、私はこの歌集を諦めていた可能性もあった、とつくづくと考えるのだ。 最近では、副賞として歌集出版が約束された短歌賞がいくつか新設されている。二〇一三年から始まった現代短歌社賞は、第一歌集の出版を前提として作品三百首を公募する賞で、受賞者には歌集出版のほか、五百部が無条件で贈呈される。本賞によって出版された歌集には現代歌人協会賞・現代歌人クラブ賞を同時受賞した北山あさひの『崖にて』や門脇篤史『風に舞ふ付箋紙』、山本夏子『空を鳴らして』、直近では西藤定『蓮池譜』など、実力を備えた作者の第一歌集が並ぶ。また、書肆侃侃房の笹井宏之賞の副賞としても、柴田葵『母の愛、僕のラブ』、鈴木ちはね『予言』、榊原紘『悪友』の三冊が出版されている。 これらは新人を対象とした賞だが、中堅と言っていい作者のなかにも様々な状況から歌集を出版したくてもできない人も当然多い。そんななか、この九月に発行された西巻真『ダスビダーニャ』はクラウドファンディングによって資金集めがなされた歌集であり、賛同した多くの人の後押しによってこの世に誕生した歌集でもある。 葬(フューネラル)といふ語にはやらかく包まれてひとのからだは燃えてゆきたり あへて死者を数でかぞへよ死のひとつひとつは計り難きものゆゑ ぼくはぼくを生きるほかなく沸点を越えてゆらめく水を見つめる 読み終へてわたしに兆す火のことをあなたに打ち明けて夜が明ける 生きることの苦しさと美しさが渦巻いて襲ってくるようなこの歌集を読み終えて、この本がでなかった可能性のことを考えて胸が締め付けられた。前半には死をモチーフにした歌が並ぶが、葬(フューネラル)という言葉のもたらす陶酔感によって「生きている側」の生が照らし出されるように、この歌集の主体は言葉を紡ぐ営みによってままならない生をなんとか生き延びているように感じられる。そして、詩を書くという行為は本質的にはそれを書き、読む個人の救済のためにあるのだということをまざまざと見せつけられている気がするのだ。 「あなたの歌集が読みたい」と軽率に言って後悔したことが私にはある。それでも、それを願った人たちによってこの歌集が誕生した、この物語を喜びたいと思う。 |
||||||
| 2021年11月号
|
||||||
| 『読解は自由か』 山崎 聡子 |
||||||
|
少し前の話になるが、小説家の桜庭一樹が発表した「少女を捨てる」(文學界二〇二一年九月号)をめぐって、あるやりとりが話題になった。 |
||||||
| 2021年10月号
|
||||||
| 『正しく怒る』 山崎 聡子 |
||||||
|
「現代短歌」九月号の特集「Anthology of 60 Tanka
Poets born after 1990」を面白く読んだ。本号はタイトルどおり、一九九〇年以降に生まれた歌人六十人の自選十首と「もっとも影響を受けた一首」を紹介した特集号で、一九九〇年生まれの小原奈実までが収録されたアンソロジー『桜前線開架宣言』(二〇一六年)以降に出てきた作家を総覧できる充実の特集となっている。 ネロ帝の若き晩年を思ふとき孤独とは火の燃えつくす芯(菅原百合絵) 乗ればいい 胸きつくまで締められた馬ずぶ濡れになったとしても(坂井ユリ) 花びらはいつまで意識があるのかをただすこしだけ橋から見ていた(松尾唯花) 火は火でしょう、ひとつの名字を滅ぼして青年の手はうつくしいまま(帷子つらね) ぼくらがいちばんきれいなときに きのこ雲 自撮りをしたりするのだろうね(三上春海) 正直に言って、六十人もの歌人を世代論でくくるのはほとんど暴論にしかならないとは思う。それでも、私がこれらの歌を読んで感じるのは、他者の痛みや自らがもつ暴力性に対する鋭敏な想像力を基調に作歌する作者が総じて多いということだ。 「暴君」と言われたネロ帝の孤独を、胸を馬具で締め上げられながら人間に奉仕する馬の存在を、あるはずのない花びらの意識の喪失の瞬間を思うとき、その心は人間、さらには人外のものがもつ痛みへと添う。帷子の歌は婚姻の暗喩とも読めるが、人から名前を奪った青年の無自覚に美しさを見出してしまう感覚を、作者は自ら罰しているように感じられる。また、三上の歌では茨木のり子の詩の一節と「自撮りをする」日常の間に二字空けで唐突に「きのこ雲」が差し込まれることで、暴力によって奪われかねない日々の壊れやすさが暗示される。 アイライン引くのがうまくなっているあなたに毎日があったのね(乾遥香) 唇をなめる。お寿司の味がする。i will give you all my
love.(山中千瀬) 潮騒をはべらせながら棒切れで〈愛〉の字を書く字は愛で書く(佐原キオ) 特集中の対談で藪内亮輔と大森静佳が「祈り」というキーワードを挙げていたが、日常を愛でることで自分を含む世界の健やかさを願う感覚も多くの作者に共通している。乾の歌では「あなた」を「わたしの見ていなかった時間」まで遡って抱きとめようとしているようだし、山中の「i will give you all my love」も佐原の歌で念押しされる「字は愛で書く」も、現実の「ここ」をなんとかユートピアに変えるための祈りのように思えてくる。 さて、本特集に関してもう一つ話題になったのは、扉文で「無検査のダイヤモンドの大売り出し!」というランボオの詩を引用し、「このアンソロジーに自分がなぜ呼ばれなかったのか、不満顔のきみのために理由を書こう」などと書いた編集後記が一部で反発を招いたことだ(原文は誌面を確認してください)。最大限に好意的に解釈すれば、若手に対する期待も込めたアジテーションの一種なのだろうけれど、編集者と著者との関係として「選ぶ」側の特権を強化する物言いは不誠実だし、フェアではないという指摘は全くその通りだろう。 |
||||||
| 2021年9月号 | ||||||
| 『関係性のなかの暴力を詠む』 山崎 聡子 |
||||||
| 川本千栄の第四歌集『森へ行った日』をくるしい気持ちで読み終えた。川本さんの歌は『子育てをうたう』(松村由利子著)などに引かれているのを読んだことがあり、そこでも主体がくるしそうに喘いでいたと記憶しているが、歌集として通して読むと、自らの内にある暴力性に非常に自覚的な作者だという印象をもった。 「君のため」かかる言葉の横暴を生徒に与え子にも与える ルール守って登校しろとわれが言い登校できなくなりし女生徒 叱られたわけは覚えず叩かれたことだけ恨んで子は言い募る 女よとイエスはマリアに言いたりき 母さん僕は遠くへ行った 小さい小さいお名前シール貼ってある青い鉛筆本棚の隅 本歌集において「内なる暴力」が描かれるのは、主に教師として対峙する生徒たちと、自らの息子に対してだ。一首目、二首目には、「君のため」と言い募ることの暴力性を何よりも自覚していながら、教師という枠組みの中でしか振るまうことができない自分の無力感、結果として生徒の人生を損なわせてしまったことへの後悔がにじむ。息子との関係を詠んだ歌では、自分が親として当たり前に行使した影響力が、息子というフィルターを通してある種の暴力として照らし出されるさまが描かれる。 イエスが自らの母であるマリアを「女よ」と突き放したように、親子とは究極の他者であり、濃密な時間の後に離れていくのが自然なことではある。しかし、「小さいお名前シール」の歌にある蜜月を思うとき、 最も近い他者との関係性の移ろいやすさに胸が詰まる。 貝の身の苦しみとして成る真珠一粒ずつを耳に噛ませて 教科書のローザ・パークス何回も何年もバスの座席を追われ また、直接に人間を詠んだものでないこれらの歌も、川本の「暴力」への感受性の強さを示している。つまり、真珠を産む過程での貝の苦しみに思いを寄せ、教科書の中で何度も「あの場面」を再現させられるローザ・パークスを空想することは、生きていることがすなわち加害そのものであるという感覚に下支えされているように思うのだ。 発生の最終過程の数日を過ごす氏のF傍らにいる カウントダウンの単位は日から時になってまもなく分になることだろう 父と母の遺伝子を持って生まれるというだけのこと どのひともみな 同時期に読んだ牧野芝草の第二歌集『勾配』から引いた。川本の歌とは反対に、牧野の歌では、人との関係性のなかにある暴力性が慎重にマスキングされている。 掲出歌は明らかに挽歌だが、「F氏」との関係性や主体の感情は直接的には示されず、死を受精から始まった生物の発生の最終過程という「理知の目」でみつめようとしている。牧野自身があとがきで「感度(sensitivity)と増幅度(gain)」という言葉を使って説明しているが、言葉が他者に与える影響を慎重にコントロールした結果として、牧野は「関係性を歌の道具にしない」ことを選び取っているのだろう。 人と関わることは多かれ少なかれ何らかの影響を与え合うことであり、そこにはある種の暴力が伴う。他者を短歌に詠み込むときにはその暴力性との距離をどうとるかが作者自身に問われているのではないだろうか。 |
||||||
| 2021年8月号 | ||||||
| 「心」 と「人生」 山崎 聡子 |
||||||
|
時評をネタに時評を書くのは反則だろうと思いつつ、「歌壇」七月号の平岡直子の時評に見逃せない示唆があったので取り上げたい。「大森静佳について」と題されたこの文章は、昨年出版された大森の『この世の息 歌人・河野裕子論』や近年の彼女の作品と論を取り上げつつ、現代短歌の読みにおける倫理観とそれを代替するものについて考察がなされている。 平岡の指摘のとおり、大森の同書は「母性」を切り口に読まれがちだった河野裕子の歌に仄暗い身体性と前衛歌人との共鳴という新たな視点から切り込んだという意味で画期的な論であり、大森の近作に短歌を類型的な「人生」に重ねる読解に対する批評が加えられていることは事実だろう。当欄でも、大森の「産めば歌も変わるよと言いしひとびとをわればゆるさず陶器のごとく」(「短歌研究」二〇二〇年一月号)を取り上げたが、個々の人生が多様化するなか、一定のライフイベントを想定したステレオタイプな読みが次第に効力を失っていくのはほとんど不可避な流れではある。 一方で平岡は、「短歌のメインストリームの文体がまさにこのステレオタイプの人生に依存することで発達してきた」と述べたうえで、「人生に対して最適化された文体は、人生との接続を制限されると生命線が消えてしまう。短歌は更新を拒んで化石になるか、今までに築いてきた財産のうちの大部分を失うか、二者択一の危機に晒されている」という恐るべき予言をしている。それでは、「人生」の代わりに依拠すべきものは何か、というのがこの時評の肝なのだが、平岡はその代替として大森が提示しているのが「心」であると読み解き、「心をいわば純身体に昇格させることで、社会性という服を着ない凡庸性のあるフォルムを見出している」と指摘する。つまり、「心」という個人的内面を社会に開かれたものとして感知させることで、社会的外面に頼った読みとは異なる水路が開かれるというわけだが、ここで平岡直子が言おうとしていることはそのまま平岡自身の歌にも当てはまる。 メリー・ゴー・ロマンに死ねる人たちが命乞いするところをみたい 心臓と心のあいだにいるはつかねずみがおもしろいほどすぐに死ぬ すごい雨とすごい風だよ 魂は口にくわえてきみに追いつく (『みじかい髪も長い髪も炎』/本阿弥書店) 平岡直子はとても社会的な歌人だと思う。その意味は、社会問題を直截的に書いているからでも、何かを強く指弾しているからでもなく、平岡が「書かないこと」を選択している無数のものが、逆説的に社会や「短歌」というシステムの鋭い批評にもなっているということだ。「ロマンに死ねる人たち」を冷たく突き放すように、平岡の歌では安易な共感を拒んで言葉が拡散されていくが、ここには予定調和的な共感を排することで、心と言葉が直接つながってしまったような不思議な手触りがある。生命の核である「心臓」と精神の核である「心」の間で死んでしまうはつかねずみは私たちの暗喩かもしれないけれど、このような脆さを抱え込みつつ他者をどうしようもなく希求するときの「心」そのものを平岡は言葉の作用だけで描こうとしている。 「心」という掴みどころのないものに体重をかけて作歌をするのは簡単ではない。しかしそもそも、これまで私たちが共有している思われた「人生」がどれほど「同じ」だったろうか。そのことを考えるとき、「心」以外をすっかり脱ぎ捨ててしまっている平岡の短歌は、逆に人間そのものを投影しているような気がしてくるのだ。 |
||||||
| 2021年7月号 | ||||||
| 『「シーン」について』 山崎 聡子 | ||||||
| 先日発売された瀬戸夏子による短歌ブックガイド『はつなつみずうみ分光器』(左右社)を読んでいて、「テン年代」というコラムが目に留まった。「読むべき歌集55」と銘打った同書は二〇〇〇年から二〇二〇年までに発行された歌集(第三歌集まで)を縦横無尽に取り上げて評がなされている。ユニークなのは、この本が単なる歌集紹介に留まらず、関連する短歌史的な出来事を取り上げ、この年代の「シーン」ともいうべき空気を書き留めようする明瞭な思想に貫かれていることだ。 歴史をつくるのは暴力だと思う。けれど歴史抜きにものごとはすすまないとも思う。わたしはこの本で自分が考えるここ二十年の短歌の歴史を紹介した。もちろん主観である(中略)。とはいえ、わたしの主観のなかに存在する客観らしきものがここはおさえてほうがいいのではという部分には耳を貸したつもりだ。良くも悪くもきちんと暴力をふるえていたらいいなと思う。 瀬戸があとがきにこう書いているとおり、個人の視点から歴史を記すことはある種の暴力を伴う。しかし、ここでの瀬戸の歴史を記録しようとする「暴力」は、放っておいたら消えてしまったであろう小さな歴史を書き留めることに使われている。 私もこの時期に短歌を書きはじめ、上下の年代の動きを傍らで(ぼんやりと)見ていた一人だが、そこには短歌総合誌に取り上げられないようなシーンにおいて、文学フリマを背景とした爆発的な同人誌の流行があり、大学短歌会の興隆があり、短歌投稿サイトが生まれ、ネットプリントなどの新たな媒体の発明があった。そのことが、二〇〇七年の『短歌ヴァーサス』の終刊と結び付けられ、多様な短歌の発表媒体を得た一種のムーブメントとして記されたことは、確かに「歴史」なのだと思う。私自身も先行世代の同人誌である[sai]や「風通し」を読み、平岡直子や服部真里子、藪内亮輔が参加した「町」や瀬戸自身も同人であった「率」、自分より年下の世代の「羽根と根」、「穀物」といった同人誌に刺激を受け、多くの歌人の名前と作品をこれらの同人誌やネットを通して知ってきた。前出の平岡直子は待望の歌集を刊行したが、ここ数年を例に挙げても「羽根と根」の阿波野巧也と橋爪志保、「穀物」の川野芽生と山階基など、これらの同人誌出身の歌人の歌集出版が相次いでいる。つまり、これらの「ムーブメント」の豊潤な成果が目に見える形で出てきたのがこの数年のことなのだと思う。 もう一つ、私がここに付け加えるとしたら、その都度メンバーを募集する互選形式の無記名歌会が各地で始まったことを挙げたい。その筆頭が早稲田短歌会のOBを中心に二〇〇五年ごろ立ち上げられた「ガルマン歌会」だが、「ノーヒエラルキー歌会」と謳ったこの会は、若手からベテランまで様々なバックグラウンドの歌人延べ三百名が参加し、自由な批評の場として機能してきた。その活動を支え、歌会をオープンな場にすべく尽力してきた谷川由里子の第一歌集もこのほど同じ左右社から発行された。 ずっと月みてるとまるで月になる ドゥッカ・ドゥ・ドゥ・ドゥッカ・ドゥ・ドゥ(谷川由里子『サワーマッシュ』) 谷川の歌は音楽のように流れる日々を結晶化しているが、歌会はライブのようなもので、そこに流れる音楽やその場が纏う空気は記録されようがない。谷川の歌がこうしてまとまったことも、私にとってはある「シーン」の記録だ。 これらの二冊を読みながら、当事者の熱によって記録された「歴史」のほんの片隅にいられたことを嬉しく思い返した。 |
||||||
| 2021年6月号 | ||||||
| 『突き放される』 山崎 聡子 | ||||||
| 最近、とある記事が「炎上」して話題になった。発端はエッセイストの島田彩氏が発表した大阪・新今宮で体験した(とされる)人々との交流を書いたウェブエッセイだ。土地勘がないため知らなかったのだが、新今宮は日雇い労働者の街として知られるあいりん地区に位置し、近年では再開発が著しい土地柄らしい。ここを訪れた際に思いがけぬ親切を受けた筆者は、「借りができた分、貸しをつくる」と、偶然出会ったホームレスの男性に食事をおごり、その代わりに街案内を依頼する。その顛末をつづった文章は一部に好意的な反応もみられたものの、男性との不均衡な関係を「デート」と呼んで無自覚に振る舞うさまが、さらには記事自体が自治体のブランド向上事業として広告代理店に依頼されたものだったことが批判を呼んだ。個人的に恐ろしく感じたのが、この文章が、一見フラットな、「耳当たりの良い」文体で書かれていることだ。 「ホームレスとデートって、正直どうなの?」そう思われたかもしれない。でも私の中では、たまたま出会って、たまたまデートし、たまたま友達になった人。その人がたまたま、家を持たずに暮らしている人だった。それだけのこと。(本文より) この一文を読んで、正直私はどきりとした。土地に根差す貧困と格差を直視することなく、あなたと私の違いは家がないことだけ、と言い切ってしまう鈍さは当然糾弾されるべきだが、視点を平板化し、自分の理解の範疇にその人を引き入れて消費したいという欲望を私自身がもっていないかと言えば嘘になるからだ。それは歌の読みにおいても同様で、「わからない」に立ち止まらず、勝手な補助線を引いて自分の「わかる」範囲に引き入れてしまうことが私にはある。その態度が、この記事と無縁と思えなかったのだ。 そんなことを考えながら新宿の紀伊国屋書店に立ち寄ったら、平井弘の新刊『遺らず』が平積みされていたので興奮して買って帰り、早速に殴られた。 いつのことだか思ひだしてごらんだからあんなことなかつたでせう 傘のさきでいぢるのは豆乳のふくろこれつぽつちこれつぽつち 6と9だから15といふはなしマウスもダックもきかされたらう 私自身平井の短歌に打ちのめされてきた一人だが、平井の歌を「わかる」と思ったことは一度もない。平井の歌を読むと、ただただ体内の仄暗い部分がのったりと脈打つのを感じるだけだ。一方で、例えば、多くの人が示してきた補助線である、戦争による兄世代の喪失や、無垢かつ性的な存在でもある「妹」の象徴性などについては、後付けで「わからされてきた」感じがしている。それは同時代を生きた人たちにとってはある種の真実なのだろうけれど、私にはその感覚を自分のものとして共有することができない。それでも、今まっさらな状態で『遺らず』を読んでいると、歌を引き寄せようとするたびに何度も引き離される感覚を自分が喜んでいるのを感じる。「あんなことはなかった」と断定する声の主は誰なのか。二首目の「傘でふくろをいじる」は地下鉄サリン事件の実行犯を、「6と9」の歌は原爆の投下日と終戦の日を思わせるが、なんらかの社会的な事象の暗喩を匂わせながらも、この歌集のなかの「声」はくぐもって、私たちにやすやすと「わからせる」ことをしない。 何かを読んで「わかる」と思うことは一つの価値ではある。それでも、「わからない」と思いながら作者の精神に降りていくときの仄暗い喜びを、私はこうして待っていたのかもしれない。 |
||||||
| 2021年5月号 | ||||||
| 『十年後のその日に』 山崎 聡子 | ||||||
|
東日本大震災から十年が経った。震災について考えようとするとき、私はただただ何も話せなくなる。ほぼ無傷の東京に住んでいて、何かを話せる立場にないと思ったから。何かを話すのが怖かったから。当時、震災を詠みこんだ歌が怒涛のように流れてきたけれど、私自身は当時もその後も震災について短歌や文章に直接的に書いたことはない。半年後に仕事で南三陸を訪れて夥しいほどに積み上げられたぐしゃぐしゃの車を見たことも、遺体の検視を担当した歯科医師から話を聞いたことも、とうとう家族以外には話すことができなかった。そして、その小さな接点を絶対に忘れないだろうという当時の予感とは裏腹に、わたしはあっという間に記憶を薄れさせていった。 この春、『3653日目〈塔短歌会・東北〉震災詠の記録』が発行された。これは塔短歌会の東北にゆかりがあるメンバーが震災直後から発行する冊子をまとめたもので、震災からの日数を冠して『99日目』から『3299日目』まで計九冊が収録されている。 十年経って思い出すのは、当時、誰がどの立場で震災を詠むか、というのが度々話題になったことだ。一例が、福島在住の鈴木博太の短歌研究新人賞受賞作「ハッピーアイランド」だが、原発を扱った本作を推挙した穂村弘は、「福島」の直訳をタイトルにしたこの作品について、作者が福島在住で安堵したと度々言及している。つまり、「福島の人間以外が福島を『ハッピーアイランド』と呼ぶのはまずい」という論理的な意識が働いたわけだが、当時は地震とそれによって引き起こされた原発事故について、当事者性の濃淡を推し量りながら、薄氷を踏むように作品の鑑賞がなされていたように記憶している。 しかし、十年分の記録を読んで改めて考えさせられるのは、震災を近く目の当たりにした地においても当事者性の濃淡があり、書くことへの逡巡があり、沈黙があり、現実を言葉にするときの格闘があったということだ。参加している二十数名のなかには、被災した自宅の暗がりで歌を書きつけたという梶原さい子のような人もいれば、壮絶な経験ゆえにしばらくは書くことができなかったという佐藤涼子のような人も、「自分は傷ついていない」との葛藤を抱えながら震災を詠み続ける人間もいる。座談会やエッセイには、震災を「歌題」にすることの迷いや時間の経過による心境の変化が率直に語られ、混沌や割り切れなさも含め「その時」を記録し、記憶に焼き付けようとした歌人たちの息づかいが保存されている。 〈99日目〉被災地にならざる幸い母は言う 余震に揺れいる蠅取りリボン(数又みはる) 〈733日目〉時折を想ふ水漬きしわがピアノの弦断つときを 極まる鳴を(梶原さい子) 〈1883日目〉シャコエビは食べなくなった どうしてと聞かれて答えられなくて、吐く(佐藤涼子) 〈2199日目〉夢の中なんども津波押し寄せてなんども失くす今はなき家(逢坂みずき) 『99日目』で「人ごとの論評、飾り立てた言葉、奇をてらう歌。ああ、本当に遠い」と書いたのは梶原だが、「その日」だけ追悼特集を見て黙祷する私(たち)との遠さは今後も大きくなるばかりだろう。それでも、短歌を通してパーソナルな記憶に触れること、被災前の海辺の町とその後の変質について知ることは、女川に、気仙沼に、福島に、少しだけ私を近くする。 図らずも十年目のその日を私たちは喪失と分断の中で迎えることになった。それでも私が何も失っていないのに変わりはないが、あの春のことを繰り返し知ることでしか忘れないことはできない。 |
||||||
| 2021年4月号 | ||||||
| 『美意識の変遷』 山崎 聡子 | ||||||
| 「ねむらない樹」Vol.6の黒瀬珂瀾特集を読んでいたら、唐突にある記憶が蘇った。短歌を始めたばかりの頃、一度だけ学生短歌会の合同合宿に参加し、黒瀬さんを遠くから目撃したことがあったのだ。年譜によると当時の黒瀬さんは『黒耀宮』を出したばかり。ピカピカの黒いロングコートを着て、目つきと舌鋒はひたすら鋭く、夜になると酔っぱらってゆらゆらと揺れていた。当時の私には立ち居振る舞いのすべてが異形の人のように映り、大学で教えていただいた水原紫苑さんとともに「これが歌人か……」と強烈にインプットされた。 さて、本特集では、インタビューや既刊歌集の抄出によって、この四十代の歌人の変遷を辿ることができる構成となっている。私にとってはリアルタイムで歌に触れてきた歌人がどのように短歌と出会い、何を考えて、どのように作歌しているかを知る貴重な機会となった。 濃密なインタビューは誌面を読んでほしいが、主題から外れたところで印象に残ったのは、「あ 雨の匂い 日暮れの舗装路を閑かに多数派が埋めていく」という勝野かおりの短歌を引きながら、短歌をやめていった人たちに言及しているくだりだ。 「勝野さんにはあちこち連れ回してもらって、僕を短歌の奥へ引っ張ってくれた人です。その勝野さんも歌をやめてしまった。みんなやめていきますね。先輩、後輩、賞をとった人も。(中略)寂しいけど、なぜか、僕は今まで残ってしまった。勝野さんの歌の気持ちがわかります」 若い頃に鮮烈な歌を残したまま作歌を辞めてしまう人は多い。その理由は生活環境の変化など様々だが、歌に対する理想や美意識が強い場合は特に、過去の自分を更新しながら作歌を続けるのはとても苦しいことだろう。黒瀬珂瀾はもちろん鮮烈に現れた歌人だが、だからこそ、最新歌集『ひかりの針がうたふ』を読むと、変わっていくことの痛みを抱えながら、変わらない美意識を貫こうとする意思が確かに息づいていることに感動を覚える。 死をかつて優しき岸と謳ひたるわれらが注ぎあふチリワイン 漂流の浮標にたたずむ青鷺のさみしくないか児を世になすは 飛鯊は夕陽へ逃げて朽網川しづかなりわれは母になれぬを 『ひかりの針がうたふ』 僕たちは月より細く光りつつ死ぬ、と誰かが呟く真昼 『空庭』 ふと気づく受胎告知日 受胎せぬ精をおまへに放ちし後に 『黒耀宮』 かつて堅牢な耽美的世界を構築し、「死」を親しく甘美なものと描写していた黒瀬の歌は、第三歌集『蓮喰ひ人の日記』以降、子を成し、その生を願うことで結果的に「生」の日向に引きずり込まれていっているように思える。また、『黒耀宮』にみられる「生殖をなしえない性」としての潔癖なイメージは、「母になれぬ」性の悲しみに転化して語られる。 朝に訪ひまた保育所を夕に訪ふわれら親こそ月を欲つ愚者(ムーンレイカー) 父われの胸乳にひたに捻りゐる娘よ黄砂ふる夜が来る 『ひかりの針がうたふ』 一方で、これらの歌では、保育所の夜、子供との添い寝という日常の場面が「月を欲つ愚者」「黄砂ふる夜」という一種過剰な語彙によって鮮やかに異化されており、これまでの美意識を踏襲した新たな歌の地平線を見るようで胸が熱くなる。 「残った」人間は、少しずつかつての自分を捨てながら変わっていくしかない。それは淋しいことでもあるけれど、黒瀬珂瀾の歌集を読んで、変わることの痛みとその先にある豊饒さを思った。 |
||||||
| 2021年3月号 | ||||||
| 『歌集を薦めるということ』 山崎 聡子 | ||||||
|
このところ立て続けに「短歌に興味があるのだけれどどの本がお勧めですか」と聞かれることが重なった。勤務先でも「木下龍也さんの歌集を買って面白かった」という人がいたし、穂村弘のエッセイや河野裕子、笹井宏之の紹介記事から歌集に辿り着いたという人を身近に何人も知っている。いずれもジャンルを問わず多読するタイプの読書好きで、近年、こういった人たちがリーチできる範囲に歌集が置かれる機会が増えたことにも関係があるのかもしれない。 しかし、何の気なしに投げかけられる「どの歌集がお勧めですか」という問いを前に、私はいつだって固まってしまう。なぜなら、短歌というジャンルが包括する範囲があまりにも広すぎるうえに、自分が読んでいるのはほんの一部に過ぎず、その人にとっての「最初の一冊」を選ぶことに気後れする気持ちがあるからだ。 そんな折、私自身も参加した短歌研究二月号の特集「短歌好きになりたい友人のための歌集入門」を面白く読んだ。この特集は三十人の歌人に「短歌を始めたばかりか、これから始めたい人にお薦めしたい歌集」を「四十歳未満」「四十歳以上」に分けてアンケートをとり、結果を集計したものだ。「四十歳」で区切る意義については戸惑う声が多く聞かれたものの、答えのなかにそれぞれの歌人の作歌に対するスタンスや短歌観が透けて見えて非常に興味深い。 藤島秀憲のように「『最近なんだかなあ』を連発する迷える友に」「自分の言葉に酔い痴れてしまう友に」とやたらに具体的な人物像を挙げてその人に寄り添った歌集を薦めようとする人もいれば、「年齢を重ねた人なら遠慮しない」「詩歌の剛速球を」と塚本邦雄『感幻樂』や水原紫苑『客人』を薦める黒瀬珂瀾のような人もいる。推薦する人が最も多かったのは俵万智『サラダ記念日』と石川啄木の『一握の砂・悲しき玩具』だが、各人が挙げた見事にばらけた歌集名と推薦理由を読んでいると、もっと無責任に熱意と思い込みによって歌集を薦めていいのだ、という謎の勇気が湧いてくる。 同号の時評では奇しくも花山周子が歌集の書評の賞であるBR賞(現代短歌社主催)を通して、「歌集の書評」(歌集を人に薦めること)について論考している。歌集の書評が「大枚をはたいて出版した著者のアフターケアを担う」という恐ろしい指摘は今回は置いておくとして、同賞で佳作となった乾遥香の書評に対して「断定していない書き方のなかに作品に対する距離感の潔癖さを読み取った」という内山晶太の評を引用しつつも、そこに本の魅力を伝えようとする熱・オーラが不在であるとして、「だから同じ『光と私語』を扱った山﨑修平の『仮構された「私」あるいは「私たち」』のなかの一首の読みに〈ぐっと惹きつけられたという染野の反応に私は座談会中最も惹きつけられた」と率直に書いているのが印象に残った。 花山が暗に指摘しているように、「人に本を薦める」ことは、時に自分のもっている熱を他者にぶつける暴力的な行為と言えるのかもしれない。そして、いくら熱をもって薦めたとして、チューニングが合わなければ相手に響くことがないというのも多くの人が経験している通りだ。しかし、私自身がそうであったように、「何か」が引っかかったときに自分で世界を開いていけるような一冊を薦めることができれば、推薦者冥利に尽きるというものだろう。 その「何か」を次に繋げるためにも、書店の片隅にできれば歌集や歌書が並んでいてほしい、といつも考えている。 |
||||||
| 2021年2月号 | ||||||
| 『語られるべき声を聞く』 山崎 聡子 | ||||||
| 二〇二〇年は間違いなく歌集の豊作年だったが、いくつかの歌集を前に思うのは、これまで埋もれていた「名もなき声」が確かに語られているということだ。これまでも、たとえば永井祐や斉藤斎藤、山田航らの短歌が非正規雇用や不景気といった社会的なキーワードで語られることは多くあったように思う。しかし、そのことに感じてきたのは、わかりやすい肩書も属性もない、激しくも鋭くもない、ときにぼそぼそした声はどこに行ってしまうのだろう、ということだった。 その埋もれてしまった「声」のことを思うとき、北山あさひの歌集『崖にて』(現代短歌社) に出てくる人たちのことを考える。 元気かな むかし彼氏に叩かれてそれでも笑っていた女の子 もしかしたら眩しいだけの水かもと思いつつまだ旧姓で呼ぶ 父は父だけの父性を生きており団地の跡のように寂しい あの赤いプラダの財布よかったな買おうかな働いて働いて 私の記憶にも恋人に叩かれて否定されてそれでも笑っている女の子、というのが確かにいた。あの子は今、どこで何をしているのだろう。それから、結婚した友達を旧姓で呼ぶときのすんとした淋しさ。家族という不確かで頼りない単位のこと。北山の文体は飛ぶように自由で饒舌だけれど、そこには日本の辺境で、社会にもみくちゃにされながら生きることしかできない人の人生が幾重にも折り畳まれている。 北山と同い年で同じく北海道出身の山田航の歌に「たぶん親の年収超せない僕たちがペットボトルを補充してゆく」というしばしば引用される歌があるが、この歌の核になっているのは「僕たち」と親世代との経済的な分断であり、社会に対する批評的なまなざしだろう。一方で、北山のプラダの歌を読むとき、北山の歌の方が圧倒的に「年収」に見放され、「年収」の遡上にもあがっていない感じがする。「働いて働いて」という繰り返しから、この作中主体が十万円弱(筆者調べ)のプラダの財布を相当頑張らないと買えないことがわかる。しかし、働いて働いてやっと買える財布がつながる先は「社会」ではなく、社会を批評する術もなくその怒涛に放り込まれる「一個人」の方なのだ。 同じく今年出た田宮智美の歌集『にず』ではこんな歌が印象に残った。 震災後通い始めたメンクリの道の辺に建つ仮設住宅 異常無しと診断されるばかりなり震災より続く月経不順 こんな仕事こんな仕事と思いつつひと月居れば給料日くる 薄い壁越しに花火の音を聴き裸でそうめん茹でる 一人だ 田宮の歌集では、震災後の東北で暮らす日々が描かれるが、主体は家や家族を失ったわけではなく、被災者支援の対象からも外れた立場にある。つまり、社会的には「異常無し」でありながら、震災を境に自分自身が変質してしまったという感覚が歌集全体を覆っている。この襞の深さに一瞬たじろぎそうになるが、それでも「ひと月居れば給料日くる」の率直さ、裸でそうめんを茹でる主体のどっしりとした生への肯定感に救われるような思いがする。 |
||||||
| 2021年1月号 | ||||||
| 『欲望の出所』 山崎 聡子 | ||||||
| 第六十六回角川短歌賞が発表され、未来短歌会から田中翠香「光射す海」と、道券はな「嵌めてください」のダブル受賞となった。各短歌賞の歴史をみても、同じ結社から同時に受賞者が出るのは極めて稀であり、まずはお二人の受賞をこころから祝福したい。 田中翠香「光射す海」は、シリアを舞台に、戦場ジャーナリストの視点から紛争地を捉えた連作だ。こういった「成り代わり」によって連作を編む場合、ディテールの細かさが作品の命綱となることは間違いないだろう。なぜなら、ディテールの破綻や粗さはすなわち「この語り手は信頼できるか」という読者の疑問として跳ね返ってくるからだ。その点、田中の連作は、我々が報道を通してしか知りえない紛争地の手触りを想像力だけで立ち上げており、その目の細かさは高感度のカメラアイを思わせる。 死者たちはビニールシートにくるまれて半目を開けてみな空を見る トルコからシリアへ向かう検問所の事務所にかかるルノワールの絵 水を飲みシートベルトを外したらそっときらめくTOYOTAのロゴよ 例えば、死者たちの顔から空に向かってカメラがパンするような映像的な描写の巧みさ。「ルノワールの絵」「TOYOTAのロゴ」というアイテムの意外さと「ありえるかもしれない」感じ。田中は影響を受けた作品として映画『娘は戦場で生まれた』を挙げていたが、作品の中にただ一人の人間の目を固定するという短歌的なアプローチは、カメラを持つ人間と被写体の関係を思わせ、本作のドキュメンタリー性を担保しているように思う。一方、選考座談会では「作中主体=作者」を疑うことなく評が進められており、読後にすっきりしないものを感じたのは私だけではないはずだ。「(最近の歌集や賞は)リアリティ重視、本人の境遇とかキャラクターを重視している感じがして」という藪内亮輔の問題提起があったが、作者が作品として立ち上げた「リアリティ」と、境遇上の「リアル」を分けた地点から批評を始めることがまずは必要だろう。 田中が想像力を梃に「外」に接続することを志向しているとしたら、道券の作品は自らの「内」に深く根を下ろしていくような表現が印象に残った。 硝子玉を眼窩に嵌めた人形よ見るとはひしとせめぎあうこと いつかいつか羞(やさ)しいあなたを立たせたい老衰という眩しい水際 皮膚いちまい隔てて触れるあなたには濁流がただとどろいている 保冷庫のあおいひかりに濡れているあなたを握り潰したかった 一、二首目は人形展を題材にした歌。人形を「見る側」であるはずの主体は、いつのまにか「見られる側」に立ち、人形の身体となかば同化していく。この人形と「わたし」との関係は、濃密な性愛のなかに立たせた「わたし」と「あなた」の暗喩のように響き、関係性をさらに張り詰めたものにしている。皮膚と皮膚を触れさせても届かない濁流があること。人との関係の中で自らが(人形のように)歪められいく感覚。「老衰という水際」「握り潰したかった」というほのかに加害性を帯びた認識は、人との関係の中で生まれる自らの暗い欲望に向き合うことから出てきた表現のように思う。 アプローチやその表出の仕方がどうであれ、歌はその人の欲望を映すのではないか、と最近よく考える。田中の作品にある「物語を語りたい」という欲求も、道券の歌の「あなた」へのほの暗い欲望も、作者の表現に対する強い欲望を物語っている。その欲望の切実さこそが、作品の確かな武器になることは間違いないだろう。 |
||||||
| 2020年12月号 | ||||||
| 『わたしは透明になれるか』 山崎 聡子 | ||||||
| 「角川短歌」十一月号の井上法子のコラムには身をつまされた。「青年の主張」と題されたこのコラムは「親父の小言」というコラムと見開きで掲載され、タイトルからして若者に一家言ある中高年(男性)と理想を語る若者、という家父長制的なグロテスクさを感じるコーナーだ。ただ、内容については、本当に「親父の小言」になっているものもあれば、短歌にまつわる思い出話を書く人もいて、執筆者の、というよりも、編集部の意図を強く感じる見開きとなっている。 さて、「たましいのディメンションについて」というタイトルが付された井上のこの文章は、「青年の主張」などという枠を飛び越えた、魂からの叫びだろう。 「半年間、浴びるようにうたの世界の書物を手にして強く感じたのは、どうしてうたの世界のひとびとは、こんなにもおのれをかたりたがるのだろう? という疑問でした。(中略)わたしは私的なものごとを詠わない、と書くと、覚悟や度胸が足りない、といったご指摘を受けることがままあるのですが、世界には、わたくしごとよりも、もっと強く胸に迫るうつくしいものごとが多すぎるのです。(中略)ことばだけの透明な存在になりたいのです。これは甘えでしょうか。贅沢な悩みでしょうか。」 この文章を読んだとき、短歌を始めたばかりの、自分を消してしまいたいと思っていた自分を思い出して泣きそうになった。ことばだけで世界を捉えなおしたい、覆したい、何か美しいもの、ときに醜いものを構築したいというのは、詩を書くうえでのほとんど原始的な欲求だろう。だからこそ、学生短歌会を出て外部の歌会に行ったときに、短歌の批評としてそこに書かれていない個人的なプロフィール(出生地や婚姻歴まで)に触れる読みが展開されるのに戸惑ったし、プロフィールを晒すことが表現者としての覚悟に直結するという思想を率直に言って恐ろしく感じた。では、ことばだけの存在にわたしたちはなれるのか。 「わたくしごとよりうつくしいものごと」という井上の文章を読んで一番に考えたのは、川野芽生の歌集『Lilith』のことだ。あとがきに「人間は言葉に仕える司祭としてのみ存在意義を持つと思っていて、それでも、言葉が人間なしで成り立たないことがときにたまならなく口惜しく、悲しくなります」という思い詰めたような一文があるが、川野もまさに「透明なわたし」を志向して、ことばの力だけで世界を構築しようとしている作者の一人だろう。 Harassとは猟犬をけしかける声 その鹿がつかれはてて死ぬまで 〈男みなかつて狩人〉その嘘に駆り立てらるる猟犬たちよ ウェルギリウスわれなり薔薇といふ九重の地獄(Inferno)ひらけば 魔女を焼く火のくれなゐに樹々は立ちそのただなかにわれは往かなむ 歌壇賞を受賞した表題作「Lilith」からとった。西洋文学や神話のモチーフを取り入れ、堅牢なことばによって構築された本作は、リアリズム的な短歌の作り方とは無縁だが、ここには世界の不均衡に対する告発と闘争の意思がありありと浮かぶ。自らウェルギリスとなって地獄の扉を開き、魔女を焼く炎のなかに身を差し入れさせるものは、現実世界の痛みであり怒りだろう。 ことばが発するそばから何らかの文脈に汚されている以上、作者は透明な存在にはなりえないし、どんな詩も作者自身の反映であることは免れないかもしれない。それでも、ことばが「わたし」から離れて別の生命を得ることの奇跡を私は目撃したいと思っている。 |
||||||
| 2020年11月号 | ||||||
| 『重い身体・軽い身体』 山崎 聡子 | ||||||
|
『世界で一番すばらしい俺』(工藤吉生、短歌研究社)を読んで、短歌にも体重があるだろうか、と思ってもみなかったことを考えた。 目を閉じて頭を下にして落ちた六十九キログラムの自分 親指に指紋があると思い出し無性に見たくなり飛び起きる 生命を恥じるとりわけ火に触れた指を即座に引っ込めるとき 力の限りがんばりますと言わされて自分の胸を破り捨てたい 工藤の短歌の特徴は、ボディーブローのようにきいてくる身体の、人生の重さだろう。一首目は、失恋から飛び降りを図った学生時代を詠んだ一首。六十九キロという実体をともなった重みが読者にのしかかるように降ってくる。この「重い」身体は、彼にとっては居心地のよい容れものではないのだろう。「親指に指紋があることを思い出す」という自分の意識と身体との乖離、また「生命を恥じる」「自分の胸を破り捨てたい」の歌にあるような過剰なまでの自己罰的な感情の発露をみるとき、彼の命そのものがどっしりと臓腑に落ちてくるような感覚に陥る。そして、この重い身体を引きずるように生きている人物に好感さえ抱いてしまっていることに戸惑うのだ。 一方で、身体が「軽い」短歌として思い浮かんだのが、同時期に発行された阿波野巧也の『ビギナーズラック』(左右社)だ。 ぼくの手にiPhoneだけが明るくて自分の身体で歩いてゆける お金もらってうれしい昼間 バファリンでお酒を飲む 風景が体になじむ たばことか神社の話をしてあるく ふつうでいたいなこのままずっと 歯列矯正の症例写真を見ることが趣味 ささやかにぼくを支える 阿波野の歌で、主体はよく歩いている。iPhoneの灯りを掲げて街中を歩き回るこの人物は、軽やかな「ちょうど良い」身体をもっているように思える。世界は心地よく開かれ、または心地よいものを自ら選び取って風景を自分に「なじませていく」。当然、世界は心地よいもので溢れてばかりではない。けれど、阿波野の歌では、「歯列矯正の症例写真」のようなささやかなものをお守りに変えることで、なんとか日々を鮮やかな記憶として定着させようとしている。 そして、工藤が逸脱してしまった「ふつう」と、「ふつう」を守ろうとする阿波野の世界観の違いが如実に表れるのは、自らの内部よりも、外部への視線の向け方にある。 それでも町は生きものだからいい ぼくの自転車がない でも、だからいい フードコートはほぼ家族連れ、この中の誰かが罪人でもかまわない(阿波野巧也) N君の家が床屋であることをどうして笑ったんだろオレは 戦えばオレをぶちのめせるだろう中学生の低い挨拶(工藤吉生) 阿波野の歌では、「ぼく」も「ぼくの自転車」も「フードコートの家族連れ」も循環する町の風景の一つでしかない。その中で生きる自分と他者とを相対化する意識が「誰かが罪人でもかまわない」という赦しにも諦観にも思える態度につながる。一方で、工藤の歌では、主体の意識は罪を犯す側と犯される側を行き来し、他者も含めた世界が自分の自意識で覆いつくされるような濃厚な気配がある。おそらくは世界に対しての「自分」の比重が歌の重さの印象の違いにつながっているのだろう。 短歌を書くことは私にとって内なる自意識との闘いだ。だからこそ、そこから自由に見える阿波野の歌も、自意識を極限まで煮詰めた工藤の歌もひとしく眩しく思う。 |
||||||
| 2020年10月号 | ||||||
| 『死は追いつけない』 山崎 聡子 | ||||||
|
自分にその資格があるとは到底思えないのだけれど、岡井さんの訃報を聞いてからしばらくは何も手につかず、岡井さんの歌を頭の中で反芻することを繰り返していた。遠く遠く眺めることしか叶わなかった私なんかでも、だ。だから、歌壇にとって、そして直接声を聴き、話をし、その作品と人間性に長年触れてきた人たちにとってどれほどの衝撃か。その喪失の大きさを思って呆然としている。 『ネフスキィ』で描かれるのは、死と不死のあわいである。ふくらんだりひきのばされたりとする韻律により、すこしずつ、すこしずつ押し拡げられる時空を揺蕩っていると、アキレスが亀に追いつけないように、死は岡井隆に追いつけないんじゃないかと思ってしまう。 斉藤斎藤が現代詩文庫『岡井隆歌集』(思潮社)でこう書いていたけれど、私も、そしてたぶん多くの人も、死を飄々とかわして永遠に前進し続ける存在として岡井さんを感知していたように思う。その根拠は、最後まで変幻自在で挑戦的だった作品群は当然のこと、私にとっては、同年代の短歌の友人たちから聞いた(例えば、石川美南さんや笹公人さんが『短歌研究』の追悼文に書かれていたような)厳しくもフラットに若手に開かれていた視線であり、「歌集批評会の後に一緒にファミレスに行ったことがある」という真偽不明の自慢話の中にあるチャーミングなお人柄だった。そこには、たとえ直接触れ合ったことはなくても同時代のしっぽを生きているという喜びがあり、それがいつまでも続いてほしいという願望に似た気持ちがあった。私は岡井さんと言葉を交わしたことすらないのに、そんな気持ちをもっていたのはなんでだろう。一昨年の夏の大会で初期未来の歌人を取り上げたとき、田中槐さんが「私たちはもうすぐ歴史になることに触れている」と話していたことを強烈に覚えている。寺山修司や塚本邦雄は私にとってはほとんど歴史なのに、岡井さんについては歴史になるあわいのわずかな時間を目撃することができた。その幸福を、今更ながらに思う。 屍の胸を剖きつつ思う、此処嘗つて地上もつともくらき工房(『土地よ、痛みを負え』) 死について 死つてさ、それは深いよ底知れぬ青空か暗い月夜だ 新型コロナウイルス感染死が来たらごろりと眠り「死」に挨拶す ああこんなことつてあるか死はこちらむいててほしい阿婆世といへど (「未来」二〇二〇年五月号・六月号) 今回ばかりは考えがまとまらず、とりとめのない文章になった。でも、いま私(たち)にできることは、これらの歌たちの残像を浮かべたまま前に進むこと。そのことを今一度強く胸に刻みたいと思う。 |
||||||
| 2020年9月号 | ||||||
| 『なんかをめぐって』 山崎 聡子 | ||||||
|
「歌壇」七月号に掲載された町田康、東直子、堀本裕樹の鼎談『文学のことば、日常のことば』を面白く読んだ。この三人の共通点として、「ことば」を基盤にジャンル横断的に活動していることが挙げられるだろう。町田がパンク歌手であり、詩集を出版していることはよく知られているが、最近では作中に短歌が登場する小説『人間小唄』を発表し、現在も山頭火の生涯を題材にした小説を執筆中だという。東も小説や絵本、戯曲などを継続的に発表しているし、俳人の堀本もかつては俳句と並行して短歌を書いていたこともあるそうだ。そんな取り合わせの妙もあって、この鼎談は、小説、詩歌などの各ジャンルで「ことば」がどう扱われているか、また、「私性」をどう捉えるかが浮き彫りとなるスリリングなものとなっている。 |
||||||
| 2020年8月号 | ||||||
| きらめきの「その後」 山崎 聡子 | ||||||
|
荻原裕幸が十九年ぶりに上梓した最新歌集『リリカル・アンドロイド』を読んで、数年前に穂村弘の『水中翼船炎上中』を読んだときに似た不思議な感覚を得た。と言っても、この二つの歌集はまったく似てはいないと思う。それは、荻原と穂村の作家性の違いも去ることながら、子供時代の回想などのノスタルジックな歌が多い穂村の歌集と比べると、荻原の視線がその時々の「いま」に向いているからに他ならない。それでも、そこに共通点を見出してしまうのは、この二人の近作を読んでいると、人間が垂直方向に「成長」したり、「老成」したりするという物語は本当に終わるんだなあ……という強烈な予感があるからだ。 三十にちかくはるけきわが生の水より淡き日日続きをり (『甘藍派宣言』) 母か堕胎か決めかねてゐる恋人の火星の雪のやうな顔つき(『あるまじろん』) 五十代だけれどそれはそれとして辛夷の奥にひろがるひかり 半生のほぼすべての朝を瑞穂区にめざめてけふはあぢさゐの朝 秋のはじめの妻はわたしの目をのぞく闇を見るのと同じ目をする それは世界の端でもあつてきみの手を青葉をにぎるやうに握った (『リリカル・アンドロイド』) 荻原は実年齢をよく歌に詠みこんでいるが、この歌集でも「五十代」という年齢に触れた歌が登場する。しかし、「それはそれとして」という言葉にみられるように、年齢が感慨として語られることはなく、『甘藍派宣言』の二十代の日々と地続きの歌たちがここにある。「半生のほぼすべての朝を瑞穂区にめざめて」いうのは一瞬すさまじいことのようだけれど、カタルシスを産みやすい「半生」という言葉をあじさいの淡い色彩の中に着地させることで、その短くはない時間はあえなく霧散してしまう。また、繊細に描写される「妻」を詠んだ歌も、初期作の続きのような甘やかさを讃えている。この時間が引き延ばされたような感覚は、過去を執拗に詠んだ穂村にも共通しているように思う。 数回前に、妻や母という女性に付されがちな属性的な読みについて書いたが、年齢というのもある意味では硬直化した「人生の物語」を惹起する要素になるだろう。その物語の終わりというのを、私は穂村や荻原の近年の歌から感じるのだ。 と、そんなことを考えているときに、「短歌研究」六月号の「『永井祐』と『短歌2010』」を読んだ。この中で、永井は、穂村らの口語短歌と自らの方法論の違いに「きらめきの欠如」を挙げている。つまり、この永井の理論を借りるならば、私が穂村や荻原の歌に感じた時間的な流れの緩さというのは、「きらめき」から出発した作者たちにとって、「きらめきのその後」の時間が膨大であったこととも関係があるのではないか。そのことへの格闘が、荻原にとっての記号短歌であったり、穂村にとっての『手紙魔まみ』であったりしたのかもしれない。そして、おそらくは「きらめき」すらも通過していないそれ以降の世代に至っては、青春性や老いといった共通の物語を求めることはさらに難しくなっていくだろう。 定型的な物語ではない個別の生をどう表現していくか。ニューウェーブから永井に向かう流れを追いながら、そこにこれからの短歌の難しさと豊かさが同時にあるように思った。 |
||||||
| 2020年7月号 | ||||||
| 『「声」を集める』 山崎 聡子 | ||||||
|
緊急事態宣言が発令されてからひと月あまりが経った。私自身も仕事は在宅勤務、子どもは保育園に登園できなくなり、かつてない混沌のなかでの生活が続いている。その渦中にあって社会を動かす仕事に携わる方々のことを思うと、同時に、自分が安全地帯で生活していることの痛みも感じる。「未来」もいつもどおり発行されている。そのために努力をしてくださった方々に、心から感謝をあらわしたい。
そんな折、きちんと読めずにいた「短歌研究」五月号を読んだ。この号は、「二八〇歌人新作作品集」と銘打って一冊丸ごとが短歌の作品集となっている。短歌研究では三月号に「女性歌人特集」、五月号に「男性歌人特集」を組むのが恒例だったが、近年ではその名称(一時期まで、男性歌人のみが「現代代表歌人特集」、女性は「女流歌人特集」とされていた)を含め、特集のあり方を疑問視する声が高まっていた。編集後記で「男性、女性という括りが編集方針と合わなくなった」と触れられているとおり、今年は年齢・性別関係なく「あいうえお順」での掲載となっている。頭から順に読んでいくと、これまで「性別ごと」「年代順」という前提に自分自身の読みが引っ張られていたことを自覚する。この方法がベストかはわからないが、少しずつ変化しようという雑誌の意思を好ましく思った。
さて、この特集の締め切りは、私が知る限りは3月の半ば。国内では「客船の中」に限られていた新型コロナウィルスの感染が市中に広がりをみせ、深刻に受け止められ始めた時期と重なる。そのため、特集は図らずとも、その時期の人々の微妙な心の揺れを活写するとともに、その後に訪れたさらに深刻な事態の予言のようでもある。
接岸するクルーズ船の長き夜に三千の人揺れているらん(佐伯裕子)
「自粛とわたしとどっちが大事?」(抱き寄せて)そんな質問をさせてごめんね(斉藤斎藤)
飴のように不安が伸びて光る今いちどデビット・リンチ占い(平岡直子)
ひとあまた病む日々なれど生命居住可能惑星(ルビ:ハビタブル・プラネット)なお優しきひびき(佐藤弓生)
佐伯の歌は、船の中で感染の危機に晒されたまま待機している乗客たちを描写しているが、暗い海に揺れているのはさながら「閉じ込められ」「外に出られなくなった」その後の日本、さらには世界の人々の暗喩のようでもある。また、斉藤の歌は「自粛」と「強制」がほぼ同意語となり、「自粛の要請」「自粛警察」という奇妙な言葉が誕生した世間の同調圧力をシニカルに捉えている。そして、ふだんは時事詠的な作歌をしないであろう平岡の歌にみられる、「飴のよう」に押し寄せてる不安と、(暴力的な作風で知られるカルト映画監督の)デビット・リンチの名前を冠した奇妙な占いの二物衝突は、運命をゆだねるには無軌道すぎる現在の政治の意思決定のありようを思い起こさせる。一方、「コロナ後」に大きく変質した世界を思うと、佐藤の歌の「生命居住可能惑星」いう楽園的なイメージの美しさが胸を打つ。
多くの作家の作品を横並びで扱う短歌雑誌の「恒例企画」については、さまざまに意見があるだろう。しかし、それぞれに作風もスタンスも違う歌人たちの声を生々しく伝える本特集を読むと、短歌という詩形の現実への瞬発力と、証言媒体としての強さを改めて確信する。ばらばらの声が総体として「いま」の合わせ鏡となりうること。年齢も性別もシャッフルされた特集のあり方が、そのことをいつも以上に浮かび上がらせている。 |
||||||
| 2020年6月号 | ||||||
| 『「不要不急」に思うこと』 山崎聡子 | ||||||
|
新型コロナウィルスの感染拡大に伴って、さまざまなイベント・会合が中止になっている。東京を含む一都七県では本日(四月八日)緊急事態宣言が出され、「不要不急の」外出自粛が強く促されるなど、明らかな形で私たちの生活が変わってしまった。舞台や映画、ライブなどの生活の楽しみとして享受していたもの、友人との集いや趣味、学校生活、仕事……。そのすべてがウィルスという目に見えないものによって押し流された。未来の春の批評会も中止になった。そのあっという間の変化に、わたしの心はまだ追いつかない。 「不要不急の」というのであれば、多くの芸術はまったく不要不急であるのに違いはない。ウィルスの特性を考えれば人が多く集まる場所への外出が感染の温床となることは明らかであり、私の科学的な頭は一応はそれを理解する。一方で、運営の危機を訴える映画館経営者のSNSに「みんなが辛いのだから今は我慢して」という返信が連なり、劇作家の野田秀樹が発表した「劇場の閉鎖は演劇の死」という声明に批判が殺到したというニュースを読むと、暗澹たる気持ちになる。私たちが普段生かされているのは、不要不急の何かによってであり、その場を作り出すために人生を賭している人がいる。政府からの保証も期待できないなか、有事の名のもとに現場の悲鳴が切り捨てられてしまうことの怖さを思う。 幸いなことに、短歌を含む文芸は、書く人と読む人という相互の関係性が、会うことなく成立する。Twitter上では「#今こそ短歌」というハッシュタグがシェアされ、ビデオ会議システムを利用した歌会も散発的に開催されての観測範囲では、少し懐かしいメーリングリストを使った歌会も行われていた。 しかし、と私は思う。行くはずだった二、三の歌会を見送った後に思うのは、いま、強烈に誰かと会って短歌の話がしたいということだ。短歌というのは、「場」の文芸だとよく言われる。それはもちろんそうなのだけれど、私がいま歌会を恋しく思うのにはもう少し違う理由がある。新型コロナの問題に直面して、人々が同じ事象に対して、全く違うコンテクストをもっているという事実に私は驚いてきた。だれもが当事者であるはずなのに、たとえば、正規雇用者と非正規雇用者、都市生活者とそうでない人、高齢者と若者、医療従事者と非医療従事者、子供や介護が必要な人間が身近にいるかなど、細かな立場の違いによる分断があちこちで起きている。身近なところでも「マスクを買い占めているのは高齢者」という真偽不明の決めつけや、「子どもの休校で仕事を休んでいる母親とその仕事をカバーする独身者」という対立構造を耳にし、胸が押しつぶされそうになった。こんな状態が長く続けば、誰の心にも仮想の敵が生まれて、分断は深まっていくだろう。 私が歌会を恋しく思うのは、歌会で一つのテキストを読みあうことは、決めつけや分断とは真逆の行為だと思うからだ。他人のコンテクストに深く入り込んで、多面的に物事を捉えようという心の動き。それを短歌という媒体を通して行うことを愛しているからだ。 ともすると、心が暗く沈みがちな今だからこそ、私は短歌の話がしたい。そのための方法は手紙でもメールでもウェブでもいい。不要不急ではなくても、そのことは、私の生命維持に必要なのだ。 ――「アーティストは必要不可欠であるだけでなく、生命維持に必要なのだ。特に今は」 (モニカ・グリュッタースドイツ文化相/ニューズウィーク日本版) |
||||||
| 2020年5月号 | ||||||
| 『乱反射する「母」と「ラブ」』 山崎聡子 | ||||||
|
産めば歌も変わるよと言いしひとびとをわれはゆるさず陶器のごとく 短歌研究2月号の大森静佳の歌にこうあって、その切り口の鋭さに慄いた。男性歌人には想像もつかないかもしれないが、「産んだら歌が変わる」「歌が良くなる」というのは女性歌人に投げかけられがちな常套句だ。たちが悪いのは発言する本人は百パーセント善意のもとに発言していることであり、私自身も面と向かって言われたときにすぐには反応ができなかった。そのとき、あいまいな表情でやりすごしてしまった自分を、今となっては悔やんでいる。 女性である創作者が「産む」ことによって何らかの天啓(?)を受け変化するという神話の背景には、女性が創作物単体ではなく、その属性も含めてジャッジされてきた歴史があるのだろう。それに抗う戦いは個人単位でさまざまに繰り広げられてきたが、そういった属性をめぐるステレオタイプに対し、高度に構築された作為によって問いかけをしているのが、柴田葵の第一歌集『母の愛、僕のラブ』(書肆侃々房)だ。柴田は歌集のタイトルになった一連で、第一回笹井宏之賞を受賞している。 【神様はいないのこれは学問よしあわせになる勉強会よ】 僕らはママの健全なスヌーピーできるだけ死なないから撫でて てづくりをする信念のママの子に産まれて着色されない僕ら 【戦争にいかせたくない わたし自身が戦争になってもこの子だけは】 僕にはもう他に女ができたから男もできたから母さんの余地はないから 説明が必要になるが、「母の愛、僕のラブ」という連作は、「母」と二人で暮らす「僕」の独白からはじまる。ここでの母と僕の関係は、自家中毒的で濃密だ。「ママの健全なスヌーピー」「手づくりを信念とする」というキーワードからは、この母親の「母性」をめぐる信仰の強さが透けて見える。また、【 】で括られた歌は母自身の言葉と読めるが、「わたし自身が戦争になってもこの子だけは」といった信仰上の母性をデフォルメしたようなレトリックは、一連に異様な緊迫感を与えている。さらには、当初は「僕」という人称から少年だと思われた作中主体は、連作の途中で「ボクっ子」(僕という人称を使う女の子)であるとわかる。この「母」、もしくは「女」という存在に対する戯画化とジェンダーのねじれは、おそらくはステレオタイプな見立てに対する作者なりの格闘であろうことがはっきりと見て取れる。 窓際のマトリョーシカはかろやかに女が女に女へはいる もうあなただけの体じゃないのよとわたしに微笑む全然知らないお婆さん 幾人も私の内に住まわせて いいの、全部を連れていくから 産むことと死ぬこと生きることぜんぶ眩しい回転寿司かもしれず 飽きるほど誕生日してめくるめくまっ白な髪を抱きしめあおう 「かろやか」という女に付せられがちな形容詞や「もうあなただけの体ではない」という定型句にレトリックをもって違和感を提示しながら、柴田は、自分のなかにあるありもしない人たちまでを「連れていく」という。この歌集の「わたし」は面白いほどひとつの像を結ぶことがないのに、ただ生の怒涛とそれを全力で肯定しようとする意志のみが強く手渡される。生活していくことのすべてを乱反射させながら人間が人間を産み継いでいく混沌のこと。これを「母性」とくくる人を、わたしは許さない。 |
||||||
| 2020年4月号 | ||||||
| 『「わたし」のいるところ』 山崎聡子 | ||||||
|
このお正月、ジュンパ・ラヒリ『わたしのいるところ』とカン・ハンナ『まだまだです』を続けて読んだ流れで、外国語でものを書くことについて考えた。 ラヒリは、アメリカで育ったベンガル系インド人の作家で、これまで自分のルーツに近い登場人物たちを多く描いてきた。彼女の小説の読後感はときに苦いが、それは生まれながらに「異邦人」であること、二つの国と言葉の間にある運命を自分では選べなかったこととも関係があるのだろう。そのラヒリが、イタリアに移住し、自らの意思で獲得したイタリア語で書いた小説が『わたしのいるところ』なのだ。 わたしが読んだのは邦訳だが、この小説では、これまで顕著だった「異邦人」としての眼差しが慎重にマスクされているのに気づく。主人公はローマと思われる都市に生まれ育った女性で、一人で暮らす身の回りや、既婚の男友達とのかかわり、年老いた母親との微妙な関係性が淡々と描写される。ここでは主人公も周囲の人たちも誰一人として名前をもたず、それぞれの関係も淡く名付けがたい。ラヒリにとっては、英語でもヒンディー語でもない第三の言語で書くことが、私小説的な「わたし」を抜け出し、無名の「わたし」を立ち上がらせるのに必要なプロセスだったのだろうか。 一方のカンは、現在、「NHK短歌」のレギュラーをつとめ、テレビタレントとして活躍しながら短歌を書いている、韓国出身の歌人だ。以前、別の短歌番組で驚くほどのびのびとした歌を詠むこの女性に釘付けになったのを覚えているが、この数年で新人賞の候補で名前を見るようになり、こうして歌集が出版された。その歌集『まだまだです』には、外国で生活することの寄る辺なさがそこここに立ち現れている。 カンさんは在日ですか?違います、ニューカマー、いえ異邦人です 話したいことを話せず喉かゆしハーブの香りの飴なめて待つ 「好き嫌いではなくこれからは中国語」配られたティッシュの赤い広告 一階にあるファミマでは白い手も黒い手もみなおにぎりを取る 外国での生活は、自分が何者であるかを突き付けられ、アイデンティを勝手に推し量られることの繰り返しだろう。「異邦人」と自らを定義することには、外野からの決めつけを跳ねつける軽やかさと強さが混在しているように思う。「話したいことを話せない」のは外国語だからではなくて、思いを言葉にしたときに生じる言葉と自分との距離のことだろうか。「ハーブの香りの飴」という下句がこの歌に浮遊感を与えていて、いっそう寄る辺なさが募る。テッシュの歌もファミマの歌も、内側からは目に留まりにくいものをビビッドに掬い取っていてどきっとさせられる。 スーパーの片隅にある見切り品がまっすぐ前を向くように直す 「誰よりも優しく賢く産んだのに寂しくさせる子」母がまた言う 一方で、この歌集が「異邦人」としての視点に終始していないのは、強固な「わたし」像が匂い立っているからだろう。スーパーの見切り品に心を寄せる繊細さとまっすぐ前を向くタフネスが同居する「わたし」。両親からの愛情を受け、それをてらいなく表現する「わたし」。この人物像が作者の内なるものであるのは紛れないが、「わたし」が否応なしに立ち上がってしまうこの表現形式との親和性の高さゆえとも言えないか。 ラヒリの小説の示唆的なタイトルを思い浮かべながら、短歌は「わたしのいるところ」を映し出す鏡のようだと思った。 |
||||||
| 2020年3月号 | ||||||
| 『すべて失うも良し』 高島裕 | ||||||
|
角川『短歌年鑑』令和二年版掲載の座談会「国語教育と短歌ーなぜ文学か」(柳宣宏・栗木京子・小島ゆかり・佐佐木定綱)に注目した。 この座談会は、二〇二二年度から実施される高校学習指導要領によって、国語の科目編成が変わり、使用説明書やプレゼンの文書などの実用的な文章について学ぶことにウェイトが置かれる一方で、近現代の文学について学ぶことが疎かになるのではないかという危惧を中心議題とするものである。四人とも、実用的な文章だけしか学ばないことがいかに世界と人生をつまらないものにしてしまうか、そして、文学を学ぶことが、すぐには役に立たないとしても、世界と人生にとっていかに大切で、意味あることかを、それぞれの言葉で語っている。 だが、無味乾燥な「実用的文書」を正しく理解し、把握することは、これから先の時代において、死活的に重要である。契約、規約、使用説明書など、以前なら形式だけのものとして読み飛ばしても支障なかったものが、今はそうではないことは、誰もが感じているだろう。 わたしたちが携っているような、エンターテインメントとは別の、有用性では測れない目に見えない価値を追求する文芸は、マーケットとしては取るに足らないものであるにもかかわらず、その市場規模には不釣り合いな、高い社会的認知を受けている。それは、学校制度を通じて、国家がその「文学的価値」を保証しているからである。その点で、文学は貨幣に似ている。貨幣同様、その「価値」は、つきつめれば無根拠である。だから、歌人を含む現代文学の担い手が、学校制度による保証が揺らぐことに敏感になるのは、当然である。 だが、座談会の終わり近く、小島ゆかりが語った、東洋大学の「現代学生百人一首」の選者を務めた際の経験は、この「保証」がいかほどのものであるかを示している。 小島 (略)私以外の二人か三人の選者の先生は教員で、私だけが違う。私が特選にしたいと思ったのは〈ほんとうはやさしくしたい だけどいつも心の中にギザギザナイフ〉という高校生の歌で、特選が無理なら入選にしたいと言ったんですけど、先生方がうーんと言うんです。…(中略)…「これは印刷されて活字になって長く残るんです、父兄も見ます、十年後にも残るんです。やっぱりこういうのは止めましょう」って、押し切られて佳作になってしまった。 この座談会でも言及があり、小島が判者を務める、高岡の「高校生万葉短歌バトル」を見に行ったことがある。高校生たちの作品も歌合も熱気あるいきいきしたもので、見ていて楽しく、心強くもあったが、その一方で、「いじめやドラッグの歌はここには出せないだろうな」とも思った。ほのかな恋心や温かな友情を詠む彼ら、彼女らの向こうには、憎悪と殺意をたぎらせた、かつての私のような十代が、数知れず、表現への飢渇をくすぶらせているに違いない。もちろん大人になれば、どんなネガティブな表現も発表できる。だが、学校制度を通じた国家保証を頼りにしている限り、わたしたちは、小島が経験したような規制と無縁ではありえない。 短歌が、日本語による文芸が、「上品なご趣味」であることを自己否定し、真の生命を取り戻すためには、実用国語に席を譲って、国家保証を失ってしまうのも良いかもしれない。歌はほんらい学校で教わるものではなく、人が生き、語る場から生まれ、詠み継がれ、読み継がれるものだからだ。 |
||||||
| 2020年2月号 | ||||||
| 『他者としての韓国』 高島裕 | ||||||
|
『短歌研究』一月号では、「韓国と短歌」をテーマとして、吉川宏志と、思想家・内田樹との対談が行われた。 まず内田が、最悪と言われる最近の日韓関係について、日本国内において嫌韓感情が蔓延しているのは、目覚ましい経済発展を遂げ、やがて日本よりも豊かな国になるであろう韓国に対する嫉妬と、安倍政権が排外的愛国主義をかき立てて延命を図ろうとしていることによるもので、メディアの世論操作がそのことを覆い隠し、韓国が理不尽に日本を攻撃しているという印象を作り出しているのだ、という認識を述べる。韓国における日本製品の不買運動ひとつをとっても、内田のこの認識は成り立たないように思える。最近の日本における嫌韓、韓国における反日の蔓延は、情報技術の進化によって、互いの細部が可視化されたことによる、(似た者同士ゆえの)異文化アレルギーであり、本質において、政治的にニュートラルな現象だと思える。 それはさておき、続いて吉川が、政治的主題による作歌の難しさに触れて、こう述べている。 短歌は難しくて、政治に対する怒りをストレートに言っちゃえば言っちゃうほど、読むほうが身を引いてしまうところがある。(中略)ただ、間接的に表現するばかりだと、歌が弱くなってしまいますし、何を伝えたいのかが分からなくなってしまう。それはとても悩ましいとろですね。 悩ましいことなど何もない。主題が政治であれ、風景であれ、家族であれ、歌詠みが考えるべきなのは、定型を媒介として、言葉の力をいかに豊かに引き出すか、ただそれのみである。短歌を、それ以外のもののために利用しようとしているから、こんな倒錯した「悩み」が生まれるのだ。この点について、筆者は吉川に対し、再三指摘し、批判してきたが、まったく改める気配がないのは、残念である。 続いて、近現代短歌が韓国をどう詠んできたかを、与謝野鉄幹、石川啄木から近藤芳美、李正子、そしてカン・ハンナに至るまでの作品を取り上げ、語り合っている。たとえば鉄幹の「から山に、桜を植ゑて、から人に、やまと男子(をのこ)の、歌うたはせむ。」について、「日本文化を押しつけるという、後の時代の朝鮮支配のやり方を、先取りしている感じがありますね。(吉川)」などと言い、また近藤芳美の「鶴嘴を己れの影に打ちつづくきびしき西日となりたる中に」について、「日本人の一人として、朝鮮人を使役している立場で(中略)つらい仕事を強いている心苦しさは、やはり伝わってくる(吉川)」と述べている。つまりあくまでも、韓国が主題としてどう詠まれてきたか、ということを語っているに過ぎない。さまざまある主題の中のひとつとしての韓国を語っているに過ぎない。 だが、歌詠みとして、韓国に対するアプローチが、この程度のものであってよいのだろうか。まず、韓国語は、日本語に最も近い外国語である。ゲルマン諸語の間の類縁性には及ぶべくもないが、日本語の詩歌に携る者として、この最も近い異言語とその詩歌表現(時調など)のありように関心を持つべきだろう。 また、和歌を中心とする日本の伝統文化のルーツとして、朝鮮は決定的、根源的な位置を占めている。それを認めたがらない日本人の意識に対し、歌詠みとして、和歌文化の継承者として、揺さぶりをかけるべきだろう。既定の短歌の枠組みの中で、主題として韓国を詠み読むだけでは、他者としての韓国には出会えない。 |
||||||
| 2020年1月号 | ||||||
| 『富山の息吹』 高島裕 | ||||||
|
去る十一月十日、富山市・高志の国文学館で開かれた、「現代短歌ミニシンポジウムin富山 〈いま〉を吹き抜ける」を見に行った。このイベントは、山階基『風にあたる』・笠木拓『はるかカーテンコールまで』ともに第一歌集となる二冊の刊行を記念して、黒瀬珂瀾が中心となって開催されたものである。笠木は富山在住、関東から山階を招いた。午後一時半スタート、前半は山階・笠木を交えての公開歌会、後半は黒瀬の司会で、山階・笠木の二人が、互いの歌集や現代短歌、それぞれの短歌観などについて、語り合うシンポジウムが行われた。 前半の公開歌会は、文字通り歌会そのものを聴衆に見せるというもので、山階・笠木のほか、地元富山石川在住の十人ほどの歌詠み達が、互いの歌々を批評し合った。提出された歌々も、それについての議論も、いきいきとして熱を帯び、言葉と表現の可能性が開かれてゆく過程を、聴衆として共有するのは、なかなか新鮮だった。 続くシンポジウムでは、山階・笠木が、互いに相手の歌集から十首を選び、またそれぞれが、ここ十年ほどの現代短歌の中から五首を選んでレジュメとし、黒瀬の司会でさまざま語り合った。その中で山階が、作歌にあたって文語か口語かを意識することはなく、自分にとってしっくりくる表現を求めて、結果口語になることが多いだけだと言っていたのが印象的だった。そして、この対論の中で、「しっくりくる」ということが、ひとつのキーワードになっていたと思う。山階も笠木も、表現のテクニカルな面白さに淫することなく、自分の中に生起するイメージに過不足なくぴったりくる言葉を掘り当てるまで、けして妥協しない、という作歌姿勢を共有している。ここ十年、二十年ほどの口語表現の進化をしっかり咀嚼しつつ、詩型の可能性を未来に開いてゆく若い二人の、この「まっとうな」姿勢をとても心強く感じた。 もうひとつ注目すべき点は、このような現代短歌の最前線に触れるイベントが、富山の地で開催され、成立したということである。当日会場は、短歌に携わり、また関心を持つ、さまざまな年代の方々が集い、みなさん熱心に聴き入っていた。 富山には昔から短歌に携わる人々のネットワークが存在し、いくつかの歌誌も発行されてきた。近年では、亡き辺見じゅんが富山を拠点に設立した「弦」の存在が大きい。辺見の歌業文業が、父角川源義を通じて、ふるさと富山の風土に深く染め上げられているのは、周知の通りである。 さらに、戦中戦後の時期、筆者の生家にも程近い南砺市城端、福光の地が、民藝運動を軸とした、文芸・芸術のサロンとなっていた。福光に疎開していた棟方志功はこの地で画業を深化させ、この地をよく訪れた柳宗悦は、城端善徳寺に籠って『美の法門』を書き上げ、民藝運動の理念を宗教的に基礎づけた。その背景には、文芸・芸術に深い関心と希求を持ち、棟方や柳らを支えた、数多くの地元の人々の存在があった。そしてさらに重要なのは、室町期の一向一揆以来、この土地に深く根付いている浄土真宗の教えである。棟方も柳も、浄土真宗の教えに触れることで、その創造と理念を深化させたのである。念仏の響きは、富山の清冽な風光風土と一体化して、精神を洗い、育むのだ。 そう考えると、まさに浄土真宗の僧侶として、黒瀬珂瀾が富山にいることの意味は大きい。富山の地はふたたび、懐かしく新しい、世界性を具えた創造精神を生み出し、育むであろう。 |
||||||
| 2019年12月号 | ||||||
| 『バカの幸ふ国』 高島裕 | ||||||
|
「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が、その中の作品「平和の少女像」に対する抗議が相次いだことにより、展示中止になった、と聞いた時、事情をよく知らなかった私は、その抗議は韓国側からのものかと思った。慰安婦の心の傷と抗議の思いを込めた少女像を、「作品」として展示するなど、軽率であり、許せない、というようなことなのか、とぼんやり思っていた。 ところが、実際は、全く逆であった。この展示を見た松井一郎大阪市長や河村たかし名古屋市長が、「日本人の心を踏みにじるもの」(河村)、「我々の先祖がけだもの的に取り扱われるような展示物」(松井)などと騒ぎ出し、この展示に税金が使われていることを問題視して、展示中止を求めた、そしてそれに続いて、この展示に対する抗議と脅迫が相次ぎ、展示中止に追い込まれた、ということであった。私は、「こいつら、バカか」と思った。 その後の補助金不交付の件も含め、この問題を「検閲」として捉える議論が多い。だが検閲とは、公権力が、自らに都合の悪い思想信条の表現を見つけ出し、排除するというものであろう。松井や河村の発言やそれに続く動きは、そんな上等なものではない。「問いかけ」として置かれているものと、政治的主張との区別がそもそもできていない者たちが権力・暴力を行使して表現を圧殺している、ということであり、つまりは群れなすバカが芸術を狩る、という事態が進行しつつあるのだ。 「平和の少女像」の作者が、まさにあの「少女像」を製作した、韓国の彫刻家夫婦であったとしても、まずは作品として、問いかけとして受け取った上で、作品批評の言葉によって批評されるべきであるのはいうまでもない。反対者はこの企画展に税金が使われていることを言い募っているが、日本国やその地方自治体に税金を納めているのは、日本人だけではない。日本人にとって居心地の悪い問題提起のために税金を使うな、などと、誰にも言う権利はない。 山かげの大根畑に雨ふりてあめは青しと日記にしるす 遠山光栄(心の花) 遅れたる歌稿急ぐと泣く吾子を背に結びつつペン取りにけり 羽山誠子(潮音) モンペ服白鉢巻にひきしまりならぶ早乙女いたくうつくし 原常雄(覇王樹) 代数の考査不首尾に帰り来し子は「轟沈」の語を用ゐたり 犬飼武(水甕) 『短歌』八月号の特集「戦中のうた 一九四一-一九四五年の結社誌から」より、戦時中に詠まれた歌々を引いた。厳しい言論統制と検閲の中、刈り残された雑草のようにこうした歌々は詠まれ、人が生きて日々を暮らす息づかいとともに、歌のいのちを繋いでいった。 危機は繰り返される。しかし、同じようにではない。この先、わたしたちが向き合わねばならないのは、大東亜戦争の際の国家権力よりも、なお一層愚劣で幼稚な、未知なる「権力」である。 大切なのは、どんな厳しい状況の中でも、無為と無駄が許される時空間を確保し、守り抜くことである。降る雨を青いと感じて日記に記したり、家事育児に忙殺れる中で一銭にもならぬ歌作のペンを取ったりすることを決して止めないことである。目先の効率や損得勘定では測れない場所に、創造の拠点を確保し続けることである。 |
||||||
| 2019年11月号 | ||||||
| 『河原の石として』 高島裕 | ||||||
|
『短歌研究』連載の、今井恵子「短歌渉猟ー和文脈を追いかけて」が、六月号をもって終了した。二年余りにわたって続けられたこの連載だが、その初回から、筆者は注目してきた。古今の短歌・和歌はもちろん、社会的・学問的事象に広く取材しつつ、この詩型を成り立たせている日本語表現の特質・美質を、さまざまな角度から考察している。その真摯な問題意識に共感できるだけでなく、さまざまな対象、事象を自在に「渉猟」してゆく筆の運び、文章スタイルそのものが、日本語の美質を活かした表現の実践となっていて、読む者を豊かな気持ちにさせてくれる。 その最終回で今井は、令和改元による、万葉集への関心の高まりを喜びつつも、品田悦一による批判的見解にも触れ、次のように述べている。 今日、『万葉集』の価値を認めないという人はいないと思われる。品田がいうように近代国家日本の国民詩として再構築された経緯があったとしても、政治利用されただけではなく、詩歌として共感できる感情が根付いていよう。 また、角川『短歌』六月号の時評で、廣野翔一は、『短歌研究』一月号の特集「平成の大御歌と御歌」に触れている。そして、天皇制と短歌との結びつきについての葛藤を失った点でこの特集を批判した瀬戸夏子や川野芽生の見解に対する「拒絶感」を表明した上で、次のように述べている。 「天皇制との関係は、文学としての短歌の「原罪」であると同時に、文芸としての「強味(つよみ)」でもあるのだ」と(中略)大辻隆弘は書いているが、私は前に述べた瀬戸や川野の反応があまりにも「原罪」を強調し、なおかつこの特集を取り巻く権力とシステムという外縁しか触れないやり方はどうなのかなと感じた。 万葉集や天皇といった、古くから継承されている(とされる)、ナショナルアイデンティティーの中核をなす事象に対し、反権力の文脈から否定的な見方をする人々に、今井も廣野も、違和感を持っている。そうした見方が、「詩歌として共感できる感情」に分け入ることなく、「外縁しか触れないやり方」に見えるからだ。だが、ここで問題となっている「権力とシステム」は、「外縁」から詩歌を「政治利用」するだけではなく、「詩歌として共感できる感情」そのものを成り立たせ、方向づけるものである。 万葉集の文学的価値や天皇の歴史的尊厳を高く引き上げてきたのは、近代日本、戦後日本の国力である。実際は、万葉集と同等の文学的価値を見出し得る古いテクスト、歌謡は、世界中に、無数に存在するであろう。天皇についても、ローマ法王やダライ・ラマなど、比較可能な宗教的王統はいくらでも存在する。日本の天皇だけが特殊な存在なわけではない。もちろんそれでも、万葉集なり天皇なりの、他にはない固有性を指摘することはできる。けれどもそれは、河原の石ころのひとつひとつが、よく見れば少しずつ色や形が違っているのと同じことである。 |
||||||
| 2019年10月号 | ||||||
| 『「人間」という物語』 高島裕 | ||||||
|
『短歌』五月号の特集は「ヘビーヴァース」であった。「ライトヴァース」が盛んだった時代に比して、社会の空気が暗転した現在の短歌表現のありようを浮き彫りにしようという企画意図が明瞭である。 だが、考えてみれば、どんなに「ライト」に見える表現であっても、それが作品として力を持つためには、どこかに「重いもの」を含んでいなければならない。悲しみや苦しみ、つきつめれば「死」につながる何かを含まない言葉は、詩歌とはなり得ない。 だからこの特集は、優れた書き手、語り手たちによる充実した内容ではあったが、「ヘビーヴァース」という新奇な呼称とは裏腹に、短歌、詩歌の普遍的な本質を改めて確認するような議論にならざるを得なかった。 その中にあって、寺井龍哉の論考「口語に、乞うご期待」は、極めて現在的な問題意識に貫かれており、「ヘビーヴァース」の名において共有されるべきテーマが何であるのかに答えようとしている。 寺井は、大きな話題となった、短歌における「人間」をめぐっての、馬場あき子と永井祐との見解の齟齬を取り上げ、「馬場が『人間』を考究の対象として設定してきたのに対し、永井はその内実を一括して把握できるとは考えず、いちいち現実にそくして補充すべきものととらえている」とまとめる。そして、既存の短歌らしさからははみ出してしまう「現実」を捉えるために、新たな口語文体が必要だったとして、近年の注目すべき口語歌を数首取り上げて分析した上で、「作品の蓄積によって、口語的な文体の持つ意味はより明確になり、やがて多かれ少なかれ硬直化し規範化する。そこで作品にあらわれるものが、いま『人間』と呼ばれているものの位置を占めることになるのだろう。まだそれが見えないだけだ」「期待をはずれたところに残存する事象や想念を果敢に作品化しようとするとき、期待を固定化させた眼が新たな表現をつかみそこねるのはやむをえまい」と結論づける。 作品に対する期待を、既存の「短歌らしさ」に固定化した者の眼には、新しい口語文体は「人間」「人生」に根ざすことのない、軽く無価値なものに見えるかもしれないが、新しい口語歌は、その「短歌らしさ」をはみ出した「現実」を捉えようとして編み出されたもので、蓄積と洗練の果てに、「人間」「人生」と同等の重みを獲得するだろう、ということだ。歴史と現在を貫く広い視野がもたらす、説得力のある見解である。 だが、この結論の後、寺井はさらに重要なことを言っている。「作品を生み出した時点から時を経た作者自身が、当の作品にとっては他者に他ならないということは、誰もが知っている」と。 「誰もが知っている」にもかかわらず、誰もがその事実に眼をつむり、作品と作者の一体性を信じているふりをし続けているのはなぜか。それは、時間的な自己同一性を保持する「人間」という物語の中に自分や他人を置いて、安心したいからだ。その安心は心の安寧のために必要なものであり、一概に否定することはできない。だが、安心を守りたいがために、本当は信じてもいない物語を振りかざして、新しい試みを軽いとか無意味だとか決めつけるならば、やがて「現実」からの手痛いしっぺ返しを食らうことになるだろう。 本当は「作品を生み出した時点」においてすでに、言葉は、生身の作者からはズレてしまっている。「人間」や「人生」の重さと考えられてきたものは、たんに言葉の強度として捉え直されねばならない。 |
||||||
| 2019年9月号 |
||||||
| 『母と個』 高島裕 | ||||||
|
山木礼子の『短歌研究』作品連載に注目した。 キッチンへ近づかないで うつくしいものの怖さはもう教へたよ(三月号「花籠に花」) やはらかな毛布にふたり子を溶かしわたしも溶ける 報はれたいな(六月号「チーズと火薬」) 泣き顔がどうも舅に似てきたな ともあれ深く抱きしめてやる あかるいが助けてくれぬ常夜灯 早く寝てくれ寝てください 使ひすてのわたしがほしい 封切ればあたらしい笑顔で立ちあがる 筆者(高島)自身の歌も含めて、男性が父親として詠む育児の歌は、どうしても手放しの愛情に彩られてしまいがちである。それにひきかえ、山木の母親としての歌々は、幼い生命への柔らかく甘やかな眼差しを詩的美感へと造形しながらも、明確にわが子との距離を保ち、表現者としての自分、個としての自分を確保しようとする強い意志に貫かれている。結果、冷静明晰でリアルな育児の現場が、見事に作品化されている。 こうした作品としての達成は、もちろん山木自身の豊かな才質によるものなのだが、それはまた当然、性差にリンクしてもいる。男性歌人(高島を含む)が、わが子に対する手放しの愛情を詠んでしまえるのは、表現者としての自分、個としての自分が予め保証されているからだ。わが子への愛に溶けてしまったかのように詠んだとしても、けして溶けてしまうことのない〈個〉が、しっかり確保されている。筆者がここで言っているのは、目に見えない本質論などではない。 子を持ちても歌会へ通ふ日々をもつ男性歌人をふかく憎みつ(三月号「花籠に花」) 父親となった男性歌人が、独身時代と変わらず歌会に通い続けたとしても、「今日はお子さんはどうしたの?」と心配されることはまずない。当然家で妻が子供の世話をしているだろうと、みんな思っている。 だが、母親となった女性歌人が、夫に子供を預けて、独身時代と変わらず歌会に通い続けたとしたらどうだろう。はっきり言われるか言われないかは別として、その行動は倫理的指弾の対象となるだろう。 しかし、女であり、妻であり、母であることは、やみがたい表現欲求を抱えた個であることを消し去るわけではない。欲求があり、能力があることが明白であるにもかかわらず、女であり、妻であり、母であることによって、個としての表現者たることを諦めさせようとする社会的倫理的圧力が存在することを、私たちは(とくに男性は)しっかり認識するべきだ。 もちろん、男性に保証されている〈個〉は、宿命としての孤独でもあり、生命継受の営みから排除された者の悲しみでもある。また、厳然たる自然の掟として、子育てにおいて、母親にしかなしえぬことが多くあり、子供にとって、(父親ではなく)母親の存在が致命的に重要であることはいうまでもない。しかしそれらすべては、母親となった女性が、個としての表現者たることを完うしてはならぬ理由とはならない。 |
||||||
| 2019年8月号 |
||||||
| 『ニューウェーブ=記号短歌?』 高島裕 | ||||||
| 加藤治郎は、『短歌』二月号掲載の「ニューウェーブ三十年」と題する文章の中で、次のように述べている。 一九九〇年代のニューウェーブは、口語体を基盤として、解釈不能・音読不能の記号的表現を試みた。ニューウェーブを他と識別するのは「解釈不能・音読不能 「ニューウェーブを他と識別するのは『解釈不能・音読不能の記号的表現』が作品にあるかどうかである」というくだりに、筆者は大変驚いた。筆者の知る限り、「ニューウェーブ」の定義としてこれは新説である。この新説を詳しく検討してみよう。 まず「作品にあるかどうかである」という部分には、二通りの解釈が可能である。①一首の作品の中に「解釈不能・音読不能の記号的表現」があるかどうかである。 ②「解釈不能・音読不能の記号的表現」を含む作品を作ったことのある作者の作品であるかどうかである。 もし①であるとすれば、「マガジンをまるめて歩くいい日だぜ ときおりぽんと股で鳴らして 加藤治郎」「体温計くわえて窓に額つけ「ゆひら」とさわぐ雪のことかよ 穂村弘」といった、いわゆるニューウェーブの名歌とされている歌々をはじめ、直接に記号的表現を用いないすべての歌がニューウェーブから除外されてしまう。 ②であるとすれば、この定義が短歌史的に意味を持つためには、「解釈不能・音読不能の記号的表現」の表現としての本質が、当該の作者の作者性と必然的に結びついていなければならない。ではその表現としての本質とは何か。 加藤はこの文章の中でそれに触れ、意識があって深層意識があるというだけでなく、「意識の領域に破片のように散乱する意識」「意識を切り刻む、あるいは駆け抜けてゆく意識」があり、それを表現するのには「記号を使ったレトリック」によるほかなかった、と述べている。そしてそれは、ワープロを生んだ文書処理ソフトウェアがもたらす、文字表記をめぐるデジタル環境と不可分であったという。つまり、デジタル環境がもたらすノイズや偶発性のようなものが意識を侵食し、変容させてゆくリアリティーを捉えるのが「解釈不能・音読不能の記号的表現」であり、直接に記号的表現を用いなくても、当該作者の作品が、こうしたリアリティーに触れているならば、それはニューウェーブ短歌だということになろう。 それを踏まえた上で、もう一度あの名歌二首を見てみよう。「マガジンを」の歌は、新しいポップな自画像を生み出しているが、この自画像はクリアで安定した意識のもとに統一的に捉えられており、意識を切り裂くノイズのようなものの入り込む余地はない。「体温計」の歌は、「ゆひら」という意味以前の発声にノイズを感じるが、「雪のことかよ」という、意味への回収こそが一首の叙情を生んでいるのだから、やはり、ノイズや偶発性の表現とはいえない。よってこれら二首は「解釈不能・音読不能の記号的表現」の詩的本質を持たないから、ニューウェーブ短歌とは呼べず、口語体による「ライトヴァース」だということになる。 一九九〇年代の尖鋭的な口語歌の短歌史的本質は、風土と歴史的罪責意識からの切断である。記号短歌は、そのひとつの現れに過ぎない。 |
||||||
| 2019年7月号 |
||||||
| 『修辞こそすべて』 高島裕 | ||||||
|
『短歌』二〇一九年版短歌年鑑に「生きづらさと短歌」と題する座談会(島田修三・川野里子・大松逹知・川野芽生・阿波野巧也)が載っている。冒頭で司会の島田が言っているように、「根源的な生きづらさは自明のことで、それを持っていない人は文学なんてやらない方がいい」のである。だが、今日この時代が「根源的な生きづらさ」が、より強く意識されてしまうような社会的・精神的情況にあることは、多くの人の感じているところであろう。座談会では、各自が「生きづらさをうたった歌」十首を選んできて、それをもとに、現在の生きづらさを、短歌との関わりの中で議論している。 こうした議論がいつもそうであるように、この座談会でも、社会的倫理性と文学芸術における表現との位相差が鋭く意識された。「短歌の話をしに来て、社会の話になっても仕方ない(阿波野)」「現実の担保との関わりあいは短歌にとっていつも厳しい問題だけど、私はそこに重きを置きすぎると短歌の表現としての可能性が制約される感じがする。結局本物探しになると思う(川野里子)」といった発言からもわかる通り、座談会のメンバーはこの位相差を明確に自覚しており、この問題にたいする健全な警戒感を共有している。 しかし、このことが繰り返し確認されているということは、逆に言うと、この位相差を無化してしまうような力が、議論の中に働き続けているということでもある。次に引く阿波野の発言に立ち止まった。 生きづらさを直接詠った歌となると「まひる野」系が多い気がする(笑)。手法として自分の現実をどう歌に出すかという ときに、人間を出していくと、こういう ところになっていくのかなという気がした。「塔」とか「未来」の人だったら同じような社会状況でもこうは作らないだろう。そこは隠して修辞的にどうカッコよく見せていくか……。 ストレートに作っている歌しか信じられなかった。歌を作っている人を歌からどれだけ信用するかというのを大事に思っていて、生きづらさを詠うときに、ほんまか、と思ってしまったらもう駄目なわ これは、生きづらさうたった歌を選ぶことについての発言であり、歌の評価そのものについて言っているわけではない。だが、詩歌表現における「人間」と「修辞」との対立図式が今なお生きており、それが今日の「生きづらさ」の中で、一層強く人々の認識を拘束しつつあることを示してはいるだろう。 苦しみて生きつつをれば枇杷(びは)の花終りて冬の後半となる 佐藤佐太郎 この歌は阿波野が「ベタに苦しいと言っている歌」として選んでいる。しかし、上二句の過剰に「ベタ」な言い方は、「枇杷の花」という具象、そして「冬の後半となる」という平板な季節指定と干渉し合うことで、殺風景な世界の中を、心を抱いて生きてゆくことのやりきれなさを、よく言い当てている。つまり、「ベタ」であることそのものが、すぐれた修辞となっているのだ。いわゆるストレートな表現も、詩歌においては修辞の一様態として評価されねばならない。阿波野は、そんなことは百も承知であろうが、こうした基本前提を見失わせかねない空気が広がっているとすれば、問題である。 いわゆるストレートな表現が、作者の生の声であるというのは錯覚である。いや、デリダが指摘したように、「声」を特権化して真実とみなすこと自体が錯覚である。「人間」など、最初からどこにもいないのだ。 |
||||||
| 2019年6月号 |
||||||
| 『令和の時代へ』 高島裕 | ||||||
|
この文章が掲載される頃には、令和の御代が始まっているはずである。筆者は今、平成最後の日々の中で、この文章を書き始めている。 もちろん、元号によって時間を区切ることは人為的な決め事に過ぎず、しかも日本の中だけでしか通用しない。元号の使用によって、人々の生きる時間が、「日本」という幻想共同体へとゆるやかに統合される。それは、形式的には、天皇による時空の支配という理念を保持し、継承するものである。 今回の改元にあたって、典拠をこれまでのような漢籍ではなく、初めて日本の古典に求めたことが強調された。だが、そもそも元号という制度自体が古代中華帝国を模倣したものであり、自国の古典から引用することに何かオリジナリティーがあるかのように思うのは、馬鹿げたことである。 さらにいえば、「令和」の典拠とされた万葉集の梅花の宴は、大宰府という外国への窓口で、唐の文芸文化への強い憧れのもとに催されたものである。 品田悦一らによる批判的研究が積み上げられているにもかかわらず、首相の口から、相も変わらず「天皇から庶民まで」という、万葉集に対する誤った見方が繰り返され、またしても、国民統合の幻想的な拠り所として、万葉集が機能させられることとなった。 しかし、これら一切のことを分かった上でなお、あの日の昼前に、社用車のカーラジオから「新元号は『れいわ』。命令の『令』と平和の『和』です」と聞こえてきたときの、にわかに胸が澄み渡ってゆくような感覚に、筆者は抗うことができない。和歌文学を継承するこの伝統詩型に携わるということは、窮極、この抗えなさに向き合い、悩み続けることであろう。 「令」と「和」の結びつきは意外であり、それでいて説得力がある。つまり詩性が豊かである。「令」は「気高くうるわしい」くらいの意味だが、「命令」「法令」というより日常的な用法や、同音の「冷」とのイメージ連合などから、クールに引き締まった印象を醸し出す。この「令」と「和」が結びつくことで、「平和」という理念に対する新しい解釈が提示されている。平和とは、ただのんびりと安楽に過ごすことではない。そこには、使命を帯びて緊張した精神の美しい姿がなければならない…。こうして見てくると、新元号には、制度としてだけでなく、漢字の詩的イメージ喚起力そのものによって人々の深層意識に働きかけ、統治に役立てようという政治的意図がこめられていることがわかる。 もちろん、人々の安寧秩序が維持されるためには、何らかの統治が必要であり、統治のために、人々の心持ちを一定の方向に誘導しようとすることは、必ずしも悪ではない。だが、ここでわたしたちがしっかり認識しておくべきことは、詩は、このようにして権力と結びつくものだということであり、そして短歌詩型は、国家統治において人々の帰属意識の発揚が求められるとき、いつでも召喚される文化装置であるということだ。新元号は和歌そのものではないが、わたしたちになじみ深い、万葉集の梅花の宴における詠歌の序文から引用されたことを、重く受け止めるべきである。 幻想の次元でのお祭り騒ぎは、国家社会の実質に根差す危機には、いささかも触れることはない。二度目の東京オリンピックは、国家衰亡の序曲となるだろう。「令和」が最後の元号となる予感に胸ときめかせながら、虚空に向けて歌い続けよう。 |
||||||
| 2019年5月号 |
||||||
| 『もっと本質論を』 高島裕 | ||||||
|
江田浩司は現在、「短歌往来」の「評論月評」のコーナーを執筆しているが、昨年十二月号の文章に注目した。江田はその中でまず「歌壇ジャーナリズムや短歌創作者によって、光が当てられるべき評論集や論考は数多くある。将来の短歌のためにも財産となるそれらの評論集や論考を、正当に評価するべき態度なくして、短歌批評の貧窮を言挙げするのは本末転倒に等しい。」と述べ、暗に、重要な仕事でありながら「歌壇ジャーナリズムや短歌創作者によって」見過ごされている評論が多く存在することを指摘している。 では、それはどのような評論か。江田が最初に挙げているのは、天草季紅が同人誌「さて、」に連載している「時調(シジョ)」に関わる論考である。江田が注目するのは、天草が、短歌や日本の歌人と、朝鮮の伝統定型詩である時調との関わりを掘り起こし、そこに意味を見出そうとしている点である。 日本の伝統詩型である短歌に携っているわたしたちは、隣国朝鮮の伝統詩型について何も知らないし、知ろうともしていない。歴史的な関わりから漢詩には一定の関心を持つ(しかしそれも現代中国詩ではない)が、同じアルタイ語族である朝鮮語の伝統定型詩についてまるで無関心であるのは、極めて異常なことと思わねばならない。ここには、グローバルグローバルと言いながら、日本という箱庭の中で世界が完結していると思い込みたがる日本人の、また短歌創作者の、深い病が露出している。 だが、わたしたちが、時調をはじめ、外国語の詩歌についてよく知らないのには、別の、より本質的な理由もある。それは、およそ詩歌というものが、言語の固有の物質性において開示されるものであるため、翻訳が不可能であるということである。詩歌は、日本語、朝鮮語、英語といったそれぞれの言語の、固有の質感において読み味わうものである。だから、TANKAなどと称して、音韻構造を異にする外語でそれらしい短詩を作ったのを短歌の国際化などと言っているのは、およそ詩歌というものの本質を見誤っていると評さざるを得ない。わたしたちにとって真の国際化とは、言語の壁を越えて、外国の詩歌、外国の伝統詩を直接に読み、またその担い手たちと交わることであろう。詩歌は翻訳不可能であるがゆえに、ナショナリズム、パトリオティズムの源泉となりうる。短歌がかけがえない価値をもつものだという矜持を保ちつつ、わたしたちにとっての短歌に相当するかけがえなさを、世界のあらゆる言語が詩歌の形で持っているであろうと想像することは、極めて重要である。 目の前の技術論は必要だし、時代に見合った主題論、口語と文語、「私」性などなど、短歌の世界には多くの論点があり、日々議論されている。けれどもその一方で、そもそも詩歌とは何か、言語とはどういうものか、そして言語のさまざまな働きの中で、詩歌はどういう働き方をするものなのか、日本語はどういう言語か、短詩型文学は日本語のどういう特質と結びつくものなのか、といった本質論が語られることは少ない。本質論を軽視し、一文芸ジャンルの狭小な視界に入ってくるものだけしか見ようとしないならば、短歌は独善と内輪ウケに終始して先細りしてゆくほかないだろう。 江田は天草の後に岡部隆志のアジア歌垣論、藤井貞和の文法体系構築を取り上げ、世界に開かれた広い視野と、本質論の必要性を示唆している。江田は、短歌に携りつつ、本質論への志向を保ち続けている、数少ない書き手の一人である。 |
||||||
| 2019年4月号 |
||||||
| 『「国詩」の危機』 高島裕 | ||||||
|
近年、短歌の世界で、ジェンダーをめぐる議論が盛んである。この最も普遍的なテーマは、発言主体そのものの根っこを規定するものであるため、どのように語っても足元をすくわれてしまいそうな、独特の難しさがある。さらに近年は、男と女の二項対立を取り払った多様性において性を捉えるべきだとの問題意識が広がりを見せており、議論の提出の仕方、進め方には、きめ細かい気配りが求められる。 だが、最近の短歌の世界において問題となっているのは、それほど複雑なことではないように見える。それは、短歌人口の男女比に照らして、短歌史で重要な位置を占める歌人や、短歌史の形成に影響ある評論の書き手などが、男性に偏っているのではないか、そのため、女性歌人とその作品が正当に評価されないまま埋もれてしまっているのではないか、という問題提起に尽きるだろう。そしてそれは、国会議員や会社役員に占める女性の比率を高めるべきだという社会的テーマと連動するものである。 しかし、文芸には文芸固有の位相があり、社会的政治的テーマを無媒介に文芸の世界に持ち込むことは、無意味かつ有害である。この問題提起に関して言えば、女性歌人やその作品が正当に評価されているかどうかは、女性の社会的地位の如何とは本質的な関わりを持たない。 ここで思い出すのは、王朝期の文芸である。和歌をはじめとする王朝期の文芸は、日本の文芸史・精神史において特別な位置を占めている。日本の文芸および精神文化が、中国のそれと明確に区別される独自の質を獲得したのが、この時期であるからだ。そしてこの、日本文芸史における最も重要な時期に中心的な役割を果たしたのは、ことごとく女性の書き手たちである。 この時期、女性の社会的地位は低く、紫式部・清少納言・和泉式部といった偉大な書き手たちの、本名さえ伝わっていないことは、よく知られている。だが、この社会的地位の低さが、かえって彼女たちを文芸史の主役の座に押し上げることになった。公的に価値あるものと認められた漢詩文をもっぱら男たちが担い、かな文学という「サブカルチャー」が、女たちの手に委ねられたからだ。かな文字が日本語の表現において占める決定的な重要性については、ここで述べるまでもない。 問題は、「サブカルチャー」であった和歌文学を継承する近現代短歌が、かつての漢詩文のような役割を担っているところにある。明治以降、西欧由来の国民国家の理念のもとに社会体制が整えられる中で、この詩型は「日本固有の文化」として位置づけられ、国民統合のための文化装置として機能することになった。近代日本においては、和歌=短歌こそが、公的に価値を認められた「ハイカルチャー」になってしまったのである。このことと、近現代の短歌史が男性中心に見えることとは、深く関係している。近代短歌を牽引したアララギの代表歌人の多くが男性であり、彼らが方法的に王朝期和歌を否定したことも当然であった。そして、迢空や保田與重郎がこの点を突いて、フェミニンなものの文化的価値を日本の文化的アイデンティティーとの関わりにおいて見直し、アララギ批判を展開したことは、今日改めて思い返されるべきだろう。 現在、国民国家としての日本は、深いところで進行する腐食を直視しまいとして、虚しい自画自賛を繰り返している。ジェンダーをめぐる問題提起が指し示しているのは、「国詩」としての短歌の危機である。 |
||||||
| 2019年3月号 |
||||||
| 『両陛下のお歌に思う』 高島裕 | ||||||
|
特集の内容は、とても充実したもので、あらためて教えられることが多かった。とくに、座談会「両陛下のお歌を鑑賞する」(今野寿美・寺井龍哉・芳賀徹〔比較文学者〕・園池公毅〔歌会始披講諸役〕)は、近代文芸の枠組みを超えて、和歌としての大きな歴史性の中でこの詩型を捉え返しており、大変示唆に富むものであった。 この座談会で取り上げられた天皇皇后両陛下のお歌の中で、印象深かった作品をあげてみる。まずは、 務め終へ歩み速めて帰るみち月の光は白く照らせり(題「月」・御製) 夕やみのせまる田に入り稔りたる稲の根本に鎌をあてがふ(題「本」・御製) いまはとて島果ての崖踏みけりしをみなの足裏(あうら)思へばかなし(サイパン島・皇后陛下御歌) 知らずしてわれも撃ちしや春闌(た)くるバーミアンの野にみ仏在(ま)さず(皇后陛下御歌) のような、近現代短歌として秀れた作品である。とくに皇后陛下のお歌二首は、世界人心の暗部と無惨を正面から見据えており、そのお立場を考えると、驚きを禁じ得ない。 だが、さらに不可思議の感を強くするのは、次のような歌々から伝わってくる、清澄な気韻である。 父母の愛(め)でましし花思ひつつ我(わぎ)妹(も)と那須の草原(くさはら)を行く(題「草」・御製) 慰霊碑の先に広がる水俣の海青くして静かなりけり(題「静」・御製) 天地(あめつち)にきざし来たれるものありて君が春野に立たす日近し(題「立」・皇后陛下御歌) ことなべて御身(おんみ)ひとつに負(お)ひ給ひうらら陽(び)のなか何(なに)思(おぼ)すらむ(うららか・皇后陛下御歌) ここにあるのは、巧拙を論い、新しさを競い合う近現代短歌のありようとは別次元のものだ。浜に寄せる穏やかな波が、それまでに寄せた無数の波の繰り返しであるように、これらのお歌は、太古より詠み継がれてきた「歌」そのものであるというほかない。 そのことはまた、天皇・皇后の歌は、天皇・皇后の立場においてのみ詠まれうる/読まれうるものであることとも、関係している。ここにおいて、自立した個の自己表出としての近代文芸のありようは、滅却されている。 わたしたちの携るこの詩型は、皇室の伝統と不可分な和歌としての集合性・永遠性と、ざらついた現実と格闘する個の表現=近代文芸としてのありようとに分裂している。天皇制に対する幼いアレルギーが終息した今、アジア、そして世界を視野に収めた、広大な文明史的観点から、この詩型を捉え返してみるべきだろう。 |
||||||
| 2019年2月号 |
||||||
| 『これ以上ニューウェーブを語らないために』 高島裕 | ||||||
|
去る六月に名古屋で開かれた「ニューウェーブ三十年」を記念したシンポジウムが議論を呼んでいる(「ニューウェーブ30年」『ねむらない樹』vol.1所収。書肆侃侃房)。シンポジウムは、荻原裕幸・加藤治郎・西田政史・穂村弘の四人の討論によって進められ、ニューウェーブと呼ばれるムーブメントの起こりと展開、それに関わるそれぞれの思い、考えが当事者の立場から語り合われた。その中で強調されたのは、このムーブメントは、偶発的な成り行きと周囲の誤認から始まったものであり、予め何らかの構想があったわけではない、ということだった。 問題は、会場の千葉聡から出された「ニューウェーブに女性歌人はいないのか」という質問に端を発する。司会の荻原は、この質問に対して「論じられていないのでいません。それで終わりです。」と、にべもなく否定し、流してしまった。それにも関わらず、後でまたこの質問内容に立ち返り、ニューウェーブのような集団性は短歌史的に言って男性のものであり、女性歌人は独りで立てるので、こういう文学運動は必要ないのだという主旨のことを述べている。この見解は、穂村と加藤も概ね共有しており、同様の主旨のことを述べている。 さらに、最後に会場の東直子が、千葉の質問がにべもなく流されたことに疑問を呈し、林あまり、早坂類、干場しおりといった女性歌人が、なぜニューウェーブとの関わりで論じられないのかを問題提起した。これに対して、加藤治郎は、言われている女性歌人たちはニューウェーブの枠の中に閉じ込めるべきでなく、本人たちもニューウェーブと呼ばれたくなどないだろうとした上で、ニューウェーブは加藤・荻原・穂村・西田の四人だけだと明言した。穂村は、東の提起を受け容れるには、ニューウェーブの定義を歴史的に見直すことが必要だと述べ、また荻原は、ニューウェーブの認識にはまやかし感があるので、いろんな人を巻き込みたくないのだと答えた。 こうして見てくると、冷静に距離を置いて語る西田以外の、加藤・荻原・穂村の三人にとって、「ニューウェーブ」という看板は、歴史的な自負であり栄光であると同時に、自己限定の指標でもあることがわかる。言われている女性歌人たちを「ニューウェーブ」という括りの中で論じることは、彼女たちの作品世界の豊かさを矮小化してしまうのではないか、という彼らの懸念は、理解できる。しかし、一般的にはニューウェーブは、東の言うように「時代のウェーブ、流れ、波の全体運動」として捉えられているから、その見地からすると、彼らの認識は、短歌史の果実を自分たち男四人だけで独占しようとしているように見えてしまう。 だとするならば、この歴史認識上の問題を解決する方法はただひとつ、ニューウェーブの男性歌人も、東本人を含む同時代の尖鋭的な女性歌人も、ともに包摂するような、新たな短歌史的概念を創出することである。東ら、いつも隣にいた女性歌人さえ包摂できないのなら、「ニューウェーブ」という概念自体、たいしたものではないと考えるべきだ。 私見では、ニューウェーブが、ある「原点」として繰り返し顧みられるのは、その時期の一群の尖鋭的な短歌表現(もちろん四人だけではない)が、それまでの風土の重みと、歴史的罪責意識を振り払ったからである。こうした精神史的観点から、新たな、より広汎な短歌史的概念が創出されることを望む。 |
||||||
| 2019年1月号 |
||||||
| 『常民のまま歌を詠むには』 高島裕 | ||||||
|
大井学は『短歌』九月号に寄せた論考「『純粋読者』はどこにいる」の中で、「社会生活基本調査」の「趣味・娯楽の種類別行動者数」を集計したグラフを掲載している。それによると、「詩・和歌・俳句・小説などの創作」を行う人数は、調査の行われた二〇〇六年、二〇一六年の二度とも、十代・二十代までと、六十代後半以降は二十万人を超えるが、その間の年齢層では二十万人に至らず、落ち込んでいる。 筆者のような生来夢見がちな人間は、こういう風に数字で現実を示されると、はっとさせられることがある。大井は書いている。 学生時代のクラブ・部活動などで創作に携わっていたメンバーが、社会に出て忙しくなって、創作活動から離れていく。やがて退職し、子育てからも卒業して、再び創作の時間がもて、かつ意欲が湧いてくるという、実体験でもよく聞く話が、こういう数字にも表れているのかもしれません。 「未来」を読み、またこの時評を読んでいる人のうち、少なからぬ部分が、仕事や子育てで忙しい年齢にあってなお、短歌の創作を続けている人々であろう。それは、大井の示した数字では、少数派にあたる。この人々は、社会や家庭において重い責任を担い、諸事に忙殺される中、様々な困難をおして、創作を続けているのである。 困難は、大きく三つに分けられる。一つは時間をめぐる困難、二つ目は金銭をめぐる困難、そして最後に、体力に関する困難である。もちろんこの三つは、相互に絡み合っている。 この年代の人は、朝から晩まで働き、夜帰宅してからは、家事・育児にかかりきりになる。家族との触れ合いも大切だ。創作やそのための読書、原稿執筆などの作業は、それが終わって家族が寝静まったのを確かめた後である。しかし、その頃には一日の疲れがどっと押し寄せてきて、机に突っ伏して寝てしまうかもしれない。そうなると、むしろ早起きして、未明の、まだ家族が起きてこないうちにこなす方がよいかもしれない。いずれにしても、睡眠時間を削り、命を削る営みであり、体力の問題とかかわってくる。あとは、スマートフォンの力を借りて、仕事や家事・育児の隙間の時間(移動時間・待ち時間など)を活用したり、単純作業をしている時に頭の中で歌作推敲にいそしんだりするくらいであろう。 時間については、また別の問題もある。休日に歌会や批評会に出かけるということは、家庭の側から見ると、自分ひとりの道楽のために、家族で共に過ごす貴重な時間を犠牲にしているということになる。同様のことは、歌集の出版をめぐる金銭的問題についてもいえる。歌集一冊出すのに車一台分の費用がかかるとはよく言われるが、普通に考えて、そんなお金があるなら、家族のために車を買うべきであろう。 もちろん、文学芸術に一生を捧げるため、家庭を持たず、仕事も創作の都合を中心に選ぶ、という生き方もあり、それはそれで否定されるべきではない。文学芸術における評価は、その創作者がどんな生活をしているかとはまったく無関係である。だが、常民としての生活過程・生活感情の中に身を置きつつ、葛藤を抱えながら創作を続けることには、かけがえのない意味があるように思える。 文学芸術の創作と生活との葛藤は、各人それぞれが対処する問題で、こういう場で語る必要はないのかもしれない。だが、これ以上切実な問題はないのも事実である。 |
||||||
| 2018年12月号 |
||||||
|
『永井祐の韻律論に寄せて』 高島裕 |
||||||
|
なんだあのカップル十五分もおる「あーん」じゃないよ あとで真似しよ 山川 藍
それは世界中のデッキチェアがたたまれてしまうほどのあかるさでした 笹井宏之
山川歌は、四句目と結句とのはじめと最後が「あ」「よ」という同じ音であり、これによって得られた軽やかなリズムが、「主体のそれなりに意地悪な視線にコミカルなノリを加えているとも言える」として、この歌の音韻要素を指摘している。それにもかかわらず、この歌は「韻文的」とは評価されにくく、むしろ「散文的」と言われそうだと推測する。
それに対して笹井歌の方は、五句に分けることなく上から下まで一気に、散文のリズムで読み下すような作りになっているにもかかわらず、「散文的」とは言われず、むしろ「韻文的」と評される場合もありそうだと推測する。ここから永井は、次のように結論する。
「韻文的」も「散文的」も実のところ、音韻要素によっては判定されていない(括弧内略)。それは内容で判断されている。経験的に言えば、どれほど地上的なものから離れているかによって、一首の「韻文性」は認められている場合が多いように思う。
ここで永井が言っていることは、これまでさまざまに神秘化されてきた短歌の韻律というものを、あっさり地上に引き下ろしてしまったようで、小気味よくはある。だが、子細に見てゆくと、事は永井が考えるほど単純ではないことがわかる。
永井は、先の笹井歌を散文のリズムで読む歌だと言っているが、この歌をよく読むと、一首の真ん中あたりまでは定型を無視して散文のように読ませるけれども、後半「ほどの」あたりで韻律を持ち直し、最後「あかるさでした」ときっちり七音で結んで、韻律的に定型感を確保している。たとえていえば、熟練した軽業師が、わざと失敗して転落するように見せて、最後で見事に着地したような雰囲気である。この歌が韻文的なのは、韻律におけるこうした特徴によるものであり、たんに意味内容の問題として片付けることはできない。
一方の山川歌は、音数的には完全に定型を守っているが、歌の読ませどころが、一字空きを挟んで四句目から結句へ読み進んだときに感じる「落ち」のようなギャップであり、それは、韻文の本質である言葉そのものの力ではなく、物語のプロットに近いものである。この歌が散文的と評されうるのは、こうした作品そのものの構造によるものであって、たんに意味内容が地上的だからということではない。
たしかに、短歌の韻律といえばすぐに生命とか鼓動とか言って神秘化するのは馬鹿げている。だが、短歌定型における韻律とは、実に精妙に機能するものであり、一首を意味内容と音韻要素とに真っ二つに割るような単純な論理で解けるものではない。そしてその精妙さは、長い年月を語り継がれ、書き継がれ、歌い継がれてきた日本語の歴史が育んだものである―というくらいのことは言えるのではないだろうか。 |
||||||
| 2018年11月号 |
||||||
| 『まずは作品に向き合え』 高島裕 | ||||||
|
田中教子は、『短歌往来』の連載エッセイ「うたの小窓から」において、田中の考える「短歌の普遍性」(四月号)に照らして、若い世代の短歌作品のいくつかを取り上げ、批判している。 田中は連載の初回(一月号)において、永井祐の、 あの青い電車にもしもぶつかればはね飛ばされたりするんだろうな について「『そうでしょうね』と頷くしかない」と冷笑し、雪舟えまの、 ホットケーキ持たせて夫送りだすホットケーキは涙が拭ける を、「ナンセンスの感覚で詠まれている」と受け取った上で、下句の表現を「奇をてらったわざとらしさとしか感じられない」と切り捨てる。そして斉藤斎藤の、 雨の県道あるいてゆけばなんでしょうぶちまけられてこれはのり弁 を、「『さあ、新しい歌だ、驚け』と言われたようで興ざめする」と、こきおろしている。そうして最後に「定型に嵌めるということは、ただ珍しいことを言ったり、指おり数えれば良いというものではないだろう。…(中略)…定型にあった斬新な詩的口語体を創造することが、現代の最優先の課題である。」と結んでいる。 批判はどれだけ厳しくてもよい。けれども田中はここで、取り上げた一首一首の作品の、どこがどう悪いのかを一言も指摘することなく、ただ冷笑し、「奇をてらったわざとらしさ」とか「『さあ、新しい歌だ、驚け』と言われたようで興ざめする」などと一方的な断定を投げつけている。これは批評ではなく、ただの悪口である。「ともかく私の理解を超える新しいものは認めない」と言っているに等しい。 これらの作品は「ただ珍しいことを言ったり、指おり数えれば良いという」幼稚な意識で作られたもので、批評に値しない、ということだろうか。だが、たとえばここに引かれた雪舟えまの作品を見てみよう。地縁血縁から引き離され、ふたりぼっちで暮らす都市住みの夫婦。昭和の頃とは違って希望の見えない中で日々厳しい現実と向き合い、戦わねばならない。そうした夫婦像を想定してこの作品を読むならば、「ホットケーキは涙が拭ける」というフレーズは、傷みと温みを湛え、強い愛情を感じさせる。ホットケーキという素材の持つ、ほの温かく、甘く、柔らかい、ほっこりしたイメージが、この表現に必然性をもたらしている。この作品を「ナンセンスの感覚で詠まれている」とか「奇をてらったわざとらしさ」というふうにしか読めない田中の鑑賞眼は、節穴であるというほかない。 連載二回目(二月号)以降において田中は、「短歌の57577が、一つのものをまっすぐに詠むという基本の形」を「古来の定説」とし、この「定説」を基準に、斎藤茂吉の「たたかひは上海に起り居たりけり鳳仙花紅く散りゐたりけり」、寺山修司の「マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つるほどの祖国はありや」のような、評価の定まった「名歌」を引用して、一見腰折れ歌に見えて、「定説」を新たに解釈し直しているのだと称揚する。そしてそれと比較する形で、今日の若い作者の作品から批判しやすそうな歌を選んで引用し、一首がバラバラだとダメ出ししている。これは極めて安直かつアンフェアなやり方だ。 若い世代は、先行世代に叩かれることによって鍛えられるものだ。しかし、幾許かの教養知識の上にあぐらをかき、まともに作品に向き合おうともしない者の悪口雑言に晒されねばならぬいわれはない。 |
||||||
| 2018年10月号 |
||||||
| 『三島由紀夫になれないのなら』 高島裕 | ||||||
|
生物学者の本川達雄によれば、生物としての人間の本来の寿命は四十歳程度であるという。本川説では、どんな動物も心臓が十五億回打つと死ぬそうで、人間の場合は十五億回打つと四一歳になるので、そのあたりが本来の寿命だということだ。(『生物学的文明論』)これは、数え年四二歳の男の厄年とほぼ正確に一致する。そして、肉体的にだけいえば、人間は十代後半で生殖可能となるので、自分の子がその子を生むのを見届け、子育てをサポートし終えたくらいで死ぬこととなり、生物として実に合理的なサイクルだといえる。 この説は、齢知命に達した筆者の実感からしても、納得できる。厄年前後から身体に老いの兆候が現れ出したこともさることながら、その頃から、来し方の人生を振り返って「長い」と感じるようになり、同時に未来に向かってわくわくする感じがなくなった。つまり、時間的にだけいえば、「もう十分生きた」と感じるようになったのである。老いを嫌った三島由紀夫が四五歳で自決したのも、こうした生物学的な摂理との関わりにおいて捉えられるかも知れない。本川が言うように、自然界では、老いて身体能力の衰えた個体は、たちまち食い殺されてしまう。五十歳にもなった私たちは、自然界においては生存を許されていない存在である。私たちはもっぱら、医療や生活環境に関わる科学技術の力で生命を維持している、本川の言う「人工生命体」なのである。三島は美的に、自分がそういう存在になって生き延びることを拒否したのではないだろうか。 さて、三島ならざる私たちは、たとえ醜かろうと、この人工生命体を抱えて、今しばらく生きてゆかねばならない。その際、おのれの価値判断の根拠に「自然」を置くことは、自己欺瞞であることを弁えなくてはならない。 ここで想起するのが、『短歌研究』一月号巻頭に掲載された、岡井隆の「消化管出血を疑はれし後 即事」一連三十首である。 翼燃えて近づく鳥だ夕日さす原だからちよつと行き過ぎにくい 昨日午後主治医の告げし診断が王権(わうけん)のやうにわれを支配す それはまだ確実でない診断だしかし黄(き)鳥(てう)は飛び交ひ止まぬ 身体生命に関わる切迫した状況が、「鳥」「王権」といった、禍々しくも豊饒な喩語を得て、圧倒的な詩的達成をもたらしている。歌人としての業の深さに、戦慄を禁じ得ない。 だが、筆者がここで注目したいのは、こうした状況の中で、岡井は決して空を仰いだりしない、ということだ。こういう場合に普通そうするような、自然の風景に嘆きの心を委ねたり、遠い思い出を呼び出して感傷に浸ったりということは、この一連の中に微塵も見られない。その代わりに詠まれているのは、「胃カメラ」「エコオ機」といった、医療機器・医療技術と、それに関わるイメージの豊かな展開とである。 ルネサンス時代の音を連れながらエコオ機はゆくわが腹壁(ふくへき)を そして、筆者が最も心に残ったのは、次の一首である。 新しき年に向かひて歩むなか翼あかき鳥に逢へればよいが 「鳥」の喩の詩的豊饒を湛えつつ、「生きたい」という最もシンプルな希求が、何の衒いもなく提示されている。こうした岡井の姿勢の中に、三島由紀夫になれない私たちが、欺瞞なく老いに向き合い、詩に向き合うためのヒントがあるように思う。 |
||||||
| 2018年9月号 |
||||||
| 『穂村弘における〈時間〉』 高島裕 | ||||||
|
体温計くわえて窓に額つけ「ゆひら」とさわぐ雪のことかよ 穂村弘『シンジケート』
花水木の道があれより長くても短くても愛を告げられなかった 吉川宏志『青蝉』
今から四半世紀ほど前に詠まれた高名な二首である。いずれも、それまで掬い取られてこなかった新たなリアリティーを鮮やかに切り拓いている。一方、この二首は、当時気鋭の新人であった穂村と吉川との資質の違いを鮮明に示してもいる。
吉川歌は「花水木の道」の空間的長さを時間的な長さへと転換することで、それを人生の時間的継続性の喩として機能させている。こうした方法は、短歌表現を作者の実人生にひったりと重ねる、近代短歌以来の伝統に、スムーズに接続しうるものだ。
他方穂村歌の方は、口に物をくわえたまま喋ろうとする時の発音の歪みに反応しているが、そういうところに反応する幼児的感受性は、人生の時間的継続による主体の成熟を、最初から拒絶しているといっていい。それはまた、近代短歌以来の伝統からの方法的切断をも意味する。
穂村が今度十七年ぶりの新歌集として刊行した『水中翼船炎上中』は、時間の契機が導入されている点で、これまでの穂村の歌集とは大きく異なっている。歌集に封入された「メモ」の中で、穂村は歌集の各章に「現在」「子供時代」「思春期へのカウントダウン」「二十一世紀初頭のパラサイトシングル像」「母の死」等、時間的なテーマを割り振り、「見取り図」として読者に提示している。しかしそこに穂村の「転向」を見ようとするのは早計である。
水筒の蓋の磁石がくるくると回ってみんな菜の花になる 『水中翼船炎上中』以下同
母が落とした麦茶のなかの角砂糖溶けざるままに幾度めの夏
こうした歌を「あったあった」と楽しむことはできるが、これら過去に取材した歌は、現在の時点において回想され、構成されたものであり、本当に過去の時点で詠まれた歌が連れてくる、ふわりとした昔の臭いはない。それどころか「水筒の蓋の磁石」も「麦茶のなかの角砂糖」も、どこかつやつやと新しい。それは穂村にとって、それらの記憶が少しも古びていないからだろう。
ちちははが微笑みあってお互いをサランラップにくるみはじめる
ゆめのなかの母は若くてわたくしは炬燵のなかの火星探検
一首目は「二十一世紀初頭のパラサイトシングル像」に、二首目は「母の死」にそれぞれ割り振られた章から引いた。いずれも幻想を詠んでいるが、パラサイトを引き延ばすために、老いてゆく両親をサランラップに包んで「保存」しようとしたり、母の死に際してなお、電気炬燵の赤い光の中の「火星探検」を夢見たりするのは、たとえ幻想であっても、いや、幻想ならなおさら、極めて異様であり、限りなく傷ましい。
この異様さと傷ましさは、私たちの心に深く刺さってくる質を持つ。つやつやしたままの過去の記憶と、過去において想定された未来ではない、先の見通せない現実を生きていることとの落差の中に、私たちの悲しみと寂しさが浮き彫りにされている。
穂村にとって〈時間〉は、〈私〉の同一性と継続性を意味しない。それは〈現実〉を照らし出す、キラキラした無人の遊園地であり、煌々たる廃墟の光である。そして実作者としての穂村はこれからも、頑固に成熟を拒否し続けるだろう。 |
||||||
| 2018年8月号 |
||||||
| 『たかがその程度の日本のために』 高島裕 | ||||||
|
『短歌研究』六月号の特集「坂井修一VS.斉藤斎藤 対論と競作『現代社会と短歌』」は、その長大な分量を一気に読ませてしまう、濃密で衝撃的な内容であった。二部にわたって展開される、坂井修一と斉藤斎藤との対論では、巨大なIT企業による寡占支配と、そのもとでの絶望的な格差、人工知能の進化による〈人間〉の領域の侵食、といった今まさに進行している危機をまざまざと浮き彫りにしつつ、わたしたちが空気のように依拠してきた短歌のシステムが、この先は成り立たないことを宣告する。その上で、合理性では測れないような、人間のどうしようもなさやわけのわからなさを、文学芸術の本質論と重ねつつ、そこにぎりぎりの希望を見出そうとする姿勢に、深い共感を覚えた。 坂井と斉藤の対論では、世界人類の位相において生起している科学技術や社会経済の問題と、短歌の方法論や結社・総合誌・歌会などをめぐる問題とが直接にリンクされ、議論されている。短歌もまた、詩歌の営みとして、本質的には世界普遍性を有するのだから、こうした大きな視野からの議論が必要なのはいうまでもない。 ただ、坂井と斉藤とが語り残した問題があるとすれば、それは、「短歌の世界」と「世界人類」との間に横たわる「日本・日本語」という位相にかかわる危機であろう。 対論の中で、坂井が「ウォール街の論理」と呼んでいるものと関わると思うが、現状の世界において支配的な、経済的効率と功利性とを最優先する価値観に従うならば、わたしたちが日本という国家を営み、日本語という複雑で面倒な言語を話していることは、端的に言って、無駄なことではなかろうか。平成の終わりに臨んで、政府は改元の準備を進めているようだが、元号の使用によって「日本」の時空に結界を施し続けることは、グローバルな社会経済の中にあってはなはだ不便であり、不合理である。従来の左翼的文脈においてではなく、ネオリベ・グローバリズムからの元号不要論がなぜ提出されないのか、不思議である。 元号についていえることは、日本語についてもいえる。効率と功利性を最優先するならば、政府が進めている英語教育の早期化は過渡的な施策に過ぎず、ゆくゆくは、公用語を日本語から英語に切り替えるべきである。日本出身のグローバル企業のいくつかが、社内における英語使用を実践しているが、それを国家規模で行えばよい。英語教育の早期化などと言わず、生まれたときから英語で育てればよいではないか。普段の生活で使っている言語がそのまま世界で通用することの利便性は、計り知れない。 そうすることによって、わたしたちは一体何を失うというのか?日本語でしか表現できない微妙なニュアンス、感情の機微、優しさ、懐かしさ、祖先から引き継いできた日本の心、文化、伝統…。たかがその程度のもののために、目前の圧倒的な利便性を諦めるのは、愚かである。 そんな無茶な、と思われるだろうか。だが、戦後わたしたちは、郷愁を振り捨てて、ひたすら物の豊かさと利便性を追求してきたではないか。日本語の放棄は、その延長上に、ごく自然に想定される未来である。 国民国家日本の公用語として、均一に通用することを保障された近代日本語の終焉は、近代文芸としての短歌を確実に終わらせることになる。そういう未来を望まないわたしたちは、こう言い張るべきなのだ。「日本そのものが、詩なのだ。たかがその程度の日本は、それゆえにこそ、かけがえのない一個の詩なのだ」と。 |
||||||
| 2018年7月号 |
||||||
| 抵抗の拠点』 高島裕 | ||||||
|
この四月に、財務次官がセクハラ騒動で辞任した。テレビ局の女性記者と一対一で会食した際に、次官のものとされる性的な発言が密かに録音されていて、その音声が、週刊誌を通じて公開されたのである。その「性的な発言」の音声が、メディアで繰り返し流され、次官本人の否定と、「双方の言い分を聞くべき」との麻生財務大臣の意向にもかかわらず、「セクハラは許せない」「公開された音声だけでセクハラ確定」「被害者に名乗り出ろというのは酷い」という声に押されて、財務省はセクハラを認定、謝罪した。 報道は、次官本人と財務省を断罪し、麻生大臣の責任と不見識を言い立てるばかりで、テレビ局側が、かねてから嫌がっていたという女性記者をあえて次官の取材に差し向けた理由や、取材元である次官に無断で録音した音源を、他社に持ち込んで公開させたことの職業倫理上の是非を問う声はかき消されてしまった。「セクハラは許せない」という、誰にも反対できないお題目の前に、すべての疑問が封殺された形だ。こんな粗雑な手法が、ジェンダーとセクシュアリティをめぐるさまざまなコンフリクトを風通しの良い方向へ導きうるとは到底思えない。 この件で、とりわけ筆者が気になったのは、会話の一部分のみを、しかも一方の側の音声のみを切り取り、そこで確認できる発言内容をもって「セクハラである」と断定、断罪してしまったことだ。ここに露呈しているのは、言語観の貧しさである。生きた会話の中で出てきた言葉を、一切の文脈抜きで一義的に意味づけ、「セクハラ」の定義に照合するという手続きの過程では、言葉そのものが孕む多義性や、生きた会話がもたらすさまざまなニュアンス、当事者同士のこれまでの関わり合いや双方の性格などから生まれる雰囲気や文脈といった、言葉と、言葉をめぐる環境との重層性が、すべて切り捨てられてしまう。誰も反対できない正義の名において、生きた言葉が殺されてゆく。 ここで思い出すのは、およそ十五年前に上梓された矢部雅之の歌集『友達ニ出会フノハ良イ事』である。報道カメラマンとして、紛争やまぬアフガニスタンに赴いて詠まれた歌などを収めるが、ここでは「ネタ薄のローカルニュースの埋め草にすぎ」ない、デスクが「つまんない事故」と言い放った死亡事故を取材した際の、その名も「事故」という連作から引く。 めしどきのニュースぢや放送(オンエア)できんな…と思へども撮る血まみれの髪 居眠りが原因といふ 保冷車の折れまがりたるいはきナンバー 泥まみれの冷凍カツヲ口をあけ残骸の傍らに転がる はづれ飛びしホイールキャップになぎ倒され濃く匂ひたつ葱畑の葱 ガラスなき窓より夜風ふきこめば抜かれざるままキーは揺れをり ひび割れたるセーラームーンの手鏡が後部座席で映す暗闇 星一つなき空の下誰一人記憶にとどめぬ事故を撮り終ふ ここに生々しく立ち上がる〈事故〉の感触は、一義化された報道言語によっては決して伝わらないものだ。泥まみれの冷凍カツオや葱畑の葱の匂いやひび割れたセーラームーンの手鏡を呼び起こす想像力を可能にする限り、この詩型は、一義的言語によるわかりやすい物語を生産し消費させてゆく巨大な力への、ささやかな、しかし強靭な抵抗の拠点であり続けるだろう。 |
||||||
| 2018年6月号 |
||||||
| 『桜咲く頃に』 高島裕 | ||||||
|
この文章を書いている今、世間は桜の開花や花見の話題でもちきりである。毎年繰り返されることだが、寒い冬を乗り切って春の訪れを喜ぶ気持ちと、年度替りの卒業や異動による別れの切なさとが交錯する中で、人生そのものの比喩として、人々は桜を仰ぐ。日本の精神文化において桜は他の花とは違った特異な位置を占めており、それが和歌文学の歴史と深く関わっていることは周知の通りである。 二〇一四年に刊行された水原紫苑『桜は本当に美しいのか』(平凡社新書)は、歌人自身による、桜文化の相対化の試みとして注目される。水原は「私たちには、桜を、長い長い人間の欲望の呪縛から、解放すべき時が来てはいないだろうか。(中略)桜に肩代わりさせた私たちの本当の望みを、見つめる時が今ではないだろうか。」(まえがき)と問題提起して本文に入る。 ところが、この本をどれだけ読み進めても、桜文化の生成過程を暴き、その文化装置としての政治性を鋭く照射するような議論に出会うことはない。それどころか、記紀万葉に始まり、古今、王朝、新古今と、桜に寄せた古典文学を語る水原の筆は熱を帯び、とくに西行や定家の和歌を読み解くくだりは読み応えがある。「西行は、単独の『自己』として、超越的な花の『実存』に出会っている。/人目にふれることもない、吉野山の木々の花は、それぞれに、西行の前に存在を開示し、声を聞かせ、涙を誘い、西行の『心』を虚空にいざなってゆく。」といった、深い読み込みである。これでは読者は、桜文化を相対化するどころか、ますます桜文化の豊かさに魅惑されるだろう。 たしかに、古今集仮名序における貫之の政治的思惑を詳しく分析して、「大事なのは、絶対的な王権による美の宇宙の創造ないしは構築であり、それによって、人間の意識あるいは無意識までも支配するシステムを成立させることである。」と結論づけ、その王権の文化システムの中心に据えられたのが桜であったことを指摘してはいる。だが、それも、戦後的な抽象的自由に寄った言い方に過ぎず、別の立場から見れば、人の意識あるいは無意識までも洗練するような、豊かな民族文化の創造を成し遂げた、ということにもなる。そもそも、この本の中で古典和歌から能、歌舞伎に至る桜絡みの文学史を辿る中で、人の運命の深淵に思いを馳せている水原が、薄っぺらな抽象的自由などを本気で信じているはずがない。 では、この本を通じて、水原が本当に言いたかったことは何なのか。水原の筆が厳しくなるのは、近世から近代にかけて、桜の表象が、共同体のための自己犠牲を美化するように機能することに対してである。たとえば、宣長の高名な「敷島の大和心を人問はば朝日に匂ふ山桜花」の一首を、「これ見よがしな、いやな歌である。」と酷評し、この歌から、最初の特攻隊が「敷島隊」「大和隊」「朝日隊」「山桜隊」と命名されたことに、「憤怒」を表明している。 筆者は、水原のこの「憤怒」を共有しない。けれども、この絶望的な陰鬱に塗り込められた桜の表象は、二度と繰り返されるべきでない、とは思う。ここにあるのは、新古今の美学とも、この本の最後に取り上げられている、近年の「桜ソング」の優しさとも異質なものだ。それは、近代によって失われたものを、近代への囚われを自覚しないまま取り戻そうとしたときに立ち現れてしまう、悲劇的な何かである。 現在、この悲劇を「二度目の茶番」として演じようとしている者たちは、西行や定家の何をも理解しないであろう。 |
||||||
| 2018年5月号 |
||||||
| 『子規は言語をどう変えたか』 高島裕 | ||||||
|
角川『短歌』昨年十月号の特集は「和歌革新運動」であった。「正岡子規生誕百五十年」とのことだが、没後ではなく、生誕から百五十年しか経っていないという事実に、軽い眩暈を覚えた。近代短歌の始祖として、短歌史のはるか淵源に屹立するあの子規が、もしも長寿であったら筆者が生まれた後も存命だったかもしれないほど「近い」人だったことに、改めて驚いたことであった。 さて、その子規について、大辻隆弘は「調(しらべ)から韻律へ―子規におけるリアリズム的言語観の成立―」と題する評論を、本特集に寄せている。その中で大辻はまず「子規の和歌改革の本質はリアリズムの基盤となる新たな言語を創出することだった」と規定する。そして、韻律の側面から、この言語創出を跡づけようと試みる。 大辻は、子規と左千夫との論争を取り上げ、左千夫が尊重した和歌の「調(しらべ)」というものを「統辞の技術によって生まれる一首全体の玄妙な雰囲気」と定義した上で、これを子規以前の和歌における主要な価値観と位置づける。それに対して子規は、「『調』という曖昧な概念から、意味に関わる部分を削ぎ落とし」、「『調』を物理学的音声として規定しなおした」とする。そしてこの「物理学的音声」の形式が、今日私たちが用いている「韻律」の概念であり、このようにして子規は、「意味」と「韻律」を区別したのだとする。さらに子規は「ことばの意味性と韻律とを区別したうえで、ひそかに意味性の方に優位性を与え」たのだとし、こうして「歌の意味内容をより引き立てるために韻律を利用する」ような、今日の作歌法が可能になったのだ、とまとめる。 まず気になるのは、「物理学的音声」という言葉である。人間が言語実践において発する音声は、物理的音響とは別のものである。たとえば、「あ」という音声を、大きな声で叫んでも、小さな声で囁いても、高い声で言っても、低い声で言っても、同じ「あ」音として識別できるのは、音声が物理的な音響としてではなく、示差的な記号として認知されているからだ。自身の言語観として言っているわけではないにしても、「物理学的音声」などという誤った概念を不用意に頻用することは、議論の質にかかわる。 さらに、子規は短歌における意味と韻律とをはっきり区別し、そのうえで意味の方に優位を与え、韻律を意味に奉仕させるような作歌法を可能にしたという。言語(音声言語)において、意味と音声とは表裏一体で切り離すことなどできないという本質論は措くとしても、もし子規が韻律を意味に奉仕させようとしたのだとすれば、五句三十一音という古来の形式そのものを廃棄したであろう。現に新体詩(日本語による非定型詩)はそうした。そうはしないで、短歌や俳句といった、音数律にもとづく古来の定型詩を、近代のリアリティーに引き合わせたことに子規の「言語改革」の要諦があるとすれば、それは、「意味と韻律とを区別して、意味に優位を置いた」というような、粗雑な図式で捉えることはできない。 実際のところは、大辻自身が文中で触れている通り、従来一様に「なだらかな調」で詠まれていた和歌の韻律を多様化することで、近代の複雑な現実がもたらす多様なリアリティーを表現できるようにした、というのが妥当な評価であろう。そしてこの場合の韻律の多様化とは、主題(=意味)の多様化と正確に相即するものであり、意味と韻律とを区別したとか、意味に優位を置いたとかいう議論は成り立たない。 かくして私たちは、韻律という謎、定型という謎にふたたび引き戻されるのである。 |
||||||
| 2018年4月号 |
||||||
| 『読者という当事者』 高島裕 | ||||||
|
少し前のことになるが、『短歌』昨年七月号掲載の山田航の歌壇時評「もはや抗えないもの」に注目した。 この時評で山田は、『歌壇』昨年二月号掲載の目黒哲朗の連作「生きる力」を取り上げ、この連作が、実際に起きた傷害事件をもとに作られ、人が罪を犯すということについての真摯な問いかけがなされているにもかかわらず、それが文語旧かなで詠まれていることに違和感を表明している。文語旧かなで書かれた歌は、もはや今この時代のリアルを表現することができず、「言葉のコスプレ」として虚構化されるほかないというのだ。だから、虚構を詠む場合は許容されるが、現実、とくに当事者が存在するセンシティブな事件に取材するような場合には、ふざけているように見え、真摯さを減じてしまう、と主張する。「たとえるならば、アナウンサーがアニメキャラのコスプレをしてニュースを読んでいるようなものに見えた」と言う。 だが、少なくとも私は、目黒の連作を読んで、山田が言うような違和感は全く感じなかった。文語旧かなが「言葉のコスプレ」であることには半ば同意するが、「アナウンサーがアニメキャラのコスプレをしてニュースを読む」ということが、今日、異常なことの喩えとして有効だろうか。たとえば、デーモン閣下はあの姿で、かなり深刻な事象についてもコメントしており、内村光良は、コントのキャラクターのまま、地震で損壊した熊本城を訪れている。「真摯であること」と「ふざけていること」とが明確に区別できなくなっていることこそが、現在のリアリティーなのではないだろうか。もちろん、目黒の連作はこうしたリアリティーを意識的に方法化したものではない。だが、「現実と虚構」という旧態然たる図式で批判することには同意できない。 さらに、山田は目黒の作品を読んで「真に迫る作品」「作者にとっても心を強く揺さぶられた重大な経験であるというリアリティがよく伝わってきた」と言っている。その一方で文語旧かなであることを難じ、「現実に起こった事件と間違いなく実在するその当事者たちの存在から、目をそらしているようで無責任」「この事件の被害者や、あるいはネット上に心ない書き込みをした赤の他人の心を、一ミリでも揺らすことがこの文体で出来るだろうか…(中略)…メッセージの内容ではなく、現実に巻き込まれた事件を現実感のない言葉で表記している文体の方に、まず反感を持つのではないか」としている。 一体何を言っているのか、と思う。思い違いをしてはならない。山田は、目黒の作品にとって、読者という当事者なのだ。読者として「作者にとっても心を強く揺さぶられた重大な経験であるというリアリティがよく伝わってきた」ならば、それで十分ではないか。そして、目黒の作品についての、外部からの無理解を危惧するならば、その無理解に対して「もはや抗えない」などと白旗をあげて屈服し、迎合するのではなく、文語文体と旧かな表記の詩的必然を堂々と主張し、全力で目黒の作品を擁護すべきではないのか。外部からの倫理的圧迫を怖れ、文体とリアリティーの問題にかこつけて自主規制を迫るような物言いはやめるがいい。 文語旧かなは、「言葉のコスプレ」である一方、詩歌の本質としての言語の固有性(翻訳不可能性)に関わるものであると思える。その意味で、文語旧かなという歴史的表象は、本質的には、けして古くもなく、世界性に背を向けるものでもない。 |
||||||
| 2018年3月号 |
||||||
|
『賞を狙うということ』 服部真里子 |
||||||
|
二〇一七年度の短歌総合誌による連作を対象とした新人賞は、歌壇賞に大平千賀「利き手に触れる」・佐佐木頼綱「風に膨らむ地図」、短歌研究新人賞に小佐野彈「無垢な日本で」、角川短歌賞に睦月都「十七月の娘たち」という結果であった。結社内では、未来賞を工藤吉生「うしろまえ」、大西久美子「夏のにほひ」、蒼井杏「ゆるゆるフリル」が受賞している。「受賞のことば」で、「数々の賞に連作を応募してきました。そして落選してきました」と述べる工藤は、これが二十四回目の応募だという。 私もまた、何度も新人賞に応募してきた。あなたの短歌はすばらしいと認めてもらいたかったからだ。そして何度も落選してきた。ずっと賞に固執して苦しんできた。 賞に応募することは、自分の歌の価値判断を外部にゆだねることだ。自分の中に、「これがいい歌」という揺るぎない価値基準がある人に、賞は必要ない。人に認められようと認められまいと、自分の「いい歌」を作ればいいからだ。賞を狙うのは、普遍的な「いい歌」の基準が自分の外部にあると考え、それをある程度信頼する人だろう。 賞を狙う=外部の価値基準で評価されたいと欲望を持つことを、よろしくないと思う人は多い。個人的には、自分の価値基準と外部のそれが矛盾するとは限らないし、外部の価値基準に合わせようとトライすることで自分の歌が磨かれると思うので、ぜんぜん悪いとは思わないが、その欲望があると苦しいのは事実だ。外部の価値基準なんて実は存在すら不明だし、実在したとしても人や時代によって変わる。そんなものに、歌はいいとしてうっかり心を託してしまえば、振り回されて苦しくなるのは当然だ。自分の価値基準だけを信じて短歌を作っていけるなら、それが理想だとは思う。 詩人の文月悠光は、講談社主催のアイドルオーディション「ミスiD」(個性的な女の子の活動を応援するオーディション)に詩人として出場した経験を、cakesのweb連載『臆病な詩人、街へ出る。』(二月に立東舎より書籍化)で次のように書いている。 選考通過の電話を受けて、私は青ざめた。写真撮影? 自己PR動画? 美少女たちと比較されることになる。公開処刑だ、と身震いした。といっても、今からやれることは限られている。 せめてもの心づもりとして私がやったことは、動画撮影に備えて朗読用の詩を書くことと、ダイエット。最終選考までの2ヶ月で5キロ近く痩せた。 ダイエットをして、それをエッセイに書くのは、「私は容姿の評価を気にしている」という告白だ。「私は詩で勝負しているのだから、そんなの気にしない」とかっこつけることもできたのに、彼女はそうしなかった。容姿の価値基準で評価されたいという、どちらかといえばかっこ悪い欲望に、正々堂々と向き合う姿に心を動かされる。 自分の価値基準だけを信じて短歌を作っていける強い人が、果たしてどれほどいるだろう。外部の基準で認められたいという欲望は、かっこ悪くてはずかしくて、できたら直視したくないものだ。しかし、外部の価値基準も、それに認められたいという欲望も、多くの人にとっては確かに存在する。存在する以上、どんな態度をとるにせよ、つきあっていくしかない。 賞を狙わない人は立派だ。外部の価値基準に認められたいという欲望に負けず、自分の価値基準を信じて戦っているのだから。 賞を狙う人は立派だ。外部の価値基準に認められたいという欲望に向き合い、かっこ悪さから逃げずに戦っているのだから。 |
||||||
| 2018年2月号 |
||||||
| 『早稲田文学増刊女性号』 盛田志保子 | ||||||
|
昨年九月に刊行された「早稲田文学増刊女性号」が話題になり、十一月には雑誌としては異例の増刷が決定された。「女性」と「書く」ことの関係性をテーマに、女性の書き手ばかり八十二人を集めた文芸誌である。作家の川上未映子が責任編集を務め、企画、人選、依頼、校正、編集の全てを担い制作された。 見た目はホールケーキのようだ。白を基調に、ピンク、深い緑、紫、水色……。表紙の中央には、横になって本を開く森の中の女性、すずらん、虫や動物などのイラストが描かれ、側面を見ると、表紙に使われていたそれらの色が、今度はきれいに層になっている。厚みは三センチ以上。紙の質感や色あいが一冊の中でいくつかの作品ごとに変わり、そのせいか、ぎっしり小さな文字で埋め尽くされた五百五十六ページの本は、買ったばかりのまっさらなレターパッドにも見えてきて、ページを繰りながら時々、「ああ、誰に何を書こう。」という思いに駆られた。いや、紙だけのせいではない。そこにある言葉は、そっと受け取れば深く届いて、わたしはまたそこから両手で掬えるほどのなにかを、だれかに手渡してみたくなるのだった。 川上未映子による巻頭言の一節、 それが本当のところはいったいなんであるのかがついぞわからない仕組みになっている一度きりの「生」や「死」とおなじように、まだ誰にも知られていない「女性」があるはず。まだ語られていない「女性」があるはず。 という部分を読んだとき、頭に浮かんだのは母であり、今は亡き祖母であり、そのまた母であり、妹であり、同級生であり、近所のママ友であり……。石垣りんの「唱歌」、永瀬清子の詩「村にて」、ジーン・リースの小説「ジャズと呼ばせておけ」、樋口一葉「大つごもり」(川上未映子による現代語訳)など、時おり女の家族を思いながら読んだ。 角川「短歌」十一月号の歌壇時評では、山田航が「女性号」をとりあげ、「大正生まれの安立スハルに、体系化されたフェミニズムの知識はなかっただろう。しかし人生経験の中で自然に得られた生き方の指針が、フェミニズムと限りなく接近したかた ちになって歌から強くにじみ出ている。」と書いている。あらためて短歌ってそういうものだろうなと思う。生きることと歌うことが切っても切れない。だからこそ「強くにじみ出ている」のだ。それは、現実の人生を直に詠みこんでいく場合に限った話ではない。今回わたしは「女性号」のなかでも特に、雪舟えまの「俺たちフェアリーている(短歌版)七十七首」に感動した。短歌が持っている確かな、明るい、そして未知数の力を感じさせてくれたからだ。何首か引用しても魅力は伝わらないが、例えば……。 『恐竜のひみつ』をめくり君はつぶや「恐竜にひみつなどない」 風とばかり思っていたが俺たちは草原編み機を見ていたのかも 雪舟えまは小説家でもあり、この連作には小説のなかの登場人物が登場する。歌人は彼らになりきっているわけでもなく、ト書きでもなく、脚本でもなく、短歌であるむしろ自然詠である。あれ、短歌ってこんなに自由だっけ。うれしいものだっけ。七十七首の紛れもない五七五七七。 「塔」十一月号の短歌時評では花山周子女性に限らず、人は誰しもが、その場所でのマイノリティーとして生きている。」と書いている。本当にその通りだと思う。 「早稲田文学女性号」、二〇一七年で一番新しくて懐かしい、大きな収穫であった。 |
||||||
| 2018年1月号 |
||||||
| 『私の前衛短歌』 服部真里子 |
||||||
| ほほゑみに肖てはるかなれ霜月の火事の中なるピアノ一臺 塚本邦雄『感幻樂』 短歌=百人一首、と思っていた大学一年生の私は、早稲田短歌会の勉強会で出会ったこの一首にびっくりした。短歌ってこんな自由な、詩みたいなのでいいんだ、と思ったところから、私の前衛短歌は始まる。だから、永田和宏『私の前衛短歌』(砂子屋書房)にこんな一節が出てきたときもびっくりした。 前衛短歌の功罪の功は非常に大きいけれど、ひとつ罪をあげるとすると、「あれはしてはいけない」、「これをしてはいけない」という禁止条項を非常に強調した面がある。 私の目には「自由」に映った前衛短歌が、永田の目には「禁止条項を強調する」ものに映ったのか。当然ながら、前衛短歌の時代をリアルタイムで経験した永田と、塚本の死後に短歌を始めた私とでは、受容のしかたがかなり違う。 二〇一七年十月二十二日の朝日新聞「短歌時評」では、大辻隆弘がこの本を紹介しつつ「前衛短歌は作中の『私』と現実の作者の区別を強調し日常生活を歌うことを禁じた」と自身の前衛短歌観を述べている。 確かに前衛短歌は、発生においては「作中の『私』と現実の作者の区別を強調」することが最大の目的だったかもしれない。しかし現在、二〇〇六年に短歌を始めた私が前衛短歌を読むと、前景化してくるのはそこではない。では何かというと、「心のきらきら」である。ひどいネーミングで申し訳ないが他に思いつかなかった。 くちなしの実煮る妹よ鏖殺ののちに来む世のはつなつのため くちなしの実を煮ると、水は黄金色に染まる。透きとおった黄金は、煮殺されたくちなしの血の色だ。はつなつはかがやかしい季節だけれど、鏖殺ののちのそれは、新しい世を贖うために流されたおびただしい血のゆえに、ますます背徳的な黄金色にかがやくことだろう。イノセントなイメージを持つ「妹」が行うからこそ、この幻視の惨酷な美しさが際だつ。 このような映像を思い浮かべると、私は心がきらきらする。この心のきらきらよりも、塚本に妹がいたか否かが重要だとは、今となってはどうしても思えないのである。日常生活を歌うことを禁じたというより、単に日常生活より心のきらきらの方に興味があっただけのような気がする。 また、前衛的といわれる短歌が、必ずしも「作中の『私』と現実の作者の区別」をしているわけでもない。岡井隆は、短歌研究文庫の『塚本邦雄歌集』(短歌研究社)の解説で、「父」「ちちはは」という語を詠み込んだ塚本の歌を引き、 塚本が父母を歌に読み込む時のこころは、単に歌のための素材としてだけであろうか、そんな筈はないのである。(中略)やはり、あり得たかも知れない親たちの姿を、意識下にしのばせていたとうけとれるのである。 と書いているが、これと同じことが先に引いた歌の「妹」にも言えよう。年譜と歌が呼応することだけが、作中の「私」と現実の作者の一致ではないはずだ。塚本の歌には、塚本の心が何にきらきらして、何にしなかったのかが、はっきりと表れている。そこに塚塚本の顔を見ることはできないだろうか。前衛短歌は、歌から現実の作者を切り離したというより、作者の顔の反映のしかたをそれまでと変えたのではないか。 |
||||||
| 2017年12月号 |
||||||
|
『短歌の醍醐味』 盛田志保子 |
||||||
|
あさやけみてないて ゆうやけみてないて 私は昔から時々この歌のことを思い出しては、どういう意味なんだろうと考えてしまう。あさやけをみて赤い涙を、ゆうやけみて黄色い涙を、こぼすなきむしかみさま。その涙は見たものそのものの色だけを映しているということだろうか。静かな湖面が空の色を映すように。 そしてもしかしたら、なきむしかみさまの涙は「言葉」ではないかと思ったりもする。しかも美しく、美味で、タダ同然で、大人にも子供にも愛され、どこでも無邪気にぺろぺろとなめてもらえる、それはまぎれもなく、「詩の言葉」なのではないかと。本当はもっと、実物のドロップスくらいすてきなものかもしれないけれど。 短歌だって詩だ。しかし、あさやけを見て感動しあさやけの歌を作ろうとするとき、それはあさやけの色そのもの「だけ」にはなりえない。それを伝えようとするけれど、作者自身の成分が意識的にも無意識的にも、色合いや味わいとして混じってくるからだ。言葉である以上。なきむしかみさまは、なんといっても神様だから、あさやけいろの涙をこぼす。わたしたちは人間だから、そこまでまじりっけなしの涙をこぼすことはできない。たぶん完全完璧な写生であるかどうかという問題ではない。そのことは、どこかほの明るい残念さであり、どこか腹の底に力の入るような面白さでもある。 角川「短歌」十月号、坂井修一と詩人のアーサー・ビナードとの対談がおもしろかった。AIが短歌を作るようになるかという話で、坂井は新人賞の賞金狙いなどのような目標があるならば「その可能性はある」としつつ、「ただ我々は賞取るために歌を作っているわけじゃないですからね。賛否両論の怒号の中を楽しみ苦しみ生きていく、その苦悩や歓喜をバネとして表現していく、というところに醍醐味があるんじゃないですか。」と言っている。たしかに、うっかり忘れがちではあるが、目的なんてあるようでないのだ、わたしたちのやっていることには。それにも拘らず「賛否両論の怒号の中を」とは、いよいよ魅力的な話だと思う。実際、短歌を一人で作っている時はなんの痛みもない。だが、発表する、人の目にさらす、そういう中で思いもよらない「苦悩や歓喜」に見舞われる。たかが趣味、たかが遊びなのに、と割に合わない気がすることもあるが、よろよろになってもまた歌を作り人に見せてしまう。(たぶん)ゴールは(特に)ない。 そういえば、冒頭の歌の二番はこうだ。 かなしくてもないて うれしくてもないて |
||||||
| 2017年11月号 |
||||||
|
『天の川銀河発電所』 実況中継 服部真里子 |
||||||
|
俳句を読んでみたい。短歌と同じ定型詩だし。でも、読み方がよくわからない。どんな作家がいるのかもわからない。そんなあなたにぴったりの俳句アンソロジーが出た。『天の川銀河発電所 Born after1968現代俳句ガイドブック』(左右社、佐藤文香編著)である。『桜前線開架宣言Born after1970現代短歌日本代表』(山田航編著、二〇一五年)の俳句版で、一九六八年以降生まれの作家五四名の作品を、「おもしろい」「かっこいい」「かわいい」の三つの章立てで収録している。俳句を読み慣れない私でも楽しめたので、私流の読み方を紹介したい。例えば、鴇田智哉。 うたごゑを口がうたへば孑孒も 顔のあるところを秋の蚊に喰はる 歌は口でしか歌えないのに、わざわざ「口がうたへば」と書いて、口を人から切り離す。蚊に喰われた箇所が、顔の中というより、世界全体の空間の中で把握される。人体のパーツが、持ち主を離れて勝手に動いているようで怖い感じがするけど、私ちゃんと俳句読めてる?
この本がありがたいのは、今が旬と思われる一八名には、それぞれ佐藤ともう一人の俳句作家による「読み解き実況」対談がついているところ。そこで「読み解き実況」である。 佐藤 鴇田さんは以前インタビューで 「それだけで生えている」ような句が書きたいと言っています。何かを見て写し取るんじゃなくて、何か自体であるような。だから句が命そのものであるようなところがある。それは句が妙であることともほぼイコールで、すごくおばけっぽい。(後略) 俳句作家の二人に、「おばけっぽい」「事件現場みたい」と言われているところをみると、私が感じたことは外れてもいなかったのか。なるほど、現実の不思議な手ざわりを、言い方で取り出して見せている句なんだ。「初期」ってことは、最近の句はまた違うのかな? それも読んでみたい。 もちろん、詩歌の感じ方に正解も不正解もないのはわかっている。でも、詳しい人に基本路線を示してもらえると、自分がそれとどう違うか、あるいは同じなのかがわかって、自分なりの読み方もしやすくなると思いませんか。 俳句に触れると、では、短歌にしかできないことは何なのだろうと考えてしまう。 胸に森その一本に鵙来たる 藤井あかり 眼と心をひとすじつなぐ道があり夕鵙(ゆうもず)などもそこを通りぬ 収録された俳句と、内容の近い短歌を並べてみた。俳句は、ただ一樹をめがけて、あやまたず飛んでくる鵙を、ぴたりと言い収める。短歌は字数が多い分、「身体の中へ鵙が来る」という内容以外に、「眼と心をつなぐ道がある」という前提を述べ、夕鵙以外のものが道を通る可能性を「も」で示唆する「語り口」が出てくる。単純な比較はできないが、そんなことを感じた。 『天の川銀河発電所』、必読です。 |
||||||
| 2017年10月号 |
||||||
| 『短歌の得意分野』 盛田志保子 | ||||||
|
総合誌を読んでいると、時々、大人の話にこっそり耳をすましている子供に戻ったような心境になる。昔、実家の居間には祖父の姉妹たちが集まって「お茶飲み」をしていた。なんの話をしていたのか。みんなきちんと坐って祖父を囲みお茶を飲んでいた。笑い声、沈黙、また笑い声。時々お小遣いをくれた。あの空気を思い出す。 総合誌には必ず戦争の話がある。病気や介護の話がある。政治の話があり家族の話がありつまりは世間話がある。人間のことが人間によって語られ、答えもオチもなくただあふれている。 「歌壇」七月号には、特集「介護の歌から見えてくる家族の姿」が組まれていて、ひとつひとつのエッセイを興味深く読んだ。介護の担い手、受け手、嫁という存在、家族のありかた……。問題は複雑で一筋縄ではいかないということだけがわかる。ただ、時々思わず笑ってしまう瞬間があった。 「この人らぼけてはんねん」ケアハウス という母を歌った自作短歌を受けて、萩岡の、「他人(ひと)のことはよくわかるのか。私も他人の歌をあれこれ言うことがあるが、自分の歌はわからないのと同じだな、と反省させられた。」というところなど。深い。 わたしは以前から介護短歌が好きで、テレビ番組などもよく見てしまう。「思いを整えて三十一文字ちょうどにする」、「自分のために歌う」、そしてそのために必要な一滴の冷たさ、つまり客観性というようなことを思い出させる。時にユーモアともいえるかもしれない。歌を作るためにも生活のためにも参考になるのだ。ものを違う角度から見たり、自分を冷静に観察したり、驚いたり、短歌を作ることは「今ここ」の風向きを読み直す(変える)ヒントをくれる。 そしてなぜ「子育て短歌」はブームになるほど流行らず(ないとは言わないが)、
「介護短歌」はこんなに花盛りなのかということをよく考える。わたしには短歌という詩形が、介護を通じて死や老いというものとタッグを組み、楽し気に足取り軽く走っていくのが見える。 子育ては、死とは遠く、未来しかない。そう願わない親はいない。もしかしたら歌人は、本能的にそこを嗅ぎ取るから、手放しに子育てを題材として選びづらいのかもしれない。もちろんすばらしい歌もある。一度、世間に大募集してみればいいのにとも思う。とはいえ、ふたを開けたら旦那さんへの愚痴川柳ばかり集まったりして。若いということは、そして「子育て」とは一歩引く余裕がないことでもある。 伊藤一彦が角川「短歌」七月号の「特集 もっとうまくなりたい人のための 短歌再入門」の中で、歌作りに悩む人へ向けてこんなことを書いている。「高齢者の方であれば、同じ高齢者の自分を飾ろうとしていない率直な歌を読むと、自分の心の力みに気付かされ、もっと楽に歌に向かえばいいのだという気持ちになるはずです。」わたしはこの、「自分を飾ろうとしていない」というところにハッとした。やっぱり若いうちは難しいかも、と。そしてこのエッセイのタイトルは「心の中に宝物がある」なのだが、わたしはきっとこういう方向に行きたいのだと思う。うまくいえないけれど。 そして将来、自分は介護短歌を作るだろうかと想像してみる。こればっかりはわからない。その時になってみないと。人間の最期について考えてみる。こればっかりはわからない。その時になってみないと。 実家に集まっていた祖父たちはもうこの世にいない。なんの話をしていたのだろう。 |
||||||
| 2017年9月号 |
||||||
| 『言葉を獲得する──現代における結社の機能』 服部真里子 |
||||||
|
ディズニーの映画「シュガー・ラッシュ」は、とあるアーケードゲームの悪役ラルフが、悪役の集会「BAD-ANON」に参加するところから始まる。悪役たちは輪になって座り、まずひとりが
「おれは〇〇(名前)、悪役だ」と自己紹介をする。他のメンバーの 「ハイ、○○」 という応答を受け、彼は悪役としてのつらさを話しはじめる。 あるいは、ジョナサン・ラーソン作のミュージカル 「RENT」で、 「Life Support」が歌われるシーン。メンバーの共通項を 「悪役」から 「HIV陽性」
に代えただけで、 「BAD-ANON」 とほぼ同じことが行われる。 明言されてはいないが、私はこれらを、当事者ミーティング
(同じような立場や境遇にいる仲間同士で、それぞれが思うことを話しあう集まり) と呼ばれるものではないかと推測している。結社誌に自分の短歌を発表し、発表された他の人の短歌を読むのは、これに近い行為なのではないか。 当事者ミーティングでは不思議な現象が起こる。話す人が「私」を主語にすればするほど、聞く人は自分の痛みが言語化されているように感じるのだ。共感とはまた違う。言葉にするなら、「他者の語る痛みの言葉によって、自分自身の痛みを語る言葉を獲得する」といったところだろうか。すると、痛みはなぜか少しやわらぐのだ。 また、NABA (日本アノレキシア(拒食症)・ブリミア(過食症)協会)による摂食障害の当事者ミーティングは、「ミーティングを安心・安全な場にするために」、「言いっぱなし、聞きっぱなし」(他の人の話に口をはさんだり、批評・批判をしない)、
「ミーティング内で話されたこと、見たことは外に持ち出さない」の二つのルールを設けている。 (http://naba1987.web.fc2.com/index.html)(傍点筆者)。短歌の、作者と作中主体はイコールではないというおおよそのコンセンサスは、作者自身を批判・批評から守り、場を安心・安全にするためのルールとして機能していると言えないだろうか。 手術すれば声を失くしてしまうけれどわたしは生きるぜったい生きる 西田未保 見えぬ人少し見える人連れ立ちて雛を見んとて中山法華経寺 池田照子 雛壇の五段目あたり靴を持ち怒り顔なる従者のいると 同 花の旅のチラシを見ればどこもどこも一緒に行きたし長く病む母 篠田理恵 検査後の母の空気はやわらかく庭の蜜柑は小鳥が食べた 新原 繭 われの名は智子と言えば老い母は智子という名の娘(こ)がいたと言う 村松智子 半袖を着られず後悔した夜にカッターナイフを買ってしまう 理宇 消したいのは出前のにおいじゃなく私むせるほど撒く新ファブリーズ 小川けいと ひきこもり我は悩むそんな我太陽の光が我とかしそうで 井上美恵 (引用歌はすべて未来六月号より) 「同じ痛み」なんて気安く言ってはいけない。けれど、「未来」を読んでいると、痛みはひとつひとつがその人だけのものでありながら、ひとつのものでもあり、「私」たちは痛みでつながっていると思う瞬間がある。他の人の歌を読むことが、自分の歌を詠むときの勉強になるのは、多くの人が経験で知っているだろう。私たちは、他の人の痛みの歌を読むことで、自分の痛みの歌い方を学習しているのではないか。現代において短歌結社は、メンバーが互いに言葉を獲得しあう場として機能しているのではないか。 |
||||||
| 2017年8月号 |
||||||
|
『女歌への入り口』 盛田志保子 |
||||||
|
わたしは今まで男性歌人だったのかもしれない。角川「短歌」の歌壇時評、瀬戸夏子による「死ね、オフィーリア、死ね」を改めて読み直しながらそう思った。 「死ね」で始まるタイトルに驚く方も多いかもしれないが、驚きつつ読むうちに、最後はそこに隠された本当の意味がわかる。 角川「短歌」にこの文章が掲載されたのは、今年の二月号から四月号に当たるのだが、インターネットなどでも話題になったこの歌壇時評を、わたしはすぐに取り上げることができなかった。なぜなら瀬戸は歌壇における「女性差別」について真正面から書いていたからだ。 わたしは初めてこの文章を最後まで読んだとき、「よく書いたなあ!」と思わず声に出し、心から感嘆した。そして次に、自分はどうしたらいいかわからなかった。余計なことを言わないほうがいいよ、というささやき声が頭の中で聞こえたような気がした。そんなことがまた怖かった。 ではなぜ今書くのかというと、総合誌を読むようになってから、時々驚くことがあるからだ。それは誰かの会話であったり、ある歌をめぐる解釈における男女の違いであったりした。それを単純に「おもしろい」と感じるときと、妙にひっかかり心の中でぶつくさ言うようなときとあって、そのことについて考えていると、おのずと瀬戸の時評のことが思い出されてくるのだった。 瀬戸はまず、角川「短歌」二月号での文章の冒頭で、阿木津英の功績があきらかに過小評価されすぎていることをあげている。一九八〇年代前半の女歌論議のなかで阿木津が展開したフェミニズム批評的意識を歌壇は受け入れなかったと。「(略)女性は自分が何をつくっているのか自覚がない、方法意識がないなどという理由をもって棚上げされ、一方特別席に坐りそこねた多くの女性歌人たちは、個々の歌人としてではなく、(女性歌人)として括られる。」という阿木津の指摘は現在にも当てはまると瀬戸は言う。ところで私は思うのだが、よく言われるこの「女性は自分が何をつくっているのか自覚がない」というのは、本当に他人からわかることなのだろうか。謎である。 また同じく四月号で瀬戸は、おもしろいことに、塚本邦雄のことを女性歌人(、、、、)だと発見している。「しかし『前衛短歌』という、強引に言ってしまえば、女性的な短歌の世界に君臨している、醒めた視点から世界を鳥瞰することのできる歌をつくることができる魔女とは、塚本邦雄その人のことであった。」と。もしこれだけを見て失礼だとかめちゃくちゃだとかいう人がいたら、一度黙ってこの時評を全部読んでほしいと思う。 最後に、この三月、水原紫苑著『桜は本当に美しいのか』の改訂版が出版されたので、「独りうたう女たち」から引用して終わりたい。「(略)今までのところ、短歌の歴史は、ほとんど男たちによる歴史である。それは、世界中でも女の社会進出が遅れているこの国で、珍しい現象ではないのだが、歴史的にも短歌ほど女の才能に適しているジャンルはまれであるし、実際すぐれた女の歌人は世代ごとに見ても男よりはるかに多いのに、残念なことである。(略)女による女の歌の歴史が、語られていくべきだ。」そして別の項からも一文。「短歌は、日本の根源的な闇に直接繋がっている。」 わたしはこれまで、塚本邦雄ほどヒリヒリもしていない、瀬戸夏子ほど深く考えようともしない、鈍感な男性歌人の一人であったと思う。(実際には棚上げでも) やっと「女歌」というものに興味がわいてきたところだ。 |
||||||
| 2017年7月号 |
||||||
| 『枡野浩一のかんたん短歌』 服部真里子 | ||||||
| 枡野浩一による短歌入門書『かんたん短歌の作り方』の中心となった連載「マスノ短歌教」が始まったのは一九九七年。マスノ短歌教が誕生してから、今年でちょうど二十年になる。これを期に、枡野浩一のかんたん短歌について考えてみたい。 かんたん短歌とは、「簡単な言葉だけでつくられているのに、読むと思わず感嘆してしまうような短歌」(『かんたん短歌の作り方』)で、ルールは【ア、あくまで五七五七七で!】【イ、いつもの言葉づかいで!】【ウ、嘘をついてでも面白く!】の三つ。例として枡野の作品を引く。 毎日のように手紙は来るけれどあなた以外の人からである 枡野 浩一 かなしみはだれのものでもありがちでありふれていておもしろくない こんなにもふざけたきょうがある以上どんなあすでもありうるだろう かんたん短歌は必然的に、名詞より助辞に重きを置いた短歌になる。なぜなら、ルール【ア、あくまで五七五七七で!】を守ろうとすると、名詞は音数の調整が難しいため、どうしてもてにをはや語順が工夫のしどころになるからだ。名詞は、個々人の過去の経験によって、喚起されるイメージがかなりぶれる品詞である。「自分と同じ経験をしていない人にこの表現は通じるか? と、常に自問してください。」と説く枡野に従えば、自然と一首のなかで名詞の比重は減る(「比重」であって「個数」ではない。一首の醸し出すものが、どのくらい名詞に因っているかという意味)。 枡野の短歌を読んでいて、漠然と「『私』の顔が見えにくい」と感じた。大辻隆弘は『近代短歌の範型』で、短歌における「私」を、次の三つのレベルに分けている。 レベル①「私」…一首の背後に感じられる「私」(=「視点の定点」「作中主体」) レベル②「私」…連作・歌集の背後に感じられる「私」(=「私像」) レベル③「私」…現実の生を生きる生身の「私」(=「作者」) 私が「見えにくい」と感じた「私」とは、このうちどれにあたるのだろうか。 先に引いた三首を読むと、レベル①の「私」は見える。二・三首目は、具体的な映像をむすぶのは難しいが、ぎりぎり「歌に書いてあることを考えている人」はいる。レベル③はテキストの外の「私」、つまり枡野浩一(の、「短歌以外のさまざまなデータや情報から作り上げられた虚像」)だからもちろん見える。つまり、主にレベル②の「私」が見えにくいということになる。 その理由は、枡野が、短歌における名詞の比重を軽くしたからではないか。もっと言えば、名詞にかぎらず、枡野はあらゆる個人的な経験を、おそらく「自分と同じ経験をしていない人にこの表現は通じるか? と、常に自問」した結果、歌から遠ざけた。その「個人的な経験」こそが、レベル②の「私」を作り出すものだったのではないか。そして、かつてかんたん短歌が「これは短歌ではない」と言われたのは、レベル②の「私」が見えづらかったためではないか。 ところで枡野は、レベル③の「私」について、次のように述べている。 どんなに胸をうつ言葉であっても、その言葉を発した人がこれまで何をしてきたか、これから何をしていくか……ということをぬきにして、言葉だけを味わうことなんてできない。(『日本ゴロン』) 枡野が、短歌の中でレベル②の「私」を弱めたことと、短歌の外にあるレベル③の「私」が短歌に強く関わると考えていることは、どこかつながっているように思える。 |
||||||
| 2017年6月号 |
||||||
|
『和歌・短歌』 盛田志保子 |
||||||
|
少し前、たまたまテレビで見かけたのだが、藤原定家の子孫で歌道の家として知られる京都の冷泉家の方が、「和歌は自分の見たもの聞いたものを詠むのではない。四季の移り変わりを詠むもの、だけれど、現実にほんとうに見たかどうかの話ではない。」と言っていてショックを受けた。まず、わたしはいつから、短歌とは「自分の見たもの聞いたもの」を詠むべきものだと思っていたんだろう、という衝撃。そして、「自分の見たもの聞いたもの」を詠まないとすると一体なにを詠むのか、自分の目や耳を使わずに四季の移り変わりを詠むとはどういうことなのか、という衝撃。しかしよく考えてみると、自分の短歌のどこに「自分の見たもの聞いたもの」が入っているというのだろう。あんまり入っていないじゃないか。 「現代短歌」三月号では、『十首でわかる短歌史』という特集が組まれている。編集後記によると、今回、執筆者である九人の歌人たちへ、「いまわの際にある人が言いました。『わたしは短歌のことをよく知りません。上代から現代まで、短歌を十首あげて、その歴史をかいつまんで教えてください。わたしにはそれ以上の時間がない』」という原稿依頼状を出したのだそうだ。九人はそれぞれ自分の持つ短歌観を駆使して、この「わたし」に宛てて手紙のような「短歌史」を思い思いの文体で綴っていく。いつもより少し芝居がかったような書き手たちの文章も楽しい。 ところで、九人のうち六人が藤原定家をあげ、そのうちの四人が同じ歌をあげている。『新古今和歌集』より。 見わたせば花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕ぐれ 藤原定家 今回、歌会なら一番の得票率だ。短歌の歴史を語るうえで重要な一首なのである。濱松哲朗はこの歌について「(略)定家のこの歌はある意味、日本語表現の極致かもしれません。何しろ、三句目で「なかりけり」と告げられる前に、私達は既に花と紅葉の姿を目の前に現出させてしまうのですから。圧倒的に寂しい光景の下の句に至る過程で見せられたこの、存在しない世界の魅力は、消し去りがたい印象を読者に与えます。」と書いている。「ない」のに「ある」。「ある」のに「ない」。魔法のようだ。 そしてわたしは冒頭の冷泉家の方の言葉をまた思い出すのである。 「歌壇」三月号の特集『短歌の中に残したい言葉』も興味深かった。「欲る」「まがなし」「真夜」「ゆんで」「いかのぼり」……。今野寿美いわく、歌ことばは「実作者が過去の作品に接して享受するほかない。」という。「短歌のなかくらいでしか使われなくなった文語や、それに近いことばは、過去の作品に接して親しむなかから身につけるほかない。逆に多くの作品を読むなかで脳裏に刻まれたことばは記憶の底に残り、自分が表現する際におのずと呼び起こされる。(略)歌ことばの多くは、その条件に適った、歌人にとっての財産なのだとわたしは思っている。」 もしかしたら、「自分の見たもの聞いたものを詠むのではない」という言葉は、短歌はこんなふうに時代をこえて、変わらないもののために、みんなでおおらかに作るものだよ、という意味もあるのかもしれない。自分の言葉という幻想にとらわれず、堂々と歌ことばを使ってみたいものだ。 |
||||||
| 2017年5月号 |
||||||
|
『内的要請と外的要請』 服部真里子 |
||||||
| それはなお続くはるさめ 銀河まで寄ろうそのあと嘘をゆるそう 山中千瀬
『さよならうどん博士』 お気づきだろうか。この歌、「卒業・おめでとう」の沓冠折句(各句の最初の音をつなげ、次に最後の音をつなげると、言葉が現れる技巧)になっているのである。 それらすべて嘘なのだから千年を夜来香(イエライシャン)しくじるように咲く (双生児) 獣性をうつくしく見る。にんげんはがっさい海へつながらん雨 (十二月) ちちははをようやく許しこれからの生きるさきざきのとおい祝福 (チョコレート) 『さよならうどん博士』から、さらに折句の歌を引いた。嘘、永続する雨、許し、祝福などのイメージが共通するのは、同一の作者の内的要請を反映した結果と言えよう。通常の歌より制限が多いからこそ、折句は良くも悪くも、作者にとって使いやすいイメージを引き寄せる。先ほどの例でいうなら、「リンゴのようだ」と言いたい人は、「み」が来ても「ミカン」を思いつかず、つい「蜜入りリンゴ」とか「リンゴみたいな」とか言ってしまい、そこにその人らしさがにじみ出るといったところか。 折句が作者の内的要請を阻害しないとしたら、抵抗感の根底にあるものは何か。 |
||||||
|
2017年4月号 |
||||||
| 『総合誌を読もう』 盛田志保子 | ||||||
|
「未来」以外の短歌誌を滅多に読まないわたしが、時評を担当することになって困っている。引き受けてしまった今、ばたばたと総合誌やら他の結社誌やらを手元に集め、取り散らかしている。どうなるかわからない。だが、これが半年、一年続くころ、自分の中でなにが起きるか知りたい。なにも起きないかもしれない。だれかの役に立つかはわからない。 定型という形を借りて短歌をやっている以上、どんなにもがいても斜に構えてもシラを切っても、大きな「短歌」という枠からは出られない。そして時代の影響を全く受けずに歌を作ることもできないだろう。 とりあえず冬の総合誌をあれこれ読んでみた。ごうっという風が頭の上のほうを吹いているのに気付いた感じ。思えば、「未来」に所属していない現役の歌人が今いったいどんな歌を詠むのか、わたしは知らないのだった。もちろん歌集を読むことはある。だが、総合誌を楽しみのために読む、という贅沢をわたしは知らずに来た。 総合誌には、知っている歌人、知らない歌人、結社を超えて年齢も時に性別さえもよくわからない歌人たちが、作品を並べてそこにいる。すごい。短歌のデパートや~。と一気に頭が沸点に達する。そして、歌を読みながら思うのは、やはり「この人はどんな人だろう」ということのようである。 子供のころからチラシの裏に描く落書きは人の顔ばかりであった。いつか大人になれば、興味の対象は花鳥風月に移行していくのではないかと(なぜか)思っていた。しかし未だに、がっかりするほど、自分や周りの人のことで頭がいっぱいだ。そんなことを思いながら、短歌研究1月号、田口綾子氏の「短歌時評」を読む。 近年、「作者=作中主体」という基本的な図式に則った短歌の読みから離れた、または離れようとする歌を作る作者がどんどんあらわれている。その一方で田口氏自身は、ある昔の歌人の作品を読むさいに、「『評伝』的な情報に読みを助けられた。」という。これは多くの人に経験があるのではないだろうか。評伝は作者自身のプロフィールのような要素を持つ。「では、『作者=作中主体』の構図を脱したがっている歌人たちについての評伝は、書かれてゆくのだろうか。」と。そうだ、たしかに。どうなっていくのだろう。そして歌の背景に「人」が見えるということは結局どういうことなのか……。 たとえば、総合誌の巻頭を飾るベテラン歌人たちは時に謙虚である。謙虚とも違うのだけど。角川短歌一月号の特集には、短いエッセイ「私が考える良い歌とは」が添えられている。「私は名歌を作るなんて到底できない。せめて悪い歌を作らないように心掛けよう。」(高野公彦)、「「千に三つ」位は人の心に残る作品が出来れば嬉しい。」(尾崎左永子)、「明らかなことは良い歌とはまだ自分が作ったことのない歌のことです。」(渡辺松男)……。なんだろう、この、「まさか!」とは言わせないなにか。変な話だが、ポーズではなく、本当にそう思ってるっぽい。と、感じてしまうのだ。そうしてわたしは、頭のどこかで、こういう人が詠む歌、と思って歌を読むのである。いやになるほどシンプルだ。そしてそこにつまらなさや限界があるし、同時にしあわせやよろこびもあるように思う。「本当のことである」必要はないのだけれど、わたしたちは言葉を通して、やはりどこかで夢を見たいと思う生き物なのではないかと思う。読むときも、詠むときも。 次回、服部真里子氏にパスをする。これから一年間、交互に書いていく予定だ。 |
||||||
| 2017年3月号 |
||||||
| 書かない人の方が多い、から書いた方がいい 吉野亜矢 | ||||||
|
時評を書くに当たって、短歌総合誌のいくつかを定期購読することにした。もともとそういう習慣があまりなかったので、予想はしていたものの難渋した。一冊すら読み込む前に次の号が届き、積み上がっていくのである。楽しみを通り越して絶望的な気分になったが、思い起こせば「未來」が届き始めた頃もそうであった。当初、得体の知れぬ森であったものが、構成に慣れ、出て来る名前に慣れしていくうちに、自分の中にだんだんと地図ができていった。気を取り直し、まずは目を通すようにしたのが時評の類であった。 「歌壇」(本阿弥書店)は三人の筆者が月交代で執筆するスタイルで、二〇一六年三月~一二月は福士りか、西之原一貴、奥田亡羊が担当。「短歌研究」(短歌研究社)は一人の筆者が三か月交代で執筆しており、二〇一六年三月~十一月は、三枝浩樹、寺井龍哉、喜多昭夫。「短歌往来」(ながらみ書房)には評論を対象にした「評論月評」があり、二〇一六年三月以降の執筆者は四月までが岩内敏行、五月以降が田中教子。(「現代短歌」(現代短歌社)には力尽きて手を出せなかった。お許しいただきたい。)いずれも二ページであり、文字数は前後するだろうが、この辺りが月刊時評の標準的な分量と言えそうである。 この傾向に一線を画すのが「角川短歌」(㈱KADOKAWA)の「歌壇時評」である。執筆者は二名、基本半年交代、分量はなんと六ページ、文字数にして六千字というから四百字詰原稿用紙だと一五枚になる(ちなみにこの原稿は十九字×七十六行、約千四百字)。二〇一六年四月~一二月の執筆者は川野里子、阿波野巧也、大井学、中津昌子、魚村晋太郎、佐々木定綱(顔ぶれが多いのは、途中体調を崩した川野を、大井と中津が引き継ぐ形となったため)。対象の期間では阿波野の論に立ち止まることが多かった。 「自己目的化した〈驚異〉」や、「理知的な言い換えによる「上手い」認識」では、言葉やものは驚異や認識のための記号となってしまう。(「共感と驚異と匿名と機知」二〇一六年三月号) 職業詠も情勢も《私》に引き寄せて詠わない限り脆いものになる。〈私〉の重力場を〈公〉の重力場よりつよく鍛え上げること。短歌の「一人称性(私性)」を利用する者はその意識を持たねばならないだろう。(「『砂丘律』を中心に仕事と日常のことを考えてみた」二〇一六年四月号) 若い世代に発表の機会がないのは、一概に実力がないからではなくて、総合誌が特集として特別扱いでしか機会を与えないという理由もあるだろう。(「短歌総合誌について私が不満におもってること」二〇一六年六月号) 最終回となった六月号は、タイトルを始め、なかなか思い切った発言が散りばめられているが、全体としては配慮の行き届いた礼儀正しい指摘となっている。この稿では歌壇における「歌人=男性」の無意識についても触れられており、読み応えがある。 二〇一七年、この長文時評を担当するのは松村正直と瀬戸夏子である。瀬戸は初回の一月号において「このまずしいところから、遅れてやってきて」と題して、短歌に関する自分の来歴と地方で情報的に「まずしい」環境にある現状を述べ、「まずしさ」を希望に変えて、「遅れ」をタイミングとして受け止めて、執筆したいとしている。 同時期に時評を書いていた方々には一方的に連帯意識を持っていた。これから書く人にもである。私の担当は今回で終わりです。十か月間ありがとうございました。 |
||||||
| 2017年2月号 |
||||||
| 読み返すという贅沢 吉野亜矢 | ||||||
|
二〇一六年一一月に発行された同人誌「66」(ロクロク)を読んだ。発行者である「ロクロクの会」は、浦河奈々、遠藤由季、岸野亜紗子、後藤由紀恵、齋藤芳生、高木佳子、鶴田伊津、富田睦子、錦見映理子、沼尻つた子、山内頌子、玲はる名の「おおむね四十代の女性歌人グループ」であり、誌面はメンバー十二名による十五首詠、近現代の女性歌人十一名の一首評、66の会の歌会記録の、大きく三部に分かれる。 一首評の部は、各人が持ち寄った一首について座談会形式で批評が展開されるのだが、言葉の原義や制作時の社会的・個人的背景、短歌史を踏まえた読み解きが行われており、信頼感を覚えた。 ときをりは無菌室より取りだしてたしかめてみるわれのたましひ 大村陽子『砂がこぼれて』(本阿弥書店、一九九三年)より。選は鶴田伊津。一九九一年に第二回歌壇賞を受賞するも現在は歌を続けておらず、私も初めてその作品を目にした。 わが父が犬の乳房を揉みながら慰安婦きぬ江の黒子(ほくろ)を言へり 乳首がかすかに痒し桃色のカバーのノブを廻してをれば 一九五六年生まれとのことなので受賞当時で満三五歳、二〇一六年現在で六十歳の歌人だが、父親の介護といったテーマは今日的でもあり、「女性としての家父長制への憎しみ」(錦見)、「官能性」(齋藤)といった指摘を興味深く読んだ。〈歌〉と〈歌人〉が話題にされる期間が短くなり、ただ消費されていく傾向への危惧とともに大村の歌を提示した、鶴田の視点に注目する。 けざやかに菜の花燃やすこの夕焼ならおそらくは死とつりあへる 笹原玉子『われらみな神話の住人』(北冬舎、一九九七年)より。選は物部鳥奈(こと玲はる名)。(掲出歌はやや異質だが)「散文的な、一行詩のような歌」(錦見)、「この人大変なんだなあとかそういうことを思わずに読める」(沼尻)、「ポエティックで物語的な歌は評に挙が」りにくいが「今後評が出てくればいい」(遠藤)。沼尻の評には、いわゆる私性の濃い歌に向き合う時のしんどさを思い微苦笑を誘われ、遠藤の評には、ならばどういった批評が可能かを考えさせられた。 他にも、錦見が取り上げた飯田有子『林檎貫通式』(コンテンツワークス・二〇〇一年)の「雪まみれの頭をふってきみはもう絶対泣かない機械となりぬ」や、浦河の取り上げた水原紫苑『くわんおん』(河出書房新社・一九九九年)の「投げられしナイフを避(よ)けて踊りゐし未生のわれの髪繊(ほそ)かりき」などは、一度読んでいるはずなだけに、彼女たちの議論に触れて再度読み返したくなった。 全体の中で十五首詠はメンバーの、歌会記録は会の紹介として、座談会の発言をよりよく理解できるよう機能している。信頼関係があって交わされる、本来はクローズドの場での議論を共有できる貴重さが、この冊子にはある。彼女たちと私は、性別・世代に加え、全員が結社に所属しているという点でも共通性が高いと言えるが、何より、広げるばかりではなく選ぶこと、絞り込むことを意識する年代に差し掛かっている点が大きいと思う。新旧多くの媒体から読むべき作品が流れて来ることに焦る心持ちがあったが、全体への目配りよりも、自ずからの偏りの方が、自身を豊かにしてくれるのではないか。何を詠まないか、だけではなく、何を読まないかということについても、自覚的になりたいと思う。 |
||||||
| 2017年1月号 |
||||||
| 第一歌集の出し方 吉野亜矢 | ||||||
|
第四十二回現代歌人集会賞が虫武一俊『羽虫群』(書肆侃侃房、二〇一六年)に決まった。著者は一九八一年生まれ、二〇〇八年に作歌を始め、二〇一二年に短歌研究社のうたう☆クラブ大賞受賞とある。収録されているのは石川美南の監修による三〇八首だが、背景には四千首を超える膨大な作品群があったという。 生きかたが洟かむように恥ずかしく花の影にも背を向けている しあわせは夜の電車でうたた寝の誰かにもたれかかられること この格差社会の底の草原におれはこそこそ草を食う鹿 現状を打破しなきゃって妹がおれにひきあわせる髭の人 敵国の王子のようにほほ笑んで歓迎会を無事やり過ごす 細かい背景を知らずとも、著者の人となりの伝わる歌だと思う。内向的だが人恋しさはあって繊細、うまく馴染むことができない社会に対しても攻撃性を持つことはなく、荒地ではなく草原を見る。兄の行く末に気を回す妹の差金を戸惑いながらも受け取り、様々なものを乗り越えて辿り着いた仕事場での身の処し方ともども、ユーモラスに描写する。人柄全開である。 手のなかに切ってしばらく経つ爪のかけらがあってとても静かだ 窓枠のかたちの届く距離が日々変化して人生はおもしろい 記憶にも川は流れて橋脚に割れる姿を眺めてしまう 献血の出前バスから黒布の覗くしずかな極東の午後 「おれ」への拘泥から一歩離れた歌を引いた。一首目、爪切りから以前切った爪が出てきた場面か。二首目、季節の移ろいが窓枠の影の位置を変化させる。三首目、実景ではないと断ることで却って写生的に思われる川の流れ。四首目、現実から遊離して、無人無音で再生される街の光景。 この歌集の魅力は、一首一首の味わいに加えて、「引きこもりの青年が短歌という表現手段を得て外界との交わりに一歩を踏み出す」という、一種のビルドゥングスロマン(教養小説、自己形成小説)の体裁を具えている点にある。同じく賞の候補となった鳥居『キリンの子』同様、著者のキャラクターへの依存を指摘されがちな出発ではあろう。二度はない祝福だが、芯に太太とした私があることは、短歌の力の一つに違いない。 この新鋭短歌シリーズは、新しい短歌作家の第一歌集の出版を後押しするというコンセプトの下に始められ、一期十二冊を第二期まで完結している。加藤治郎と東直子が主たる監修者として参加し、著者とともに歌集を作り上げていく形式をとる。十年以上前に初めて歌集を編んだ時、私にも手助けをしてくれた複数の人がいた。手探りでなくそうした出会いがあるなら、何と素晴らしいことだろう。レーベル創設のきっかけが、二〇〇九年一月に二十六歳で亡くなった笹井宏之の歌集を同社が出版したことにあるというのも感慨を深くする。同年の本誌三月号(686号)には「故」と添えられた笹井の歌が並んでいる。八年前のことになる。 空へ空へとひきぬいてゆく黄昏のはためきかけてやめたティッシュを 笹井宏之 |
||||||
| 2016年12月号 |
||||||
| 長い時評のような歌集に 吉野亜矢 | ||||||
|
一九九二年に死んだ祖母を、今でも折に触れて思い出す。一九九五年と二〇一一年の大震災、衝撃的な事件事故があった時など、祖母はこれを知らずに亡くなったのだな、幸せなことだな、という風に。 二〇一六年九月、斉藤斎藤の『人の道、死ぬと町』(短歌研究社)が刊行された。二〇〇四年の第一歌集『渡辺のわたし』から干支一巡りしての第二歌集であり、当初は奇抜に思われた名前も、歌壇ではすっかり馴染んだ感がある。二〇〇四年から二〇一五年までの、制作年を章題とする作品約九〇〇首を収めた今回の歌集には、私の祖母や(第一歌集に挽歌が収められた)斉藤の母親が知らない今の日本が描かれている。 歌数について、なぜ「約」かと言うと、手作業で数えたということと、①地の文との判別が困難、②他者の作品の引用、③自作の再掲等、これを一首とカウントしてよいか判断しかねる事例がままあるからである。そのこと一つとっても、この歌集の特異性が分かる。 手に取って読み通すにはかなりの労力を要するが、それはボリュームということだけでなく、取り扱われているテーマが重量級だからだ。主要な連作のテーマを挙げると、結婚(「君との暮らしがはじまるだろう(仮)」)や歌友の死(「棺、『棺』」他)といった身の周りの状況から、凶悪事件の被害者、加害者と死刑制度(「今だから、宅間守」、)、東日本大震災(「NORMAL RADIATION BACKGROUND 1 池袋」、「同2 西新宿」、「同3 福島」他)、少子高齢化と子供を持たないという選択(「わたしが減ってゆく街で」)、核と日本人のあゆみ(「広島復興大博覧会展」他)等、われわれが生きて暮らす今の根深い在りように考察は及んでいる。短歌には元々、記録文学としての性質があるが、足を運び、文献に当たり、長い詞書や夥しい注釈を添えた連作は、新しいルポルタージュを見ているようでもある。 詞書の多用が見られるようになるのは、2007の章の「今だから、宅間守」以降である(大阪池田小事件は二〇〇一年、犯人の死刑執行は二〇〇四年)。短歌作品においても、韻律のずらし、はずしを多用する歌人であったが、小さなフォントで添えられた文章は、定型に乗せることで生じる陶酔と完結感、死者(他者)を生者(わたし)に奉仕させてしまうことを牽制しながら、歌を補う役割を負っている。読みやすい本だとは思わないが、第一歌集においては、すれ違いざまに気になることを呟いて去っていくようなところがあったのが、伝えるということについて、読者への信頼からか何らかの責任感からか、少し前向きになった気がする。「大切なのは、何を書くかではなく、何を書かないかだ」(「棺、『棺』」)とする、率直な吐露に共感する。 乗りかかった舟だから来月も乗る美しい日本に私(51) 声がしてけむりの花火 にっぽんはもうちょっとできる子と思ってた(184) 淡々と滅べばいいという思いがないと言ったら嘘になるのだ(240) 2006の章、2011の章、2013の章から引いた。角川短歌十月号の時評において魚村晋太郎は、「短歌にとってのあたらしさ」を、一つは時代の反映、一つは表現領域の拡大と定義している。斉藤はまさに、後者の意味でのあたらしさを短歌にもたらした人だと思う。私は、日本も私もじゃあこれで、という訳にはいかないと思っている。短歌を詠むことが滅びに奉仕しないよう、黙るなり詠むなりしていきたい。 |
||||||
| 2016年11月号 |
||||||
| 八〇年代生まれの歌人たち 吉野亜矢 | ||||||
| 遅ればせながら読んでおきたいと思った歌人がいる。山田航と吉田隼人だ。 山田は一九八三年生まれ、札幌市出身、「かばん」所属。二〇〇九年に角川短歌賞と現代短歌評論賞を受賞し、二〇一二年の『さよならバグ・チルドレン』(ふらんす堂)で北海道新聞短歌賞と現代歌人協会賞を受賞。第二歌集に『水に沈む羊』(港の人、二〇一六年)。 手に取った順から言うと、山田の編著であるアンソロジー『桜前線開架宣言 Born after 1970現代短歌日本代表』(左右社、二〇一五年)が最初に来る。その名の通り、一九七〇年以降に生まれた歌人四十人についての解題とまとまった数の作品が読めるようになっており、山田本人についても、四十一人目として栞に収録されている。 花火の火を君と分け合ふ獣から人類になる儀式のやうに 放課後の窓の茜の中にゐてとろいめらいとまどろむきみは 泣き虫も弱虫も虫(バグ) 夏空に飛び交うものをふたり見てゐた ホームランを打てず、スタートラインにも立てず、「たぶん親の収入超せない」僕たち。抒情に混じる言葉遊びのセンスは、別途『ことばおてだまジャグリング』(文藝春秋、二〇一六年)に結集したようだ。そして郊外の無個性なニュータウンと、「浮かない」ことが求められる学校にテーマを求めた第二歌集から。 火に焙るマシュマロときに素晴らしい記憶に変はるかなしみもある オルゴール作りが君の母の趣味 君の名前は忘れたけれど ただ白いだけの液体つくりだす俺のからだを抱くんだきみは 溺れても死なないみづだ幼さが凶器に変はる空間もある 吉田は一九八九年生まれ。二〇一三年、「忘却のための試論」で角川短歌賞を受賞し、二〇一六年には同タイトルの歌集により現代歌人協会賞を受賞。所属結社等はない。本歌集が「二〇一一年」、「二〇一一年以前」、「二〇一一年以後」の三部構成になっているのは、吉田が福島県出身であることに深く関わる。巻末には初出一覧があり、同人誌や短歌総合誌に発表した連作が基本となっているが、特に「率」掲載の作品には、同人をはじめとする読者への信頼が感じられる。角川短歌賞は五〇首単位であり(掲載されている受賞作は四九首だが、削られた一首は山田のアンソロジーで読める)、長い連作を成立させる動機や技術が必要とされるが、仏文の博士課程にあるという吉田には、論も作も構築的に積み上げていく粘り強さ(しつこさ)がある。 誰もが誰かを傷付けずにはいられない季節がきます 傘の用意を 燃えおつるせつなの紙の態(すがた)して百合咲きてあり燃えおちざりき 生前のわが使ひゐし歯ブラシは水まはりの掃除に役立てり いもうととまためぐり逢ふいつだつてなにかが安いマクドナルドで をかされしあなたとふしめがちに逢ふあくありうむのあをきくらがり 頻出する「傘」のイメージ、虚構らしき家族の導入、生への呪詛、死のなまめかしさ。従来の流通形態では、「歌集出版など到底望めない経済的条件にあった」という。書肆侃侃房の挑戦の価値を思う。 |
||||||
| 2016年10月号 |
||||||
| あたらしい短歌 吉野亜矢 | ||||||
| 詩と批評の雑誌『ユリイカ』(青土社)が、二〇一六年八月号で短歌を特集している。タイトルは、「あたらしい短歌、ここにあります」。冒頭では、歌壇外への発信を得意とする穂村弘が詩人の最果タヒ(さいはてたひ、と読む)と対談しており、雪舟えま、俵万智、巻上公一、戸川純、斉藤斎藤、瀬戸夏子、結崎剛、井上敏樹、福永信、木下古栗、ミムラ、壇蜜、DARTHREIDER a.k.a.Rei Wordup、澤部渡、雨宮まみ、ルネッサンス吉田、木下龍也、尾崎世界観といった人々(半分以上が異分野の表現者である)が短歌作品を寄せている。 菫色のサインは日露の娘と初恋の比喩、そう、どちらかといえば僕だ 瀬戸 夏子 デュロキセチン処方Max服薬すれば過活動性的逸脱観念奔逸減薬すれば息をする塵【ごみ】死ぬ気力すらない ルネッサンス吉田 論考では、穂村とともに短歌のニューウェーブを背負った加藤治郎、荻原裕幸らも寄稿しており、人物に迫るという形で岡井隆、鳥居、清家雪子(漫画家、『月に吠えらんねえ』の作者)も登場している。吉川宏志は、「過去(筆者注:ここでは十五年といった期間のこと)を検証する議論があまりなされないのが、現代の短歌界の大きな問題点」と指摘し、瀬戸の歌について「価値観の異なる人々には全く伝わらない表現だと思うが、感性や心情を共有するサークルの中では、高く評価をされているようである」と書く。この主張が比較的馴染みやすいのは、自分自身が結社や歌会で受けた訓練との地続き感があるからだろうか。死角があるとしたら、それも共有していることになろう。その吉川に「歌壇から認められないことを積極的にアピールする歌人」と分類される枡野浩一は、佐々木あららとともに商業出版へのこだわりを論じる中で、山田航の著作を「穂村史観」でまとめられていると評している(二〇一五年一二月に『桜前線開架宣言 Born after 1970現代短歌日本代表』と題するアンソロジーを出した山田には、穂村との共著もある)。その山田は石川美南とともに巻末に「あたらしい短歌のキーワード15」を執筆しており、「家族」「学校」「地元」「労働」「言葉遊び」「BL/百合」といった項を担当している。このBL(ボーイズラブ、男性同士の恋愛を扱った女性向けの創作物)に関して石井辰彦は、「チープなエロティシズム」「短歌よりコミックに近い存在」とし、LGBTQ―多様な性の当事者による詩の物足りなさについても言及している(本題は、保守的な若者に《教養》としての《性愛》を深めることを勧めるもの)。その他にも、二〇一四年の短歌研究新人賞受賞作における虚構の設定で物議を醸した石井僚一が歌会について熱く語り、二〇一六年に『忘却のための試論』で現代歌人協会賞を受賞した吉田隼人が専門のフランス文学を駆使して短歌における私性を「抒情詩の〈私〉」として考察している。吉田の論文調の文章はついていこうという意欲を刺激するが、これだけの紙幅を費やして作者と作品の切り離しを試みながら、同じ誌面で自身の角川短歌賞受賞作について、「身近な人を自殺で亡くすという実体験があって」(東直子)という言い方をされてしまうのは皮肉である。穂村と岡井の発言でも、行き着くのはこの私性の問題であったり、文学と生きがいという短歌の価値の両端であるように読んだ。 他にも多様な論者が興味深い論を展開している。手に取ればその人なりの発見がある、刺激的な特集だ。 |
||||||
| 2016年9月号 |
||||||
| 参院選を前に 吉野亜矢 | ||||||
| 二〇一六年七月上旬、街には選挙の言葉が溢れている。言葉の扱いという意味で、それらはとても興味深い。特に幸福実現党のキャッチコピーがこわい。「愛してるから、黙ってられない。」の舌足らずな語調と、理由にならない理由、並び配置される女性党首の顔。黙っていられないのは自分だけではないと思うが、相手側の言い分に耳を傾ける姿勢は感じられず、こうした物言いを女性性に帰属させて納得させてしまおうという意図を感じる。 選挙の際には様々な言葉が生まれる。他国の例でも、英国の脱EUを意味する「Brexit(ブレキジット)」=Great
Britain+exit(離脱)が記憶に新しい。僅差でその離脱派が勝利した後にはそれを悔いる「Bregret(ブリグレット)」=同+regret(後悔)という言葉まで現れた。国としては緩やかに失速していく傾向にあるような気がするが、言葉の扱いにおいては依然逞しさも感じる。 参院選に向けて政党や政治団体の発する日本語に目を向けると、自民党は「この道を。力強く、前へ。」。この道とは何か、という疑問はあるが、老舗だけあって変なツッコミどころを作ったりはしない。政権パートナーである公明党は、弱者を意識した「希望が、ゆきわたる国へ。」。三月に民主党に維新の党が合流する形で発足した野党第一党の民進党は、党名の解題とも読める「国民【国民=ルビ=あなた】と進む。」。日本共産党は、野党共闘を意識した「力あわせ、未来ひらく」。昨年十一月に維新の党から分離する形で発足したおおさか維新の会は、「古い政治を壊す。新しい政治を創る。」。憲法学者の小林節が五月に立ち上げた政治団体、国民怒りの声は、団体名自体がキャッチコピーのようだが、広報素材を見ると「1%の富裕層ではなく99%の普通の人の声を届けます」がそれに当たるか。以下略。 与野党共通して言えるのは、句読点が好きだなあということである。「、」や「。」が入ることで切れ目がはっきりし、きびきびとした印象と発話者の確信を伝える効果がある。一方、短歌では、修辞として積極的に活用する場合を除いて基本的に句読点はあらわれない。掬い上げようとされるのは、言葉の隙間の言い澱みのような部分だと思う。前回に続いての言及になるが、永田和宏は、昨年九月に京都で行った提言「言葉の危機的状況を巡って」において、自分の言葉は政治家の言葉には絶対なれない、と感じた経験を紹介している(同内容の講演は十二月に東京でも行われた)。永田はその三週間ほど前、新宿で行われたデモで、「安全保障関連法案に反対する学者の会」の呼び掛け人の一人として群衆に語りかける機会があり、雑踏の中で言葉を届ける難しさを痛感するとともに、その場で耳にした政治家のスピーチに、自分のものとは全く違う迫力を感じたという。プロの言葉に感服しながらも、民衆に伝わる「政治の言葉」と、「われわれの言葉」は違うだろうというのが、永田の問題意識である。 短歌研究七月号では寺井龍哉が「水原紫苑の眺望」と題する時評で、高校の「うた部」を舞台に短歌が人と人とをつなぐきっかけとなる小説『うたうとは小さないのちひろいあげ』(村上しいこ著、講談社)を紹介しつつ、水原が『桜は本当に美しいのか』(平凡社)で指摘した視点―詩型が持つ共同体への従属傾向を対比させている。歌による自問自答や揺らぎの表現も、個の発露を可能にするだけではなく、集団への同化や現状維持に奉仕する可能性がある。 |
||||||
| 2016年8月号 |
||||||
| 言葉のたくらみ 吉野亜矢 | ||||||
| 五月二十七日、G7伊勢志摩サミットを終えたオバマが、アメリカの現職大統領としては初めて広島を訪れた。平和記念資料館を視察し、原爆死没者慰霊碑に献花し、十七分間にわたるスピーチを行った。 私は地方公務員なので、首長の名の下に挨拶文を起草する機会がある。そんなこともあって人の挨拶文には関心があり、首相官邸(kantei.go.jp)の「総理の演説・記者会見など」の項はよく見る。少し前に話題になった「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式」や「沖縄全戦没者追悼式」における総理挨拶文は、初めて読めば胸を打つ美文だが、使い回されていたことが叩かれた。入れ替わりの乏しい聴衆を前に、過去の不変の事象に対して毎回言葉を繰り出す難しさはあり、様式性のもたらす慰めもあろうが、「今」を反映すれば、触れるべきことは微妙にでも変わるはずである。 オバマの広島スピーチはすぐにテキスト化され、日米その他のメディアで提供された。少し待てば、親切にも日英対訳も出た。注意深く選ばれた言葉や構文は、「私たち」を特定の国民に限定して読まれることのないよう、「人類」や「文明」といった普遍的な概念に引き付けて展開されている。冒頭の問い、「なぜ我々はここヒロシマに来るのか?(Why do we come to this place, to Hiroshima?)」は中盤で回収され、「だからこそ我々はここに来る(That is why we come to this place.)」となる。日米同盟や欧州連合の価値と実績、それでもなお止むことのない世界の対立、悪(evil)に対して防衛手段を持つことの必要性を訴えた上で、初めてアメリカ国民を特定する文脈「私の国のように核を貯蔵している国々は(Among those nations like my own that hold nuclear stockpiles)」が現れる。究極の目標としての核廃絶の可能性に触れながら、「独立宣言に謳われた理想を実現することはアメリカ国内(within our own borders)やアメリカ国民の間において(among
our own citizens)さえ簡単なことではない」と続く。(ourが特定国民を指す形で使われているのはここだけである。)「我々は人類という一つの家族の一員(we are part of a single human family)」という気恥ずかしくなるような文言の後、「だからこそ我々はヒロシマに来る」のフレーズが反復され、「道徳的な目覚めの始まり(the start of our own moral awakening)」を訴えてスピーチは終わる。 五月、『時代の危機と向き合う短歌』が青磁社から刊行された。副題にある「原発問題・特定秘密保護法・安保法制までのながれ」を受けて、吉川宏志が中心となり、京都(平成二十七年九月)と東京(同十二月)で開催したシンポジウムの記録集である。京都では三枝昂之の講演、永田和宏の提言、中津昌子、澤村斉美、黒瀬珂瀾による鼎談があり一四〇人が参加した。東京では永田の講演と今野寿美のミニトーク、吉川、染野太朗、田村元、三原由紀子によるパネルディスカッションが行われ、三九〇人が参加したという。私は京都の、立ち見も出た当日の盛況を思い出す。永田は「歌人として時代に向き合うとはどういうことか」を問題提起し、機会詠においてレトリックが自己目的化することへの自制を説いた。 言葉にはたくらみがあり、詩歌においてもそれを振り切ることは難しい。一方、政治で何をどう伝えるかの技術は必須である。私は挨拶文へのこだわりと同じ意味で、IDF(イスラエル国防軍)のツイッターに見入ってしまう。そのメッセージは明快で、美しいとすら思われる。 |
||||||
| 2016年7月号 |
||||||
| どんな名前でも 吉野亜矢 |
||||||
| 三年前、誘ってくれる人があってとある歌会に出た。参加者は私も含めて十八人(詠草は二十一首)、大学生中心の比較的若い層で構成されており、見知った顔はいなかったと思う。なぜ誘われ、なぜ出かけて行ったのかは忘れてしまったが、京都の会場に着くと、セーラー服姿の女の子の隣に座ることになった。高校生? と誰かに聞くと、そうじゃないけど、あの子はあれでいいんだ、みたいな答えが返ってきた気がする。 土煙り不在の父へ会いに行く夏影冷えて黒い遮断機 後に歌集『キリンの子』(KADOKAWA、二〇一六年刊)にも収められた、鳥居のこの日の詠草である。メモでは一画少ない正の字が書いてある。ちなみに私の詠草はTの字が書いてあり、最高得点歌は九票だった。この歌は歌集収録時には少し手を入れられている。 土煙【煙=ルビ=けむ】り不在の父に会いにいく夏影冷えて黒い遮断機 漢字とひらがなの配分、助詞の選択、そして読み仮名に配慮がなされたことが分かる。 ゆっくりとうすく光を引き伸ばし銀のひかりで切るセロテープ 53 顔文字の趣味のよくない友だちが空の写真のメールを寄越す132 海越えて来るかがやきのひと粒の光源として春のみつばち 126 鳥居の歌集は発売早々評判を呼び、ネット書店では本体定価一六〇〇円を上回る価格がついていると聞く。私は頼みのジュンク堂書店三宮店で在庫切れだったため、近隣の住吉店にあった一冊を取り寄せてもらい読んだ。反響の要因の一つと言っていい彼女自身の過酷な出自は、歌集と同時に刊行されたノンフィクション、『セーラー服の歌人
鳥居 拾った新聞で字を覚えたホームレス少女の物語』(岩岡千景著、KADOKAWA・アスキー・メディアワークス刊)に詳しいはずだ。そうした体験を匂わせる歌を引くこともできる。 永遠に泣いている子がそこにいる「ドアにちゅうい」の指先腫らし 89 失ったふるさとなおも夢に出て夢の魚を買って帰らむ 109 君の死に火は似合わない紫陽花が咲くみずうみに浮かべる棺 119 賛否のある歌集とも聞くが、私はまだ署名入りの批判を見たことがない。この歌集が嫌いだと言う人は、彼女の歌を(短歌以外の立脚点から)称賛する人たちを好かないだけではないか、と思う。 学生にとっての制服は、人としての未熟さを表象するのと引き換えに、庇護の対象としてのサインを送る役割も担う。鳥居は「義務教育を受けられないまま大人になった人たちがいることを表現するために、成人した今もセーラー服を着て活動をしている」という。しかし学齢期を過ぎた女が身に着けるセーラー服は、商品化された性のパッケージとしてしか受け取られないこともある。三年前、恐ろしいほど率直な自己紹介とともにもらったリーフレットには、被写体である鳥居自身が函状のものに身を曲げて収まり、まっすぐこちらを見返している写真があった。オーバーサイズの白いシャツ、腿まで上がった黒いスカート、赤く塗った口元に寄せられた両手。この危なっかしさに無自覚なはずはない。 ほんとうの名前を持つゆえこの猫はどんな名で呼ばれても振り向く 142 鳥居は問いかけている。弱い自分に、世界は支配以外のものを与えるのか? と。 |
||||||
| 2016年6月号 | ||||||
| 受賞ラッシュを祝う 吉野亜矢 |
||||||
| 未来の歌人に立て続けにめでたいニュースがあった。大島史洋が歌集『ふくろう』(短歌研究社、二〇一五年三月)により第五〇回迢空賞、黒瀬珂瀾が『蓮喰ひ人の日記』(短歌研究社、二〇一五年八月)により第十四回前川佐美雄賞、小川佳世子が『ゆきふる』(ながらみ書房、二〇一五年一二月)により第二十四回ながらみ書房出版賞を受賞した。大島の『ふくろう』については四月号に新年会の報告が掲載されたところなので、ここでは他の二冊について触れたい。 黒瀬の『蓮喰ひ人の日記』は、二〇一一年二月から翌年三月にかけて、研究者である妻に伴い滞在したアイルランドとイギリスでの生活を題材にしている。その間東日本大震災と妻の出産という、一方は社会的歴史的な、一方は個人的な事件に遭遇するのだが、それらを縦横に織りなしつつ、また『ユリシーズ』を引用しつつ、異国での時間を歌物語のように紡いでゆく。「六の月」から始まる章立ては「十の月」まで満ちると再び「一の月」となり、「九の月」を最後に終わる。子の成長を全ての軸に据えながら、家族の私的な記録以上のものが掬い取られている。 胎の子よ聞こゆるか今スウィフトが赤子の調理法説きやまぬ 日本の震災の一週間後、身重の妻の目の前で三世紀前の文豪による皮肉な貧困解消策が朗読される。 海老チリと豚の甘酢の混じりあふタッパの底を歩み来たりぬ その三日後の歌は、詞書「3/21 Wok(盒飯)とはテイクアウェイの中華料理屋。中国移民は中国語で、韓国移民はハングルで笑ひかけてくる。」に違和感を覚えた。ハングルは文字を指すため、「中国語」に対置されると意味が若干ずれる。しかし私は、そんなことは承知であろう黒瀬の選択に結局は同意する。朝鮮半島で流通する言語を日本語で表現しようとすると、韓国語、朝鮮語、韓国・朝鮮語と、幾通りもの選択肢があり、そのいずれも万人を満足させることはない。NHKがハングル講座を名乗るのはこのジレンマを避けるためであり、私にそう指摘した人々は、同じジレンマを避けて在日コリアンと呼ばれたり、また名乗ったりする。そうした逡巡を経て掲出歌を振り返ると、現地語化した外来語やら普通名詞化した商標やらが入り交じった、猥雑で生命力のある味わいが立ち上がる。 小川の『ゆきふる』は二〇〇六年から二〇一五年までの十年間の作品約五百首を収める。 いくたびか外光に触れいくつもがどこかへ行った私の臓器 闘病という言葉はあとがきも含めて使われていないが、この間度重なる入院や手術を経験したようだ。治癒の目安となる五年目にがんが再発し、入院の支度をしていて、二〇一一年三月一一日を迎えたという。津波に家屋を流された土地と、空洞を抱えた闇が痛ましく重なる。人は様々な場所で、あの震災を受け止めた。 なにゆえにパジャマに柄はあるのかと思うようなる大いなる問い 新月の夜に願いを書いてみてひらがなのほうが叶う気がする 病と縁深い身体を授かったことについての嘆きや諦念だけでなく、どこかとぼけたユーモアもこの人の持ち味だ。欠詠したことがない、という言葉を思い出す。 今月から時評を担当することになった。歴代の執筆者が向き合ってきたであろう「時評とは何か」について、考える一年になるだろう。 |
||||||
| 2016年5月号 | ||||||
| 遠からず来るだろう 中島裕介 | ||||||
| 触ることのできる極小のプラズマを、妖精のように現実空間に投影し、動かす技術を開発した落合陽一。彼が二〇一五年末に刊行した書籍が『魔法の世紀』。「魔法」とは言い得て妙である。幻想でしかなかったモノが、現実に現れるとき、短歌において写生は、幻視はなお可能であるのか。少なくともこれまでと同じようにはできなくなるのではないか――と考えさせられる。 同様に、人工知能(AI)の技術も急激に発達している。短歌においてAIはどのような影響を及ぼしうるか。 アメリカのある音楽家・音楽学者がバッハの音楽を分析し、AIに学習させた。そして、AIがバッハ風に作曲した曲と、別の音楽学者がバッハ風に作曲した曲を聴衆に聴かせ、どちらがAIの曲かを当てさせるコンサートを開いた。結果、多くの聴衆が別の音楽学者の曲を「AIの作曲したものだ」と認識したという。これが一九八〇年代から九〇年代の話だ。最近、スペインの大学が開発したAIは一秒以下でクラシック(風の)音楽を一曲作るという。近年の日本でもAIに小説のあらすじやショートショート散文を作らせる研究は多数行われている。短歌におけるAI利用を、研究・実践している人は多くなさそうだが、AIに、たとえば斎藤茂吉の短歌を学習させ、茂吉風の新作を作らせることも、本腰で研究する人が現れれば難しくないだろう。 Googleが開発したAIが、「どういうものが猫であるか」のお手本を人間から教わることなく、インターネット上の画像や動画に映るどれが猫であるかを学習し、識別できるようになったのは二〇一二年。二〇一五年には複数の画像を組み合わせた「夢」を産み出すこともできるようになっている。AIが膨大なデータからモノのイメージを把握し、それを応用して新しいイメージを作り出せるならば、膨大な和歌・短歌から、たとえばアララギ的な要素を踏まえた新しい短歌の文体をAIが作り出せそうだ。 インターネット上の外国語の自動翻訳機能(これもAIだ)を使ったことがある方もおられるだろう。アメリカの新聞社では、スポーツや経済のような定型文が適用できる短い記事をすでにAIが書くケースもある。今後、プログラムさえできれば、和歌も短歌も、文語も口語も関係なく、AIが自動的に意味を字義通りに解釈してくれるようになるだろう。 二〇一六年一月末に政府が「AIによる創作物に著作権を認めるか」という検討作業に着手した。現時点ではAIによる創作物には著作権がない――つまり、AIが作った短歌を、誰かが個人の実名で発表しても特に問題はない。ならば、たとえばAIが自動生成した短歌に、「岡井隆」の名が付されたとき、あなたは本当にその歌を〈正しく〉読むことができるか。よい歌ならば「岡井隆ならどんな歌でもありうる」と褒めてしまわないか(それでもよいのだが)。 AIが短歌を作り、AIが読んで、AIが解釈する。それも大量に。そこに、岡井の『現代短歌入門』における有名なテーゼ |
||||||
| 短歌における〈私性〉というのは、作品の背後に一人の人の――そう、ただ一人だけの人の顔が見えるということです | ||||||
| というときの〈顔〉が入り込む余地はあるのか――いや、元々その〈顔〉は本当に作者の顔をしていたのか。短歌という営みはどのように存在・存続しうるのか。そういう思考実験をすべき時期に来ている、と私は認識している。 二年三ヶ月にわたり時評を担当させていただきありがとうございました。 |
||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2016年4月号 | ||||||
| ポストモダンという語 中島裕介 | ||||||
| 大辻隆弘がツイッター上で、山田航と森井マスミの評論に憤っている。 | ||||||
| この時代に「ポストモダン」を称揚することは文学表現の瓦解に手を貸すことになる。(中略)その事態を招来する覚悟があるのか? 服部さんの(角川「短歌」二〇一五年四月号掲載歌「水仙と盗聴、わたしが傾くとわたしを巡るわずかなる水」を巡る議論で提示された:筆者注)「読み」に対する姿勢を「ポストモダン」の側に回収し、私を「モダン」の権威主義の側に置く、という図式はたしかにわかりやすい。 |
||||||
| とした上で、大辻は山田・森井という「ポストモダン」側に立場表明を迫るものだ。なお、本稿では紙幅の都合で森井の「短歌往来」二〇一六年二月号の評論「言葉を共有すること ――ポストモダンと短歌」を扱わない。ご容赦いただきたい。 「短歌研究」二〇一五年十二月号に掲載された、山田航の「評論展望」は、永井祐の角川「短歌」二〇一五年八月号時評での「短歌の世界に流通している「人間」は「昭和の人間」であるように思う」と引き、近代的な固定観念にとらわれがちな歌壇の傾向を指摘する。大辻の同誌九月号時評の「短歌における抒情の問題は、煎じつめれば、短歌において時間をどう表現するかという問題に収斂する。(中略)口語短歌の作者は、みずからの抒情を確立する新たな時間表現の技法を開発する必要に迫られているはずだ」という指摘を対比させる。山田は、 |
||||||
| 「文語」にしても「時間」にしても、きわめて近代的な観念だ。そして近代とは前近代的なものを解放するというよりも、ある特定のものを隠蔽しようとするはたらきが強いものだった。 | ||||||
| と、近代的な固定観念にとらわれることの問題点を指摘する。山田が、大辻の評論を近代=モダンの問題にとらわれているもの、と位置づけているのは分かる。 さて、そもそも「ポストモダン」とはなにか。元々はフランスの哲学者リオタールが提唱した考え方であって、 |
||||||
| 分野によって用法は多義的であるが、近代全体を問題視し、しかも対抗する一元的な原理を展開しない(『岩波哲学・思想事典』、1998、岩波書店。本項は岩崎稔。) | ||||||
| と整理される。ポストモダン(的思考)は「近代全体」を問題視はするが、別にそれと対抗するものでもなければ、「現代(的思考)」を意味するものでもない。『リオタール 寓話集』の「訳者あとがき」で訳者・本間邦雄がうまくまとめている。 | ||||||
| また、リオタールの言う”ポスト・モダン”は(中略)近代に続く時代という、時代区分の意味ではない。(中略)キリスト教的救済や歴史の成就といった「大きな物語」が有効でなくなった現在において、そのような歴史性をベースに置く考え方を停止し、宙吊りにするなかで思考し感覚する情況がリオタールの言う“ポスト・モダン”である。その意味では、”ポスト・モダン”は”最近”を意味するのではなく、”近代”の思考と同様にむしろ普遍的、偏在的なのである。 | ||||||
| このリオタールの「ポストモダン」は、山田の、近代に対する問題意識と合致していると言っていい。ただ、山田が「『ポストモダン』を称揚」しているとまで言いうるかというと、そこまでは言い切れないように見える(森井の評論は確かに「称揚」しているように読めるが)。「ポストモダン」は「称揚」すべき類のものでもなく、歴史性とは別のしかたで、文学表現を築いていく態度のことだろう。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2016年3月号 | ||||||
| 同人誌のはなし 中島裕介 | ||||||
| 同人誌「率」第九号と「Tri」第二号がどちらも荻原裕幸特集を組んでおり、いずれも刺激的な内容となっている。二つの同人誌が同時期に荻原を選び取ったのも偶然ではない。「率」の巻頭言では藪内亮輔が | ||||||
| 私は、この歌人(荻原裕幸:筆者注)と作品は、抒情とその変化という面から再考すれば、現代からみたリアリティを発見できると考えている。 | ||||||
| と述べている。「Tri」の巻頭にある大井学の評論「荻原裕幸の「定型」――その問題意識」においても、冒頭に荻原が一九九二年に発表した文章を引用し、 | ||||||
| 二〇一四年の短歌研究新人賞を受賞した石井僚一の「父親のような雨に打たれて」という作品を巡る(虚構やリアリティに関する:筆者注)騒動について、予めの「回答」を語っていたようにも思われる文章ではなかろうか。(中略)二十年以上前に騒動発生の予言と回答を準備していた、とでも言えば面白いのだろう。けれど実際は、この二十年以上もの間、荻原が指摘していたリアリズムを巡る「主張」とモラルとの混同が解決されないままだつたということだろう。 | ||||||
| と荻原の問題意識が現在の短歌の情況、特にリアリティを巡る議論にも密接に繋がっていることを示しており、両者の着眼点には大いに頷ける。他に「率」では宝川踊が、「Tri」では濱松哲朗が、いずれも柄谷行人を援用しているのも興味深い。 | ||||||
| 同人誌即売会「コミックマーケット(コミケ)」といえば、マンガやアニメ、ゲームといった分野の同人誌が主だが、それ以外の分野の同人誌もある。二〇一五年末に開催されたコミケに出品された技術関係の同人誌「SunPro会誌 2016」では博多市(筆名)という方が「機械学習で石川啄木の未完の短歌を完成させる」という文章を公開している(筆者はウェブ上でのみ拝見した)。 この文章は、石川啄木の『悲しき玩具』の元となったノートにある「大跨に緣側を歩けば」 (二句目冒頭は「縁側」の「縁」の旧字体。)という〈未完の短歌〉に続く三句目以降をコンピュータに制作させる試みについて記されている。その制作過程は、①『一握の砂』と『悲しき玩具』にある歌・七四五首をコンピュータに分析させて、基盤となる語彙を整理し、②短歌定型に沿った三句目以降を自動的に一万首作らせ、③石川啄木の短歌らしくなる語の組み合わせを解析し、④自動的に作られた一万首のうち、最も啄木らしい歌を数値的に選ぶというもの。でき上がった歌は次のとおり。 |
||||||
| 大跨に緣側を歩けば、板軋む。 かへりけるかな―― 道廣くなりき。 |
||||||
| この試みを行った博多市自身、この歌の出来は良くないという感想を持っており、私も同感だ。しかし、こういった試み自体は面白く、基盤となる語彙がより豊かであれば、歌の出来も良くなるだろう。人が作った歌と遜色がない短歌をコンピュータが作るとき、虚構やリアリティを今と同じように議論できるだろうか? ところで、「率」第九号の瀬戸夏子「以後のきらめき」の補注で、短歌一首を自動生成させるプログラム犬猿短歌(佐々木あらら制作)や偶然短歌botを、瀬戸は荻原の短歌に対置させて次のようにいう。 |
||||||
| 良くも悪くも短歌というのは人間のものだ、いまのところは、ということになりそうである。(原文傍点に代えて下線) | ||||||
| 全く同感。あくまで「いまのところは」なのだ。人間にとっての短歌の位置はまだ変わり得る。だから面白い。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2016年2月号 | ||||||
| 今年の新人賞 中島裕介 | ||||||
| 今年の、総合誌における新人賞の結果が出揃いつつある。 第六十一回角川短歌賞は阪大短歌会の鈴木加成太「革靴とスニーカー」。 |
||||||
| やわらかく世界に踏み入れるためのスニーカーには夜風の匂い 鉛筆でごく簡潔に描く地図の星のしるしのところへ向かう 星屑を蹴散らしてゆく淋しさをひと晩で知り尽くす革靴 地平線焼き切るときの火の匂い 簡易珈琲のふくろをひらく |
||||||
| 就職活動で履く革靴と大学生としての生活で履くスニーカーが対比されている。「世界」「夜風」「星」「星屑」「地平線」など、肯定的なイメージを、就職活動を通じて触れた美質として見出している。この点は選考委員からも好評を得ている。引用一首目はやや像が結びにくい感もあるが、就職活動の時間帯ではなく、大学生としての生活世界として夜に外出する自身の様子を「スニーカーには夜風の匂い」と甘やかに表現している。最後の引用歌は、インスタントコーヒーの袋に入れる切れ目と地平線、地平線を焼き切る火(太陽)と焙煎の香りやその現れが鮮やかに描かれており、個人的に最も好みの歌である。 第五十八回短歌研究新人賞は遠野真「さなぎの議題」。 |
||||||
| 肉親の殴打に耐えた腕と手でテストに刻みつける正答 割れた窓そこから出入りするひかりさよならウィリアムズ博士たち 痣のないお腹を隠すキャミソール 罪を脱ぐのもまた罪であり おかあさん白線ちゃんとわたろうとしたよ白線わたろうとした |
||||||
| 作者は男性だが、思春期の女子学生に成り代わって詠われた連作。全体に虐待や自傷の気配がある。二首目の「ウィリアムズ博士」は昆虫の変態について研究した動物学者。さなぎのように内部で変わってゆく学生のことを、様々な仕方で見ている大人を「博士たち」と呼んでいるのだろう。 遠野の連作について田丸まひるがウェブサイト「詩客」の時評で |
||||||
| 虐待を思わせぶりにちらつかせるような歌は、むしろ生々しさを遠ざけていないか。敢えて言えばあざとく、作り物めいている。 | ||||||
| と否定的な見解を示し、十二月上旬までに遠野からの反論・田丸からの再反論が行われた。田丸の評言が詩的であるため、議論としてやや上滑りしている感があるが、田丸は、虐待というテーマを扱うには、遠野の作品の質が不十分なのではないかと疑義を呈したかったものと理解した。この疑問についてさらに議論されてよいだろう。 歌壇賞も飯田彩乃が受賞したとの報があり、遠野と共に未来会員が受賞することとなったことを一会員として喜ぶ。 |
||||||
| また、ここ五年から十年の間、主な新人賞で京大短歌会と早稲田大学短歌会の会員やそのOB・OGが活躍していたが、鈴木加成太の属する阪大短歌会や昨年の短歌研究新人賞受賞者である石井僚一の属する北海道大学短歌会のほか、今年の新人賞候補者の所属先を見ても、東大の本郷短歌会、九大、外大、奈良女など様々な名が見える。大学短歌会全体でのレベルが上がっているのだろう。確かに、東京と地方とで短歌に関する情報やイベントの、量や多様さに格差があることは否めない。その一方で、大学という磁場が、新しい才能が現れる土壌を東京以外の地域にも形成し、発展させる契機となれば嬉しい。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2016年1月号 | ||||||
| キュレーションとしての短歌批評 中島裕介 | ||||||
| 「塔」二〇一五年七月号の大森静佳の時評「『批評ニューウェーブ』への疑問」に、久真八志がツイッター上で疑義を呈している。 | ||||||
| 発端は中日新聞同年四月十一日付夕刊の山田航による時評「批評ニューウェーブ」である。(この時評でも過去に取り上げた)光森裕樹や田中濯らの、統計データや語彙分析を元にし、高い説得力を持った批評が現れてくる情況を山田は「批評ニューウェーブ」と評する。こういった批評が以下のような情況改善を産むという。 | ||||||
| まず印象批評を抑制し、ある程度客観的な議論をするためのインフラになる。次に、歌集出版や結社運営をビジネス化させるために、現状では何が足りないのかという分析ができる。 | ||||||
| また、山田はさらに次のようにもいう。 | ||||||
| 「短歌ニューウェーブ」は、短歌に限定された修辞論以外の引き出しが要求されている。歌論だけを読んで歌論を書くのは、もはや単なる不勉強にしかならない。 | ||||||
| このような山田の見解に、大森は一定の賛意を示した上で、 | ||||||
| 私たちが目指すべきなのは、本当に客観的な批評なのだろうか。(中略)歌をほとんど引用することなく、数字やデータから読み取れることを抽出・分析するという批評の後ろには誰がいるのだろうか。そういった言わば透明な批評ばかりでは案外つまらなくないだろうか。(原文傍点に代えて下線) | ||||||
| と疑問を呈する。 | ||||||
| 十月半ばになってから、久真がツイッター上で、この大森の時評に不快感を表明する。久真の反論は、〈計量分析をした程度で「客観的」だと考えること〉〈「数字やデータから読み取れることを抽出・分析するという批評」を「透明な批評」と評したこと〉だとまとめられるだろうか(三上春海がブログで大森への擁護とともに本件の経緯を整理している)。 | ||||||
| ところで、森田真生の『数学する身体』(新潮社)が十月に刊行された。森田は教育機関や研究機関に属さずに数学の研究や普及に努める、三十歳の気鋭の独立研究者である。同著は、数学者・岡潔に特に心を寄せて、〈数学と、身体や心〉の関係やあり様に迫ってゆく。岡潔は「情緒」という言葉を好んだというが、森田も | ||||||
| (略)数えることも測ることも、計算することも論証することも、すべては生身の身体にはない正確で、確実な知を求める欲求の産物である。(中略) 一方で、数学はただ単に身体と対立するものでもない。数学は身体の能力を補完し、延長する営みであり、それゆえ、身体のないところに数学はない。 |
||||||
| という。 | ||||||
| 大森の時評については、私も久真と概ね同様に考える。確実な知を求める数学にすら情緒があるのだ。計量分析でも短歌から情緒が失われはしないだろう。考える対象の決断も、情報を集めて分析した後の解釈もまた、人が行っている。それは、批評で扱う歌集や歌を選び解釈するのと、実は大差ないのではないか。 | ||||||
| 私が「未来」時評の最初に触れたように情報が氾濫する昨今、「情報のノイズの海の中から、特定のコンテキスト(ここでは「モノの見方・結びつけ方」:中島注)を付与することによって新たな情報を生み出す」(佐々木俊尚『キュレーションの時代』(ちくま新書))ような、〈キュレーションとしての短歌批評〉もまた、歌集を読み解く批評と共存してよいのではないだろうか。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年12月号 | ||||||
| 「水仙と盗聴」問題 中島裕介 | ||||||
| 水仙と盗聴、わたしが傾くとわたしを巡るわずかなる水 服部真里子 | ||||||
| 角川「短歌」四月号特集「次代を担う20代歌人の歌」に掲載された連作「塩と契約」の一首目である。この一首について小池光が「まったく手が出ない」と評したところから、この一首の解釈にとどまらない、短歌の読解に関する議論が巻き起こった。服部自身が「歌壇」六月号の時評で | ||||||
| ひとりの人間の言葉は、その人の身体がさらされてきた言葉の歴史である。そして、すべての人間は別の身体に住んでいる。よって私たち――作者と読者は、そもそも
|
||||||
| という、暴論とも言える発言を行ったことで議論は加速した。さらに服部は「歌壇」九月号の時評で、「歌壇」六月号での服部発言を受けた「短歌研究」八月号における内山晶太の時評の | ||||||
| 服部は、作品の言葉をいったん不完全なものとして捉え、それを作者読者間で共用し、短歌を共作していくステップを経ることではじめて他者の言葉を共有できると考えているのだろう。 | ||||||
| に対して「これが私の言いたかったことに近い」と表明している。 | ||||||
| 角川「短歌」十月号の歌壇時評「名詞萌えの放恣」で大辻隆弘は「内山の意見は至極まっとうなものである」と評価した上で、服部の「歌壇」六月号における「ひとりの人間の言葉は」以降を指して | ||||||
| 個人の言語体系は個人の身体に等しい。個人の身体が他者と共有できないように、言語体系も他者と共有できない。服部はそう言い切ったのである。(中略)自分の真意が内山の言うような穏当なものに過ぎないと言うのなら、服部は潔く前言を撤回すべきだろう。 | ||||||
| と指弾する。この大辻の、服部発言の解釈には私も同意する。 | ||||||
| さらに大辻は、「現代短歌新聞」八月号のインタビューにおける服部の「名詞萌えをするタイプですね。ぐっときた単語を、歌の中におけないかな、といじったりしながら作ることが多いです」という作歌姿勢を指して、 | ||||||
| 各人が異なったイメージを抱く抽象的な名詞を、「わからなさ」を残したまま、あえて歌の表現の中核に置く。そのことによって読者の間には、さまざまな多義的な読みが生まれてくる。(略) しかしながら、その構図は、服部の歌とその読者にのみ当てはまる構図にすぎない。(中略)「名詞萌え」から生み出された読みに対する放恣な姿勢。私はそれを認めることができない。 |
||||||
| と断ずる。「名詞萌え」か「助詞・助動詞萌え」か、と聞かれればおそらく「名詞萌え」型だろう私は、大辻の問題意識はわかるが、「放恣」とまで言われると違和感を覚える。 | ||||||
| 服部の「名詞萌え」発言を受けて、大辻とは反対に、名詞の可能性を見出しているのが、「塔」十月号の時評における大森静佳である。大森は斉藤斎藤が「歌壇」二〇一二年十月号に書いた「てにをはの読解が第一」を援用しながら、 | ||||||
| 動詞や助詞、助動詞が一首の力を縦方向に深めてゆくとすれば、名詞は横方向にイメージを乱反射させる。(中略)服部は、名詞の飛躍や二物衝撃の力によって、斉藤が指摘するような危うさ(斉藤の「読者の好みに引き寄せられた『迎えて読む読み』になりがちである」という傾向:筆者注)を超えようとしているのではないのか。 | ||||||
| と擁護する。心情的にはこちらに賭けたい。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年11月号 | ||||||
| 視覚と短歌のしあわせな関係 中島裕介 | ||||||
| 笹公人の第一歌集『念力家族』(初版は宝珍。文庫版は朝日新聞出版)を原案としたNHKのテレビドラマが今年四月から放映されている。一話が十分で構成され、九月に全十六話の最終回を迎える。歌集の映像化というと最近では小島なおの『乱反射』の映画化が思い起こされるところだろう。 ドラマ『念力家族』を観て私が最初に驚いたのは人物造形の工夫だ。例えば、文庫版は分からないが、宝珍版『念力家族』の同名の連作に登場する「弟」は、ドラマに影も形も登場しない。他方、ドラマのストーリーは歌集中の「妹」と、他の連作「生徒会長レイコ」に登場する「レイコ」とを翻案したキャラクタを軸に展開する。例えば、歌集では |
||||||
| 憧れの山田先輩念写して微笑む春の妹無垢なり | ||||||
| となっている歌が、ドラマ第二話のタイトルでは「憧れの山田先輩念写して微笑む春の玲子無垢なり」となり、元々別人として構成されていた人物をまとめる形になっている。ドラマ自体を見やすく、楽しみやすくするためだろう。 テレビの映像ではないが、イラストレータが、自身の好きな短歌をイラスト化した本も最近刊行された。安福望『食器と食パンとペン 私の好きな短歌』(キノブックス)である。「未来」の会員の歌も多数イラスト化されている。この本を開くと、イラスト自体の視覚的な魅力はもちろん、歌に描かれた情景に対する安福の解釈、そこからさらに押し広げたイメージを描いている点に魅かれる。例えば、山階基の |
||||||
| 買った時から傷のあるこの服をようやくすこし許しはじめる | ||||||
| に対する安福のイラストは、水色の服の背の、傷があった部分から樹の枝が生え、青い鳥の巣を支えている。傷のあった服に対する自己の許しが、なかなか見つからない幸せ(として青い鳥)を支えるという象徴的な描写はなかなか感動的だ。 他方、映画から影響を受けた短歌について考察している論考もある。「玲瓏」の五十嵐淳雄が「塚本邦雄の映画手帳」と題された不定期連載を「短歌研究」二〇一三年十一月号から行っており、二〇一五年八月号で十回を数える。この連載は、塚本邦雄が自身の鑑賞した映画についてメモを残した、一冊の手帳に、五十嵐が多角的に分析を加えたものである。この映画手帳に残されたメモは、一九五八年から一九八八年までの三十年にもわたるもので、映画を観た日や題名などが、コメントもなく列挙され、ページによっては映画のスチル写真が貼り付けられているという。その手帳に挙げられた映画作品はもちろん、五十嵐は、その原作小説や日本語版の訳注、塚本の映画に関する著作など様々な資料を比較・検討している。その上で、塚本の歌の着想過程を丁寧に追い、時にその解釈について大胆な提案をしている。例えば、 |
||||||
| カフカ忌の無人郵便局灼けて賴信紙のうすみどりの格子 『綠色研究』 | ||||||
| という歌について、オーソン・ウェルズ監督、カフカ原作の映画「審判」と、塚本の著作を照合し、無人郵便局のような不条理な世界のなかで「定型のパラダイムを突き破ろうとする意志を持った」塚本自身の姿を五十嵐は見て取る。このような五十嵐の仕事はとても興味深く今後の連載も楽しみである。 映像やイラストのような視覚に訴える表現と、短歌を含む文字表現が互いに影響を与え合う。短歌にとってよりよい関係が、さらに育まれると私も嬉しい。 |
||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年10月号 | ||||||
| 戦争と、もう一度虚構のはなし 中島裕介 | ||||||
| 例年のことではあるが、夏には総合誌でも戦争や戦後の短歌に関する特集が組まれる。今年は戦後七十年であり、政局の動きもあってか、「歌壇」六月号、同八月号、「うた新聞」八月号はなど、いずれの特集も力が入っている。「短歌研究」八月号は特集「戦後七十年をふりかえる」とともに、終戦後最初に刊行された、日本短歌社時代の同誌昭和二十年九月号を巻末に収録している。 角川「短歌」八月号は特別企画「戦争の肉声」として岩田正に永井祐が戦争体験をインタビューしている。ここで岩田は戦争における〈嘘〉について繰り返し話す。 |
||||||
| 僕の隊が守っていた倉庫があったのですが、戦争中は武器を守っていると思って寝ずに毎晩見張っていたのですが、敗戦になって開けてみたら、中には食べ物がいっぱい入っていたんです。嘘で塗り固められているんだよね。 | ||||||
| ここで〈嘘〉の話を緩やかに受けて、〈虚構〉へと話題を変える。なお、〈虚構〉に関わるものが、戦争に即関係するものではないことを予め申し添えたい。 「北冬」第一六号は井辻朱美責任編集であり、「[井辻朱美]について考える」と「[現在の短歌]について考える」の二つの特集が並ぶ。いずれの原稿も充実した特集であるが、ここでは黒瀬珂瀾「[現在の短歌]における虚構」を取り上げる。黒瀬は、松宮静雄が〈SF短歌〉の名を初めて冠して一九八〇年に刊行した歌集『SF短歌 ウルの墓』を挙げて、 |
||||||
| 小説内で(文明や人間に対する:筆者注)批判をストレートに記してしまうことは作品世界の虚構性の低下を招く。それ(批判)ができるのは(中略)小説的な構造を持つ韻文、つまり叙事詩である。 | ||||||
| と、短歌(連作)の叙事詩的機能を示す。他方、SFのような〈虚構〉の世界を短歌で作り上げる際、小説のように、読者の知識を補うような描写ができない。そのため、作品を通じて形成しうる〈虚構〉の世界は読者の知識に依存し、「現実生活に直結する感情を紡ぐことになる」。この点を黒瀬は | ||||||
| それが現代短歌の虚構であり、虚構の困難さから生じる短歌的叙事詩の「現実性」こそが、矛盾するようだが、短歌の虚構の可能性を広げるのではないか。 | ||||||
| と示唆する。 | ||||||
| 角川「短歌」八月号の大辻隆弘の時評は、黒瀬の論とも通底するところがある。大辻は「本郷短歌」第四号に掲載された安田百合絵の評論「『短歌契約』試論」を取り上げているのだが、安田の評論はフランス文学における〈自伝契約〉という概念を足がかりにしている。つまり、〈自伝〉の書き手と読み手の間には、その自伝の「作者と語り手と主人公は全て同一である」というお約束ともいうべき〈契約〉が前提とされているという。安田はさらに短歌の作者と読者の間にも〈短歌契約〉というべき「生身の作者と私像と作中主体は全て同一である」というお約束が暗黙裡に結ばれているとし、現代フランス文学において〈自伝契約〉が無効になったのと同様に、〈短歌契約〉も無効になりつつある一方、〈新たな短歌契約〉が可能かどうか問題提起をする。安田の論をうけて大辻は「現代短歌は、近代以後への過渡期にあるのだろう」という。 先に上げた黒瀬の評論で「作者が現実を違えた作品の『虚構性』を生み出すのはモラル観という読者側の感情だ」と黒瀬はいう。だとすると、〈新しい短歌契約〉が「虚構性」を容れるものならば、読者自身のモラル観自体も新しくなることが〈新しい短歌契約〉を結ぶ前提になるだろう。 |
||||||
| 2015年9月号 | ||||||
| 新装版『uta0001.txt』など 中島裕介 | ||||||
| 二〇一五年五月一日、中澤系の歌集『uta0001.txt』が双風舎より復刊された。 中澤系は一九九七年に未来短歌会に入会、難病に冒され、二〇〇四年に歌集『uta 0001.txt』がさいかち真氏らの尽力により雁書館から刊行された後、二〇〇九年に没している。二〇〇四年の雁書館版の『uta 0001.txt』は増刷分を含めて八〇〇冊が流通したようだが、二〇〇八年に雁書館が廃業している。 代表歌といえば、この巻頭歌だろう。 |
||||||
| 3番線快速電車が通過します理解できない人は下がって | ||||||
| この歌集の復刊に関する詳細はウェブ上のtankafulの、本多真弓氏の手による「歌集復刊~中澤系プロジェクト~」と題された一連の記事に詳しいが、二〇一二年から批評会を開催したり、中澤氏の家族や出版社に連絡を取ったり、さらには刊行直前に中澤系当人による〈本人版〉とも言うべき歌集のゲラを発見し反映するなど、長期に渡り作業を行われたようだ。まずは本多氏やご令妹の書道家・中澤瓈光(りこう)氏をはじめ、復刊に尽力された方々を讃えたい。 六月六日には紀伊國屋書店新宿本店のイベントスペースにて「歌人・中澤系が生きた時代、そして今」が開催され、穂村弘と、新装版『uta0001.txt』に特別寄稿をしている社会学者・宮台真司のトークが行われた。 このイベントで穂村は、雁書館版の栞(新装版にも収録されている)で |
||||||
| 中澤系の言葉は、巨大な生き物のような世界のシステムを高感度に捉え、その無数の触手に絡まれ撫でられながら真っ白になってゆく人間の姿を描き出すことに成功している。 | ||||||
| と述べたのと同様の解釈を示しつつ、斉藤斎藤や永井祐といった歌人に先行する者としても位置付けられることを示した。宮台はバブル期からその後を共有する同時代人として、自身のうつ病体験などから中澤系の短歌への共感と理解を表明した。 | ||||||
| ところで、演劇の分野では田村公人『都市の舞台俳優たち ―アーバニズムの下位文化理論の検証に向かって―』(ハーベスト社)という本が話題になっている。 副題になっている「アーバニズムの下位文化理論」とは、東京のような大都市圏では、その人口の多さゆえに多様なネットワークが形成され、社会常識のような一般的・支配的な通念とは異なる通念・考え方・価値観が生まれてくる、とする理論である。この説の実例を求めて、『都市の舞台俳優たち』の著者は東京の小劇場劇団に十二年以上関わり、高額のチケットノルマ――公演にかかる費用を確保するため、俳優やスタッフが売りさばかなければならない一定数のチケットのこと。売れなかったチケットの代金は俳優たち自身が自己負担しなければならない――やその売り方、そして金銭的・家庭的など様々な事情により演劇を離れてゆく人々を観察・調査したのである。 この著書で述べられているのは小劇場演劇の世界であるが、〈下位文化〉という点では短歌も含め、「商売にならない」文化全般と通底する。大都市圏とそうでない地域とでは短歌に関する状況は異なるだろうし、チケットノルマのように、歌人も様々な経費を自己負担している。歌人にも同書を面白くご覧いただけるだろう。 新装版『uta0001.txt』の再刊にあたっては一千部を刷り、歌壇への謹呈――いわば、歌壇におけるチケットノルマの自己負担――を行わずに初版の大部分が売れ、さらには二〇一五年七月に重版が行われるという。同書のさらなる展開が楽しみである。 |
||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年8月号 | ||||||
| 連作について 中島裕介 | ||||||
| 角川「短歌」五月号の特集は「連作を極める」。「第六一回角川短歌賞〆切直前」と副題がついているのだから〈連作の構成が角川短歌賞への近道である〉と賞側から投げかけられているかのようである。そして、〈構成が賞への近道〉であるのは恐らく事実だろう、と新人賞に縁のない身としても想像できる。 特集の執筆者は大松達知、今井恵子、大辻隆弘、梅内美華子、光森裕樹、山田航、大森静佳、伊波真人の八名。近年の角川短歌賞受賞者である後四者は「受賞者が明かす『工夫』したこと」とまとめられており、原稿依頼の段階で新人賞受賞時の〈工夫〉について書くよう指定があったのだろう。中でも山田の〈工夫〉はかなり具体的で、大辻や今井の論じる「連作の構成法」が作者の立場から、露悪的なほどあけすけに、しかし分析的に書かれている。例えば「冒頭一首目、二首目とラスト一首目、二首目。この四首には自信作を入れておいてください」「序盤十首と終盤五首に統一されたムードがあれば、それだけで全体の空気感も十分に支配されます」。さらに新人賞応募作については「新人賞は『伸びしろ』を重視しますので、わざと完成度低めの歌を一割くらい入れることも戦術の一つです」という。――連作全体の空気感を壊さない〈完成度低めの歌〉を意識的に配置できる技量がある人は、さっさと新人賞を獲って勝ち抜けて欲しい……と考えるのは野暮なのだろう。 同誌が扱ったものが読者にとってプラグマティックに「短歌連作をうまく作る方法」について語っている一方、連作と短歌の関係を本質的に探ろうとする評論もある。例えば同人誌「率」第七号の特集「〈前衛短歌〉再考」に瀬戸夏子が寄せた巻頭言は興味深い。 |
||||||
| 短歌を短歌たらしめたもの。 それは連作という手法だ。 うたの語彙の共同体がうしなわれ、一首を屹立させることはむずかしくなった。そこで、連作が生まれた。連作ならばプロフィール紹介ができる。地の歌がうまれた。確定された〈わたくし〉から発せられる声を信じることによって、自分以外の他の〈自我〉、そしてその歌を理解することができるという幻想。私は連作形式そのものを全否定しているわけではない。けれど、(中略)連作自体が語りつがれているケースはほとんどない。 |
||||||
| 連作という形式によって、作者とは異なる〈作中主体〉のキャラクタ要素が構成される、その要素により読者は歌それ自体ではなく、背後にいる〈作者〉を理解できると思い込む。この見解に私は同意する。 北海道大学短歌会の会誌「北大短歌」第三号で三上春海が「〈現代短歌〉とは何だったのか」という意欲的な評論を発表している。この評論の中で三上は、穂村弘の『短歌の友人』所収「モードの多様化」にある |
||||||
| 斎藤茂吉の作品を頂点とする、このような近代短歌的なモード(写実的な方向性:筆者注)を支えてきたものは「生の一回性」の原理だと思う。 | ||||||
| という一節に注目し、この〈生の一回性〉の原理を下支えするものとして、〈連作〉〈歌集〉〈歌壇〉の存在があるという。 三上は、〈連作〉についての分析の過程で派生したであろう論考を自身のブログに記し、その後の光森裕樹の指摘と共に公開している。こちらも〈連作〉と〈自我〉、〈生の一回性〉を考える上で興味深いものとなっている。 |
||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年7月号 | ||||||
| 「次代を担う」 中島裕介 | ||||||
| ある総合誌の編集者の方から酒席で聞いたことなので詳細は不正確だが、その総合誌の購読者層の八割以上が六十歳以上なのだそうだ(会員諸氏の想像通りだろうか)。そして、その多くは歌壇や文学全体への関心が高くない。そのためだろう、若手に焦点を当てた特集を組むと売上がガクンと落ち込むのだという。 「短歌研究」は毎年十一月号に「新進気鋭の歌人たち」という特集を組んでいるが、他の総合誌が立て続けに若手特集を組んでいる。先の〈売上〉の話を考えると、近年の学生短歌会の活況を考慮してもなお特異な事態だろう。結論めいたことを先に言えば、若手を取り上げることはそれだけでも喜ばしい。若手歌人が短歌の歴史的文脈にどのように接続し得、どのような新しい豊かさをもたらすのか――これが継続的に問われなければ短歌全体がより豊かになることはない。 二〇一五年十一月号の「短歌研究」の特集で取り上げられたのは一九六一年生まれの木下こうから一九九二年生まれの寺井龍哉までの十二名。短歌研究新人賞の受賞者である石井僚一をはじめ、同賞の候補に挙がった者を中心に、木下や楠誓英ら、話題の第一歌集を刊行した者が加わる構成となっている。 「短歌往来」は二〇一五年一月号に「次代を担う歌人のうた ――自選三〇首」をまとめている。一九六八年生まれの千葉聡から一九八九年生まれの大森静佳までの二十二名が自選三〇首とエッセイを掲載している。短歌研究新人賞を一九九八年に受けた千葉や二〇〇六年に現代歌人協会賞を受けた松木秀、「未来」選者の黒瀬珂瀾を含む。ここ十五~二十年に台頭し、評価が安定して高い歌人が含まれており、幅が広すぎる気もするが、「短歌往来」は毎号「今月の新人」に一ページを割いており、そちらとの差別化を図ったと見ることもできよう。 角川「短歌」は四月号に「次代を担う二〇代歌人の歌」。こちらは刊行時点で二十代の、角川短歌賞以外の賞を含む新人賞受賞者十名が登場。新作七首を発表するとともに、この七首に対して佐佐木幸綱・馬場あき子・花山多佳子・小池光・岡井隆が二名ずつ評を加えている。この評が――おそらく編集部からの要請だろうが、一部なりとも批判を含んでいる(当然のことながら、〈批判〉は悪いことではない。問題だと思われる部分を指摘する/されることに、〈次代への可能性〉がある)。 「歌壇」五月号は「次代を担う注目の新人たち」。年齢が記載されていないがおそらく二十代から四十代の、二十三名が寄稿。二〇一四年の歌壇賞受賞者である佐伯紺や、第一歌集を既に刊行している木下龍也や瀬戸夏子、二〇一五年の歌壇賞候補者など、結社や同人誌が重ならないように配慮されている(その点、二〇一五年の歌壇賞受賞者である小谷奈央が寄稿していないのはやや不思議である)。結果的に、今回取り上げた四誌の中では最もフレッシュな層を汲み出そうとする意図が見受けられた。その積極性を評価したい。 |
||||||
| (ユ/カ)レテイル(セ/シャ)カイ(サ/ボ)クラガ(フリ/シニ)オエテかみさまのてはじゃぐちをひねる 木下龍也 | ||||||
| 喪失をおそれるな 〈!〉 って標識が左後ろへ流れていった |
鈴木ちはね | |||||
| ところで、「短歌研究」以外三誌の特集の題名を見ると共通して「次代を担う」というフレーズが含まれる。「次代」はどんな「今」の次なのだろう? | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年6月号 | ||||||
| 「よむ」ことと「論ずる」こと 中島裕介 | ||||||
| 松澤俊二による『「よむ」ことの近代 和歌・短歌の政治学』(青弓社)が二〇一四年末に刊行された。この本は、序章の節題に「「近代短歌」研究から和歌・短歌の「近代」研究へ」と記されているように〈近代短歌〉という観念に縛られてはいない。近代以前の和歌と短歌の連続性や、「非専門的」な歌人や読者への考察、そして作者の〈詠む〉意図だけでなく読者の〈読み〉についても豊かな考察を加えている。これにより同書は、作者の意図を追求するような文学研究に留まらず、「近代」研究に踏み込んでいる。 第一章から第三章までは天皇制と和歌・短歌の関わりから日本の近代を彫琢しており、特に面白い。第三章・天皇の「御製」歌について扱っている箇所から引く。 |
||||||
| 「御製」は明治の初年代からアジア・太平洋戦争期に至るまで、天皇と国家のイデオロギーを広宣する装置であり続けた。しかしそれが表象した内容は一律ではない(略)とりわけて日露戦争期以降は、「国民」としてのありうべき範型が「御製」によって示されるようになった。(略) ともあれ、公に広められた「御製」が他者を動かし、他者にはたらきかける志向性を持ち続けたという点は揺るがない。その意味で、「御製」はまぎれもなく「政治」そのものだった。 |
||||||
| 松澤は、学生時代には國学院大学短歌研究会や「PUNCH-MAN」に所属、現在も同人誌「pool」に所属している。「pool」の初期には松澤の短歌が掲載されており、その〈詠む〉体験と〈読まれる〉体験がその後の研究や「pool」等での評論につながっているのだろう。「pool」八号には『「よむ」ことの近代』の序章にあたる評論が掲載されているので、気になる方はこちらを先にご覧になるのも一手だろう。 歌書ではないが、松澤の本と同時期に刊行された大澤聡『批評メディア論』(岩波書店)も非常に興味深い。松澤が「詠むこと」と「読むこと」の両面から近代に対する問いを立てた。これに対比させれば大澤は、一九二〇~三〇年代における「論ずること」と「論が知られること」(メディア)との両面から、戦前期の論壇・文壇が形成される過程と、〈専門的な〉論者・読者と〈非専門的な〉論者・読者――〈大衆〉の分化が明確化したことを示している。同書の先に見据えられている問題の核は、ここで論じられている戦前期から連綿と続く、現在の批評や論壇、文壇の情況にある――そして、大澤の視野には入っていないだろうが、結果的に現在の歌壇にも該当するものだろう。 新聞や雑誌といったメディアの発達により、処理しきれないほどの大量の小説作品や評論が発表されるようになり、それらを〈教養〉として吸収/消費することが求められた大衆のために、小説や評論を要領よくまとめた時評や座談会が求められる。その中で評価と知名度を得た評論家をスターとして祭り上げ、様々な媒体はスター評論家を繰り返し招くようになる。 |
||||||
| 限定された固有名群(有名な評論家たちの名:筆者注)が誌面を占有する。とすれば、言論界の「論調」の膠着化は不可避だ。書き手たちが各個の役割期待に応じた結果でもある。(略)この(言語化されない、それぞれの雑誌の:筆者注)傾向性において、「論壇」という擬制的な共同体(=「お座敷」)は構築されていった。そして、暗黙のリストに登録されることがいわゆる「論壇人」の必須要件となる。 | ||||||
| 大澤は更に、当時のメディアが新人発掘や議論の活性化を図った方法を論じている。詳細は同書をご覧いただきたい。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年5月号 | ||||||
| TPPと文学のはなし 中島裕介 | ||||||
| 角川「短歌」二月号の時評に田中濯が「短歌をお金持ちの玩具にしないためにいまできること」を寄せている。著書『二十一世紀の資本』で所得格差が拡大する歴史とメカニズムを指摘したフランスの経済学者トマ・ピケティを枕に、光森裕樹が作成した一九七九年から二〇一四年までに刊行された歌集のグラフを参照し、歌集出版社に対しては「歌集出版費用を(中略)できるだけ安くして欲しい」と訴える。その一方で、短歌の読者に対しては歌集出版費用が安価で抑えられる電子書籍について次のように述べる。 | ||||||
| 世代によっては電書(「電子書籍」の略:中島注)が根本的に拒否感や嫌悪感を招く存在であることは承知している。だがそれでも、皆さんどうぞ電書をご理解いただきたいと私は頭を下げたい。もちろん、歌集は紙で出したほうがよいものだ。(中略)しかしそれは今後、ますます困難になっていくだろう。既にいくつかの電書歌集が出版されているが、ほぼスルーされていまに至っている。 | ||||||
| 田中は先日第二歌集『氷』(角川学芸出版)を刊行したが、その経験を経ての訴えである。私は田中のこの姿勢に同調する。 ところで、二〇一四年二月に入って、環太平洋戦略的経済連携協定――いわゆるTPPに含まれる内容のうち、著作権について保護期間の二十年延長と非親告罪化で大筋合意に至ったというニュースが流れた。 著作権の保護延長問題が表面化した二〇〇六~七年頃の議論を受けて刊行された『著作権保護期間 延長は文化を振興するか?』(田中辰雄・林紘一郎編著、勁草書房、二〇〇八年)、特に丹治吉順「本の滅び方:保護期間中に書籍が消えてゆく過程と仕組み」と田中辰雄「本のライフサイクルを考える」の二論文は示唆に富んでいる。これらの論文は、執筆された時点で死後五十年が経過していない、つまり著作権が有効な一九五七年から六六年に亡くなった一七一〇人の著作の出版状況を検証している。丹治の論文によると、一七一〇人のうち約一三〇〇人は没後に一冊も本が刊行されない。一冊だけ刊行されるのも約三〇〇人。残り一〇〇人ほどの人々の著作ですらなかなか手に入らない。没後も一〇〇点以上の本が刊行されるのはたった四人。文化的・資料的価値が高くとも、五十年のうちにほとんどの著作者や著作物は人の目に触れる機会を得られない。著作権が死後七十年に延長されれば、パブリックドメイン化する(知的財産権がなくなる)頃には、今以上に膨大な数の著作者・著作物が存在すら忘れ去られていることだろう。 芥川龍之介が一九一九年に発表した「後世」という文章から一部を引用しよう。 |
||||||
| 時々私は廿年の後、或は五十年の後、或は更に百年の後、私の存在さへ知らない時代が来ると云ふ事を想像する。(中略) しかし誰かゞ偶然私の作品集を見つけ出して、その中の短い一篇を、或は其一篇の中の何行かを読むと云ふ事がないであらうか。更に虫の好い望みを云へば、その一篇なり何行かなりが、私の知らない未来の読者に、多少にもせよ美しい夢を見せるといふ事がないであらうか。 |
||||||
| あの芥川ですら、自作が後世の人に影響を及ぼすことを気弱に願ったのだ。凡百の我々が作るただの一首でも後世に残るには――残る可能性を少しでも高めるには、田中が訴えたように、出版コストが低い電子書籍版の歌集を受け入れるのも一案だ。その方が、作者としても読者としても、歌人・歌壇にとって長期的に有益なはずだ。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年4月号 | ||||||
| 結社の外部は何の内部か 中島裕介 | ||||||
| 角川短歌賞受賞者の光森裕樹が運営するサイトtankafulが面白い。このサイトは光森が編集を担い、当人以外からの寄稿も募っているようであるが、今回は光森自身の記事に注目したい。 昨年十二月に「短歌結社の5年を数える」、今年一月に「短歌に関わるなかで不便に感じていること:アンケート結果より」という記事を光森が寄せている。前者は二〇〇九年から二〇一四年の角川『短歌年鑑』に掲載されている結社の数が約十五%減ったというデータを提示し、後者はtankaful自体の運営についてアンケートを取った結果を開示しているものだ。特に後者のうち、「日頃、短歌に関わるなかで不便に感じていることや気になっているテーマ」という設問があり、その回答をここで幾つか紹介しておきたい。「主に物理的、経済的要因からイベントに参加しづらい」「歌集が入手しづらい」などの回答があったほか、結社については「結社誌などにおいて、分かち書きや横書き、あるいは平仮名を多用した長い歌などを提出しづらい」「結社の由来、歴史、結社誌面の構成など、口伝えにしか分からないことが多すぎる。全部wikiのような形式でまとめて欲しい」「数ページでも良いので、結社誌の見本がネットで確認できると良い」といった意見があったようだ。「未来」の(特に若い)会員であれば、入会前に同じ悩みを持ったこともあろう。結社が減りつつある中でなお生き残るには、結社の外にいる人の意見・要望を取り入れる必要が出てくる。 角川「短歌」二月号の特集「入門書では教えない 私のウラ作歌法」で林和清が「玲瓏」入会時に塚本邦雄から受けたアドバイスを披露している。 |
||||||
| (「結社誌などをあまり読まない」と林が答えたことに対して)「その方がいい。短歌を本気でやってみたいのなら、できるだけ短歌から遠ざかるのがいい。短歌から遠い分野、音楽や美術映画、フランス語など、それを一生懸命やりなさい。」 | ||||||
| もちろん、短歌・和歌にも極めて詳しい塚本の発言だ。どんな人でも鵜呑みにしてよいアドバイスではないだろう。とはいえ、「短歌のために、短歌以外の分野のことを懸命に学ぶ」というのは結社だけではなく、個々の短歌作者にとっても必要な要素なのではないか。 他分野と繋がった短歌をこれまでも紹介してきたが、また別の一例を紹介したい。昨年末のことだが、Twitterに「偶然短歌bot」なるものが登場した。「bot(ボット)」とは「ロボット」を語源に持つ、人に代わって自動的に決められた行動を繰り返すプログラムのこと。偶然短歌botは、誰もが編集可能なインターネット百科事典であるWikipedia日本語版のうち、たまたま五七五七七になっている箇所を抜き出して自動的に発表するbotである。 |
||||||
|
ある道を右に曲がれば東大で、まっすぐ行けば公園なのね 省くため、壁に向かって棍棒を投げては拾い、拾っては投げ |
||||||
| 前者はボディビルダー・タレントのマッスル北村氏の、後者はPCゲーム「ダンジョン・マスター」のWikipediaの記事から生成された〈偶然短歌〉だ。 今年一月に入り、ハフィントン・ポストやWEDGEといった知名度の高いニュースサイトでも取り上げられ、偶然短歌botには今や三万人以上のフォロワ(Twitter上のファン)が付いている。こういう機会からでも短歌に触れる人が増えると嬉しい。 |
||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年3月号 | ||||||
| 「中東短歌」と『書き出し小説』と私 中島裕介 | ||||||
| 二〇一三年四月の第一回文学フリマ大阪から刊行が開始された「中東短歌」が、予定通り第三号をもって終刊となった。三号とも充実した内容で、第三号に掲載された中では三井修と千種創一の評論と、齋藤芳生と短編小説作家イブラーヒーム・サムーイールとの対談が特に興味深い。 千種の評論「短い歌と短い小説についての短い仮説」によると、アラブ世界では、聖書やクルアーン(コーラン。イスラム教の聖典)、千夜一夜物語などの素地に加えて、欧州のメディアや知識が流入したことで、短編小説が長編小説と並ぶ一分野として確立されるに至っている、という。千種はアラブ圏の短編小説の傾向を整理した上で、短歌との共通項として①短さ、②言語濃縮、③写実主義的(リアリズム)傾向、④見せ掛けの簡易性、⑤テーマの単一性、⑥メディアとの結びつきを挙げ、アラブ世界の短編小説と日本の短歌のいずれもが近代化の中で似た位置を占めているのではないか、という仮説を提示する。 齋藤とイブラーヒーム・サムーイールとの対談「シリアとの距離を埋めるもの」は、千種の仮説と響きあうかのように、アラブ圏における短編小説と日本における短歌の共通項を模索している。齋藤の住む福島の震災・原発被害とサムーイールが国を逃れざるを得なかったシリアの戦乱、インターネットの文学への影響などが語られた後、サムーイールは短歌における一人称的傾向について質問し、以下のように続ける。 |
||||||
| サム(筆者注:サムーイール) とお訊きしたのも、私も一人称で小説を書くからです。一人称には、読み手をより書き手に近づける役割があると思います。小説で「私」というとき、私だけを指すのではありません。「集団としての私」なのです。 | ||||||
| ところで、最近、天久聖一『書き出し小説』がベストセラーになっている(Amazonのランキングによると、二〇一四年十二月十八日の刊行後、文庫や写真集なども含めた本全体の売上で最高一八六位(十二月二十日)。日本文学に限定すると、私が視認した限りで発売後二週間は一位に座しているようだ)。「書き出し小説」は読者投稿を扱った著作でも知られるマンガ家の天久聖一が考案した、「文字通り書き出しのみによって成立したもっともミニマルな文学形式」であるという。同書はウェブサイト(二〇一四年末時点での最新記事はhttp://portal.nifty.com/kiji/141227165959_1.htm)を通じて投稿された三万作から四二一の「書き出し小説」を選び出したもので、作家の長嶋有も別名で投稿したことがあるそうだ(http://joshi-spa.jp/23658)。 | ||||||
| メールではじまった恋は最高裁で幕をとじた。 | Yves Saint Lauにゃん | |||||
| 大きくひしゃげた眼鏡を、だが男はいつものように中指で持ち上げた。 | 凡コバ夫 | |||||
| この雨は、めぐりめぐっていつか私の涙を構成する。 | おかめちゃん | |||||
| 歌評のように、これらの「書き出し小説」の魅力を引き出しながら読もうとするならば、みなさんはどう読解するだろう。作中で状況を認識している主体を敢えて「作者そのもの」と捉えるのではなく、このあとに登場するであろうキャラクターや小説らしい三人称文体、あるいはこれらのサムーイールが述べた「集団としての私」だと捉えるのではないだろうか。もし読解する際の姿勢の違いが異なるならば、その原因は短歌や小説といった形式に起因するのか否か。この点は今後も議論したい。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年2月号 | ||||||
| うごく短歌、再び 中島裕介 | ||||||
| 二〇一四年夏の未来短歌会の、夏の大会一日目で実施されたシンポジウム「この十年の『未来』と短歌会」の採録が十二月号に早速掲載されている。中沢直人による「未来」年表と、十二月号におけるまとめは、未来短歌会と歌壇全体の動きを思い返す上で優れた仕事である。 他方、このシンポジウムをご覧になった方は後半の、主に斉藤斎藤と大辻隆弘の間で交わされた口語と文語、そして〈私性〉に関する議論も刺激的に記憶しているのではなかろうか。採録でも両名が言及しているが、シンポジウム後もTwitter――インターネット上のミニブログサービス――を通じて、斉藤と大辻はより議論を深め、総合誌等でも関連する評論を発表している。 主に比較対象とされているのは斎藤茂吉と永井祐である。まずは両名の評論で多く引かれている歌を挙げておく。 |
||||||
| わたつみの方を思ひて居たりしが暮れたる途に佇みにけり 斎藤茂吉 白壁にたばこの灰で字を書こう思いつかないこすりつけよう 永井祐 |
||||||
| まず、(永井のこの歌についてではないが)「短歌人」九月号における斉藤斎藤が時評「口語短歌の「た」について」で | ||||||
| つまり永井をふくむ口語短歌の話者は、特定の時点に固定されておらず、時間軸を移動しながら発話している。 | ||||||
| と分析している。「短歌往来」十一月号には大辻隆弘が「浮遊する「今」」を寄せ、「短歌研究」十一月号の特集「短歌の〈わたくし〉を考える」では大辻が「三つの私」、斉藤は「文語の〈われわれ〉、口語の〈わ〉〈た〉〈し〉」が並ぶ。 基本的に大辻も斉藤も共通した認識を持っており、乱暴にまとめれば |
||||||
| ・ | 文語と口語では助動詞の数が違うため、時間表現の扱いが異なる。どちらが優位ということではなく、文語は話者の位置が固定的であり、語は複層的に扱われる。 | |||||
| ・ | 文語と口語で時間表現が異なるが故に、短歌における〈私〉の扱い・立ち位置も異なる。 | |||||
| 斉藤斎藤が「短歌研究」に掲載した表がわかりやすい(図1及び2。時間表現に関する「テンス(時制)」――表現された行動が現在・未来・過去のいずれを指すか――と、「アスペクト(相)」――その行動がどのような長さを持っているのか――については言語学の入門書に大抵載っている)。 | ||||||
| 斉藤と大辻に差があるとすれば「文語と口語の差を理解した上で、自分はどちらに賭けるか」という作家としての挟持だけだ。両名の論作両面を今後も興味深く待ちたい。 なお、斉藤は、口語と作中主体に対する問題意識を十年近く持ち続けてきた。「短歌人」二〇〇五年二月号に掲載された評論「うごく短歌」を引用しておこう。 |
||||||
| 一首の外部にいる作者の心情や思想を詠うのではなく、一首の内部において作中主体が抒情する、認識する、その他もろもろの行為をする動くのままにとらえてみたい。 | ||||||
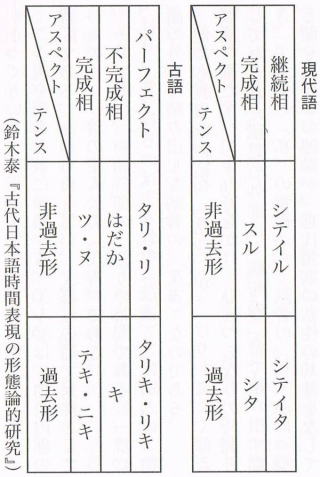 (図1) (図1)  (図2) (図2) |
図像はいずれも斉藤斎藤「文語の〈われわれ〉、口語の〈わ〉〈た〉〈し〉」(短歌研究2014年11月号)より | |||||
| ページトップへ | ||||||
| 2015年1月号 | ||||||
| 哲学から遠く離れて 中島裕介 | ||||||
| 最近、角川「短歌」や「短歌研究」で他分野の専門家と歌人の対談がやや増えている。読み物としても面白いことが多い。 他方、今年の八月二十三日、未来短歌会の横浜大会と同じ日に、塔短歌会の六十周年記念全国大会が開催された。大会直前に、塔短歌会の主宰が永田和宏から吉川宏志へ代わることが記者発表されたことは、ご存知の方も多いだろう。その大会では鷲田清一・内田樹・永田和宏の三名による「言葉の危機的状況をめぐって」と題された鼎談が催されたという。鷲田と内田は共に、現代哲学の一分野である現象学を研究する哲学者・倫理学者。今では、鷲田は大阪大学前総長、内田は作家・思想家というイメージが強いだろうか。個人的なことだが、私は学生時代に鷲田と内田の著作や訳書に触れて哲学に関心を持った。そんな二人が短歌やことばについて話すというのだから、未来短歌会の大会と日程が重なっていなければ京都まで鼎談を聞きに行きたかった。 近年の未来短歌会の全国大会でも作家の町田康を招いたことは記憶に新しい。「未来」の編集後記で岡井が度々書いているように、未来短歌会の大会等の場に他分野の専門家を招き、共に短歌について考える機会がさらに持てると楽しそうだ。 ところで、今年七月には哲学者・批評家の千葉雅也が『別のしかたで ツイッター哲学』を刊行した。ツイッター(Twitter)は一四〇文字以内という文字制限の中で、「ツイート」(呟き)と呼ばれる短文を投稿・共有するウェブサービスである。『別のしかたで』は、三十代半ばの千葉が二〇〇九年から二〇一四年までにツイッターに投稿した哲学や芸術に関する思考や日常のツイートを再構成した本だ。あとがきにこんな一文がある。 |
||||||
| ツイッターの一四〇字以内というのも、短歌の五七五七七やフランス詩の一二音節も、非意味的切断による個体化の「原器」であると言えるでしょう。 |
||||||
| 千葉の前著『動きすぎてはいけない』もそうだが、千葉の哲学的関心は、見落としや疲れといった、人間の〈有限性〉ゆえに他のヒトやモノから切り離されてしまうことにある。――怖がる必要はない。先の引用を乱暴に、短歌向けに言い換えれば「短歌には定型(=非意味的切断)があるから、作者の気持ちをひとまとまりの作品にできる(=個体化)。」という、よく言われるフレーズに収め得よう。ただ、〈定型〉を契機にして哲学的に考えうるように、短歌のいろんな側面から他の分野と繋がりうる可能性が、きっとまだまだある。 なお、『別のしかたで』には短歌にも通じるツイートがいくつも掲載されている。 |
||||||
| 〔これは詩だ〕 いったいどういう言語態を、これは詩だ、と認めていいのか。佐藤雄一さんによれば、それを受けとめる人を詩人と化すようなものが詩であるという。この定義は寛大であると同時に厳しくあると思う。 |
||||||
|
〔ゼロ〕 詩情はほとんどゼロ、言語の物質的存在感も限りなくゼロ、まるで何事でもないただの文の断片であるが、しかしそれとして玩味(がんみ)すると詩のようでもあるようなもの、に対する感性を持つこと……。 |
||||||
|
〔密室〕 ミステリも、近現代詩も、密室性を構築するわけです。そして詩は、その短さ((筆者注:エドガー・アラン・)ポーは詩は短いものだということを強調している)において、極まった密室劇であるわけです。 |
||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2014年12月号 | ||||||
| 虚構を読みうる場はどこか 中島裕介 | ||||||
| 第五十七回短歌研究新人賞は石井僚一「父親のような雨に打たれて」に決まったことが「短歌研究」二〇一四年九月号にて発表された。その後、同誌十月号には短歌研究新人賞の選考委員の一人である加藤治郎による特別寄稿という形で「虚構の議論へ」が掲載されている。「選考委員は石井の受賞作を「実父の死」を主題にしたものと読んだが、石井の実父は存命である」ということに対してある種の〈問題〉提起を行うものである。ただし、この〈問題〉が(歌壇的な場に)及ぼす影響とその範囲はなかなか想像しにくい。 石井の作品をいくつか見ておこう。 |
||||||
| 父危篤の報受けし宵缶ビール一本分の速度違反を 石井僚一 ふれてみても、つめたく、つめたい、だけ、ただ、ただ、父の、死、これ、が、これ、が、が、が、が 同 傘を盗まれても性善説信ず父親のような雨に打たれて 同 「父の死」が固有名詞であることの取り戻せない可笑しさで泣く 同 ネクタイは締めるものではなく解(ほど)くものだと言いし父の横顔 同 |
||||||
| ここで挙げた一首目は実父から観た祖父像であるが、二首目を境に作者自身の実父への心寄せに焦点が移行している。 加藤の〈問題〉提起の焦点は大きく分けて二つ。①新人賞の選考において、受賞作と前衛短歌との関係が選考委員には分からないこと、②石井が、「自身の父親は存命中だが、『死に際の祖父をみとる父の姿と、自分自身の父への思いを重ねた』」というネタバレ(背景説明や楽屋オチ)を「短歌研究」本誌ではなく、最初に石井がインタビューを受けた北海道新聞で行ったこと、である。 この影響を〈狭く〉見積もれば、石井が作品イメージを戦略的にコントロールしていないことへの批判、ネタバレ情報を北海道新聞新聞より「短歌研究」に先に提供するという信義則に則らなかったことへの批判に限られる。〈広く〉影響する可能性を想像してみると、新人賞応募作品における傾向と対策がより入念に練られる情況の到来、匿名で行われる現行の新人賞の仕組みにも繋がるかもしれないというあたりだろうか。 ところで、「歌壇」八月号の特集は「短歌の空想の力――フィクションとファンタジーの魅力」と題されており、その総論として斉藤斎藤が「読者にとって「空想」とは何か」を寄せている。斉藤は大辻隆弘の『子規への遡行』を援用して、Ⅰ一人称単数、Ⅱ単元描写(連作や歌集中で作中主体が一貫していること)、Ⅲプロフィールとの一致、の三つの条件を挙げ、 |
||||||
| 短歌作品が、〈私性〉にもとづく「事実」に見えるためには、少なくとも三つの条件を満たす必要がある。(中略)裏を返せばこの「事実」の三条件のいずれかを何らかの形で踏み外した作品は、読者に「空想」と見なされる | ||||||
| と上手くまとめている。 短歌研究新人賞の話に戻る。加藤自身も前掲稿で虚構が全面的にダメだと言っているわけではない。ただ、石井の作品は斉藤のいうⅡ単元描写という点で「踏み外」す企図があったが、その企図が選考委員には通じていなかった。企図が全部通じなくても新人賞が獲れるならそれはそれで羨ましい話だが、加藤の稿は「作品の企図をなるべく読者に伝わるよう意識してほしい」という激励と捉えるのが妥当なところだろう。 石井僚一は同誌十一月号でなんらかの応答をすると聞いている。その内容がどのようなものになるか楽しみにしている。 |
||||||
| ページトップへ | ||||||
| |
||||||
| 2014年11月号 | ||||||
| 展示される短歌、そして都市 中島裕介 | ||||||
| 『本・ことば・デザイン』展と題した展示が東京・六本木にある東京ミッドタウン・デザインハブにて八月二九日から九月二八日まで開催された。ブックディレクターである幅允孝が「『デザイン』を感じる本と、その本の中でもっとも印象に残るテキスト、それら本来は目に見えない言葉というものを展示会場で視覚化」することを目的として本展を構成したという。短歌からは穂村弘が参加しており、穂村はこの展示で扱う本として『葛原妙子全歌集』を選び出し、そこから三首を展示に使用している。
展示会場は美術大学や関連団体による共同オフィスの、幅の広い廊下が使用されている。その廊下の一角の、天井付近に円形の三枚の白い紙が層状に設置されたものが穂村の展示だ。(図1) |
||||||
| 東京は大き魔なれば魔のひとりわれのくるまの迅速なりき 葛原妙子 | ||||||
| ここで挙げられた三首はいずれも都市の情景を見通したものである。天井付近という見落としそうな位置に置かれていることも印象的だ。 | ||||||
| 八月三一日から九月十五日までの間には、東京・麹町にあり、十月には取り壊されることが決まっている九階建てのビルをまるごとアートで覆うイベント「BCTION」が開催された。このイベントには青木麦生と佐々木あららの両名が短歌の展示で参加した。青木麦生は二〇〇七年から自作短歌を、カッティングシート(色付きの薄い塩化ビニール)を用いて町中に貼り付ける展示をしており、今回は青木と佐々木両名の作品計二十三首が展示されている(筆者は女子トイレの展示までは視認していないが)。 例えば、鏡が床に置かれ、天地が逆転したように見える空間に、このような歌が展示されている。(図2) |
||||||
| 脚立から見える世界に住みついて君のつむじを眺めて暮らす 青木麦生 | ||||||
| 穂村の〈デザイン〉としての展示と、青木・佐々木の〈アート〉としての展示の区別と効果について論じる紙幅はここにないが、いずれも歌集のなかに留まらない短歌の表現として非常に興味深い。 短歌、あるいは歌がはらむ詩性とは、その作品に向き合う中で、読者(あるいは作者)にとっての世界の見え方を変えるものだ。その変化のチャンスは歌集を読むときに限定されなければならないわけではない。都市の一隅に掲げられた、普段は見逃していた短歌をふと見かけることで、都市の、世界の見え方を変える人も現れ得る。これも一行詩としての短歌の強みであり、新たな可能性である。 書を捨てよ町へ出よう――町に歌があるから。 |
||||||
 (図1) 穂村弘による葛原妙子の歌の展示。見上げなければ見つからない。(撮影=筆者) |
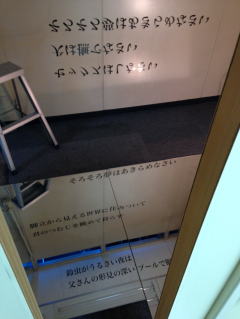 (図2) 青木麦生の歌の展示。床置きの鏡に壁に書かれた歌が映る。(撮影=筆者) |
|||||
| ページトップへ | ||||||
| |
||||||
| 2014年10月号 | ||||||
| あたらしい結社のかたち 中島裕介 | ||||||
|
二〇一四年七月十九日、大阪府立大学が大阪・なんばで運営するまちライブラリーにおいて大阪短歌チョップというイベントが開催された。 |
||||||
| 会場で販売された「大阪短歌チョップ メモリアルブック」によると、このイベントの「企画」として短歌人会の天野慶、大阪で「空き家歌会」という歌会を主催する牛隆佑、新鋭短歌シリーズ第二期で第一歌集を刊行する岡野大嗣、昨年の角川短歌賞で予選を通過したじゃこ、投稿者の短歌に自作の写真を付けた雑誌「うたらば」を自費で刊行する田中ましろ、「短歌研究」のうたう☆クラブ大賞を受賞した虫武一俊の名が並ぶ。関西で、インターネットを通じて短歌に触れる十代から三十代あたりの人々にとってはよく知られる面々である。 | ||||||
| 大阪短歌チョップは、簡単にいうと「短歌のための、大人の学園祭」だ。会場の各所で歌集の販売、ネット短歌を主題にしたシンポジウムのほか、塔短歌会の江戸雪への公開インタビュー、初心者向けの歌会やゲーム形式の作歌、競技かるたA級の歌人・三潴忠典による実演、短歌に添えられたイラストやマンガの展示などが行われる。「うたのかべ」と題した歌会は、投稿された歌二一七首が壁一面に掲出され、来場者が投票するほか、NHKラジオ「夜はぷちぷちケータイ短歌」で司会を務めた芸人だいたひかるや田中ましろらが選歌する。 | ||||||
| ふるさとと呼べないだろうこの街は途中で辞めた部活みたいで 碧南ゆづき | ||||||
| 「じゃあ僕は新幹線で」食パンをちぎってもごもご噛むようにして 飯田和馬 | ||||||
| 前者は来場者による投票で一位を獲得した歌、後者はだいたひかるが選んだ歌である。前者は活動的な社会とそうではない自分のあり様が異なって感じられることを部活動で言い表している点が面白い。後者は、相手とは異なる経路でどこかへ行くことをきっぱりとは言い切れない様子を表していると解釈した。 | ||||||
| 先にも触れた「うたらば」は、各号によって異なるテーマに沿って詠草を公募し、田中が選歌し、写真と詩を添えて、田中の私費で刊行するフリーペーパーである。とてもカラフルで見やすく、短歌に興味がなくとも手に取る人は多いだろう。 | ||||||
| ところで結社とはなにか。例えば大野道夫『短歌・俳句の社会学』にこうある。・短歌・俳句の創作と歌人・俳人の養成を目的とし、(中略)「観念」と「人」を中心とした系譜性、擬似血縁的な強い関係である超血縁性、そして機能的階統制(ヒエラルキー)を特徴とした集団、と定義したい。特に同人誌との違いとしては、中心となる「人」と、選歌・選句などの機能的階統制(ヒエラルキー)の存在が重要である。 | ||||||
| 大野の定義に従い、結社と同人誌の主な違いを選歌――それ自体が階統制(ヒエラルキー)に基づくものだが――に求めれば、「うたらば」も大阪短歌チョップにおける「うたのかべ」も、特定の人物による選歌が行われる点で「結社」に近い。そう考えると「うたらば」は結社誌、大阪短歌チョップはその全国大会とも言い得よう。 | ||||||
| 他方、島田修二は『抒情の空間』で、結社にはリーダーシップをとる指導者が一人または複数存在することを指摘した上で、「同人組織ではリーダーシップは集団そのものです」(P.60)と述べる。田中がどの程度リーダーシップを発揮しているのかは分からないが、大野のいう系譜性を排する一方で、同人誌的な〈なかよし〉感導入しているように見える。「うたらば」はあたらしい結社の在り方を示しているのではないか。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2014年9月号 | ||||||
| 作者の個人的属性、時代状況 中島裕介 | ||||||
| 歌の読解における、作者の個人的属性や時代状況の扱いについては以前から議論の多くなされるところだ。 | ||||||
| 「うた新聞」六月号の特集「短歌の〈背景〉について」には、文章の長短があるものの総勢二十人が寄稿している。三枝昂之「データの生かし方 ――背景を知って鑑賞の幅を広げる」はその題名の通り、 | ||||||
| 春の夜にわが思ふなりわかき日のからくれなゐや悲しかりける 前川佐美雄 | ||||||
| を挙げて、①作者の――性別や年令、作風などといった――個人的情報を適用しない読み、②作者の個人的情報としての来歴を適用した読み、③時代状況を適用した読みの三種類を提示する。その上で三枝は、①の読みが基本であるとしつつも、②と③の読みを適用しなければ「わかき日のからくれなゐ」という一節に込められた青春愛惜の情や、時代状況に対する危機と嘆きが把握できないことを示す。同じ特集の中で、中津昌子は岡井隆の『E/T』を扱い、作者が歌集全体を通じて演出的に個人的情報を読者に提供する仕方を、三宅勇介は幕末期の国学者・歌人の平賀元義の歌を読む際に国学の知識が必要となることを、それぞれ論じている。三枝の分類を敷衍すると、中津の論は三枝の②、三宅の論は③の重要性を扱ったものと言い得よう。 | ||||||
| 「本郷短歌」第三号の特集「短歌 ジェンダー ――身体・こころ・言葉――」のうち、宝珠山陽太の評論は大口玲子『トリサンナイタ』と俵万智『プーさんの鼻』を引き比べつつ、一見すると真逆の印象を与えそうな両歌集が、いずれも近代的な〈母性〉という政治的に形作られたイメージを作中主体という場において戦略的に利用した点で共通した歌集であることを明らかにしている。服部恵典「『歌人』という男」は既に方々の時評でも論じられているが、過去十年の短歌研究新人賞を分析し、新人賞の選考委員が文体や感覚を元に、応募作が歌壇において一般的に想定される〈女性〉像に当てはまるかどうかを判定する様子を「性別当てゲーム」と服部は批判的に表現する。その上で、〈女性〉像ばかりが評語として用いられることから、歌壇における〈歌人〉という一般的な像が中性ではなく〈異性愛者の男性〉を指すものであり、それゆえ、 | ||||||
| 少量の「女性らしさ」でも作者の特異な「個性」として評価される。つまり、女性の歌人の歌の評価は、いつも「女性的な感性」に回収され得る運命にある。 | ||||||
| ことを暴き出した。 | ||||||
| 「うた新聞」の特集は歌の読解の場で作者の個人的属性を扱うことによる良い面を、「本郷短歌」の特集は、個人的属性のうちジェンダーに焦点を当てることで、その悪い面を扱ったといえよう。つまり、宝珠山は三枝の分類でいう③を扱い、大口や俵が〈母性〉というある種の時代状況に応じて仮構されたイメージに則り、あるいはそのイメージを応用して歌集を編み、評価を受ける状況を論じた。服部は三枝の②を扱い、読みに援用される〈男性〉や〈女性〉という個人的属性が極めて偏見的に限定されていたものでしかないことを論じたのである。 | ||||||
| この差はなにか――「現代」か否かだ。前川の歌を読む際には、彼の、既に明らかにされ、論じ尽くされた個人的属性や時代状況が読者の理解が大きく深める。翻って、現在進行形の現代短歌の読解に際しては個人的属性自体が多様化し、時代状況も論じ切られていない、流動的な状態にあることを前提にする必要がある。大変な作業ではあるが、新しいぶどう酒は新しい革袋に入れなければならないのだ。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
|
2014年8月号 |
||||||
| 隆盛する学生短歌会 中島裕介 | ||||||
| 学生短歌会がかつてない活況を示していることは改めて言うまでもないことだろう。新人賞を見れば、2006年頃から学生短歌会の現役会員やOBが受賞者に名を連ねる。角川短歌賞における澤村斉美・光森裕樹・大森静佳・薮内亮輔・吉田隼人・伊波真人、短歌研究新人賞における吉岡太朗、山崎聡子、吉田竜宇、歌壇賞に至っては平岡直子、服部真里子、佐伯紺と早稲田短歌会から三人が立て続けに受賞している。「現代短歌新聞」では昨年八月まで大辻隆弘が「大学短歌会はいま」と題した連載で十二の会を紹介していた。今年四月十二日の日本経済新聞朝刊の文化欄では学生短歌会の合宿の様子が大きく取り上げられたが、そこでも書かれているように学生短歌会でも二〇一〇年以降に設立された会は多い。 | ||||||
| そんな情況を反映したのだろう、「歌壇」六月号では「競詠 学生短歌会の歌人たち」という特集が組まれている。十の学生短歌会から一人ずつ、七首連作を掲載している。幾つか歌を引用しよう。 | ||||||
| 呼び鈴に触れてからそれが鳴るまでの桜の街のながき空白 鈴木加成太 | ||||||
| さみしくて暑くて、寝てた。これだから夕方は嫌だ、母がゐそうで。山下翔 | ||||||
| 北欧の消印で着く君からの手紙 雪が止まなくてこわい 永山源 | ||||||
| 山下の歌は、この特集に登場する十人の中で唯一旧かなで表記されている一方、句読点の多用も目立つ。引用歌は一人暮らしの自室の様子だろうか。夕方に寝ていたら、いるはずのない母がいるような気がするという。作中主体の母への愛憎を感じ、また「これだから」という言い回しも面白い。 | ||||||
| これに対して、若手の現代詩作家によるユニット・TOLTAは五月に開催された第十八回文学フリマで「トルタの短歌」と題した、学生短歌会を特集したフリーペーパーを配布した。「トルタの短歌」は両面フルカラーのA1版を八つ折りにしたもので、早稲田や京大を含む十三の会の、現役会員及びOB・OGを含め、短歌会全体の代表歌二十五首選とその選歌基準、会の紹介文を掲載している。内容的にかなりのボリュームがあるが、それだけの印刷物が無料配布されたという事実にも驚かされる。中でも京大短歌会のコーナーは(贔屓目抜きで)際立っている。永田和宏の「母を知らぬわれに母無き五十年湖降る雪ふりながら消ゆ」をOBの歌として挙げるだけでも反則級だが、これを「青春は燃えるようなものだけではない。ただ、理性と憧憬の中に静かに冷えてゆくしかない、そのような青春もあるのだ」と評する薮内亮輔の文章にもしびれる。 | ||||||
| ところで、「歌壇」の特集に登場した十名の半数は結社に所属しており、そうでない中でも新人賞の選考過程で見たことのある名前が多い。そのような、既に定評のある若手歌人の作品を、学生短歌会全体や各学生短歌会を代表したものとして捉えてはならない。その意味でも、今回の特集に学生短歌会や若手歌人を論じる評論や座談会が含まれていなかったのは残念だ。もちろん、学生短歌会という場は〈歌壇〉から論じにくい。ただでさえ〈歌壇〉の見通しが立ちにくくなっている現状、学生短歌会の会員は――歌会や様々な交流を通じて、会ごとの歌風がなんとなく引き継がれていくとはいえ――結社のように何らかの方向性や思想のもとに集まるわけではない。あくまで〈短歌という文芸の一形態に惹かれた〉という一点で集まる。その傾向は「うたらば」や「うたつかい」といった、結社に所属しない若手の同人誌にもあてはまるところだ。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
|
2014年7月号 |
||||||
| 代作問題と「弱い言葉」 中島裕介 | ||||||
| 角川「短歌」二〇一四年四月号では緊急特別企画「感動はどこにあるのか ――作品と作者と〈物語〉」が組まれている。今年二月初旬から話題になった「佐村河内守」名義の音楽作品の代作問題を五人の歌人が論じている。順不同で触れる。 | ||||||
| 大辻隆弘は、代作問題における実際の作曲家である新垣隆が「芸術性」と「大衆性」の間で揺れ動いていたことに着目・共感する。そして、現在の短歌においては「大衆性」が拡大しつつあるとした上で、「短歌が『大衆性』という価値のみを追いかけるとき、そこには短歌版の佐村河内氏が必ず登場してくるだろう」と予言している。 | ||||||
| 吉川宏志は二つの提言をしている。一つは〈作者〉をイメージして――つまり〈作者〉の〈物語〉を付与して、作品を鑑賞することの危険性を指摘し、作品と〈作者〉の関係を批評的に見つめることへの提案。もう一つは、大辻の言を使ってまとめると、「芸術性」「大衆性」など、異なる価値観の間で議論を交わし、双方の価値を認める人を少しずつでも増やすことへの提案である。◆高木佳子は吉川の一つめの指摘と同様に作品の受け手が〈物語〉を完成させ、享受してしまう傾向を指摘し、短歌の実作者・読者に「作品自体の真価を判断するリテラシーを身につけるべきである」と迫る。 | ||||||
| 他方、染野太朗は河合隼雄『物語を生きる』を引用して、〈物語〉は人の認識や存在がモノに何かを関係づけ、意味付けるという、本質的な機能だという。その上で代作問題のような「偽りの物語」を手放しで肯定しないが、人が〈物語〉を欲求すること自体は肯定しなければならない、というのだ。乱暴にまとめると、高木の「〈物語〉を留保して読むリテラシーを身につけるべき」という潔癖な態度に、染野は留保を求める構図を見て取れる。 | ||||||
| 三枝昂之は自身の『百舌と文鎮』や斎藤茂吉の『短歌小論』、竹山広の | ||||||
| 原爆を知れるは広島と長崎にて日本といふ国にはあらず | ||||||
| を例に挙げて、「作者の人生という付加価値なしで作品と向かい合うことができるか」という問いを投げかける。この歌は竹山広の人生・背景――〈物語〉を知る場合と知らない場合で歌の読み方・解釈が異なるのだが、そのいずれの読みの可能性をも、三枝は評価する。この三枝の論は、好意的に見れば、〈物語〉の肯定と排除の間で、吉川のいう「双方の価値を認める」立場にあると受け取ることもできよう。 | ||||||
| 実際のところ、現在の短歌実作者・読者も三枝のような態度の者が多いのではないかと私は推測する。普段の歌会や評論の場でも、程度の差や傾向はあるとしても、作品以外の〈物語〉の援用度合いを〇%から一〇〇%の間で操作して、最も豊穣な読みを導き出そうとするではないか(ただし、ここでの〈物語〉という語は意図的に限定的に用いた)。 | ||||||
| ところで、「SIGHT」二〇一四年春号に掲載されている哲学者・内田樹と作家・高橋源一郎の対談が面白い。代作問題や現在の政治が話題になった後、政治的なスローガンは単純であるがゆえに、「強い言葉」として人々に影響を及ぼしている状況について、高橋は以下のようにいう。 | ||||||
| つまり、僕らの「物事は複雑だよ」という論理は、強い言葉にならないと思うんだよね。弱い言葉を無限に集めるしかなくて、僕らは集める側に回ってるということなんです。 | ||||||
| 物事は複雑であり、短歌もまた複雑な〈物語〉から生まれるのではなかったか。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2014年6月号 | ||||||
| 日系人の短歌から考える作歌の態度 中島裕介 | ||||||
| 「短歌研究」二〇一四年三月号に、小塩卓哉が第一回から十年間、選考委員長として関わってきた海外日系文芸祭(みなとみらい文芸祭)を振り返っている。この海外日系文芸祭は、小塩のエッセイ「一冊の『短歌研究』から海外日系文芸祭の十年」によると「海外日系人と国内の短歌・俳句愛好者との交流を目的に始めたもの」であった。 | ||||||
| 二〇一三年、第十回の大賞受賞作の作者はブラジル・サンパウロ在住。 | ||||||
| われ移民さくらさくらとうたえどもはなびらあびる夢にとどかず 尾山峯雄 | ||||||
| 「受賞のことば」に「渡伯五十年」とある。移民先で日本の唱歌である「さくらさくら」を歌いながら労働に長年励んできた。その中で、成功し、故郷に錦を飾り、散る桜の花弁を浴びることを夢に願っていたのだろう。その夢に届かなかったという痛切さがこの歌にある。 | ||||||
| 海外日系文芸祭は第十回にいたり、 | ||||||
| 応募数は回を追うごとに増えてきたのですが、海外移住者からの作品が年々減少してきた実情を踏まえ(「第十回海外日系文芸祭作品集」あとがき)「一旦終了する」ことになったという。この要因を小塩は「何と言っても海外日系社会からの応募が高齢化によって減少したことにある」と断ずる。◆世界で日本人移民が最も多いブラジルを見ても、国立国会図書館が二〇〇八年に公開した「ブラジル移民の百年」(http://www.ndl.go.jp/brasil/)において | ||||||
| コロニア(筆者注:二世以降を含む移民及びその社会)を構成するのは一世と一部の二世のみとなり、これらの人たちと高齢化とともにコロニアは衰退していくことになった。 | ||||||
| とある。国際交流基金が三年に一度実施している海外日本語教育機関調査の二〇一二年度版でも、近年のブラジル日系人の日本語離れが暗示されている。いずれも小塩の要因分析と違わないと言ってよいだろう。 | ||||||
| 小塩のエッセイは併せて、改造社時代の「短歌研究」昭和十二年六月号の記事「ブラジル歌壇の展望」を紹介しつつ、一九三〇年頃から文芸分野への関心が高まり、戦前から戦後にかけてブラジル歌壇が隆盛したという歴史をまとめている。◆他方、田中濯は詩客の二〇一三年四月十二日付短歌時評で細川周平『日系ブラジル移民文学』を取り上げていた。田中は同書に「『素人の文学』を語ること」の重要性を見出し、いくつかの示唆に富む指摘をしているが、中でも同書が「副次的に優れた『結社論』を展開するに至った」点を一つ引用しよう。 | ||||||
| ブラジル歌壇は老齢化・衰微化をせざるをえず、それは日本の短歌の老齢化・衰微化を先取りしていること。(中略) | ||||||
| しかし日本語社会が縮小するなかで、書く習慣を保つには、一定の知的持久力を必要とする。社交の楽しみは継続を支えるのに不可欠だ。 | ||||||
| として、社交の価値を説くのである。 | ||||||
| 田中はこの「社交の価値」を、「作家性により価値を置くひとびと」には「ある程度は、苦々しいもの」だが「傾聴に値する意見」としている。 | ||||||
| 「社交の価値」は、私も心情的には理解できる。ただ、斉藤斎藤が『歌壇』二〇一三年十二月号「〈なかよし〉について」である種の懸念を示したように、結社に所属する歌人が「素人の文学」と同じ態度を表明する、というわけにはいかないだろう。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
|
2014年5月号 * 時評 |
||||||
| あやむるこころ 中島裕介 | ||||||
| 「短歌往来」で島内景二が「短歌の近代」という連載を今年からはじめている。二月号の題は「皆殺しの短歌と、四海兄弟の和歌」。この論によると、 | ||||||
| 五月來る硝子のかなた深閑と嬰兒みなころされたるみどり 塚本邦雄 | ||||||
| (「邦」は異体字、「硝」は正字) | ||||||
| 瓶内に群れゐる蟻をみなごろしせよと言はれてしたりきわれは 竹山広 | ||||||
| の二首は作者の戦争体験を背景にリアリティを持つが、江戸末期~明治初期の思想家である林桜園の |
||||||
| 水鳥の |
||||||
| は歴史的・同時代的背景を考慮してもなおリアリティがなく、強烈な違和感を覚える、という。一方で島内は、短詩系文学における時代区分を①「古代短歌」の奈良時代、②「和歌」の平安時代から江戸時代まで、③「近代短歌」の明治以降の三つに分けることを提案する。そして、和歌を詠むこともできた林の「皆殺し」という語に対して違和感を覚える原因を、島内は平安時代に形成された〈和の思想〉に求める。「平和=四海兄弟」をモットーとする〈和の思想〉と「皆殺し」という語や思想が噛み合っていないからだ、と。翻って、塚本や竹山の歌において「皆殺し」という語は〈和の思想〉とは情況が異なるが故に受容される。これらの島内の指摘は興味深い。 | ||||||
| 他方、「短歌研究」二〇一四年一月号における「新春対談 岡井隆vs馬場あき子」で岡井は塚本の「馬を洗はば馬のたましい冱ゆるまで人戀はば人あやむるこころ」を挙げて、「人をあやめるというような行為とかそういうものを今、説明できない」と発言し、馬場も同調する。以下、対話を一部省略しつつ引用する。 | ||||||
| 馬場 私なんかも昔、女の恨みの歌を随分と書いていたときがある、(略)完全に自分の所有にするには殺すしかないという。そんなことを今書いたらたいへんなことになるでしょう。年中ストーカー殺人がありますのでね。 | ||||||
| 馬場 (略)殺すというのはあの時代が持っていた意味の深さというのがあるのよね。時代そのものに対する恨みとか、それから、自分の中にある何かを圧殺したいとか。いろいろなものがあったのよね。それが今はわからなくなっちゃったのよ。 | ||||||
| 岡井 (塚本の「日本脱出したし 皇帝ペンギンも皇帝ペンギン飼育係りも」を挙げて、母国を否定するという考え方を提示し)その当時、我々にとってはごく普通にあった考えでしょう。今それを説明するのがすごくむつかしい。 | ||||||
| 馬場発言の一つ目は「現在の社会状況に比して『殺し』を扱うことの困難」、馬場の二つ目及び岡井の発言は「作歌当時に『殺し』や『日本脱出』が象徴していた心情や背景が通用しないこと」を指していると言える。この両名は、島内の示した三区分の「近代短歌」に、現在の時代情況が合致しないと認識しているように見える。現在の若手歌人の歌集を見ても、島内の三区分のあとに「〈和の思想〉的な現代」という区分が付け加えられるべきかもしれない。 | ||||||
| ところで、京都・清水寺で(公財)日本漢字能力検定協会(漢検)が毎年発表している「今年の漢字」に対抗して、埼玉県の寺院が「今年の四字熟語」が制定する、という。二〇一四年一月二三日に発表された第一回の「今年の四字熟語」は「四海兄弟」。「短歌往来」二月号の刊行時期から考えても、この四字熟語は島内の論と無関係だが、時代情況の違いは示唆されていよう。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2014年4月号 * 時評 | ||||||
| 紙製の歌集を出す、ということ。 中島裕介 | ||||||
| 一昨年の十月に「短歌をカネにかえたくて」というイベントを共催させていただいた。内容は「マイナーな作者が存在を知ってもらい、自作を読んでもらい、評価をしてもらう――短歌をカネにかえる契機を作るには、良い歌が収録されていることはもちろんのことながら、作者が作品以外の価値を付加する必要がある」というもの。そうでもしなければ〈お仕事〉は経験豊かな常連歌人と、常連さんオススメの新人賞受賞者へ流れていってしまう。 | ||||||
| 歌集に「造本や装幀の美しさ」という付加価値が付いている近刊の歌集として、澤村斉美『galley』、堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』、秋月祐一『迷子のカピバラ』などが挙げられる。もちろん彼らがカネのために造本や装幀に凝ったわけではないだろう。ただ、「優れた歌が収録された歌集が美しい」ことは、結果的に歌集が直接手に取られる機会を増やす。 | ||||||
| 澤村の『galley』の表紙には、光沢のある透明な箔押しで、ひらがなや様々な記号が置かれている。厚めの紙でできた扉は、表紙と同じ並びのひらがなや記号の一部が型押しされているため、それらが透明な紙から浮かび上がってくるようだ。本文はクリーム色めいた白い紙と青みがかった白い紙に十六ページごとに交互に刷られており、小口からみても驚かされる。なお、歌集の装幀を行った濱崎実幸に澤村が、青磁社の永田淳と塔短歌会の西之原一貴を交えて、インタビューしたブログ(http://galleria-galley.hateblo.jp/)が公開されている。 | ||||||
| ハンガーにカーディガン揺れ夏の窓はおとろへてゆくばかりの光 | ||||||
| 巻頭歌。ハンガーにかかっているカーディガンが揺れたので、窓に意識を向けると、晩夏なのかあるいは夕暮れなのか、陽光が衰えてゆくという。日常的な光景を述べているが、説明的な助詞を切り詰めた結果、光景と光景の関係が淡くなり、読者の読みを誘発する。 | ||||||
| 堂園の『やがて秋茄子へと到る』は光森裕樹『鈴を産むひばり』と同じ出版社・港の人から刊行されており、同じく活版印刷。帯も栞もなく、表紙は葉脈の浮き出た押し葉標本とタイトルと作者名だけ。本文は一ページ一首組。 | ||||||
| 秋茄子を両手に乗せて光らせてどうして死ぬんだろう僕たちは | ||||||
| 歌集のタイトルになった一首。黒く光る秋茄子を死の象徴と捉え、「僕」ではなく、後ろに一歩引いた「僕たち」の視点で人間の無常観を考える。歌集全体も作中主体が幽霊であるような淡い感覚に覆われている。 | ||||||
| 澤村の歌集も堂園の歌集も、語のレベルでは立ち止まってしまう難しい語彙は少ない。しかし、一首ごとに技巧が凝らされており、歌集の美しさと併せて歌を楽しめる。 | ||||||
| ところで、昨年十月には紀伊國屋書店新宿本店で「本屋で歌集を買いたい」が、十一月に「新鋭短歌シリーズ出版記念会」が開催された。残念ながら私はどちらにも参加できなかったので、事後の感想や報告をウェブで読む限りだが、それぞれ〈書店〉や〈出版社〉という立場から歌集という媒体を再検討する、有意義なイベントだったようだ。「短歌をカネにかえたくて」が〈作者〉の側からアプローチしたイベントだったとすると、今度は〈読者〉についても再検討してよさそうだ。作者も出版社も本屋も、読者に短歌を届けたいから工夫し心を砕く。だからこそ「歌人でない読者はどういうものか」「読者はどんな人の、どんな歌を読みたいのか」「相変わらず紙の歌集で読みたいのか」といずれ検討してみたいのだ。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||
|
2014年3月号 * 時評 |
||||||
| 震災後と復興の文学論 中島裕介 | ||||||
| この号がお手元に届くのは三月十一日よりも少し前だろうか。東日本大震災から二年半ほどが経過した昨秋、青土社から二冊の本が立て続けに出版された。 | ||||||
| 十一月に刊行されたのは木村朗子『震災後文学論 ――あたらしい日本文学のために』。同書では、東日本大震災及び原発問題(311)に関する認識を、 | ||||||
| 地震や津波からはきっと復興するだろう。しかし原発事故による放射能汚染から逃れることはおそらく誰にもできないだろう。 | ||||||
| と、震災が単なる天災ではなく、同時多発テロ(911)に連なる人災であると整理する。震災直後に書かれた主な小説作品を①震災を作中で直接描くもの、②震災を作中で間接的に描くもの、③震災の経験が刻印されていると思われ難いが、震災と重ねあわせて読み解きうるものに大別する。その上で、作家・佐藤友哉の評論を引用し、 | ||||||
| 震災後文学とは、したがって、単に震災後に書かれた文学を意味しない。書くことの困難のなかで書かれた作品こそが、震災後文学なのである。今までどおりの表現では太刀打ちできない局面を切り開こうとする文学 | ||||||
| 他方、福嶋亮大『復興文学論』は十月に発表された。東日本大震災及び原発問題に直接影響を受けたものではなく、柿本人麻呂や紀貫之から村上春樹、宮﨑駿らまでをも論じる。福嶋は「出来事の後=跡に新しい題材や方法論を呼び込みながらシステムに再び活気を与える」「復興期あるいは<戦後>」こそが「日本文化に創造性が満ち溢れる」時期であるとする。 | ||||||
| 人麻呂の長歌「近江の荒都を過ぐる時作れる歌」(『万葉集』巻一・二九)は、六七二年に起きた壬申の乱によって廃墟になった古都・大津宮を回顧すると共に、眼前の風景を描いている。その反歌二首「ささなみの志賀の辛崎幸くあれど大宮人の船待ちかねつ」(三〇)と「ささなみの志賀の大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも」(三一)では、眼前にはいない「大宮人」や「昔の人」に古都で呼びかける。 | ||||||
| これらの長歌と反歌によって | ||||||
| 人麻呂は政治的敗者の魂の淀む土地に対して鎮魂の企図を含んだ呪術的な言葉を差し向けていた | ||||||
| のであり、また、それらの歌を通じて | ||||||
| 遷都のたびに必然的に発生する古都は、歌人たちによって忘却の淵から救出され、文学的情念を喚起する対象に変えられていったのである |
||||||
| と、「懐かしい古都=古郷として復興」する文学のあり方を福嶋は示して見せる。 | ||||||
| もちろん私も、福嶋が示した儀式的な歌のあり方が、今日の短歌でも適用可能だと思わない。木村が示した射程の広い「震災後文学」の可能性とあわせて、「書くことの困難」の中でなお書くことの、ヒントにはなるだろう。 | ||||||
| ところで、福嶋の『復興文学論』にはこんな一節がある。 | ||||||
| 万葉歌人たちは、未開の自然ではなくあくまで文明を出発点として、自分たちの自画像を描き出した(ゆえに『万葉集』を「素朴」でプリミティブな歌集だと考えるアララギ派的見解には到底同意できない)。 | ||||||
| 今も? 本当に? まさかね……? | ||||||
| ページトップへ | ||||||
| 2014年2月号 * 時評 | ||||||
| 未知のものに出会わざるを得ない時代の表現 中島裕介 | ||||||
| 今回から時評を担当させていただく。時評を担うには力不足に過ぎるが、追々その不足を埋めていきたい。そのためにも忌憚ない意見・批判が頂ければ幸いである。第一回ということで、この時評の方針にも関係する、私の現状認識に触れておく。 | ||||||
| 総務省が二〇一一年八月に「『情報流通インデックス』計量結果の公表」(http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_01000004.html)を行っている。マスメディア、電話、郵便等といった媒体で伝えられるありとあらゆる情報が日本でどれだけ発信され、人は情報をどれだけ受け取り、消費してきたかを示したものだ。この調査結果によると「二〇〇一年から二〇〇九年の間に、人が処理できる情報量は十%増えたが、流通する情報量は二倍になった」という。人が処理できる情報量が少々増えても、人を取り巻く情報量はそれ以上に増えてきた。 | ||||||
| この情報量増大の流れは、残念ながら不可逆である。二〇〇九年時点でこれだけの乖離があったのだ。二〇一四年現在ではこの差が広がることはあれ、埋まることはない。あなたがいかにブラウン管のテレビを愛していたとしても、そこに色鮮やかな番組はもう映らず、白黒の砂嵐が飛んでいるだけだ。高画質・多チャンネルの地上波デジタル放送をブラウン管テレビで見るには別途、受像機を用意する必要がある。 | ||||||
| 前述の調査によると、流通している情報量のうち、未だそのほとんどをテレビやラジオといった放送が占めている一方、インターネットの情報量は七十倍以上増加している。企業によって一方的に情報が配信される放送ではなく、インターネットを通じてであれば、一個人が普段から写真や動画を気軽に発信でき、友人と楽しく交流することができる。そんな現在、ネットでも分かる日常についてだけ書かれた短歌をわざわざ読みたいか。私はノーだ。インターネットは短歌の作り方・読まれ方にも変化をもたらす。 | ||||||
| 阪神淡路大震災、911、そして東日本大震災という大災害・大事件も、情報量が多い現在だからこそ、表現を大きく変容させる。フィクション以上に圧倒的な事態が現実に起こり、これまでの日常はフィクションだったかのように簡単に変わってしまう。災害や事件がリアリティのある情報として流通しているからだ。テレビの報道が「映画みたい」に見えるのは、これまでリアリティのある、フィクションの映像表現が数多く試みられてきたからだ。 | ||||||
| この避けようのない情報量氾濫の中で、短歌や、短歌と人との関わりがどうなるのか。結社のあり方について言えば、角川「短歌」九月号の特集「歌壇の歴史と現在」における「今後も超血縁性の横の関係も、機能的階統制の縦の関係もゆるやかになってネットワーク組織化していく」という大野道夫の指摘、あるいはこれを斉藤斎藤が「歌壇」十二月号の年間時評で端的に「ネットが短歌につながるとともに、結社のネット化もすすんでいる」とまとめた言がわかりやすい。評価や評判という点では、「短歌研究」十二月号の座談会で穂村弘は、歌壇に慣れている者には歌集に対する評価の良し悪しがネットからは分かりにくいと発言している。新刊の歌集に対する評判やその汲み取られ方、ひいては歌の読まれ方、評価される歌のあり方も変わってくる。 | ||||||
| そして、現在の表現については、今後の時評で論じていきたい――この時評が地上波デジタル放送における受像機の役割を果たせるように。 | ||||||
| ページトップへ | ||||||